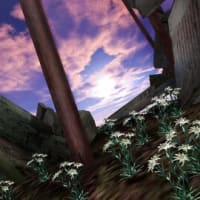東京新聞社説 2018年5月1日付
「憲法を考える 『文民統制』が揺らぐ」
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018050102000140.html
文民統制。
軍事組織が主権者代表の統制に従うのは民主主義国家の基本原理ですが、
それを危うくしかねない動きも目立ちます。
日本国憲法の危機です。
その出来事は2018年4月16日午後9時前に起きました。
国会近くの参院議員会館を出た小西洋之参院議員に、男が現職の自衛官だと名乗った上で、罵倒したのです。
「国のために働け」
「あなたがやっていることは国益を損なうことじゃないか」
「ばかなのか」
男は最終的には発言を撤回しましたが、小西氏によると罵声は約20分間続き、
男は小西氏に「国民の敵」とも述べたといいます。
◆幹部自衛官が議員罵倒
小西氏は国会で、南スーダンやイラクに派遣された陸上自衛隊部隊の日報をめぐる
組織的隠蔽(いんぺい)を厳しく追及していました。 それに対する抗議だったのでしょう。
問題は、男が自衛隊の統合幕僚監部に勤める中堅幹部だったことです。
統合幕僚監部といえば、陸海空三自衛隊で構成する自衛隊運用の要。
男は30代の三佐で、いわゆる「エリート自衛官」でした。
将来、自衛隊の大組織を率いる立場に就くかもしれない者が、国会近くの公道で、
国民の代表である国会議員を罵倒する姿は、背筋がゾッとする異様な光景です。
自衛隊員も国民の一人です。
内心の自由はもちろん憲法で保障されてはいますが、その政治的活動は法律などで厳しく制限されています。
自衛隊法61条は、選挙権の行使以外の政治的行為を禁じています。
自衛官が公道で議員活動を糾弾するのは、政治的中立を逸脱し、明らかに自衛隊法違反です。
品位の保持を求めた同法58条にも反します。
法律にのっとって、厳しく処分するのは当然です。
この問題を軽視できないのは、自衛官の行為が文民統制を揺るがす危険な芽を宿すからです。
◆旧軍に政治介入の歴史
自衛隊は憲法上、「軍」ではありませんが、世界でも有数の「武力」を有する実力組織です。
その行使は慎重の上にも慎重でなければなりません。
それを担保する仕組みが、主権者の代表が実力組織を統制する文民統制、いわゆるシビリアンコントロールです。
日本の場合、国民を代表する国会が自衛官組織の在り方を法律や予算の形で議決し、
防衛出動など活動の是非を決めます。
国の防衛に関する事務は内閣の行政権に属し、
自衛隊に対する指揮監督権を有する首相や隊務を統括する防衛相らの閣僚は、文民でなければならないと、
憲法は定めています。
つまり、野党といえども国会議員は、すべての自衛隊員が従うべき、文民統制の要なのです。
なぜこのような仕組みが、戦後日本の民主主義体制で採用されたのでしょう。
それは先の大戦の反省からにほかなりません。
戦前の日本でも軍人の政治関与は戒められていました。
明治憲法下でも「軍の編制や予算に関しては内閣統制および議会統制が一応機能していた」
(纐纈厚著「暴走する自衛隊」)といいます。
しかし1930年、ロンドン海軍軍縮条約調印は天皇の統帥権を侵すものだとして、
野党や右翼が浜口雄幸内閣を激しく攻撃した「統帥権干犯問題」を契機に、軍部は政治介入を強めます。
1932年には海軍の青年将校らが首相官邸に乱入し、犬養毅首相を殺害する「五・一五事件」、
1936年には陸軍の青年将校らが官邸などを襲撃し、高橋是清蔵相らを殺害する「二・二六」事件が起きました。
その後、政治は軍部に抵抗する力を失い、軍部独裁の下、
日本人だけで約310万人の犠牲者を出した「太平洋戦争」に突入します。
武力を有する実力組織に身を置く者が、自分の意に反する政治家を面罵する姿は、
政治に介入していった旧日本軍に重なります。
戦争放棄と戦力不保持の憲法施行から71年。
米国と軍事同盟の安全保障条約を結び、自衛隊を保持するに至りましたが、
専守防衛に徹することで、他国に脅威を与える軍事大国にならず、地域の平和と安定を維持してきました。
◆いつか来た道歩む前に
一方、自民党内では安倍晋三首相の意を受けて憲法に自衛隊を明記する改憲論議が進みます。
自衛隊が明記されるだけで何も変わらないのか、
抑制的に振る舞ってきた自衛隊のタガがはずれないか、
国民の心配は尽きません。
しかし、自衛隊トップの河野克俊統合幕僚長はこの案を「ありがたい」と述べました。
従来なら指弾された政治への言及を容認する空気が幹部自衛官の暴言の背景にあるとしたら、事態は深刻です。
文民統制は堅持すべき憲法の精神です。
それを揺るがす、如何なる言動も絶対に見過ごしてはならない。
「いつか来た道」を歩みだしてからでは遅いのです。
------------------------------------------------------------------------------
しばらくシリアスな話が続きます。
でも、「いつか来た“狂気の道”を辿ることのないように
話しておかなければならない事です。
どうぞお付き合いください。
「憲法を考える 『文民統制』が揺らぐ」
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018050102000140.html
文民統制。
軍事組織が主権者代表の統制に従うのは民主主義国家の基本原理ですが、
それを危うくしかねない動きも目立ちます。
日本国憲法の危機です。
その出来事は2018年4月16日午後9時前に起きました。
国会近くの参院議員会館を出た小西洋之参院議員に、男が現職の自衛官だと名乗った上で、罵倒したのです。
「国のために働け」
「あなたがやっていることは国益を損なうことじゃないか」
「ばかなのか」
男は最終的には発言を撤回しましたが、小西氏によると罵声は約20分間続き、
男は小西氏に「国民の敵」とも述べたといいます。
◆幹部自衛官が議員罵倒
小西氏は国会で、南スーダンやイラクに派遣された陸上自衛隊部隊の日報をめぐる
組織的隠蔽(いんぺい)を厳しく追及していました。 それに対する抗議だったのでしょう。
問題は、男が自衛隊の統合幕僚監部に勤める中堅幹部だったことです。
統合幕僚監部といえば、陸海空三自衛隊で構成する自衛隊運用の要。
男は30代の三佐で、いわゆる「エリート自衛官」でした。
将来、自衛隊の大組織を率いる立場に就くかもしれない者が、国会近くの公道で、
国民の代表である国会議員を罵倒する姿は、背筋がゾッとする異様な光景です。
自衛隊員も国民の一人です。
内心の自由はもちろん憲法で保障されてはいますが、その政治的活動は法律などで厳しく制限されています。
自衛隊法61条は、選挙権の行使以外の政治的行為を禁じています。
自衛官が公道で議員活動を糾弾するのは、政治的中立を逸脱し、明らかに自衛隊法違反です。
品位の保持を求めた同法58条にも反します。
法律にのっとって、厳しく処分するのは当然です。
この問題を軽視できないのは、自衛官の行為が文民統制を揺るがす危険な芽を宿すからです。
◆旧軍に政治介入の歴史
自衛隊は憲法上、「軍」ではありませんが、世界でも有数の「武力」を有する実力組織です。
その行使は慎重の上にも慎重でなければなりません。
それを担保する仕組みが、主権者の代表が実力組織を統制する文民統制、いわゆるシビリアンコントロールです。
日本の場合、国民を代表する国会が自衛官組織の在り方を法律や予算の形で議決し、
防衛出動など活動の是非を決めます。
国の防衛に関する事務は内閣の行政権に属し、
自衛隊に対する指揮監督権を有する首相や隊務を統括する防衛相らの閣僚は、文民でなければならないと、
憲法は定めています。
つまり、野党といえども国会議員は、すべての自衛隊員が従うべき、文民統制の要なのです。
なぜこのような仕組みが、戦後日本の民主主義体制で採用されたのでしょう。
それは先の大戦の反省からにほかなりません。
戦前の日本でも軍人の政治関与は戒められていました。
明治憲法下でも「軍の編制や予算に関しては内閣統制および議会統制が一応機能していた」
(纐纈厚著「暴走する自衛隊」)といいます。
しかし1930年、ロンドン海軍軍縮条約調印は天皇の統帥権を侵すものだとして、
野党や右翼が浜口雄幸内閣を激しく攻撃した「統帥権干犯問題」を契機に、軍部は政治介入を強めます。
1932年には海軍の青年将校らが首相官邸に乱入し、犬養毅首相を殺害する「五・一五事件」、
1936年には陸軍の青年将校らが官邸などを襲撃し、高橋是清蔵相らを殺害する「二・二六」事件が起きました。
その後、政治は軍部に抵抗する力を失い、軍部独裁の下、
日本人だけで約310万人の犠牲者を出した「太平洋戦争」に突入します。
武力を有する実力組織に身を置く者が、自分の意に反する政治家を面罵する姿は、
政治に介入していった旧日本軍に重なります。
戦争放棄と戦力不保持の憲法施行から71年。
米国と軍事同盟の安全保障条約を結び、自衛隊を保持するに至りましたが、
専守防衛に徹することで、他国に脅威を与える軍事大国にならず、地域の平和と安定を維持してきました。
◆いつか来た道歩む前に
一方、自民党内では安倍晋三首相の意を受けて憲法に自衛隊を明記する改憲論議が進みます。
自衛隊が明記されるだけで何も変わらないのか、
抑制的に振る舞ってきた自衛隊のタガがはずれないか、
国民の心配は尽きません。
しかし、自衛隊トップの河野克俊統合幕僚長はこの案を「ありがたい」と述べました。
従来なら指弾された政治への言及を容認する空気が幹部自衛官の暴言の背景にあるとしたら、事態は深刻です。
文民統制は堅持すべき憲法の精神です。
それを揺るがす、如何なる言動も絶対に見過ごしてはならない。
「いつか来た道」を歩みだしてからでは遅いのです。
------------------------------------------------------------------------------
しばらくシリアスな話が続きます。
でも、「いつか来た“狂気の道”を辿ることのないように
話しておかなければならない事です。
どうぞお付き合いください。