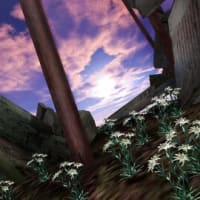北海道新聞 2018年11月16日付記事
「沿線協議、見えぬ決着 JR単独維持困難路線、公表2年 廃線合意2区間/地元支援、議論停滞」
JR北海道が「単独では維持困難」な10路線13区間を発表してから今月18日で2年が経過する。
これまでにJRが廃線を提案した5区間で合意したのは2区間。
国、地元支援による存続を打ち出した8区間では自治体の負担額を巡る議論が進まない。
JRが2021年度以降も国の財政支援を受け続けるには、維持困難路線見直しを通じた収支改善の取り組みが求められているが、
沿線協議決着への道筋は見えない。
■バス転換5区間
2015年1月に高波被害を受けて以来不通が続く日高線鵡川―様似間。
2017年2月に廃線提案を受けた沿線7町はJRとの協議入りはせず、自治体間での議論を積み重ねてきた。
現在は 《1》全線復旧し存続
《2》鵡川~日高門別間を復旧し残りをバス転換
《3》全線バス転換― の3案に絞り、今月末の方針決定を目指す。
不通から4年近くたち、ある町長は「『そろそろ決着を』との町民の声が強まっている」と疲れをにじませる。
一方、さらなる先送りを求める意見もあり、月内に結論が出るかは不透明だ。
JRが廃線・バス転換を打ち出した5区間のうち、
地元が廃止に合意したのは石勝線新夕張~夕張間(来年4月廃止)と札沼線北海道医療大学~新十津川間(廃止時期未定)。
留萌線深川~留萌間は、沿線4市町が路線存続や廃線の場合の費用などについて、ようやくJRからの説明を受け始めた段階だ。2016年夏の台風被害で運休中の根室線富良野~新得間では、沿線自治体が観光列車の運行を求めて復旧、存続を訴え、
JRと折り合いがつかない状態が続く。
■存続方針8区間
JRが国や地元支援を受け存続方針を示す8区間のうち6区間では、沿線自治体が利用促進や経費節減に向けたJRとの協議に入っているか、近く入る。
宗谷線は、いち早く昨年4月に協議を開始。沿線自治体の財政負担や無人駅、踏切の管理見直しなどの具体的な議論に入っている。
協議入りの見通しが立たない2区間は、根室線「滝川~富良野」間と日高線「苫小牧~鵡川」間。
根室線はJRが廃線方針の「富良野~新得」間と続いており、沿線自治体が合わせて検討しているため
JRとは実務者レベルの意見交換にとどまる。
日高線は、沿線自治体が胆振東部地震の震源地近くで、災害対応で検討が遅れているという。
合わせて年約130億円の赤字を出す8区間の最大の課題は維持に向けた地元からの支援額だ。
国は存続に向けて道、市町村の合計額と同規模の額を支援する方針だが、
国、道、JRのいずれも支援額自体への言及を避けている。
国は「支援は地元が主導すべきだ」、
道は「国が主導すべきだ」、
JRは「支援を受ける側からは言えない」 との立場を崩さない。
自治体負担分を地方交付税などで穴埋めする地方財政措置も定まっておらず、だれも具体的な支援規模を打ち出さないため、
議論は停滞している。
■収支改善へ計画
支援額の議論が進まない中、JRは収支改善へ、利用促進策などを盛り込んだ各区間ごとの「アクションプラン(行動計画)」を、沿線自治体と年度内に策定したい考えだ。
自家用車を使わない日を設定する「ノーマイカーデー」の実施や、
鉄道利用の買い物客への自治体からの運賃補助など具体案をJR側から提示し、働きかけを強める。
鉄路存続へ、JRの投げかけを前向きに受け止める首長も少なくない。
一方で、「地元負担額が決まらないのに、住民に利用促進のお願いなどできない」(道北の首長)との声も上がり、
自治体が一枚岩でJRに協力する体制にはなりにくい状況だ。
(文章執筆:徳永仁)
◇
■釧網線・鉄道バス乗り放題パス バス会社提案「移動そのものを観光に」
JR北海道が国と地元の財政支援を受けて存続する方針の8区間の一つ、釧網線東釧路~網走間では、
高速バス大手のウィラー(大阪市)が今秋、鉄道とバスが乗り放題になるパスを試験販売した。
10月下旬、同社など主催の視察ツアーに参加し、観光で鉄道利用を伸ばす取り組みに触れた。
販売したのは釧路~網走間の列車が2日間、沿線発着で観光地を巡る一部のバスがそのうち1日、乗り放題となるパス。
利用は9、10月に限定し、中学生以上9,800円で販売。
胆振東部地震の影響もあったが約300人が利用した。
ツアーには観光業者や自治体関係者など約100人が参加。
初日は網走市内から地元企業のバスで知床半島を回り、屈斜路湖まで移動して宿泊。
2日目はウィラーのレストランバスで阿寒摩周国立公園を巡り、釧網線川湯温泉駅から釧路駅までは鉄道に乗った。
2日間の移動距離は350キロ。
疲れはしたが、道東の大自然を落ち着いて堪能できた。
ウィラーの村瀬茂高社長は「自ら運転しないJRやバスは景観を楽しむのに適しており、移動そのものが観光になる」と述べ、
年明けに再度、パス販売に取り組むとした。
ツアーの最後に釧路市内で開かれた懇談会では、釧路市の名塚昭副市長が「釧網線を残すには観光資源の活用が不可欠」と強調。
村瀬社長は「バスやタクシーを効率的に使い、1、2年で沿線と観光地間の交通を整備したい」と、今後も釧網線に関わる考えを示した。
ある参加者が「沿線関係者はJRやウィラーが何をしてくれるかを待っている。当事者意識が足りない」と指摘していたのが印象的だった。
(文章執筆:五十地隆造)
<ことば>『単独維持困難路線』
⇒JR北海道が赤字が大きく自力では「維持困難」として2016年11月18日に公表した10路線13区間。
道内路線の半分の1,237.2キロにおよぶ。
JRは輸送密度(1キロ当たり1日平均輸送人数)が200人未満の5区間は「廃線・バス転換」方針で、
輸送密度200人以上2,000人未満の8区間は「地元負担前提で鉄路を維持する」方針。
国は今年7月、JRの経営難を受け、2019、2020年度の2年間で総額4000億円台の支援を決めた。
2021年度以降の支援は、今後の収支改善や路線見直しの推移を見て検討するとしている。
------------------------------------------------------------------------------
何度でも言うが、じれったい!!
救いなのが宗谷線沿線の積極的さで、それがあるから佐川急便と「旅客&貨物共同運行」案が出たことだ。
自分はやはり「富良野~新得間」を含む「旭川~帯広間」の「狩勝」を特別快速化して、同様に「旅客&貨物共同運行」すれば
一気に活用されるだろう。
それから、「日高線」は存続するのならサラブレッド育成が有名で観光地でもある「静内」までは残さないと意味がない。
あと、大半の路線が「普通=各駅停車」なのも自分は気になる。
それが時間がかかって「それならいっそマイカーのほうが速い」と考えられてしまうのなら「快速化」してしまって、毎日一定の乗降客が見込めない駅を廃止するのも、鉄道存続する為ならやむを得ないのかもしれない。
とにかく気になるのが、JR北海道も道庁関係者も札幌の本部&庁舎から一歩も現場に出ずふんぞり返って見下す態度だ。
慇懃無礼(インギンブレイ)もいいとこで、気に入らない。
あと困る事がある。
バス転換対象路線の「留萌線」「日高線」沿線の高速道路「深川留萌自動車道」「日高自動車道」が無料で走行できてしまい、
これが両路線の乗客を一層失くしているのだと思う。
道庁も沿線自治体関係者も、本気で鉄道を守りたいのか⁈
自分たち鉄道ファンが声を高々に保存を訴えても、彼等や沿線住民が使おうと思わない限り結果「時間切れ=廃線」に
なり兼ねないのに。
参考ブログ:「K'z Lifelog」より2018年9月24日付
「留萌本線(深川~留萌)乗車レポート! 廃止危機のローカル線は峠を越えて海へと続く」
https://www.kzlifelog.com/entry/jrh-rumoi-line-report
:「K'z Lifelog」より2018年8月8日付
「JR北海道が資金難で電気式気動車『H100形』の導入を見送りへ! 普通列車の運行への影響は? 」
https://www.kzlifelog.com/entry/jrh-h100-postpone
ただでさえエアコンがないから評判悪いのに燃費も悪い交換部品もない”お荷物”的存在のキハ40系。
それを維持するために新車導入を見送る!?
マズいぞ……、かえってJR北海道は「負の連鎖」の泥沼にハマってゆくぞ……
そんな柔軟性がないJR北海道に整備新幹線の維持運営なんて危険であり、
北海道新幹線はJR東日本に任せて、JR北海道はJR九州の要人に学びつつ在来線の運営と業務改善に徹するべきだ。
2018年11月18日付訪問者数:158名様
お付き合いいただきありがとうございました。
「沿線協議、見えぬ決着 JR単独維持困難路線、公表2年 廃線合意2区間/地元支援、議論停滞」
JR北海道が「単独では維持困難」な10路線13区間を発表してから今月18日で2年が経過する。
これまでにJRが廃線を提案した5区間で合意したのは2区間。
国、地元支援による存続を打ち出した8区間では自治体の負担額を巡る議論が進まない。
JRが2021年度以降も国の財政支援を受け続けるには、維持困難路線見直しを通じた収支改善の取り組みが求められているが、
沿線協議決着への道筋は見えない。
■バス転換5区間
2015年1月に高波被害を受けて以来不通が続く日高線鵡川―様似間。
2017年2月に廃線提案を受けた沿線7町はJRとの協議入りはせず、自治体間での議論を積み重ねてきた。
現在は 《1》全線復旧し存続
《2》鵡川~日高門別間を復旧し残りをバス転換
《3》全線バス転換― の3案に絞り、今月末の方針決定を目指す。
不通から4年近くたち、ある町長は「『そろそろ決着を』との町民の声が強まっている」と疲れをにじませる。
一方、さらなる先送りを求める意見もあり、月内に結論が出るかは不透明だ。
JRが廃線・バス転換を打ち出した5区間のうち、
地元が廃止に合意したのは石勝線新夕張~夕張間(来年4月廃止)と札沼線北海道医療大学~新十津川間(廃止時期未定)。
留萌線深川~留萌間は、沿線4市町が路線存続や廃線の場合の費用などについて、ようやくJRからの説明を受け始めた段階だ。2016年夏の台風被害で運休中の根室線富良野~新得間では、沿線自治体が観光列車の運行を求めて復旧、存続を訴え、
JRと折り合いがつかない状態が続く。
■存続方針8区間
JRが国や地元支援を受け存続方針を示す8区間のうち6区間では、沿線自治体が利用促進や経費節減に向けたJRとの協議に入っているか、近く入る。
宗谷線は、いち早く昨年4月に協議を開始。沿線自治体の財政負担や無人駅、踏切の管理見直しなどの具体的な議論に入っている。
協議入りの見通しが立たない2区間は、根室線「滝川~富良野」間と日高線「苫小牧~鵡川」間。
根室線はJRが廃線方針の「富良野~新得」間と続いており、沿線自治体が合わせて検討しているため
JRとは実務者レベルの意見交換にとどまる。
日高線は、沿線自治体が胆振東部地震の震源地近くで、災害対応で検討が遅れているという。
合わせて年約130億円の赤字を出す8区間の最大の課題は維持に向けた地元からの支援額だ。
国は存続に向けて道、市町村の合計額と同規模の額を支援する方針だが、
国、道、JRのいずれも支援額自体への言及を避けている。
国は「支援は地元が主導すべきだ」、
道は「国が主導すべきだ」、
JRは「支援を受ける側からは言えない」 との立場を崩さない。
自治体負担分を地方交付税などで穴埋めする地方財政措置も定まっておらず、だれも具体的な支援規模を打ち出さないため、
議論は停滞している。
■収支改善へ計画
支援額の議論が進まない中、JRは収支改善へ、利用促進策などを盛り込んだ各区間ごとの「アクションプラン(行動計画)」を、沿線自治体と年度内に策定したい考えだ。
自家用車を使わない日を設定する「ノーマイカーデー」の実施や、
鉄道利用の買い物客への自治体からの運賃補助など具体案をJR側から提示し、働きかけを強める。
鉄路存続へ、JRの投げかけを前向きに受け止める首長も少なくない。
一方で、「地元負担額が決まらないのに、住民に利用促進のお願いなどできない」(道北の首長)との声も上がり、
自治体が一枚岩でJRに協力する体制にはなりにくい状況だ。
(文章執筆:徳永仁)
◇
■釧網線・鉄道バス乗り放題パス バス会社提案「移動そのものを観光に」
JR北海道が国と地元の財政支援を受けて存続する方針の8区間の一つ、釧網線東釧路~網走間では、
高速バス大手のウィラー(大阪市)が今秋、鉄道とバスが乗り放題になるパスを試験販売した。
10月下旬、同社など主催の視察ツアーに参加し、観光で鉄道利用を伸ばす取り組みに触れた。
販売したのは釧路~網走間の列車が2日間、沿線発着で観光地を巡る一部のバスがそのうち1日、乗り放題となるパス。
利用は9、10月に限定し、中学生以上9,800円で販売。
胆振東部地震の影響もあったが約300人が利用した。
ツアーには観光業者や自治体関係者など約100人が参加。
初日は網走市内から地元企業のバスで知床半島を回り、屈斜路湖まで移動して宿泊。
2日目はウィラーのレストランバスで阿寒摩周国立公園を巡り、釧網線川湯温泉駅から釧路駅までは鉄道に乗った。
2日間の移動距離は350キロ。
疲れはしたが、道東の大自然を落ち着いて堪能できた。
ウィラーの村瀬茂高社長は「自ら運転しないJRやバスは景観を楽しむのに適しており、移動そのものが観光になる」と述べ、
年明けに再度、パス販売に取り組むとした。
ツアーの最後に釧路市内で開かれた懇談会では、釧路市の名塚昭副市長が「釧網線を残すには観光資源の活用が不可欠」と強調。
村瀬社長は「バスやタクシーを効率的に使い、1、2年で沿線と観光地間の交通を整備したい」と、今後も釧網線に関わる考えを示した。
ある参加者が「沿線関係者はJRやウィラーが何をしてくれるかを待っている。当事者意識が足りない」と指摘していたのが印象的だった。
(文章執筆:五十地隆造)
<ことば>『単独維持困難路線』
⇒JR北海道が赤字が大きく自力では「維持困難」として2016年11月18日に公表した10路線13区間。
道内路線の半分の1,237.2キロにおよぶ。
JRは輸送密度(1キロ当たり1日平均輸送人数)が200人未満の5区間は「廃線・バス転換」方針で、
輸送密度200人以上2,000人未満の8区間は「地元負担前提で鉄路を維持する」方針。
国は今年7月、JRの経営難を受け、2019、2020年度の2年間で総額4000億円台の支援を決めた。
2021年度以降の支援は、今後の収支改善や路線見直しの推移を見て検討するとしている。
------------------------------------------------------------------------------
何度でも言うが、じれったい!!
救いなのが宗谷線沿線の積極的さで、それがあるから佐川急便と「旅客&貨物共同運行」案が出たことだ。
自分はやはり「富良野~新得間」を含む「旭川~帯広間」の「狩勝」を特別快速化して、同様に「旅客&貨物共同運行」すれば
一気に活用されるだろう。
それから、「日高線」は存続するのならサラブレッド育成が有名で観光地でもある「静内」までは残さないと意味がない。
あと、大半の路線が「普通=各駅停車」なのも自分は気になる。
それが時間がかかって「それならいっそマイカーのほうが速い」と考えられてしまうのなら「快速化」してしまって、毎日一定の乗降客が見込めない駅を廃止するのも、鉄道存続する為ならやむを得ないのかもしれない。
とにかく気になるのが、JR北海道も道庁関係者も札幌の本部&庁舎から一歩も現場に出ずふんぞり返って見下す態度だ。
慇懃無礼(インギンブレイ)もいいとこで、気に入らない。
あと困る事がある。
バス転換対象路線の「留萌線」「日高線」沿線の高速道路「深川留萌自動車道」「日高自動車道」が無料で走行できてしまい、
これが両路線の乗客を一層失くしているのだと思う。
道庁も沿線自治体関係者も、本気で鉄道を守りたいのか⁈
自分たち鉄道ファンが声を高々に保存を訴えても、彼等や沿線住民が使おうと思わない限り結果「時間切れ=廃線」に
なり兼ねないのに。
参考ブログ:「K'z Lifelog」より2018年9月24日付
「留萌本線(深川~留萌)乗車レポート! 廃止危機のローカル線は峠を越えて海へと続く」
https://www.kzlifelog.com/entry/jrh-rumoi-line-report
:「K'z Lifelog」より2018年8月8日付
「JR北海道が資金難で電気式気動車『H100形』の導入を見送りへ! 普通列車の運行への影響は? 」
https://www.kzlifelog.com/entry/jrh-h100-postpone
ただでさえエアコンがないから評判悪いのに燃費も悪い交換部品もない”お荷物”的存在のキハ40系。
それを維持するために新車導入を見送る!?
マズいぞ……、かえってJR北海道は「負の連鎖」の泥沼にハマってゆくぞ……
そんな柔軟性がないJR北海道に整備新幹線の維持運営なんて危険であり、
北海道新幹線はJR東日本に任せて、JR北海道はJR九州の要人に学びつつ在来線の運営と業務改善に徹するべきだ。
2018年11月18日付訪問者数:158名様
お付き合いいただきありがとうございました。