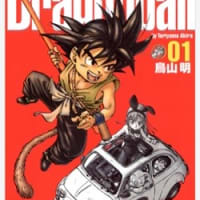その夜、千歌音は湯殿にひとり浸かっていた。
姫宮の洋館の湯殿はとにかく大きい。三十畳もの広さがある大浴場である。
すでにそこに佇んで何時間が経つだろうか。
湯はすっかり冷めて、水に近くなっているが、千歌音にはもはや冷たさも感じなかった。このぬるま湯のなかから、裸で出ていくことのほうがそら恐ろしかった。千歌音は湯の中に顔をつけたり、頭を沈めたり、そんなことばかりを繰り返していた。水のなかに潜り、ものの数分もするだけで、息苦しくなる。視界がぼんやりとして、泡ぶくだらけになる。だが、自分の重さを忘れたように、ふわふわとしてくる。皮膚がほぐれて、世界と自分との境目がなくなり、溶けていく。このまま、自分というものがなくなってしまうと、どうなってしまうのだろうか。そのほうがいっそ楽なのではないだろうか。延々とそんなことばかり、考えつづけては水に潜っている。
「…ね。…ち、…か、ね」
「ひめこ…ひめ、こ…」
「…すけて。たすけて…」
それは、自分の名を呼ぶ声? それとも、自分が叫ぶ声?
水のなかでもがくような喘ぎ声が聞こえてくる。最初は不気味だったが、しだいに耳慣れた。まるでそれが親しいものであるかのように、千歌音はその声に近づくために、水のなかに没していた。と、そのとき。誰かが、水のなかからぐい、と腕を引っ張ったのだ。絶望の井戸に囚われた我が身をすくう光りある手。それはあの人に違いない。だが、それは姫子──ではなかった。
濡れた髪のまま湯殿の椅子に座らされた千歌音は、木偶人形のようだった。
精気を失ったまま、その瞳は光りを失っている。乙羽は甲斐甲斐しく、千歌音の裸身をシャボンで洗い上げた。ひとびとの悪意で汚された千歌音のからだは、磨きあげられ、輝きを取り戻した。しかし、その顔いろだけはいまだ冴えない。
乙羽は真新しい長襦袢を、千歌音の肩に掛け、袖を通させた。
ていねいにからだを拭いたので、滴ひとつ、その玉の肌には残っていない。乙羽はまるで傑作の彫像を扱うかのように、恍惚とした面持ちでその仕事をやってのけた。後ろから腕を回して帯を結び、手早く、襟も整えてくれた。千歌音はうなだれたまま、ありがとう、と呟いただけだった。ふと、乙羽は独り言めいてみせた。夜半に沁み入るような声で。
「お嬢さまはお疲れですね。お可哀想に。なんと哀れなお嬢さま。貴女様はこんなにもお美しいのに」
「そうね、そうかもね…」
千歌音の言葉には覇気がない。
子どもが親の言葉を復唱するかのように、頷くだけだ。乙羽といる時間が長くなるにつれて、千歌音はかつてやっていた身の回りの世話をすべて任せっきりにして、動かなくなった。まるで、以前の活き人形のような時代に逆行したかのようだ。侍り女がどんなに洗い上げても、その肌は白くはあるが、古くなった餅を思わせるように固い。