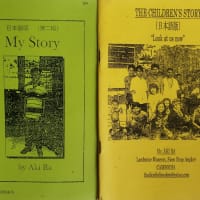セクハラ・パワハラの告発はジャニーズ、宝塚、松本人志(吉本興業)などを経てもはや社会現象になりつつあるが、これまで閉鎖空間の中で散々治外法権のように振舞ってきた業界だから、これからいくらでも出てくるものと思われる。
特に最後の動画にもあるように、タレントそのものだけでなく、監督やプロデューサー、そしてテレビ局員といったそれを取り巻く人間たちまで含めれば、その量と波及効果は極めて大きなものとなっていくのではないだろうか。
ところで私が考えているのは、ここにそう遠くない将来、「学生時代のいじめ」も含まれるようになる可能性が高い、ということだ。「いや、大人になってからの行為ならともかく、未成年の時の行為まで告発・非難の対象になるのか?」と思われるかもしれないが、韓国ではアイドルが学生時代にいじめを行っていたと大人になってから告発されるケースが何度も報道されており、後に謝罪するというケースもある(もちろん何度も述べている通り、「告発=真実とは限らない」点は注意が必要だが)。
そして日本でも、最近ジャンポケ斎藤による小・中学生時代のいじめの話が話題となり、いじめに加担していた人間から電話がきて、それが卑劣で手前勝手な保身に終始する内容だったこともあり、すでにそれらの人物を特定する動きまで出ているらしい(以前このような動きで、間違った人物を犯人だと思い込んで無実の人間を追い込んだ事例もあるため、私はこういう動きには賛同できないが)。
であるならば、今やるべきことは、学校の現場で今述べたような情報を子供に伝えてあげればよいのではないかと思う。すなわち、
「今の一時的な衝動で他者に害を加えると、将来あなたが成功するほど告発によって社会的制裁のリスクを負い続けることになる。いや、それだけならまだいい。世間から厳しい目を向けられた結果、職場にいづらくなったり家族さえ社会から袋叩きにされる中で、社会的に居場所が無くなってしまう(抹殺される)かもしれないよ。今のあなたの行為は、自分だけで責任を取れば済む問題じゃないんだ。それでも、あなたは、いじめをやりますか?」
と。
前にも書いたことがあるが、今の子たちは「空気読め」文化の残存と、一方で共有前提の崩壊により相手のどこまで踏み込んでいいかわからない怯えと承認の枯渇に苛まれており、それもあって「ゼロリスク世代」、つまりリスクに敏感な世代だと言われている(だから出る杭にならないよう徹底して気を回す)。その見立てが正しいなら、この話は覿面に効くと思うけどね(ちなみに子どもがやったことだからお目こぼしを・・・と思う向きもあるだろうが、自転車事故など含め子どもが起こした損害をそのまま請求するケースも増えており、もはや共同体の成員ではなく「ただ近くに住んでいる人」ぐらいでしかなくなっている今日、加害者の未熟さを理由になあなあで済まされる状況は終わりを迎えつつあると思われる)。
なお、私が今回こういう話を書いているのは、「道徳心」とやらに訴えてやめる人ならそれでよいが、問題は、それに従わない人間のコントロールにあるからだ。そういう観点で言えば、自分が行うことのリスクを具体的な事例を元に淡々と説明すれば、それなりに理解力のある向きには伝わると思うけどね。
そしてもちろん、スシローや山岡家の迷惑行為のように、あれだけ報道されててもつい出来心でやってしまう人間はいる(誤解を恐れずに言えば、いじめもゼロには決してならないが、それは現状維持を肯定する理由には全くならない)。そういうリスクヘッジを理解しない・できない人間は、然るべき手続きの上で制裁を加えればよいのである(実際該当者たちは退学だのになっているようなので)。
これも何度も書いていることだが、共通前提が崩壊した成熟社会においては、そもそも同じ人間と集団生活をずーっと続けさせられるということ自体が大きなストレスとなりやすい(それは少子化にもかかわらず、不登校児が増えていることにも表れている)。それなのに、相も変わらず学校という場所が近代の兵隊を養成する機関(パノプティコン)としての性質を強く残していることがそもそも問題だと言える。
また学校教師がハードワークすぎて、成り手の減少・不足が問題になっていることもよく知られている通りだ。それは部活や日報など業務の引き算がほとんどないのに、ICT化による指導形体の変更などやる事ばかり増えているからであり、そんな状況下でクラス運営をきめ細やかにやるとなれば、もはや個人に自分の生活を犠牲にするような仕事ぶりを期待するしかない(その観点で言えば、AIによる授業や映像授業の導入を通じて教師の授業負担を減らし、他の領域にリソースを割けるようにする、というのも一つの手だろう)。
要するに、現在の学校が、システムとしてすでに限界を迎えているのである。ゆえに本来、移動教室などで離れる機会を設けることでガス抜きをするとか、第三者を学校に入れることで生徒はもちろん教師の監視を行い、トラブル防止の際には内々で解決しようとせず、公共機関を頼ることを厭わない(ステークホルダーたちがもみ消すのを防止する)仕組み作りをする・・・といった根治に向けた変革が必要なのだが、教育というのは社会の中でも最も変化に時間がかかる分野の一つとも言われている。
そういった観点から、ひとまずは加害行為の将来を含めたリスクの周知によって、いじめという名の集団暴行・嫌がらせへの歯止めとするしかないと思われる。
以上。