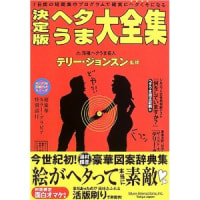三浦展の「仕事をしなければ、自分は見つからない。フリター世代の生きる道」で若者の食べ歩き、地面で寝る、座り込んで団欒するなどの姿が写真入りでレポートされている。それにつづいて、その姿から、かれらの自由、気ままさ、常識や規範の弛緩、そこからくる働く意欲の放棄、豊満、飽食の文明がもたらす知性の退化を問題にする。かれらの生き方は今や、食べたいから食べ、寝たいから寝るという本能的な生き方と化しているというのである。
そこでちょっと待てといいたい。まずこの食べ歩き、地面で寝る、座りこむ、飲み食い談笑する、かれの言う「ジベタリアン」その他、ガングロからコギャルまでの生態は、場所と時が
限定されているということである。まわりの状況次第によって、かれらは食べ歩きとジベタりアンをやっているにすぎないのである。もし退化した本能的なライフスタイルならば、それはどこでも見られる生活の姿態となっているはずであろう。
宮崎市では、街路でそのような行動は、ほとんど見られないが、三浦展の観察もまた、東京の盛り場での若者の行為と限定されているにすぎない。となると、それは、巨大都市で人の目が気にならぬ街路、孤立してしまった自己やグループだけの場を生み出そうというそれこそ帰巣の「本能」ということかもしれない。それは動物的と非難されるよりも、人間疎外から自分を守る人間的行為ということになる。
つまり若者はきわめて正常なのである。その若者たちにはフリーターになるしか、仕事がないということが、最大の問題なのである。そして、フリーターとなったら、生活は低賃金のままに据え置かれ、過酷な労働と報われぬ単純労働の結果、貧困になり、貧困ゆえに向上のエネルギーもうばわれ、下流社会という階層となっていくという現実は確かにある。ということは若者の知性や意思の欠陥からもたらされるということよりも、会社のあり方のほうに問題があるということにならないか。
ところで、2005年3月発行の本書から半年遅れの2005年8月に同じ著者の「下流社会 新たな階層集団の出現」が発行されている。この本では、下流に下がっていった若者の性格分析が詳細に展開された。この本も明快だ。下流に陥る性格の分析である。自分らしく生きる意欲は下流になるということの論証である。これもわかったようで、だんだん分からなくなる。結論をくみ上げていく材料が、ひどくあいまいである。
そこでちょっと待てといいたい。まずこの食べ歩き、地面で寝る、座りこむ、飲み食い談笑する、かれの言う「ジベタリアン」その他、ガングロからコギャルまでの生態は、場所と時が
限定されているということである。まわりの状況次第によって、かれらは食べ歩きとジベタりアンをやっているにすぎないのである。もし退化した本能的なライフスタイルならば、それはどこでも見られる生活の姿態となっているはずであろう。
宮崎市では、街路でそのような行動は、ほとんど見られないが、三浦展の観察もまた、東京の盛り場での若者の行為と限定されているにすぎない。となると、それは、巨大都市で人の目が気にならぬ街路、孤立してしまった自己やグループだけの場を生み出そうというそれこそ帰巣の「本能」ということかもしれない。それは動物的と非難されるよりも、人間疎外から自分を守る人間的行為ということになる。
つまり若者はきわめて正常なのである。その若者たちにはフリーターになるしか、仕事がないということが、最大の問題なのである。そして、フリーターとなったら、生活は低賃金のままに据え置かれ、過酷な労働と報われぬ単純労働の結果、貧困になり、貧困ゆえに向上のエネルギーもうばわれ、下流社会という階層となっていくという現実は確かにある。ということは若者の知性や意思の欠陥からもたらされるということよりも、会社のあり方のほうに問題があるということにならないか。
ところで、2005年3月発行の本書から半年遅れの2005年8月に同じ著者の「下流社会 新たな階層集団の出現」が発行されている。この本では、下流に下がっていった若者の性格分析が詳細に展開された。この本も明快だ。下流に陥る性格の分析である。自分らしく生きる意欲は下流になるということの論証である。これもわかったようで、だんだん分からなくなる。結論をくみ上げていく材料が、ひどくあいまいである。