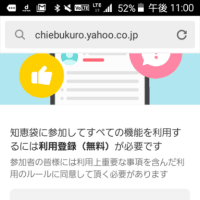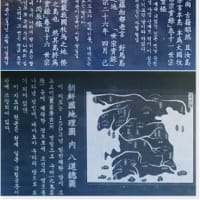ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムというのは、要するにGHQ/SCAPによる日本占領政策の一環として行わた
「戦争についての罪悪感を日本人の心に植えつけるための宣伝計画」
のことで、この存在は日米の公文書により裏付けられています。
(その「評価」についてなら様々な議論があります)
正確には、主にアメリカ本国により、いわゆる「逆コース」と呼ばれる占領政策変更の指示がマッカーサーらGHQに対してなされるまでの間になされたものです。
アメリカ側の当初の占領政策は日本を三等国に落とすというものでした。
このことはSWNCC150/4/AのI - Ultimate Objectives(究極の目的)というところに明記されています。
日本国ニ関スル米国ノ究極ノ目的ニシテ初期ニ於ケル政策が従フベキモノ左ノ如シ
(イ) 日本国ガ再ビ米国ノ脅威トナリ又ハ世界ノ平和及安全ノ脅威トナラザルコトヲ確実ニスルコト
要するに
日本が二度とアメリカに逆らえないようにしろ!
というもので、ある意味マッカーサーらGHQはそれを忠実に果たしました。
結果として、現在でも我が国はアメリカに決して逆らえない国となっているではありませんか。
実際にもマッカーサーらGHQは、冷戦の深刻化にともなうアメリカ本国による指示(いわゆる逆コース)で、やむを得ず日本統治の政策を変更しただけで、それまでは日本を三等国に叩き落とすために血眼になっていました。
また敗戦で打撃を受けた日本に対する苛斂誅求も行っていました。
これが史実です。
まず、マッカーサーは各報道機関にGHQが指示した記事を絶対に報道する様に命令していました。その命令を守らなければ、新聞や雑誌であれば発行部数を減らす処分を行うと脅迫しています。
参考:元毎日新聞東京本社社会部長森正蔵著「あるジャーナリストの敗戦日記」
元読売新聞報道局員高桑 幸吉著「マッカーサーの新聞検閲―掲載禁止・削除になった新聞記事」
マッカーサーによる日本統治政策というのは、それこそ戦前日本も顔負けの検閲などによる言論統制政策でした。
これは歴史学者(主にメディア史)である山本武利氏などによる研究で明らかになっていることであり、決して与太話などではありません。
http://book.asahi.com/reviews/reviewer/2013091500010.html
>GHQ(連合国軍総司令部)は、日本占領終結後にプレス政策をどのように進めたかの報告書をまとめた。そのタイトルが、「プレスの自由」というのだが、著者によればマッカーサーら指導部は、「メディアの自由の浸透に貢献した功績を強調している」という。検閲や自由を抑圧した具体例は極端に記述も少ないそうだ。
日本占領期にGHQの言論弾圧はいかに巧みに行われたか、その巧みさをアメリカのさまざまな機関から収集した記録文書で白日のもとにさらす。著者はその研究では第一人者であり、実際にその現実を解き明かされると大日本帝国型の言論弾圧とは異なる総合的なシステムが用いられていることがわかる。
たとえば検閲の実務には、多数の日本人が動員される。検閲者は4年余りの間に延べ2万5千人近くに及んだという。この実態については、検閲者たちの良心の痛みもあり、戦後社会ではほとんど公開されていない。著者は、そういう検閲者の生の声も紹介している。なにより生活の豊かさの保障の前に、誰もがこの同胞を売るがごとき仕事の屈辱に耐えたとの証言は貴重である。
アメリカの情報統制は、日本社会への軍国主義復活を阻止し、共産主義の国内への浸透を防ぐのを目的にしていたが、それらの目的はすぐに達せられたともいえる。なぜなら当時の日本国民は、GHQが鼓吹している民主主義思想をすぐに受け入れたからだ。その言論弾圧のシステムは国民にはまったく見えない形になっていた。日本の新聞や雑誌なども、当初の事前検閲よりのちに幾分(いくぶん)ゆるやかになる事後検閲に、逆に不安を抱くといった体質もあった。
言論弾圧は、政治的システムのマイナスより、国民の精神やその内面に打撃を与える。日本で用いられた手法は、日本人捕虜の意識調査をもとにして確立されたとの記述は衝撃だ。
→また、マッカーサーらGHQの指示により、敗戦の痛手も癒えない我が国は「終戦処理費」という名目の膨大な経費を負担させられてもいます。
「終戦処理費」については、私自身過去質問で取り上げていますので、虚心に読んでみてください。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13165640118
>結局、この後もマッカーサーの過酷な取り立てにより日本は終戦処理費(笑)という名目で米軍の占領経費を支払い続け、その総額は合計50億ドルに達します。
同時並行で、アメリカは冷戦移行による日本の赤化防止の為、日本の経済発展を促そうと、ガリオア・エロア資金といった有償の資金援助を行いました。この総額が20億ドルでした、しかし、これは後日5億ドル返済を求められましたので(セコい)実際は15億ドルとなり、日本は援助の3倍の額を終戦処理費(笑)として支出さられた
→ちなみに、この「終戦処理費」はアメリカの歴史学者であるジョン・ダワーも著書『敗北を抱きしめて』で取り上げていますが、そのダワーはサンフランシスコ平和条約締結後の日本国について、このように述べています。
>このあと間もなく実施された世論調査では、日本は独立国家になったかとの問いに「はい」と答えた者は41パーセントしかいなかった。
ここにあるのは、ひとつの分裂した国であった。沖縄は文字通り分離されていたし、日本が世界のなかでどんな位置を占めるのかという問題についても、日本人は感情に引き裂かれ不安な状態にあった。しかし、日本人がもっとも分裂したのは、政治に関する考え方の面であった。のちに、吉田茂はこの点を説明するのに分割された朝鮮半島のイメージを借りて、占領は日本人の心に「38度線」を走らせたと述べた。吉田の言葉は、リベラル派や左翼の立場にたつ反政府勢力の登場をさしていた。この反政府勢力は、占領が元来めざした「非軍事化と民主化」の理想をひきつづき追求すべきだと主張し、日本がパックス・アメリカーナに編入されることに反対し、アメリカが保護している保守政治家・官僚・大企業経営者の権力配置に対して、仮責ない批判態度をとっていた。
出典:『敗北を抱きしめて』(下)P411より
ただ、マッカーサーの占領政策があまりにも酷く、さすがに本国であるアメリカでも批判の声があがりました。
例えば、実際にマッカーサーによる日本統治を分析したアメリカの政治学者であり、外交官でもあったジョージ・ケナンは「マッカーサーは日本の産業を不具にし、経済界の指導者を追放することによって災難の種をまいた」とし
「日本社会の安定」あるいは復興に「悪影響を及ぼす」ようなものは許されるべきではない。
と談じています。
またケナンは「GHQの社会改造計画は日本を破滅させる」とも見ていました。
そして短い日本での滞在期間中に占領計画の見直しをし、1949年夏に新占領計画のための提言を文書化し、トルーマン大統領の承認を得ています。
出典:マイケル・シャラー『「日米関係」とは何だったのか』P30~32
占領軍による日本統治がまともな方向に向かうようになったのはそれからです。
が、マッカーサーによる思想統制と、その後の「逆コース」による方針変更は、我が国に深刻な思想的対立をもたらしました。
大まかに言うと
マッカーサーの進めた「改革」を支持する勢力と
「逆コース」以降の、日本従来の安定勢力とに
我が国は分断されたんです。
正直、マッカーサーの悪行については書き足りないくらいなのですが、とりあえずここまでにしておきます。
なお、マッカーサーは日本を非武装のまま放置するつもりでした。
それよりも、彼はさっさと日本での任務を終えて大統領選挙に打って出ようとしており、それを引き留め、駐留延期にこぎつけたのは、昭和天皇の交渉によるものです。
今の我が国の平和は、冷戦による「逆コース」で危機感を抱いたアメリカ本国の方針転換と、何よりも昭和天皇をはじめとする日本人自身の努力の賜物です。
昭和天皇とマッカーサー第4回会見
(昭和22年5月6日)
>天皇はまず、「日本が完全ニ軍備ヲ撤廃スル以上、ソノ安全保障ハ国連ニ期待セネバナリマセヌ」と切り出した上で、しかし「国連ガ極東委員会ノ如キモノデアルコトハ困ルト思ヒマス」と、四大国が拒否権を持っている極東委員会をひき合いに出して、事実上は国連に期待できない旨を強調し、マッカーサーの意見を求めた。
これに対し第九条の挿入に熱意をかけたマッカーサーは、破壊力の飛躍的な増大によって今後の戦争には勝者も敗者もないであろうこと等を指摘した上で、「日本ガ完全ニ軍備ヲ持タナイコト自身ガ日本ノ為ニハ最大ノ安全保障デアツテ、コレコソ日本ノ生キル唯一ノ道デアル」と、改めて‘’第九条の精神‘’を天皇に説いたのである。
出典;豊下楢彦氏『昭和天皇・マッカーサー会見』P52より
→この時点でもマッカーサーは第九条による「日本の非武装」にこだわり、昭和天皇が、それに難色を示していた事がわかります。
約3年後には朝鮮戦争が起こりました。
ちなみに昭和天皇は、かなり早い時期から朝鮮戦争発生の可能性を指摘していた、ともいわれます。
それはともかく
先に挙げたマイケル・シャラーの『「日米関係」とは何だったのか』には
戦後の日本国政府が言いなりのように見えて、いかにアメリカと交渉し、東西冷戦の中で自国の生き残りをかけて「戦っていた」か
にもかかわらず、その後の日本が次第にアメリカ従属の道に傾斜せざるを得なくなったのは、どういう流れなのか
が、まとめられています。
興味があれば、ご一読をおすすめします。
「戦争についての罪悪感を日本人の心に植えつけるための宣伝計画」
のことで、この存在は日米の公文書により裏付けられています。
(その「評価」についてなら様々な議論があります)
正確には、主にアメリカ本国により、いわゆる「逆コース」と呼ばれる占領政策変更の指示がマッカーサーらGHQに対してなされるまでの間になされたものです。
アメリカ側の当初の占領政策は日本を三等国に落とすというものでした。
このことはSWNCC150/4/AのI - Ultimate Objectives(究極の目的)というところに明記されています。
日本国ニ関スル米国ノ究極ノ目的ニシテ初期ニ於ケル政策が従フベキモノ左ノ如シ
(イ) 日本国ガ再ビ米国ノ脅威トナリ又ハ世界ノ平和及安全ノ脅威トナラザルコトヲ確実ニスルコト
要するに
日本が二度とアメリカに逆らえないようにしろ!
というもので、ある意味マッカーサーらGHQはそれを忠実に果たしました。
結果として、現在でも我が国はアメリカに決して逆らえない国となっているではありませんか。
実際にもマッカーサーらGHQは、冷戦の深刻化にともなうアメリカ本国による指示(いわゆる逆コース)で、やむを得ず日本統治の政策を変更しただけで、それまでは日本を三等国に叩き落とすために血眼になっていました。
また敗戦で打撃を受けた日本に対する苛斂誅求も行っていました。
これが史実です。
まず、マッカーサーは各報道機関にGHQが指示した記事を絶対に報道する様に命令していました。その命令を守らなければ、新聞や雑誌であれば発行部数を減らす処分を行うと脅迫しています。
参考:元毎日新聞東京本社社会部長森正蔵著「あるジャーナリストの敗戦日記」
元読売新聞報道局員高桑 幸吉著「マッカーサーの新聞検閲―掲載禁止・削除になった新聞記事」
マッカーサーによる日本統治政策というのは、それこそ戦前日本も顔負けの検閲などによる言論統制政策でした。
これは歴史学者(主にメディア史)である山本武利氏などによる研究で明らかになっていることであり、決して与太話などではありません。
http://book.asahi.com/reviews/reviewer/2013091500010.html
>GHQ(連合国軍総司令部)は、日本占領終結後にプレス政策をどのように進めたかの報告書をまとめた。そのタイトルが、「プレスの自由」というのだが、著者によればマッカーサーら指導部は、「メディアの自由の浸透に貢献した功績を強調している」という。検閲や自由を抑圧した具体例は極端に記述も少ないそうだ。
日本占領期にGHQの言論弾圧はいかに巧みに行われたか、その巧みさをアメリカのさまざまな機関から収集した記録文書で白日のもとにさらす。著者はその研究では第一人者であり、実際にその現実を解き明かされると大日本帝国型の言論弾圧とは異なる総合的なシステムが用いられていることがわかる。
たとえば検閲の実務には、多数の日本人が動員される。検閲者は4年余りの間に延べ2万5千人近くに及んだという。この実態については、検閲者たちの良心の痛みもあり、戦後社会ではほとんど公開されていない。著者は、そういう検閲者の生の声も紹介している。なにより生活の豊かさの保障の前に、誰もがこの同胞を売るがごとき仕事の屈辱に耐えたとの証言は貴重である。
アメリカの情報統制は、日本社会への軍国主義復活を阻止し、共産主義の国内への浸透を防ぐのを目的にしていたが、それらの目的はすぐに達せられたともいえる。なぜなら当時の日本国民は、GHQが鼓吹している民主主義思想をすぐに受け入れたからだ。その言論弾圧のシステムは国民にはまったく見えない形になっていた。日本の新聞や雑誌なども、当初の事前検閲よりのちに幾分(いくぶん)ゆるやかになる事後検閲に、逆に不安を抱くといった体質もあった。
言論弾圧は、政治的システムのマイナスより、国民の精神やその内面に打撃を与える。日本で用いられた手法は、日本人捕虜の意識調査をもとにして確立されたとの記述は衝撃だ。
→また、マッカーサーらGHQの指示により、敗戦の痛手も癒えない我が国は「終戦処理費」という名目の膨大な経費を負担させられてもいます。
「終戦処理費」については、私自身過去質問で取り上げていますので、虚心に読んでみてください。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13165640118
>結局、この後もマッカーサーの過酷な取り立てにより日本は終戦処理費(笑)という名目で米軍の占領経費を支払い続け、その総額は合計50億ドルに達します。
同時並行で、アメリカは冷戦移行による日本の赤化防止の為、日本の経済発展を促そうと、ガリオア・エロア資金といった有償の資金援助を行いました。この総額が20億ドルでした、しかし、これは後日5億ドル返済を求められましたので(セコい)実際は15億ドルとなり、日本は援助の3倍の額を終戦処理費(笑)として支出さられた
→ちなみに、この「終戦処理費」はアメリカの歴史学者であるジョン・ダワーも著書『敗北を抱きしめて』で取り上げていますが、そのダワーはサンフランシスコ平和条約締結後の日本国について、このように述べています。
>このあと間もなく実施された世論調査では、日本は独立国家になったかとの問いに「はい」と答えた者は41パーセントしかいなかった。
ここにあるのは、ひとつの分裂した国であった。沖縄は文字通り分離されていたし、日本が世界のなかでどんな位置を占めるのかという問題についても、日本人は感情に引き裂かれ不安な状態にあった。しかし、日本人がもっとも分裂したのは、政治に関する考え方の面であった。のちに、吉田茂はこの点を説明するのに分割された朝鮮半島のイメージを借りて、占領は日本人の心に「38度線」を走らせたと述べた。吉田の言葉は、リベラル派や左翼の立場にたつ反政府勢力の登場をさしていた。この反政府勢力は、占領が元来めざした「非軍事化と民主化」の理想をひきつづき追求すべきだと主張し、日本がパックス・アメリカーナに編入されることに反対し、アメリカが保護している保守政治家・官僚・大企業経営者の権力配置に対して、仮責ない批判態度をとっていた。
出典:『敗北を抱きしめて』(下)P411より
ただ、マッカーサーの占領政策があまりにも酷く、さすがに本国であるアメリカでも批判の声があがりました。
例えば、実際にマッカーサーによる日本統治を分析したアメリカの政治学者であり、外交官でもあったジョージ・ケナンは「マッカーサーは日本の産業を不具にし、経済界の指導者を追放することによって災難の種をまいた」とし
「日本社会の安定」あるいは復興に「悪影響を及ぼす」ようなものは許されるべきではない。
と談じています。
またケナンは「GHQの社会改造計画は日本を破滅させる」とも見ていました。
そして短い日本での滞在期間中に占領計画の見直しをし、1949年夏に新占領計画のための提言を文書化し、トルーマン大統領の承認を得ています。
出典:マイケル・シャラー『「日米関係」とは何だったのか』P30~32
占領軍による日本統治がまともな方向に向かうようになったのはそれからです。
が、マッカーサーによる思想統制と、その後の「逆コース」による方針変更は、我が国に深刻な思想的対立をもたらしました。
大まかに言うと
マッカーサーの進めた「改革」を支持する勢力と
「逆コース」以降の、日本従来の安定勢力とに
我が国は分断されたんです。
正直、マッカーサーの悪行については書き足りないくらいなのですが、とりあえずここまでにしておきます。
なお、マッカーサーは日本を非武装のまま放置するつもりでした。
それよりも、彼はさっさと日本での任務を終えて大統領選挙に打って出ようとしており、それを引き留め、駐留延期にこぎつけたのは、昭和天皇の交渉によるものです。
今の我が国の平和は、冷戦による「逆コース」で危機感を抱いたアメリカ本国の方針転換と、何よりも昭和天皇をはじめとする日本人自身の努力の賜物です。
昭和天皇とマッカーサー第4回会見
(昭和22年5月6日)
>天皇はまず、「日本が完全ニ軍備ヲ撤廃スル以上、ソノ安全保障ハ国連ニ期待セネバナリマセヌ」と切り出した上で、しかし「国連ガ極東委員会ノ如キモノデアルコトハ困ルト思ヒマス」と、四大国が拒否権を持っている極東委員会をひき合いに出して、事実上は国連に期待できない旨を強調し、マッカーサーの意見を求めた。
これに対し第九条の挿入に熱意をかけたマッカーサーは、破壊力の飛躍的な増大によって今後の戦争には勝者も敗者もないであろうこと等を指摘した上で、「日本ガ完全ニ軍備ヲ持タナイコト自身ガ日本ノ為ニハ最大ノ安全保障デアツテ、コレコソ日本ノ生キル唯一ノ道デアル」と、改めて‘’第九条の精神‘’を天皇に説いたのである。
出典;豊下楢彦氏『昭和天皇・マッカーサー会見』P52より
→この時点でもマッカーサーは第九条による「日本の非武装」にこだわり、昭和天皇が、それに難色を示していた事がわかります。
約3年後には朝鮮戦争が起こりました。
ちなみに昭和天皇は、かなり早い時期から朝鮮戦争発生の可能性を指摘していた、ともいわれます。
それはともかく
先に挙げたマイケル・シャラーの『「日米関係」とは何だったのか』には
戦後の日本国政府が言いなりのように見えて、いかにアメリカと交渉し、東西冷戦の中で自国の生き残りをかけて「戦っていた」か
にもかかわらず、その後の日本が次第にアメリカ従属の道に傾斜せざるを得なくなったのは、どういう流れなのか
が、まとめられています。
興味があれば、ご一読をおすすめします。