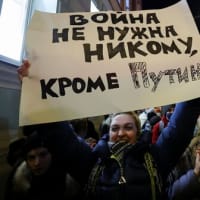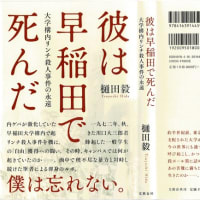Ⅱ)組織ぐるみの女性差別犯罪と国鉄労働運動破壊の事実を隠蔽してはならない
――破廉恥、あまりにも破廉恥なり‼ 革共同26全総(その2)

●誰も責任とらず、処分もなし、何の自己批判もなし
革共同26全総の議案が公表された(『共産主義者』第202号、2019年11月刊)。「議案」とあるが、「2日間の討議で採択され、公表にあたって若干の修正をおこなった」とあるので、実質的に「26全総決定」というべきものである。
同決定を一読すると、そもそも26全総は、書記長・天田三紀夫を始めとする政治局員5人が解任あるいは逃亡にいたった‘政治局崩壊’というかつてない重大な組織問題の真相を隠蔽している。したがって、その政治的・組織的責任を誰もとらず、ことごとく開き直るものとなったと断定できる。何よりも、「組織防衛上必要な最小限の修正」という名目をもって、重なり合う深刻な諸事実を組織的に隠ぺいしており、党員および労働者人民に対する謝罪と自己批判が一言もない。度外れの破廉恥さである。
そうである以上、(1)辻川問題、(2)山梨問題、(3)国労共闘解体問題(国労共闘解体・国労脱退―動労総連合拡大問題)について、筆者らの知りえた事実関係を、以下において労働者人民と革共同関係者に提示しなければなるまい。この政治局崩壊をもたらした三つの問題を‘革共同2019年問題’と呼ぶことにする。
ところで、筆者らは、今年7月、「革共同政治局が動労千葉に敵対、加えて二つの女性差別問題を隠蔽、党本部で追及・批判が噴出、ついに政治局炎上」(7月15日)と題した一文を公表した。その後、革共同中央派の現状について、複数のお便りが寄せられた。知りえなかった数々の事実が判明し、真相をほぼ解明することができた。その苦渋の決断と勇気ある行為に心から敬意を表し、感謝します。また長島由紀夫氏執筆「革共同の現状について心から思うこと」(8月1日)には、革共同関係者のみならず、この件に関心をもっておられる方たちから多くの賛同と共感の声が寄せられた。ほんとうにありがとうございます。
同時に、筆者らは、女性差別被害者Pさんおよび連帯するα部局の人々の必死の告発に思いをはせるとき、厳粛に襟を正さずにはいられなかった。
なぜなら、Pさんたちは、差別者および彼らを一貫して擁護してきた政治局および神奈川県委員会指導部を鋭く追及している。存在をかけたその告発の非妥協性は、同時に、過去に複数の政治局員(1994年秋山勝行=本人告白、2001年高山巌[西山信秀]=被害女性告発、2007年中野洋=DC会館表面化など)が引き起こしたいわゆる愛人問題=女性差別問題、それらへの組織的対応を自己批判的に検証することを必然的に要求するものともなっているからである。
実際、そこには反スターリン主義思想に立脚しかつ七・七自己批判の思想と路線をとってきた革共同の組織内思想闘争の伝統の継承と断絶、歪みや腐敗といった問題がある。
Pさんたちの告発は、この意味で革共同中央派内外にとどまらず、共産主義運動あるいは左翼政治党派にとって普遍的な意義をもっていると考える。過去には第四インターや革労協における深刻な女性差別問題もあった。
それゆえ、彼女たちの告発に真正面から自己批判的に向き合わねばならない、そしてそこから組織論的な教訓を導き出さなければならない――このことを、筆者らは強く突きつけられた思いである。
筆者らは、革共同2019年問題を究明すればするほど、中野洋を政治局員にしたことの取り返しのつかない誤り、その中野と原則的な党内闘争をできなかった自らの愚かさと力不足をただただ恥じるばかりである。同様に清水丈夫を本多延嘉亡き後の最高指導者として権威づけてきたおのれの悪しき権威主義と不見識を嫌になるほど思い知らされた。以下は、筆者らの痛恨の自己批判であることを表明する。
革共同26全総決定の問題に戻る。
26全総決定の特徴は、〈組織責任の所在隠し〉という点では、次のように整理できよう。
(イ) 辻川慎一(大原武史)ほぼ単独主犯説。
「政治局中枢の指導の誤り」というフレーズが何度も繰り返されるが、天田三紀夫や黒川純子(木崎冴子)や河村剛(坂木、高原洋三)や鎌田雅志や田中康宏(松丘静司)の名前は出てこず、それらすべては辻川がやったこととし、一切の責任を辻川になすりつけた。昨日までの‘労働者の英雄’が今日は‘すべての誤りの元凶’とされている。あまりにも見え透いた、あまりにも破廉恥な掌返しである。※川村剛→河村剛に訂正。
その一方で、驚くべきことに、辻川への追及も除名処分もないのだ。18年9月に逃亡した辻川は、こともあろうに常南交通社長の懐に入り込み、再就職先を世話してもらっている。資本に庇護されているのである。それなのに、中央派新政治局は辻川を野放しにしている。
(ロ) 天田・黒川・河村・鎌田らを救済。
彼ら4人は政治局員解任となっていない。天田、黒川、河村の三人組の罪が重いのはもちろんだが、黒川の指示でPさんを5年間にわたって直接に監視、抑圧し続けた鎌田の罪もじつに重い。その彼らに自己批判を求める追及も停止した。むしろ天田、黒川、河村、鎌田が関与する諸事実=‘不都合な真実’を告白させないために、自己批判文作成を強制終了させた。実際、天田はまったく謝罪になっていない6月11日付の「熊沢文書」を出しただけで、その後、何の謝罪・自己批判文を書いていないという。
(ハ) いまだPさんに謝罪も自己批判もしない山梨(註1)を庇護。
確信犯的な女性差別主義者である山梨(神奈川県委員会湘南支部、中央WOBメンバー)は除名されて当然であるのに、明確な処分がされていない。その山梨への自己批判指導など一切ない。その山梨と山梨を擁護し続ける神奈川県委員会を免罪している。
(ニ) 田中の責任をことごとく隠蔽、免罪。
田中康宏は辻川と同列に位置してきた政治局員であり中央WOB(労働者幹部団全国会議、昨年までの議長は辻川)の主柱である。ところが、その田中が裁定者席に鎮座したのである。そして26全総以後、中央WOB議長に納まっているのである。
(ホ) 清水丈夫(欠席、メッセージのみ)免罪=議長再任。
清水のメッセージ内容は党員には公開したのだろうか? 組織内部に「議長」自らの意思表示を公開もできない哀れな議長。その清水を議長にかつがざるをえない26全総のみすぼらしさ。ブルジョア企業ですら、会長職、社長職、取締役職にある者は、公開の場で謝罪し、辞任しているというのに、「革共同議長」を名乗る者が姿を見せることもなく、居座るとは何たる傲慢さか。党員や労働者人民を侮辱するのもはなはだしい。清水免罪=議長居座りにこそ、26全総、いや現在の革共同中央派そのものの階級的犯罪性が端的に露呈している。
(ヘ) 党中枢権力内部での権力の交代・移動劇。
3人組権力、すなわち正確には‘天田・黒川・河村=辻川⇔清水権力’の解任処分がないまま‘田中・秋月⇔清水権力’へ権力が交代・移動しただけである。とんでもない茶番劇である。
26全総は、今年3~4月以来、女性差別被害者Pさんや多くの党員の政治局批判、指導部追及が巻き起こったというのに、それを反映させ、具体化したものではない。いわゆる下克上は実現されていないのである。それゆえ、そこには思想的・政治路線的・理論的な何の転換性もない。多くの党員たちの「党は変わらなければならない」という切羽詰まった声はただ利用され、踏みにじられた。
(ト) 田中を新議長とする中央WOBが隠れた最高権力。
中央WOBは、政治局と構成メンバーが重なるが、規約上の規定が何もなく、恣意的に選抜されたグループにすぎない。その中央WOBが‘党のなかの党’として指導権を掌握し、党を牛耳ろうとしている。もっとも、田中中央WOBにそれだけの力があるのだろうか。
(チ)26全総に出席した全国委員たちの度し難い奴隷根性。
中央派を担う全国委員など中堅幹部たちは、あまりにも主体性がなく、自立性が欠如している。失墜しぼろぼろになった権威にさえ服従し、全国の党員たちのさまざまな論議を踏みにじってしまった。そのなかでも、議案および新人事案の採択でそれぞれ数人(数地方)の反対、異議が出たことは、唯一の救いである。だがそれも無視・抹殺された。
26全総決定では「党を生まれ変わらせる」「団結を生みだせる党へと変革していく」と書いている。だが、(イ)~(チ)のどこがどう、「生まれ変わらせる」「変革していく」といえるのか。何も生まれ変わっていない。どこも変革していない。党員と労働者人民を愚弄するのもはなはだしい。
●政治局崩壊=革共同2019年問題を総括できず、理論的に大混乱
また、26全総決定の特徴を、〈思想的・政治路線的・理論的な内実〉という点でみると、どのような問題があるだろうか。
(1)集団的女性差別犯罪を起こしたことをどう総括するのか。これを完全にネグレクトしている。
中央派は、7・7自己批判の立場を全否定して「血債主義粉砕」「差別糾弾主義粉砕」「血債主義者打倒」を叫び、そのあげく集団的女性差別犯罪を起こしたのである。その元となった「07年7月テーゼ」(清水丈夫原文=坂本千秋編集・執筆)を自己批判するのか、しないのか、破棄するのか、維持するのか、どうなのか。この点を明確にさせなければならない。
(2)「党と労働組合の一体的建設」論はそもそもまちがっていたのか、それとも正しいがその実践あるいは適用がまちがったのか。
「党と労働組合の一体的建設」論は第7回大会で正式決定されたが、それ以前に「綱領草案」(09年8月の25全総で採択)の第7項において打ちだされている。いわく。「党建設は……現代においては、何よりも、闘う労働組合をよみがえらせることと一体で形成・確立されるものである。」と。つまり、第7項の前段にある「共産主義者の政治的結集体」という規定を「現代においては…」という名目で実質的に否定している。「共産主義者の政治的結集体」規定を否定したことを受けて、「党建設は労働組合をよみがえらせることと一体で形成・確立される」としている。すなわち「党と労働組合の一体的建設」論がここで出されたのである。綱領草案のこの犯罪性にメスを加えなければ、何の総括にもなりえない。
(3)「国労共闘解体(国労共闘解体・国労脱退―動労総連合拡大)」方針はまちがっていたのか、それとも正しかったのか。
「動労総連合を全国に建設しよう」という路線・方針は第7回大会で正式決定されたが、その実態は、国労共闘の解体であり、国労メンバーを国労から脱退させるものだった。国労共闘解体・国労脱退は、革共同が長年にわたって国労内部で培ってきたかけがえのない地平をすべて灰燼に帰すものだった。それを正しいと強弁できるのか。
(4)天田と辻川が率先して強調し、かつ田中も唱えてきた「労働の奪還」論は、第一に、なぜ生み出されたのか。第二に、どこがどうまちがっていたのか。このことの切開が何もない。
田中は次のようにいった。「『労働の奪還』ということが討議されていますが、マルクス主義の原点と時代の要請によって生みだされた重要な実践的指針」(16年5月全国代表者会議第2報告)とまで美化していた。『前進』紙上でも、『共産主義者』誌上でも、つまり全組織をあげて「労働の奪還」論を称賛し、理論委員会が肯定、容認してきた。そのことを、全面的に自己批判しなければならない。それなのに、辻川一人の誤りとしてすませるのは、卑劣な責任逃れである。
今になって「マルクス主義を変質、解体させるもの」(26全総決定)といいながら、自己批判的=主体的総括を逃げているために、その中身が何もないのである。だが、①「労働の奪還」論もまた、綱領草案――とりわけ第1項の「労働者階級は社会の主人公」論――から生み出されたものである。それは、②賃労働が資本との関係でのみありうることを捨象して、労働だけを孤立的、したがって観念的に意義づけ、③かつ疎外労働を労働者の「誇り」として美化するという致命的な誤りに陥っている。したがって、④それはしょせん国家権力の打倒、資本の打倒なき‘働こう運動’なのである。
(5)19年3~8月過程の女性たちの告発、追及、さまざまな党員の決起によって、中央派政治局は崩壊した。その政治局は、06年3・14Ⅱをもって成立した政治局なのであり、それゆえ出発点である3・14Ⅱの肯定・美化そのものにメスを入れなければならないのではないのか。
3・14Ⅱをもって「党の革命」を叫び、数々の党内粛清を強行してきたことがまちがっていたのではないのか。「党の革命」を自己批判するのか、それともこの期に及んでもそれを美化するのか、どうなのか。
26全総は、政治局崩壊をもたらした革共同2019年問題の一つひとつを理論的に明確にさせなければならなかった。だが、何を切開し、どう自己批判しなければならないのかがまったくわかっておらず、非常に混乱している。
すなわち、7回大会(14年12月)について全否定するわけにもいかず、一部肯定するのも確信がもてず、同大会の内在的総括がまったくできないでいる。ただ綱領草案にすがりつくばかりなのである。しかし綱領草案そのものが階級的犯罪的誤りの塊なのだ。なぜ、綱領草案を問い返そうとしないのか。そしてその綱領草案の土台をなし、内容的な基軸となっている7月テーゼについて、26全総決定はまったく言及していない。奇妙なことであり、中央派の混迷ぶりを鋭角的に示している。
とまれ、革共同中央派は、政治局員および中央WOBメンバーの犯罪を引き起こした根拠を思想的・政治路線的・理論的に切開し、自己批判的に総括しなければならないのだ。そうではないのか。
その解明のためには、革共同2019問題――(1)辻川問題、(2)山梨問題、(3)国労共闘解体問題(国労共闘解体・国労脱退―動労総連合拡大問題)――を具体的に俎上に載せなければならない。26全総はその取り組みをまったく放棄しているのである。ゆえに、ここで革共同2019年問題を要約しておくこととする。
●共産主義思想と対極にある労働者幹部たちの女性差別犯罪
第一に、それは、辻川と山梨という中央WOBメンバーによるきわめて悪質な女性差別である。だが、それだけではない。辻川の場合も、山梨の場合も、黒川を筆頭に、天田、川村、鎌田、また田中らなど政治局員および中央WOBメンバーがそれを容認、加担したのである。
しかも、その歴史的前提には、マル青労同の統括責任者でもあった中野洋(政治局副議長、組織名:安田、動労千葉顧問)による2回にわたるマル青労同メンバーの愛人化という事実があった。それは、DC会館(動労千葉組合事務所がある)を舞台に半ば公然と行われており、07年には2件目が党において表面化した。清水にも報告がもたらされた。ところが、清水が「DC会館の中にとどめよ」「黙認せよ」と指示し、組織的に何ら問われることがなかった。
辻川は、1992年に地元茨城県の常南交通での争議で資本側からの接待を受けて応じた。そのことだけでも犯罪的なのに、その際に、フィリピンから日本に出稼ぎに来てフィリピンパブで働かされていた労働者Qさんを知り、長年にわたって愛人とし続けた(2011年までの19年間)。Qさんは耐えがたい民族差別と女性差別だらけの労働環境、劣悪な労働条件のもとであっても故郷の家族の生活を背負って働かなければならなかった。辻川は帝国主義支配下の腐敗した男性そのままに、そのQさんにつけこんで性的に凌辱し続けた。毎年の11月労働者集会で「国際連帯」を唱える辻川が、じつは常南交通資本と癒着し利害関係をもち、フィリピンを始めとする外国人労働者の尊厳と権利を踏みにじり、とりわけ女性を蹂躙する最悪の民族差別主義者、女性差別主義者だったのである。
辻川がそれほど長く愛人関係を続けたのは、中野の問題状況を見て、「中野もやっているのだから」と開き直ったからだと考えられる。
辻川は、その後は大阪の自治労労働者を愛人とし、さらに最近では東京の非正規労働者Cさんを愛人とした。辻川だけでなく東京西部地区委員会や労組交流センターなど中央派全体は、そのCさんが非正規の厳しい労働条件にあることを政治主義的に騒ぎ立て、Cさんを美化し、権力や資本の矢面に立たせた。辻川の女性差別を、党が利用したのである。
辻川はこの間、妻のLさんを裏切り、言語に絶する苦しみを強制し続けた。辻川は「Lは炭鉱労働者の父親の妻であるおれの母親を大事にしない。Lは嫁の資格がない」などと、Lさんを罵倒したという。おのれの裏切り行為を棚に上げ、家父長制的家族主義イデオロギーをむき出しにLさんへの女性差別を開き直ったのである。辻川は、家族関係を破壊し、3人の子どもたちに深い心の傷を与えた。
関東地方委員会統括者の黒川は、辻川フィリピン労働者愛人化の事実を、わりと早い時期に常南交通労組担当の某常任から通報があって承知していた。にもかかわらず、政治局に報告せず、中野と天田と川村には知らせ、独断で是認していた。06年3・14Ⅱ以降、中野ら政治局は、辻川の愛人=女性差別問題を知ったうえで、その辻川を政治局入りさせた。
その辻川を見て、山梨は中央WOBおよび動労神奈川支援共闘事務局という権力を行使して、前進社α部局のPさんを支配・服従関係に縛りつけ、一方的にレイプし、その後も性暴力をふるい続けた。それを何と1年間も続けた。山梨は「告発することは党破壊行為、スパイ行為だ」とPさんを脅し、かつまた「辻川もやっているじゃないか」とうそぶいた。その間、妻には嘘をつき続けた。山梨が計画的にPさんをレイプしたことは明らかだった。
山梨については、黒川および神奈川県委員会が直接に関与している。こともあろうに女性最高指導部の位置にある黒川が率先してPさんの直後の告発を握りつぶし、鎌田を指示して弾圧体制を敷き、その一方で、山梨の差別犯罪を免罪し続けた。何とそれは5年間も続けられたのである。
Pさんは、中央派という党組織の支配・服従関係に組み敷かれ、α部局の女性たち以外には誰もPさんを防衛しようとしないなかで、山梨のレイプを拒否するためには党をやめなければならないという窮地に追い詰められた。党から逃亡しなければ山梨から逃れられなかったのだ。革共同を革命党と信じてきたPさんの絶望感は、いかばかりであったろうか。
そのように、それらは政治局あるいは中央WOBという党権力を使って、党の指導・被指導関係を利用して行われた権力主義的で暴力的な女性差別である。山梨問題においては、そうした組織的差別構造がとりわけ顕著である。
すなわち、辻川問題、山梨問題は、政治局と中央WOBと神奈川県委員会が関与した、まさに組織ぐるみの女性差別犯罪なのである。
韓国・朝鮮に一魚濁水(イロタクス)――一匹の魚が川の水全体を濁らせる――ということわざがある。一人の誤った行動が社会全体の正義を汚し、多くの人々に害を与えるという意味である。平然と女性差別を繰り返す中野という堕落した労働官僚が中央派全体を腐らせ、その思想を濁らせ、共産主義者の道義性、正義性、ヒューマニズムとは無縁の集団に転落させた。したがって第二の中野、第三の中野、あるいは第四、第五のそれを生みだすこととなったのである。
そこで問われていることは何であろうか。
(a)腐敗・堕落した中野、辻川、山梨という労働者幹部たちを称賛し、指導部に押し戴く党。そのような党の建設とは、いったい何なのか。とりわけ辻川の女性差別×民族差別の事実を知りながら政治局入りさせた政治局とは、いったい何なのか。
動労千葉美化、動労千葉神格化、中野洋崇拝、「労働者党員は労働者であるがままですでに革命的・階級的である」論――そうした転倒し疎外された労働者観を動力とする党の建設が、06年3・14Ⅱ以降一挙に強められてきた。そこでは「お前は労働者性がない」という殺し文句をもって批判者を恫喝し粛清する党支配体制を張りめぐらせてきた(註2)。そのことが中野ら労働者幹部の女性差別を容認し、再生産してきたのだ。そのため、「動労総連合を全国に」というスローガンが金科玉条とされるや、そのスローガンのもとで山梨の女性差別犯罪が容認、擁護されてきたのだ。
動労千葉特化論が許しがたい集団的女性差別犯罪を結果した。そうではないのか。
(b)そのような労働者幹部たちの女性差別がまかり通り、それを容認する党の思想とは、いったい何なのか。
そこにはコミュニズムのひとかけらもない。労働者階級自己解放をとおして人間の全人間的解放をかちとるという共産主義の目標は一体どこへいってしまったのか。革共同中央派の党員一人ひとりがおのれの思想性、主体性、人間性を決定的に問い返さなければならない。少なくともPさんの告発に自らの主体性をかけて連帯し、集団的女性差別犯罪をなした責任者ども――天田、黒川、河村、鎌田、田中、その他の坂本千秋ら政治局員および中央WOBメンバー――を徹底的に追及し、打倒し、処断しなければならない。彼らはまだまだ多くの事実を隠蔽しているのだから。にもかかわらず、26全総決定に従うことは、一人ひとりにおけるコミュニズムの死ではないのか。
(c)女性差別被害者の告発を弾圧し、党における女性差別を野放しにした‘論理’の自己批判的切開が、なぜ行われないのか。その‘論理’はすべて黒川が与え、革共同中央派内において強力に作用し、それが支配的論理となったのだった。
いわく。「あなた(Pさん)が強くなりなさい」「応じたあなた(Pさん)が悪い」「山梨はPさんの指導部なのだから、Pさんは我慢しなければならない」「山梨は責任をとらせるほどの重要な指導部ではない。処分する必要はない」「今は動労神奈川建設という重大なたたかいの時だ」などなど。さらにまた、辻川の愛人問題=女性差別問題では、「男だからそれぐらいのことはあるでしょう」と言い放ったのが黒川であった。
黒川は、「男性による女性への差別などない。女性差別があるとすれば原因は女性にある」という使い古された最悪の女性差別思想の持ち主であり、そうした男尊女卑の価値観を中央派内で平然と合法化したのである。黒川によるこれらの一つひとつの言辞をしっかりと切開するのは、当然の前提ではないのか。
(d)女性である黒川、しかも党中央最高指導部の位置にある黒川がなにゆえに女性差別被害者Pさんを切り捨て、抑圧する先頭に立ったのか。黒川は最悪の女性差別主義者であり、女性同志たちの女性差別糾弾・女性解放の圧殺者である。なにゆえにそのような恐るべき女性が存在しうるのだろうか。
黒川は、神奈川県委員会時代に、学生時代からの夫にウソをついて、神奈川県委の権力者・天田と不倫し、夫を切り捨てて天田と再婚し、天田によって神奈川の権力の座についた。さらに今回、中央派政治局において権力者の地位に固執するがゆえに、率先して中央派を男性支配社会とし、そのことでおのれが男性指導部より優位に立とうとした。黒川を突き動かしたおぞましい権力欲、そのような権力志向が横行する組織、それはもう帝国主義権力とたたかわない党であるがゆえに現実化したものだった。黒川はまさに「グルジアのスターリン」(註3)そのものではないのか。
(e)洞口朋子(杉並区議会議員、元全学連書記次長)は、14年の事件発生後、被害女性Pさんからの悲痛な訴えを直接聞いた。にもかかわらず、なにゆえに黒川に権威主義的につき従い、告発圧殺の側に立ったのか。なにゆえに友である被害女性を見殺しにするという、人間として許されない行為を選択したのか。
洞口は‘第2の黒川(木崎)’になりたかったのではないのか。
Pさんおよびα部局決議による告発は、19年4月21日投票の杉並区議選に組織をあげて取り組んでいる渦中の3月末だった。Pさんらがどう考えていたのかわからないが、それは事実上あるいは客観的にみて、山梨の女性差別犯罪を隠蔽・擁護してきた張本人である黒川(選対本部長)および洞口(候補者)への強烈な不信の表明であり、異議申し立ての意味をもつものだった。
女性差別犯罪に苦しむ仲間を見殺しにした洞口が、労働者人民の切実な利害のために働く区議会議員でありうるのだろうか。議員という公人となった洞口には、自らの女性差別加担の誤りを公にする義務、杉並区民・労働者人民に謝罪する責任がある。
(f)中野、辻川、山梨らは、共産主義の思想および共産主義者の生きざま・規律、したがってまた7・7自己批判の立場とはまったく無縁で対極にある恥ずべき行為をなしたが、彼らのその「思想」とは、いったい何なのか。
たんに労働官僚にありがちな腐敗とか、ブルジョア的俗物だとするだけでは、その確信犯的な女性差別を切開するものとならない。なぜなら、中野と辻川は誰よりも率先して非常に意識的に「血債主義粉砕」「差別糾弾主義反対」「血債主義者打倒」を叫んできたし、その彼らの言動が中央派全体のあり方となってきたからである。
こうした(a)~(f)という重なり合う深刻な諸問題が突き出されているのである。
(g)あえて書くが、Pさん自身に問われていることはないのか。
07年7月テーゼが出されたとき、7月テーゼの差別的本質を見抜いて弾劾したKRさんの怒りと苦しみを、Pさんは学生戦線にあって見ていた。今、山梨による性暴力の犠牲者とされ、それを必死に告発するにいたったのであれば、あのとき加害者としてKRさんに苦しみを強制したことの深刻な誤りをとらえ返し、率直に自己批判することができるのではないだろうか。
帝国主義による階級支配の重要かつ不可欠の環をなすありとあらゆる差別=人民分断支配は、加害と被害が錯綜するじつに重層的構造をなしている。それゆえ排外主義・差別主義・権威主義とのたたかいを戦略的に位置づけ、貫くことで、帝国主義打倒のたたかいは根源的な力を発揮しうる。Pさんが7・7自己批判の立場に裏打ちされた帝国主義打倒のたたかいの意義をつかんだなら、そのとき初めて、26全総決定でうやむやにされている山梨問題の徹底糾弾とその決着のたたかいをまっとうできるのではないだろうか。
辻川問題や山梨問題は、プロレタリアート自己解放のたたかいをとおして人間の全人間的解放をかちとるという共産主義の原理が革共同中央派にそもそもあるのか、ということを問うている。だが、今ここで確認してきたように、辻川問題と山梨問題をすっかり隠蔽、擁護してしまった26全総決定が共産主義思想の反対極にあることは、あまりにも明らかである。
●第7回大会路線の具体化は‘国労共闘の自殺’
第二に、中央派の誤まてる労働運動路線の行き着いたところが国労共闘解体であった。それは、無残にも、‘国労内党員たちの自殺’にほかならなかった。
すなわち、中央派は、14年ごろから「動労総連合を全国に建設しよう」をスローガンに掲げ、第7回大会の大会決定にした。同時に「党と労働組合の一体的建設」論を大会決定にした(『共産主義者』第183号、15年2月刊)。
その第1報告「大恐慌は戦争に発展――革命情勢が全世界で到来」は、清水メモ「内外情勢分析」を基に執筆され、河村が報告した。第2報告「6回大会以降の党の歩みと中期階級決戦の展望」は、天田草稿をベースにしてライター陣が執筆し、天田が報告した。特別報告1「壮大な構想で階級的労働運動の拠点建設を」は田中が報告した。特別報告2「中期階級決戦の核心課題――動労総連合を全国に」は辻川が報告した。
その四つの報告は、それぞれのカラーがよく出ているが、政治路線内容としては完全に一致している。清水、天田、河村、田中、辻川が一様に「動労総連合を全国に」「党と労働組合の一体的建設」を基調にして執筆あるいは発言している。大会実行委員長の黒川(木崎)もまた「『組織、組織、また組織』の大運動を待ったなしに展開する、そうすれば絶対に権力を取れる」などと空文句を叫んでいる。
では、「動労総連合を全国に」方針×「党と労働組合の一体的建設」論を実践するとはどういうことか。
それは、革共同が1962年三全総以来、数十年にわたって伝統的に継承してきた国労内のたたかいとその陣地である国労共闘を解体し、党員たちが支持者・共鳴者を引き連れて国労を脱退して、動労の旗を掲げるということだった。つまり、革共同が日本革命の戦略的部隊の一つとして位置づけてきた国労、その国労を割って出るということだった。それは、国労秋田、同新潟、同福島・郡山、同東京などで踏ん張ってきた名だたる労働者党員たちが自ら国労組合員との関係を切断し、現場の労働者大衆に背を向けるものとなった。当然にも、国労のなかの支持者・共鳴者の誰もついてくるわけがなかった。
とりわけ支部書記長の位置にあった郡山工場では、国労を脱退して動労単産をつくることは、それまで営々として築いてきた国労組合員との深い信頼関係を破壊する暴挙以外のなにものでもなかった。だが党はそれを強いたのだった。
しかも、その過程では、「動労東日本」を新たにつくり、その委員長に辻川を据えるという「辻川動労総連合構想」なるものが企図された。
なぜかというと、田中は、当の革共同が趨勢的に疲弊していることへの危機感や国労共闘の苦悶・格闘を共有するわけではなく、ただ動労千葉の利害を党に対置し、党を批判するスタンスを変えることはなかったからである。天田らからすれば党の会議も組合の事情で簡単に欠席する田中は鼻持ちならない存在であった。天田は「田中は細胞性がない」「動労水戸は党細胞を組織しているが、動労千葉にはそれがない」と陰に陽に批判してきた。
かくして政治局三人組は「辻川を動労東日本のトップにすえて動労千葉を含む動労総連合を指導させる」という方針を決定し、田中に通告した。三人組が辻川と結託して田中・動労千葉を支配しようとしたのだった。
そのような中央派内権力抗争を絡ませたことによって、日本帝国主義とそのJR資本との対決という垂直的対決構造をまったくつくりだすことがないまま、「動労総連合を全国に」「組織、組織、また組織の大運動を」という組織づくりのみが叫ばれるものとなった。
JR当局による外注化攻撃にたいして、本来なら国労や動労千葉・動労水戸の枠を越えたJR労働者全体の共同の反撃を組織し、相呼応するたたかいを巻き起こしていかなければならない。さらには、カクマル副議長・松崎明死後(10年12月)、急激に求心力を失い、組織的動揺過程に入ったJR総連・東労組傘下のJR労働者にも外注化阻止を呼びかけ、ともに決起する戦略的な好機が生まれてもいた。それなのに、革共同中央派とその労働者党員たちは、「動労総連合建設」の名で、国労を割るという行動に出たのだった。敵権力を前にして労働運動にあるまじき組合分裂を策動したのである。そのようなセクト主義的な同心円的自己中心運動では外注化阻止のたたかいが成り立つはずもない。
それにしても、国労共闘の党員たちは、どのような思いで「国労を割れ」という党の方針を実行したのだろうか。「今日から動労になれ、国労共闘は自殺しろ」という党の方針を呑んだ彼らおよびその家族たちの胸中はどのようなものだったのだろうか。当事者たちとその家族たちの党への不信と怨みの声があちこちから聞こえてくるようだ。
そのようにして、15年から16年にかけて動労各単産が名乗りをあげた。そうして形成された動労総連合は、それ以前の動労総連合とはまったく質を異にしている。なぜなら、国労共闘解体という血が流されたからだ。とくに東日本で……。したがって、それ以前と区別して動労総連合2015と呼ぶこととする。
ただし15年以前の動労総連合も労働組合の原則をたびたび破ってきた。
08年6月、動労西日本から中央派メンバーが脱走し、組合の法的かつ原則的な手続きを踏みにじって勝手に「動労西日本」をでっちあげた。彼らは「動労千葉との一致がなければ動労西日本の執行委員会を開いてはならない」などと、動労千葉絶対化という党の利害で動労西日本の分裂を策したのだった。国鉄分割・民営化に敢然と反対し、動労本部カクマルによる除名処分をはねのけて、1987年6月、井面義信動労広島地本三次支部委員長を先頭に動労西日本を結成して以来、自力自闘の新たなたたかいの伝統をつくってきた動労西日本。その動労西日本に動労千葉の支配下に入れなどと強要し、それが通用しないとなると、組合分裂に走ったのだった。
そのような歴史的な階級的犯罪に加えるに、今回の国労脱退による動労総連合2015は、取り返しのつかない愚挙であり、当事者たちに党の残酷な方針を強要した以外の何ものでもなかった。
動労千葉特化路線なるものは、かくしてついに国労内のたたかいを否定するにいたったのである。
●第7回大会の発端は中野の逆三全総路線
第三に、動労総連合2015づくりのための国労共闘解体・国労脱退などという愚挙にして階級的な犯罪がなぜ生み出されたのか。
そもそも、7回大会路線とは、「一部政治局員による指導の誤り」などというものではない。前述したように、それは、中央派政治局および中央WOBの総力を挙げて推進したものである。中央派の06年3・14Ⅱ以降の階級的労働運動路線(動労千葉型労働運動、動労千葉特化路線)そのものの産物、それが7回大会路線である。
翻って、06年3・14Ⅱ以降、中央派において一気に全面化した路線は、動労千葉の絶対化、中野洋の神格化であり、「動労千葉以外は労働組合ではない」というものだった。そこで中野が強調してやまなかったのは、「体制内労働運動粉砕」論だった。それと表裏一体で押し出されたのが、統一戦線の否定であった。「動労千葉を主人公とした統一戦線」でなければ認めない、それ以外は体制内労働運動だ、というスタンスを路線化したのだった。07年段階で、その「体制内労働運動粉砕」論は公式の見解になっていた。
中野による「体制内労働運動粉砕」論は、一つには、革共同の伝統的な大衆運動論、労働運動論にまったく相反するものである。中央派にもわかりやすくいえば、それは逆三全総路線である。
中野は、1991年5月テーゼ前後の時期、「三全総路線にもどるべきだ」と語ることがあった。06年3・14Ⅱ以降は、「三全総が革共同の原点だ」と強調してきた。それは、三全総以降の1966年第三回大会および1967年10・8羽田闘争をもってする革共同と日本階級闘争の内的な発展を認めたくない、歴史を後戻りさせたいという中野の意図の表れであって、中野が三全総を理解し、尊重していたことを示すものではない。まったく逆なのだ。
三全総路線とは、ここでのテーマに即していえば、民同の支配する労働組合のなかででも、たとえ反動的な労働組合のなかででも、精力的に活動し、ダラ幹にたいする対決をとおして戦闘的労働者の潮流をつくりだすという路線である。「戦闘的労働運動の防衛」「党と労働者階級との生きた交通」を核心的なキーワードとした。その三全総路線の意義は、正規・非正規の分断、産業・職業の違いを乗り越え、女性労働者への差別や外国人労働者への排外主義攻撃などすべての差別・排外主義と対決して、もって労働者階級人民・被差別人民全体の利益のためにたたかう路線へと発展したところにある。たとえば、1989年1月の全国労組交流センター結成の声明文をみよ。
そうした三全総路線とはまったく異なる路線が中野「体制内労働運動粉砕」論である。それは、中野の三全総への無理解と拒絶を暴露しているのである。
それは、二つには、敵権力、敵資本、敵階級とのたたかいを「体制内労働運動」批判、すなわち動労千葉以外の労働運動への批判、罵倒、敵視にすりかえていくものだった。すなわち、「体制内労働運動」を「敵」の位置に置くものであり、その一方で敵権力、敵資本、敵階級との対決を実質的に放棄するものだった。1920年代末~1930年代のコミンテルンとドイツ共産党KPDによる「社会ファシズム論」(註4)の中野版といっていい。
三つには、それは、プロレタリア革命を永遠の彼岸に押しやる組合主義を本質としていた。いわく。「労働組合の団結強化の発展がプロレタリア革命だ」「労働運動の力で革命をやろう」というものであり、労働組合の延長上に革命がありうるかのような政治的詐欺をふりまくものだった。
しかも、中野の組合主義は、動労千葉の戦闘的たたかいの経験を自ら踏みにじって、動労という職能主義的組合のあり方に先祖帰りした職能主義的組合主義であった。
したがって四つには、中野「体制内労働運動粉砕」論は、党組織論そのものを否定するものである。すなわち、現実の労働者階級の真っただ中で、労働者の労働と生活の場で、さらにはさまざまな労働組合のなかで、ありとあらゆる契機を通して党と労働者階級との生きた交通関係をつくりだし、そのなかから党を建設していくという党組織論を完全に否定するものだった。
06年3・14Ⅱ以降の階級的労働運動路線=動労千葉特化路線なるものの核心にあるのが、中野の「体制内労働運動粉砕」論なのである。その延長線上に生まれたのが、7回大会路線であり、動労総連合2015づくりのための国労共闘解体・国労脱退だったのである。(動労千葉特化路線については、『革共同政治局の敗北1975~2014』第4章第5節「動労千葉特化路線という階級的犯罪」を参照。)
●‘中野組織論’に染め上げられた中央派
第四に、「党と労働組合の一体的建設論」とは何なのであろうか。もちろん、それは党と労働組合の区別と連関にかかわる理論上のとんでもない誤りである。党と労働組合を並列化するなど、およそ階級闘争の現実とかけ離れた、支離滅裂な誤謬の産物である。だが実際には、中野洋による革共同政治局支配を合理化し、執行するための理論外的な屁理屈として通用してきた。その屁理屈は清水丈夫がつくったのだった。
まず、中野の革共同政治局支配は中央WOB結成によって進められた。筆者らも、後から振り返ってみて、中央WOBの重大な意味がよくよく分かった次第である。
中央WOBは、前述したように、06年3・14Ⅱが「党の革命」として肯定・美化された後、中野洋が「労対とWOBを一緒にするな」と称して、労対すなわち中央労働者組織委員会(WOB)と区別して中央WOBを組織した。前者が職革(職業革命家)=常任によって構成されるのにたいして、後者は中野によって恣意的に全国から産別ごとに選抜された労働者幹部党員によって構成される中央労働者幹部団全国会議である。両者の関係は、まず中央WOBがあり、それを補佐、サポートする役割をするのが労対(本来のWOB)という位置づけだった。
WOBとは別のものを「中央WOB」とネーミングすること自体、つじつまが合わないのだが、中野は「政治局に準ずる正式の指導機関」として押し出したかったので、あえて「WOB」の名称を借用したのである。それが同年11月~12月のことであった。
中野存命中は、中央WOBは「政治局に準ずる」と称しながら、実際には政治局より上位にあり、中野は座長として中央WOBを通して全組織を指導せんとし、政治局―地方委員会・地区委員会―細胞はそれに振り回され、かつそれを否応なしに追認してきた。中央委員会―地区党―細胞という党の指導系統、その骨格を破壊するものであった。中野は政治局副議長であるので、正確には「二重権力」とはいえないが、中野中央WOBが天田ら前進社の党本部とは別個の最高権力であった。当然にも、中野中央WOBと党本部には矛盾、軋轢、対抗がつきなかった。
中野の意図ははっきりしていた。
中野を頂点とする動労千葉、その周りに産別ごとに恣意的に集められた労働者幹部たちが革共同の指導部となること、常任集団である労対はその書記集団であるべきだというのが、中野の意図であった。若いころには『なにをなすべきか』などレーニン組織論をそれなりに学習したこともある中野ではあるが、何も血肉化しなかった。中野の組織論は、労働組合の執行委員会と書記団という発想しかなかったのである。
つまり、革共同の組織論のなかに労働組合の組織論を公然ともちこんだもの、その核心的実体が中央WOBだったのである。この点の指摘と明確な批判が、当時の党内では出されていた。
この意味で、革共同の党組織論の基本を再確認しておこう。
「党の組織構成上の主要な部分をなすものは中央委員会と細胞(支部)である。党の中央委員会は、党という一個の生命体において頭部をなすものであり、党の活動を全体として総括し、その基本的な方針にもとづいて全党を指導することを独自の任務としている。細胞(支部)は、党の基礎組織であり、労働者階級の労働の状態、人民大衆の生活の状態にもっとも密接した形態で、党の一翼として系統的に活動し、労働者階級と人民大衆を党に不断に結びつける役割をはたすものである。
県委員会、地区委員会や産別委員会は、党中央と基礎組織を結ぶ中間の党指導機関であり、党中央委員会の指導のもとに、その所属下の党組織を単一の党の指導系統に集中するものである。党を種々の傾向の集合体、種々の党組織、党機関の集合体ではなく、あくまでも中央集権的な一個の統一体として建設していかなくてはならないのである。」(本多延嘉「革命闘争と革命党の事業の堅実で全面的な発展のために」『前進』646号論文、1973年8月、『本多延嘉著作選』第2巻所収)
この本多646号論文に照らせば明らかであるが、中央WOBはそれとまったく真逆の存在なのである。党組織論の次元でいうなら、産別的・職業的な利害を地区党とその党的・階級的全体性の上に置くものであり、中央委員会―地区党―細胞の否定だったのである。中央WOBとは、中央機関であるWOBとは別に中野によって恣意的に組織され、不定期に招集される全国会議であり、そもそも党規約を逸脱、それを破壊する、きわめて権威主義的で、解党主義的かつご都合主義的な集団なのである。内実は、動労の職能主義的組合主義のために、官僚的組織機構としての革共同を利用するものだった。
中央WOB組織化に示される中野組織論は、わかりやすくいえば、親分・子分関係の組織論でしかない。中野にとって革共同は動員しやすいシステムでしかない。そこには共産主義の死、共産主義者の死があるのである。
その中野中央WOBの存在を権威づけるために、「党は階級そのものである」「階級の敗北は党の敗北である」「革共同はプロレタリア独裁の党である」(22全総、06年9月)という類のフレーズが何度も何度も強調されていった。それは、「労働者党員を尊重し、党の各級機関の代表者にせよ」という組織政策となり、○○地区委員会の委員長は現場労働者、常任は書記長という人事が一般化されていった。それが高じて、まるで‘中野洋は神様’といった空気が組織全体を覆っていった。
じつは、それは議長・清水丈夫の自己保身策でもあった。
清水は、06年の二度目の自己批判書「政治局会議Ⅱへの提起」(06年7月)において、きわめて卑屈な態度を示し、「私は今後、党の書記のごとくに努めます」と書いたのだった。「私は中野の書記になる」と清水は必死になって訴え、自己保身に汲々としたのだ。実際、清水はそのように振る舞ってきた。
その過程でつくられたのが、07年7月テーゼであり、09年綱領草案である。7月テーゼも綱領草案も、動労千葉美化論や「労働者党員は労働者であるがままですでに革命的・階級的である」論を濃厚に反映している。したがって、そこでは帝国主義の汚濁のなかにいる労働者階級の階級性を鍛え上げる階級形成のたたかい、排外主義・差別主義・権威主義とのたたかいを否定するものであるため、党組織論としてみたとき、共産主義的全体性の否定、共産主義者の意識性の否定となっている。そのような文脈で「党と労働組合の一体的建設」論が打ちだされた。
かくして7月テーゼと綱領草案は、中野中央WOBの権力と権威を支えるものとして作用してきた。
10年3月の中野死後は、ほどなく天田・黒川・河村サイドが党権力を取り戻し、「三人組」と呼ばれ、独裁的に権力を行使してきた。中央WOBは、天田に迎合する辻川が議長となり、天田ら三人組は辻川を通して中央WOBを牛耳ってきた。天田・黒川・河村は辻川のフィリピン女性愛人問題という弱みを握っていたわけである。
そのなかで、前述したように、動労千葉を背負う政治局員・田中康宏はしばしば煮え湯を飲まされてきたのだった。
こうして中野死後も、3人組が「第二の中野」として振る舞いたい辻川を使って中央WOBを牛耳ってきたのだった。
かかる中央WOBこそ、まさしく06年3・14Ⅱのクーデターの産物、すなわち「労働者を常任の上に置く組織改革」「労働者を中心とする党指導部形成」というかけ声の具体化なのであり、彼らのいう「党の革命」の最大の組織的表現であった。
したがって、天田ら前進社官僚もまた、中央委員会―地区党―細胞という指導系統を通して指導するあり方ではなく、ただただ官僚的組織機構を動員主義的に振り回してきたのだった。全国委員会総会も必要なし、大会も必要なし、恣意的に集めた活動者会議である全国代表者会議や首都圏党員総会でさまざまな動員のための上からの指令を流すことで、すべて足りるとしてきたのだった。
天田、黒川、河村らは、もともと革共同内の最右派であり、06年以降、ますます組合主義・経済主義に身も心も染まってきたのであった。
以上が「党と労働組合の一体的建設」論の隠すことのできない真相だといえる。
(つづく)