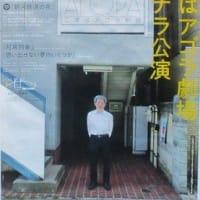都営地下鉄浅草線高輪台から北東に400m、JR高輪ゲートウェイ駅から西に600m、高輪警察と道路をはさんだ場所に高輪消防署二本榎出張所がある。1933年12月に竣工した鉄筋コンクリート3階建ての建物に、円形の灯台のような火の見櫓(望楼)があり、さらにシンボルタワーが天を衝いている。建物のコーナーがカーブを描き、円筒形の2段の構造物が乗るレトロなデザイン。この建物は海抜25メートルの丘の上にあり、竣工した87年前は周囲に高い建物もなく品川駅の先、東京湾まで見下ろすことができた。戦間期のドイツで流行したドイツ表現主義の建築物で、東京都選定歴史的建造物に指定されている。2020年3月末時点で選定建造物は96しかない。敷地面積459平方メートル、建築面積275平方メートル(延べ598平方メートル)なのでそれほど大きくはない。

この建物は、近代建築写真のネット検索でみつけた。内部の写真を撮っている人もいるので電話で問い合わせると、見学も写真撮影もOKとのことだった。官公庁なのに珍しい。ただし電話したときは新型コロナの緊急事態宣言中だったので、「この期間は遠慮していただきたい」とのことだった。それはそうだと納得し、解除されてからあいにくの梅雨空ではあったが、訪れた。
受付で申し出ると、「少し待ってください」とのことで、驚くことにスタッフの方がマン・ツー・マンで案内してくださるとのこと! ホスピタリティの高さに恐れ入った。
この消防署は1908(明治41)年7月に設置されたが、そのときはもちろん木造だった。1933(昭和8)年に建て替えられたのが現在のコンクリート製の庁舎だ。1階玄関や建物の外壁など主要構造部は変わっていない、つまり90年近い歴史をもつ建造物だ。玄関の御影石や木製ドア、金属製のドアノブなども竣工当時の「歴史もの」だ。階段や腰壁は大理石とセメントを練って固め、研ぎ出して磨いたものだ。階段は、灯台の内部階段を上るのと同じような螺旋形だが、それ自体が「ドイツ表現主義」なのだそうだ。ドイツ表現主義というと、『カリガリ博士』、『吸血鬼ノスフェラトゥ』などの映画、カンディンスキー 、グロス、ココシュカなどの画家で有名だが、アインシュタイン塔(1921)、チリハウス(1924)など建築分野もあった。曲線や曲面が特徴だそうだ。

2階へ上がる階段 曲線が特徴(階段そのものが螺旋になっている。素材は大理石とセメントを練り研ぎ出し仕上げしている)
階段だけでなく、円柱の柱、円柱と天井の間の3段のコーニスも表現主義の特徴とのことだ。3階のガス灯も1灯しかないが、当時のまま光っていた。1階階段ホールの6個のスズラン型の電球(シャンデリア?)も竣工以来のものだ。残念ながらわたしは見逃したのだが、3階講堂の天井中央に向かって集まる8本の梁や10個のアーチ窓も独特のデザインだ。
講堂の上に、金属製の階段で上る火の見櫓(望楼)があり、1971年まで利用されていたが、いまは上に上ることもできなくなっていた。
火の見櫓の上にスカイツリーのような青いタワーが立っている。これは1984年に都の「文化デザイン」事業として前野まさる・東京藝大名誉教授が設計したシンボルタワーで昔からのものではない。とはいえ、すでに34年の歴史をもつ。
3階の講堂には、江戸時代の町火消の刺し子と現代の防火服が展示されていた。もちろん素材や耐火性能は違うが、いまも「刺し子」と呼ぶそうだ。昔の2段式の木製伸縮はしごもあった。

国産初(1941年製)のポンプ車ニッサン180型(向こうは現役の日野製ポンプ車)
1階に、ちょっと驚くポンプ車が展示してあった。国産初のポンプ車ニッサン180型だ。太平洋戦争直前の1941年にこの高輪署に配置され戦後、東京オリンピックが開催された1964年10月まで活躍した。引退後は四谷三丁目の消防博物館で展示されていたが、マイホームであるこの出張所に里帰りしたとのことだった。2年前に消防博物館を見学したが、記憶に残っているのは大正か昭和初期の輸入消防車だ。国産車がこんなところにちゃんと保管されていたとは!
きれいに磨き上げられ、隣の日野製・現役ポンプ車に引けを取らない姿で保管されていた。ポンプ車は消火栓や池から水を汲み上げ、その水に圧力を加えて放水する。基本的な機能は変わらないので、連成計という汲み上げる圧力を測定する計器(消火栓のように給水側が水圧をかけている場合もあるのでプラスだけでなくマイナスも計測する)、放水する水圧を計測する圧力計は同じように付いていた。
消防出張所や高輪警察の前の道路はメリーロード高輪という小規模な商店街になっている。真水とうふ店、コーヒー専門店・コーヒーローストSAI、和菓子の玉川屋惣八、きしめん丸福などがあり、少し離れたところにはとらやという古い建物の和菓子店もあった。港区高輪という名前だけで、ハイソサエティで高級な街と思い込んでいたが、意外に庶民的な街でもあることがわかった。
また寺がずいぶん多かった。日蓮宗円真寺、曹洞宗黄梅院、浄土宗松光寺、清林寺、日蓮宗承教寺、妙福寺など寺が20-30mおきにある。泉岳寺も300mくらいのところにあるし1キロほど離れたところに新興宗教・阿含宗関東別院まであった。明暦の大火(1657)以降、都心(たとえば八丁堀)から多くの寺が転入したとのことだ。

いちばん驚いたのは、警察の隣の高野山東京別院のまさに隣にプロテスタントの高輪教会があったことだった。門前の笠をかぶり杖をつく遍路姿の弘法大師像の隣に屋根に十字架の教会という光景は珍しいというか、シュールというか・・・。この教会もなかなか見栄えがよく、フランク・ロイド・ライトの門下・岡見健彦が設計し1932年に竣工したものだ。ということは二本榎出張所と1年しか変わらない。もちろんいまも毎週日曜朝10時過ぎに普通に礼拝をしている。
さらに200mほど西に坂を下った桜田通りの交差点には明治学院がある。1863年にヘボンが横浜で開いた塾が起源で、この場所で1887年に開校した。インブリー館(1889)、記念館(1890その後改築・移築)、チャペル(礼拝堂 1916)などがいまも建っている。チャペルは、早稲田奉仕園スコットホールや旧神戸ユニオン教会を設計する一方メンソレータムを日本に普及させたW.M.ヴォーリズが設計した。コロナということもあり、敷地内には入れなかったが、外から記念館がよく見えた。

明治学院だけでなく、付近には東海大学、高輪学園、普連土学園、三田中学など学校も多い。
二本榎出張所の北東100mくらいのところに高輪台小学校があるが、ここも東京都選定歴史的建造物だと、あとで知り、近くなので外からだけでも見ておけばよかったと後悔した。
いったいこのあたりはどんなところだったのか、少し歴史を調べてみた。
江戸城からみると街はずれが白金だったという。大名屋敷はあったが、松平丹波守の下屋敷、細川越中守の中屋敷、九鬼長門守下屋敷など中屋敷や下屋敷があった地域だ。明治になり武家屋敷はなくなり、海軍の病院や埋葬地、皇族の屋敷になった。たしかに学校や寺だけでなく、大きな敷地の屋敷がいくつもあった。帰宅して地図で調べると、三菱電機高輪荘、野村證券研修センターなどだった。
二本榎という地名の由来は、上行寺(明治学院体育館)門前に10mもの大きな榎が2本あり、それが旧東海道を旅する人の目印になったからだという。メリーロード高輪のある通りが旧東海道で、いまは二本榎通りという名称になっている。

道路で女性警官が警備をしている大きな森のような屋敷があった。いったいなんだろうと思うと、敷地の隅にオレンジ色のバラの写真と「上皇上皇后両陛下ご移居記念樹」というプレートがあった。旧高松宮邸だが、高輪仙洞仮御所という名で平成天皇(上皇)夫妻邸だった。東宮御所のように青山通りのような広い道路には面していない。
品川寄りのグランドプリンス高輪やグランドプリンス新高輪がある場所も、かつては竹田宮邸と北白川宮邸があり、江戸時代は武家屋敷だった。
150年もたてば、いろんな歴史が刻まれる。港区高輪はそういう地域だった。
●アンダーラインの語句にはリンクを貼ってあります。

この建物は、近代建築写真のネット検索でみつけた。内部の写真を撮っている人もいるので電話で問い合わせると、見学も写真撮影もOKとのことだった。官公庁なのに珍しい。ただし電話したときは新型コロナの緊急事態宣言中だったので、「この期間は遠慮していただきたい」とのことだった。それはそうだと納得し、解除されてからあいにくの梅雨空ではあったが、訪れた。
受付で申し出ると、「少し待ってください」とのことで、驚くことにスタッフの方がマン・ツー・マンで案内してくださるとのこと! ホスピタリティの高さに恐れ入った。
この消防署は1908(明治41)年7月に設置されたが、そのときはもちろん木造だった。1933(昭和8)年に建て替えられたのが現在のコンクリート製の庁舎だ。1階玄関や建物の外壁など主要構造部は変わっていない、つまり90年近い歴史をもつ建造物だ。玄関の御影石や木製ドア、金属製のドアノブなども竣工当時の「歴史もの」だ。階段や腰壁は大理石とセメントを練って固め、研ぎ出して磨いたものだ。階段は、灯台の内部階段を上るのと同じような螺旋形だが、それ自体が「ドイツ表現主義」なのだそうだ。ドイツ表現主義というと、『カリガリ博士』、『吸血鬼ノスフェラトゥ』などの映画、カンディンスキー 、グロス、ココシュカなどの画家で有名だが、アインシュタイン塔(1921)、チリハウス(1924)など建築分野もあった。曲線や曲面が特徴だそうだ。

2階へ上がる階段 曲線が特徴(階段そのものが螺旋になっている。素材は大理石とセメントを練り研ぎ出し仕上げしている)
階段だけでなく、円柱の柱、円柱と天井の間の3段のコーニスも表現主義の特徴とのことだ。3階のガス灯も1灯しかないが、当時のまま光っていた。1階階段ホールの6個のスズラン型の電球(シャンデリア?)も竣工以来のものだ。残念ながらわたしは見逃したのだが、3階講堂の天井中央に向かって集まる8本の梁や10個のアーチ窓も独特のデザインだ。
講堂の上に、金属製の階段で上る火の見櫓(望楼)があり、1971年まで利用されていたが、いまは上に上ることもできなくなっていた。
火の見櫓の上にスカイツリーのような青いタワーが立っている。これは1984年に都の「文化デザイン」事業として前野まさる・東京藝大名誉教授が設計したシンボルタワーで昔からのものではない。とはいえ、すでに34年の歴史をもつ。
3階の講堂には、江戸時代の町火消の刺し子と現代の防火服が展示されていた。もちろん素材や耐火性能は違うが、いまも「刺し子」と呼ぶそうだ。昔の2段式の木製伸縮はしごもあった。

国産初(1941年製)のポンプ車ニッサン180型(向こうは現役の日野製ポンプ車)
1階に、ちょっと驚くポンプ車が展示してあった。国産初のポンプ車ニッサン180型だ。太平洋戦争直前の1941年にこの高輪署に配置され戦後、東京オリンピックが開催された1964年10月まで活躍した。引退後は四谷三丁目の消防博物館で展示されていたが、マイホームであるこの出張所に里帰りしたとのことだった。2年前に消防博物館を見学したが、記憶に残っているのは大正か昭和初期の輸入消防車だ。国産車がこんなところにちゃんと保管されていたとは!
きれいに磨き上げられ、隣の日野製・現役ポンプ車に引けを取らない姿で保管されていた。ポンプ車は消火栓や池から水を汲み上げ、その水に圧力を加えて放水する。基本的な機能は変わらないので、連成計という汲み上げる圧力を測定する計器(消火栓のように給水側が水圧をかけている場合もあるのでプラスだけでなくマイナスも計測する)、放水する水圧を計測する圧力計は同じように付いていた。
消防出張所や高輪警察の前の道路はメリーロード高輪という小規模な商店街になっている。真水とうふ店、コーヒー専門店・コーヒーローストSAI、和菓子の玉川屋惣八、きしめん丸福などがあり、少し離れたところにはとらやという古い建物の和菓子店もあった。港区高輪という名前だけで、ハイソサエティで高級な街と思い込んでいたが、意外に庶民的な街でもあることがわかった。
また寺がずいぶん多かった。日蓮宗円真寺、曹洞宗黄梅院、浄土宗松光寺、清林寺、日蓮宗承教寺、妙福寺など寺が20-30mおきにある。泉岳寺も300mくらいのところにあるし1キロほど離れたところに新興宗教・阿含宗関東別院まであった。明暦の大火(1657)以降、都心(たとえば八丁堀)から多くの寺が転入したとのことだ。

いちばん驚いたのは、警察の隣の高野山東京別院のまさに隣にプロテスタントの高輪教会があったことだった。門前の笠をかぶり杖をつく遍路姿の弘法大師像の隣に屋根に十字架の教会という光景は珍しいというか、シュールというか・・・。この教会もなかなか見栄えがよく、フランク・ロイド・ライトの門下・岡見健彦が設計し1932年に竣工したものだ。ということは二本榎出張所と1年しか変わらない。もちろんいまも毎週日曜朝10時過ぎに普通に礼拝をしている。
さらに200mほど西に坂を下った桜田通りの交差点には明治学院がある。1863年にヘボンが横浜で開いた塾が起源で、この場所で1887年に開校した。インブリー館(1889)、記念館(1890その後改築・移築)、チャペル(礼拝堂 1916)などがいまも建っている。チャペルは、早稲田奉仕園スコットホールや旧神戸ユニオン教会を設計する一方メンソレータムを日本に普及させたW.M.ヴォーリズが設計した。コロナということもあり、敷地内には入れなかったが、外から記念館がよく見えた。

明治学院だけでなく、付近には東海大学、高輪学園、普連土学園、三田中学など学校も多い。
二本榎出張所の北東100mくらいのところに高輪台小学校があるが、ここも東京都選定歴史的建造物だと、あとで知り、近くなので外からだけでも見ておけばよかったと後悔した。
いったいこのあたりはどんなところだったのか、少し歴史を調べてみた。
江戸城からみると街はずれが白金だったという。大名屋敷はあったが、松平丹波守の下屋敷、細川越中守の中屋敷、九鬼長門守下屋敷など中屋敷や下屋敷があった地域だ。明治になり武家屋敷はなくなり、海軍の病院や埋葬地、皇族の屋敷になった。たしかに学校や寺だけでなく、大きな敷地の屋敷がいくつもあった。帰宅して地図で調べると、三菱電機高輪荘、野村證券研修センターなどだった。
二本榎という地名の由来は、上行寺(明治学院体育館)門前に10mもの大きな榎が2本あり、それが旧東海道を旅する人の目印になったからだという。メリーロード高輪のある通りが旧東海道で、いまは二本榎通りという名称になっている。

道路で女性警官が警備をしている大きな森のような屋敷があった。いったいなんだろうと思うと、敷地の隅にオレンジ色のバラの写真と「上皇上皇后両陛下ご移居記念樹」というプレートがあった。旧高松宮邸だが、高輪仙洞仮御所という名で平成天皇(上皇)夫妻邸だった。東宮御所のように青山通りのような広い道路には面していない。
品川寄りのグランドプリンス高輪やグランドプリンス新高輪がある場所も、かつては竹田宮邸と北白川宮邸があり、江戸時代は武家屋敷だった。
150年もたてば、いろんな歴史が刻まれる。港区高輪はそういう地域だった。
●アンダーラインの語句にはリンクを貼ってあります。