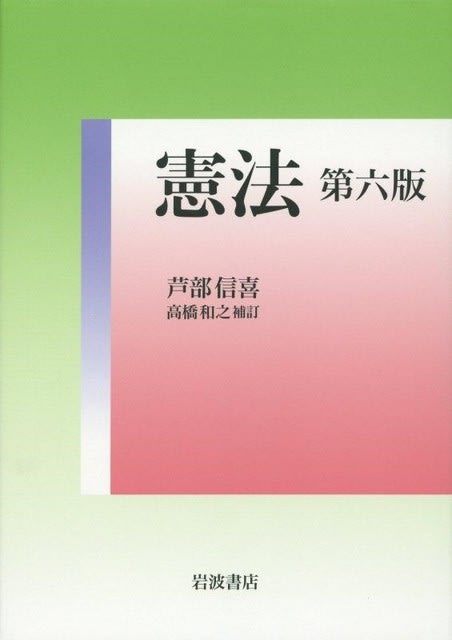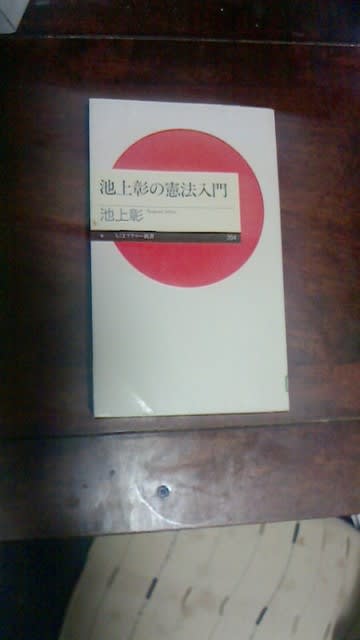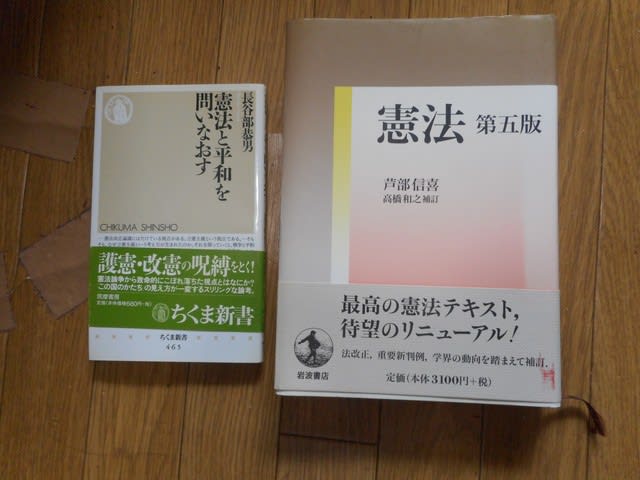写真は、
「憲法第6版」芦部信喜 岩波書店
である。
今の中学校社会「公民」の優れた教科書の構成は、
すべてこの書に拠っている。
いまだに、
憲法学で芦部信喜の業績は、
燦然と輝いているし、
この書は、彼の弟子によって補訂されており、
ほぼ最新の内容を盛り込んでいる。
もともとは、
芦部信喜先生がNHKの放送大学で講義をされたとき、
小さなテキストを書かれ、
それをもとに体系書として完成されたものである。
私は、法律学を修めていたことがあるが、
この書には、随分支えられた。
成績も、憲法が1番よかった。
あるとき、
経営学部を擁する大学の図書館に、
この書がないことを発見し、
これは嘆かわしい、すぐ備えるべきだと思った。
たまたま大学を訪れたときに、
教務主任の教授にそのことを告げると、
「すぐ準備する」ということであった。
ところが、いつまでたっても、備えられなかった。
実現したのは、10年後である。
地元図書館にリクエストした。
すると、まもなく購入された。
ありがたい話である。
地域の図書館も、ばかにならない。