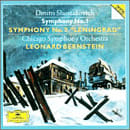
飲んできましたよ、バリウム。今朝は健康診断ということで、半日人間ドックというメニューを受診してきました。わたしはこれで人生2回目のバリウムですが、やっぱりダメだ、あれは慣れないねえ。ありゃ何なんですかねえ、バリウムってやつ。せっかくだからインターネットにきいてみた。そしたら、こういうものなんだそうで、門外漢のわたしにはやっぱりよくわかりません(笑)。物々しい器械にのれといわれ、よくわからないまま手渡された顆粒の薬剤を飲めといわれ、次は大きな紙コップになみなみとつがれた白い不気味な粘度の液体を手にもたされ、ほらそれを全部嚥下せよ、と矢継ぎ早の命令、ええいままよとゴブゴブと飲み下すヤケクソな気分は、そんなことと比較するのはいささか不謹慎にすぎるかもしれないが、全体主義国家で人体実験に供されてるかのような心持ち、不条理SFだよ、これじゃ。Shostakovich: Symphony No.7 "Leningrad" / Leonard Bernstein, Chicago Symphony Orchestra 。ドミトリ・ショスタコーヴィチは、20世紀ソヴィエトの只中を生きた作曲家。曲を発表するたびに、共産党の機関紙プラウダからの評価に生命の安全を左右された。体制批判に聴こえれば「人民の敵」、場合によってはシベリアの強制収容所送りになる。周囲の作曲家が見え見えの体制賛美音楽を発表する中、彼の作品は二重三重の屈折を孕んでいく。表面上は体制賛美、しかし一皮めくると強烈な体制批判。言葉の無い音楽の解釈の多義性を逆手にとった彼の戦略、どこまでが彼の内実なのか、どこまでが見せかけなのか、ソ連邦崩壊を待たずに彼が逝去した今となっては何ともいえない。この第七交響曲は「レニングラード」という副題を持つ。第二次大戦中のナチスドイツ軍とのレニングラード攻防戦を描いたというこの曲も謎めいた雰囲気をもっている。表面的には、ナチスの侵略をはねのけたソヴィエト人民への賛歌。しかし、曲中、ナチスの侵略として描かれている悲劇は、どうやらソ連邦内部の独裁の悲惨を重ね合わせてあるようにも聴こえてくる。独裁者スターリンに虐げられる人民の声なき怒りと悲しみ、そして諦め。バリウムを嚥下し、器械の上でぐるぐる回されてレントゲンとられてたら、そんなことを考えていたんであった。まったく蛇足だが、この曲の第一楽章、ナチスの侵略を表す旋律は、日本でかつてCMソングに使われて一世を風靡した。バブル期にやってた、シュワちゃんりえちゃんの♪チーチーンブイブイ♪(アリナミンVドリンク)である。おかげでこの曲、さらに素直に聴けなくなった(笑)。









