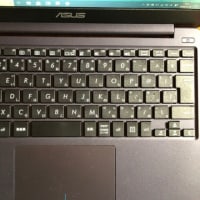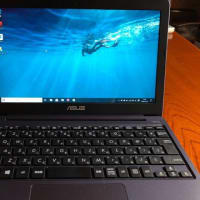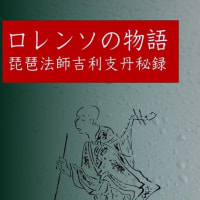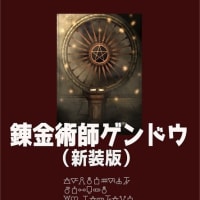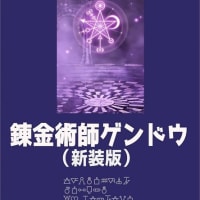いま日本で出版されている小説は「三人称」か「一人称」のいずれかで書かれている。
例外はもちろんあるけれど、いわゆる「エンターテイメント小説」は三人称が主流で、いわゆる「純文学」には一人称小説が多いようである。前者は、複雑なプロットや多角的な人物描写のために三人称を必要とし、後者は「私小説」という日本独特の小説文化の延長線上にあるから、とくくってしまったら単純過ぎるだろうか?
何度も言うが例外はある。一人称で書かれることの多いエンターテイメントの代表格がハードボイルド小説だろうし、ボルヘスの「百年の孤独」は究極的な三人称小説と言ってもいいのではないだろうか。
(余談だが、ふだん三人称で書いているミステリ作家がめずらしく一人称小説を出したら叙述トリックだった、てのはありがちかもしれない。誤解を恐れずに言えば、エンターテイメントの場合、広義の叙述トリックを仕込むつもりでない限り、一人称にはあまりメリットはないと思う)
一と三。
では、二はないのだろうか? つまり「わたし」「おれ」(一人称)や「○○が~」(三人称)ではない、「二人称」で書かれた小説はないものだろうか。
それがあるのだ。倉橋由美子の「暗い旅」である。
この小説の主人公は「あなた」である。つまり、小説中ずっと「あなた」と呼びかけられる女性の視点をとおして見た東京から京都までの新幹線の旅が、この本の主題なのだ。
読んでもらうのがいちばんなのだが、最初、違和感を感じる。「あなた」と呼びかける者はだれだろう、という思いがつきまとうのである。この呼びかける者は「あなた」の事をすべて知っている。旅の中で、どう行動したか、だれと出会いなにを思ったか、まるで三人称小説における作者のように知り尽くしているのだ。
ところが、三人称小説と違うのは、小説の視線は「あなた」からけっして離れない。それほど起伏のあるストーリー展開があるわけではないが、小説の中で起きる出来事はすべて「あなた」の目を通した描写になっている。
だから、おもしろいことに、この二人称の「あなた」を一人称の「わたし」に置き換えても小説として成立しそうなのだ。
小説を書く人間の端くれとして言わせてもらえば、二人称小説は、労多くして益少なしと思える。なぜなら、共感という意味で一人称小説より落ちるわりに、視点が移動できないので三人称小説のように多角的に描写することができないのだ。おまけに、「あなた」と呼びかける、無色透明の何者かの存在が読んでいるあいだじゅう読者に意識させてしまう。つまり邪魔なのだ。
ならば、倉橋由美子のこの小説は失敗作か、ここまで読んだ方はそう思われるかもしれない。
ちがうのだ。すくなくともわたしはこの小説に夢中になったし、なんども読み返した。この作者の最高傑作「聖少女」に比べると落ちるが、出会ったときに高校生だったわたしには、この「暗い旅」が、ヴィアンの「うたかたの日々」やサリンジャーの「ライ麦畑でつかまえて」以上の(気恥ずかしい表現を使えば)「青春の名作」に思える。
「あなた」と呼びかけているのは、作者、倉橋由美子なのである。単純な答えだ。「パルタイ」で注目を浴び、新進気鋭の作家になった倉橋が、デビューする前の鬱屈した若い自分に向かって、愛憎をこめて「あなた」と呼びかけた小説なのだ。読み終えたとき、遅まきながらそのことに気がついたわたしは、たまらなくこの小説が好きになっていた。
わたしはいま、二人称小説が書きたくてたまらない。合間に、いくつかのプロットを練っている。
一人称よりもさらにメリットがなさそうに見えるこれに挑戦したくてたまらないのだ。
もちろん作家としての夢なのだが。
けさ、新聞で倉橋由美子の死を知った。
そして、この「暗い旅」が絶版になっていることも。
小説の本を出しているもののひとりとして「死んだから再版せよ」と書くのは複雑な思いがあるのだが、おおくの人にこの小説が読まれるよう願わずにいらなれない。
例外はもちろんあるけれど、いわゆる「エンターテイメント小説」は三人称が主流で、いわゆる「純文学」には一人称小説が多いようである。前者は、複雑なプロットや多角的な人物描写のために三人称を必要とし、後者は「私小説」という日本独特の小説文化の延長線上にあるから、とくくってしまったら単純過ぎるだろうか?
何度も言うが例外はある。一人称で書かれることの多いエンターテイメントの代表格がハードボイルド小説だろうし、ボルヘスの「百年の孤独」は究極的な三人称小説と言ってもいいのではないだろうか。
(余談だが、ふだん三人称で書いているミステリ作家がめずらしく一人称小説を出したら叙述トリックだった、てのはありがちかもしれない。誤解を恐れずに言えば、エンターテイメントの場合、広義の叙述トリックを仕込むつもりでない限り、一人称にはあまりメリットはないと思う)
一と三。
では、二はないのだろうか? つまり「わたし」「おれ」(一人称)や「○○が~」(三人称)ではない、「二人称」で書かれた小説はないものだろうか。
それがあるのだ。倉橋由美子の「暗い旅」である。
この小説の主人公は「あなた」である。つまり、小説中ずっと「あなた」と呼びかけられる女性の視点をとおして見た東京から京都までの新幹線の旅が、この本の主題なのだ。
読んでもらうのがいちばんなのだが、最初、違和感を感じる。「あなた」と呼びかける者はだれだろう、という思いがつきまとうのである。この呼びかける者は「あなた」の事をすべて知っている。旅の中で、どう行動したか、だれと出会いなにを思ったか、まるで三人称小説における作者のように知り尽くしているのだ。
ところが、三人称小説と違うのは、小説の視線は「あなた」からけっして離れない。それほど起伏のあるストーリー展開があるわけではないが、小説の中で起きる出来事はすべて「あなた」の目を通した描写になっている。
だから、おもしろいことに、この二人称の「あなた」を一人称の「わたし」に置き換えても小説として成立しそうなのだ。
小説を書く人間の端くれとして言わせてもらえば、二人称小説は、労多くして益少なしと思える。なぜなら、共感という意味で一人称小説より落ちるわりに、視点が移動できないので三人称小説のように多角的に描写することができないのだ。おまけに、「あなた」と呼びかける、無色透明の何者かの存在が読んでいるあいだじゅう読者に意識させてしまう。つまり邪魔なのだ。
ならば、倉橋由美子のこの小説は失敗作か、ここまで読んだ方はそう思われるかもしれない。
ちがうのだ。すくなくともわたしはこの小説に夢中になったし、なんども読み返した。この作者の最高傑作「聖少女」に比べると落ちるが、出会ったときに高校生だったわたしには、この「暗い旅」が、ヴィアンの「うたかたの日々」やサリンジャーの「ライ麦畑でつかまえて」以上の(気恥ずかしい表現を使えば)「青春の名作」に思える。
「あなた」と呼びかけているのは、作者、倉橋由美子なのである。単純な答えだ。「パルタイ」で注目を浴び、新進気鋭の作家になった倉橋が、デビューする前の鬱屈した若い自分に向かって、愛憎をこめて「あなた」と呼びかけた小説なのだ。読み終えたとき、遅まきながらそのことに気がついたわたしは、たまらなくこの小説が好きになっていた。
わたしはいま、二人称小説が書きたくてたまらない。合間に、いくつかのプロットを練っている。
一人称よりもさらにメリットがなさそうに見えるこれに挑戦したくてたまらないのだ。
もちろん作家としての夢なのだが。
けさ、新聞で倉橋由美子の死を知った。
そして、この「暗い旅」が絶版になっていることも。
小説の本を出しているもののひとりとして「死んだから再版せよ」と書くのは複雑な思いがあるのだが、おおくの人にこの小説が読まれるよう願わずにいらなれない。