スペイン王宮を見終わり、プラド美術館へ向かう。
本当は翌日はクリスマスで休業のレイナ・ソフィア美術館に行く予定だったのだけど、寝ぼけていて間違った駅で降りてしまったのだった。
面倒だったので、そのままプラドに行くことにした。
プラド美術館に行くには、Banco de España (スペイン銀行)、という駅で降りる。
そこから歩いて10分くらいのところにある。
かなり遠いので、道を間違えたかな、と思うほど。
途中で案内板が途切れたりするので、不安になるが、一本道なので、間違えはしないはず。
この5月2日の塔が見えたらもうすぐだ。

間違えなければ(だから一本道だから間違えないって)、この外観の美術館にたどり着くはず。

正面の階段の下のところに、入り口が三つあるように見えるのがチケットカウンターで、こちらでまずはチケット購入。
そのチケット売り場の向かいにはゴヤの像が立っている。

19世紀のスペイン王室の宮廷画家だったゴヤ。
描かれる人の性格や内面まで映し出すような画法で有名だが、個人的には絵のタッチがそんなに好きではなかった。
それが、プラド美術館に所蔵されている大量のゴヤ作品から、彼の系譜が見えてきて、ちょっと好きになった。
詳しくは後ほど・・・
入り口は二つあって、上の写真の階段を上がって、中央入り口から入る方法(ベラスケス門)と、
写真の左側にあるグラウンドフロアの入り口(ゴヤ門)から入る方法と二つある。
ベラスケス門から入ると、多分「巨大な美術館に迎え入れられたー」という感覚が味わえるでしょう。
ガイドブックなどに写真が載っているのはこの入り口から見た写真。
左側のゴヤ門の入り口は、リニューアルしたばかりなので、クロークなどの設備が新しく、使いやすい。
カフェやショップも近いので、クロークに預けたまま、すぐに使える、と言う意味ではこっちの入り口が便利。
これがゴヤ門の入り口。

午前中、王宮に3時間も粘ってしまってすっかり疲れていた私は、まずは栄養補給から。
プラド美術館のカフェは新しくて、しゃれててとっても素敵。
色々と美味しそうなプレートがあって、迷う。
結局、アジのマリネとローストビーフを頂くことに。
当然昼からビールも・・・

個人的にまず驚いたのが、ルーベンスなどフランドル絵画がたくさんあったこと。
絵画鑑賞好きから見れば、プラドにフランドル絵画が所蔵されてるのは当然なのかもしれないけど、
私は普通の人なので、スペインでオランダやベルギーの絵画が見られることは全く期待してなかった。
よく考えたら、スペイン王室はフランドル地方を領有していたことがあったんだった。
それで、ルーベンスはスペイン王室の宮廷画家だったんだよね。
たくさんあるのは当たり前か・・・
以前、オランダ・ベルギーを一人で旅したことがあったので、そこで大量の美術館に行って、フランドル絵画は相当数見ていた。
(当然第一の目的はベルギービールやオランダビールを楽しむこと、第二は大好きなゴッホとマグリットを見ることだったけど、ついでにフランドル絵画もたくさん見た)
結構特徴的なので、なんか懐かしい感じ。
例えば、フランドルを代表する画家の一人であるボッシュの「快楽の園」という有名な作品がプラドにある。
裸の男女が酒池肉林していたり、まるで巨大な果物のような乗り物に乗っていたり、群がって変な格好をしていたり、かなり奇怪で、見ていて飽きない絵。
それぞれの部分が、当時の世相の風刺画になっている、というのだけど、今となっては何の風刺だか分からない。
これだけの奇怪な想像力でそれぞれ細かく書ききってることに、単純に感銘を覚える。
それからルーベンスも。
最も所蔵数では、ベルギーの美術館が上だけど、ここには美術史の教科書にも載ってるような有名な絵がたくさん所蔵されている。
そしてスペイン絵画のコーナーへ。
El Grecoというあだ名の(スペイン語で「ギリシャ人」意味)初期スペイン画家の絵が大量に所蔵されている。
エル・グレコは光の使い方がとても特徴的な画家で、一発で見て「あ、エル・グレコだ」と分かるくらい特徴的。
そしてベラスケス。
私はこの時代の画家ではベラスケスが圧倒的に好き。
彼の絵を見るのは座禅を組んでるみたいで、無駄に心を乱されないのが好きなのだ。
ゴヤに見られるような豊かな感情表現とかは無いけれど、それがいい。
「ラス・メニーナス」をはじめとする彼の著名な作品が十数点所蔵されていて、ゆっくり見た。
そしてプラド美術館が圧倒的な貯蔵点数を誇るフランシスコ・デ・ゴヤ。
「裸のマヤ」「着衣のマヤ」などの有名作品は、皆が通る一階に展示されてるんだけど、
今回感銘を受けたのは、2階にある、彼の若い頃の作品だった。
2階はほとんどゴヤだけで、何十点と所蔵されている。
ゴヤは、絵画を見ただけで、被写体の性格や心理まではっきりと分かるような、心理描写が特徴とされる。
ところが、若い頃の作品を見ると、その特徴がまだ完全にマスターされてないのだ。
それよりも若い頃の人物画を見ると不自然な印象を覚える。
口角が異常に上がって、不自然な笑みを見せたり、不自然に目が大きかったり、顔のパーツが強調されていたりする。
なんか、風刺画を見ている気分だった。
年をとり、宮廷画家になったころの彼の作品には、もう不自然さは無く、ゴヤらしい、細やかな心理描写が完成している。
それで気付いたのだが、若い頃のゴヤは、まるで風刺画を書くように、必要以上に被写体の顔のパーツや表情をデフォルメすることで、心理描写を試みようとしていたのではないか?
新聞に載ってる風刺画や似顔絵って、本人の顔をデフォルメして強調することで、本人らしさを出すでしょ?
それと同じように。
あくまで仮説だけど。
で、宮廷画家になったあとのゴヤは、そのデフォルメが不自然じゃない程度になるように調整していったのではないか。
そう思って、もう一度下の階に後年のゴヤを見に行くと、
確かに「着衣のマヤ」では、目玉が普通の人間よりなんとなく大きく明らかに焦点が合わないように描かれていて、緊張感が伝わってくる。
これに対し、「裸のマヤ」では、目玉が同じ方向を向いて視点が定まっており、口角も極端に上がっていて、自信があるように見える。
この、異常な口角の上がり方は、若い頃の彼の作品に見られたものに近い。
もう不自然ではないけど。
そうか、ゴヤは風刺画と同じデフォルメをつかっていたのか!
というひとつの仮説を得て、意気揚々とプラド美術館を後にしたのだった。











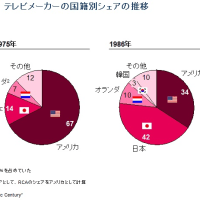
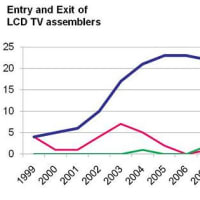
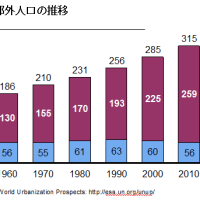
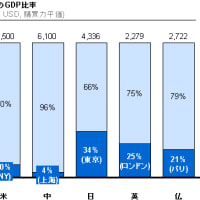

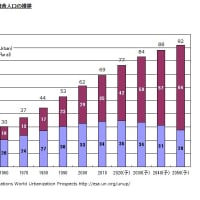
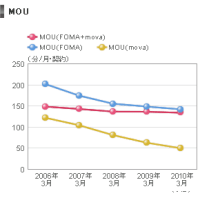
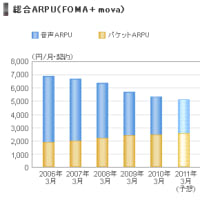
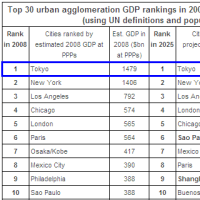
良い感じの建物ですね。ヨーロッパの美術館は建物自体に価値があったり、とても綺麗なので、絵が一層生きますね。美術館は、美術の倉庫ではなく、それを生かす環境を提供しないといけないんだな、と感じました。
スペイン・ハプスブルグ家がフランドルの絵画を集めたとすると、フランドルとスペインの絵画に影響関係はあったのでしょうか。フランドルの画家ではスペインに来た人はいたのかしら、と思いました。ベラスケスの絵って、とても落ち着いたタッチで、対象は王侯貴族ですが、フェルメールの庶民を描いた絵などと何だか似た雰囲気を感じます。
株主Etcの記事が盛り上がってる中、こういう記事にもコメントいただけるのはありがたいです。
>美術館は、美術の倉庫ではなく、それを生かす環境を提供しないといけないんだな、と感じました
これは本当にそうですね。
別に見に来てるひとは絵を勉強してる学生とかじゃなく、全体の雰囲気で非日常に浸れることを目的としてますしね。
美術館全体がひとつのエンターテイメントになってるって大切ですよね。
これとまったく同じ議論かもしれない、と思ったのがクラシック音楽の指揮者がカッコいいのは重要か、という議論。
私、西本智美という、とてもカッコよくて素敵な女性指揮者のファンなんですが、去年のN響の第九は彼女が振ったようで、大晦日にテレビで見たんです。
素敵な方なので女性を中心にファンも多いんですが、逆に「音楽性は大したことない」だとか、クラシックマニアの方には厳しい意見を言う方も多いんです。
でも、私、指揮者がカッコいいって重要だと思うんですよね。音楽性とか詳しいことは知りませんけど。
彼女が振ってるのを見るだけで惚れ惚れして、音楽が輝いて聞こえてくるわけで、音楽なんて総合エンターテイメントなんだから、指揮者のカッコよさも価値なんだよ!と思ったものです。
美術館がカッコいいのも大切ですよ。
書かれているように、もう一方のstrandの企業倫理とかのほうのコメント欄、凄いですね。レスを書くのも大変だろうなと、ほとほとLilacさんを尊敬しちゃいました。
それはさておき、クラシック音楽でも美術でも、その他の芸術でも、high arts とpopular artsの分類とか、味わい方の違いなどについては、イギリスでは日本よりもずっとミックスされ、混沌としている気がします。音楽演奏も、ポピュラーでもクラシックでも、オペラでもミュージカルでも、皆「ショー」ですからね。美術展もショーですし。去年、Tate Britainに行ったら、真ん中の長い廊下を、陸上の選手らしき若者が観客をぬって全力で走っているんです。危ないから練習するなら他でやって欲しいよ!なんて馬鹿なことを考えたのは私だけかもしれませんが、後で知ったんですが、それも一種のアートの一部だったみたいでした。発想が、まさに生きた美術館ですね。