週末は、大阪での集まりに参加しました。
話し合いでは、
今の日本の学校教育、中学受験が子供に及ぼす影響、
政府の打ち出すセンター試験廃止などの教育改革、
日米の教育の違い、などがトピックとなりました。
子供に関わる大人が自らの「恥ずかしい」という気持ちに向き合う大切さ
話し合いの中で、
「子供に関わる大人が、
自らの『恥ずかしい』という気持ちに向き合うことの大切さ」
についても言及されました。
親や先生の「恥ずかしい」という気持ちが、
いかに日本の教育に影響を与えているか。
子供が問題行動を起こしたら恥ずかしい。
この子はこんなこともできないと思われたら恥ずかしい。
子供が周りにフィットしなかったら恥ずかしい。
育て方が悪いと思われたら恥ずかしい。
教師としてこのクラスをうまくまとめられなかったら恥ずかしい。
生徒になめられたら恥ずかしい。
こうした大人側の、周りの目に映した「恥ずかしい」という気持ちが、
いかに大人がその子自身に向き合うことを妨げ、
個々の子どもが、その子らしい「道筋」と「ペース」で伸びていくのを、
邪魔してしまうか。
20世紀半ば、日本を「恥の文化」とし、
「日本人の思考や行動規範の中枢にあるのが、
他者に照らし合わせた『恥ずかしい』という気持ち」
としたのは、ルース・ベネディクトという米国の人類学者です。
・ハイリーセンシティブチャイルドに対して避けたい「~したら恥ずかしいでしょ!」
私自身、より個々の「内面的な律」を重視する「罪の文化」
とされる欧米に長らく暮しながら、
日本に帰り、この「恥の文化」を、ひしひしと感じています。
実母と過ごしていても、ここ2週間ほどで、
何度言われたでしょう。
「そんな振る舞いを子どもがしたら恥ずかしいでしょう。
ちゃんとしつけができてないと思われたら親として恥ずかしいでしょう」
そして、しみじみ思います。
私は、こうした雰囲気の中で育ったのだなあと。
そして、日本から出ることで、
どれほど自由を感じられるようになったかを。
そして、
子どもに接する大人が、
自らの「恥ずかしい」という気持ちに向き合うことがいかに大切かを思います。
私なりに「恥ずかしい」という気持ちに向き合う中で思うこと
今回の集まりに参加する前にも、
私なりに、自らの「恥ずかしい」という気持ちに
向き合うようにしていました。
私は、これまで様々な立場で教育に携わり、
子育てについて発信する身でもあります。
そうした人物の子ども達が、
周りの親御さんや先生方から見て「好ましくない行為」をしてしまい、
「普段、子育てについてあれやこれや言っているけど、
その人の子がこういう子?」
そんなように思われたら、「恥ずかしいよなあ」という私自身の気持ちに
気づいているようにしました。
そして、改めて覚悟を決めておいたんです。
たとえ、子ども達が、
「好ましくない行為」をしてしまったとしても、
周りへの印象を優先し、
表面だけとりつくろったり、
その場しのぎにおさめようと躍起になることはしないでおこう。
「周りから気に入られるいい子にさせる」のではなく、
その子自身の主体に基づく、「その子自身の体験」をさせてやりたい。
これまで様々な子ども達に関わる中で、私自身確信しているのは、
「好ましくない行為」や「問題行動」というのは、
その後の改善や成長へのチャンスでしかないということです。
ですから、
もし周りに迷惑をかけてしまったのならば共に謝りつつ、
それでも周りからどう思われても、
とにかく「その子の成長のために何ができるか?」にフォーカスし、
動き続けていこう、そう私なりに腹を据えるようにしました。
周りの大人が、我が子だけでなく他の子もひっくるめ、
子どもが起こす様々な「好ましくない行為」を、
「成長の過程」と長い目でとらえ、
「よりよくなるために何ができるだろう?」と、
現実的に動いていくのを励まし合うのならば、
確かに、子育ても随分と楽になり、
それぞれ異なる子供の個性も、よりのびのびと伸びていくのかもしれません。
それを可能とするためにも、
まずは自らの内に根づく「恥ずかしい」という気持ちに気づき、向き合い、
その都度、この子の成長にとって、
「今、何が大切なのか?」と動いていくこと必要なんですね。
米国で長年幼稚園の先生をしている方と
口を揃えて言っていたのが、
日本の細やかさ、勤勉さ、こつこつと改良を重ねる姿勢という土台の上に、
創造性や革新力が加わるならば、どんな文化だってかなわないだろう。
日本には、ものすごく「潜在的な力」がある、ということ。
15年ぶりに日本で過ごし、改めて、強く感じていることです。
「恥ずかしい」から、その子自身へと目を向けていくこと。
それは、個性の突き出しを許容し、
子ども達の創造性や革新力を培う方法のひとつでもあるのでしょうね。
以上、
今回の集まりで得た多くのインスピレーションの中のひとつです。
さて、
昨夜長野から戻り、今日から上2人は、親族の経営する保育園でボランティアです。
日々めまぐるしく貴い体験をさせていただいています。
みなさん、今日もよい日を!










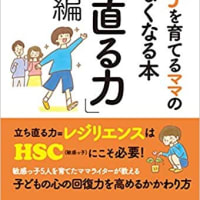





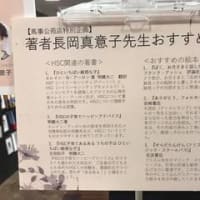

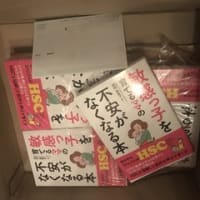

ブログも少しだけですが、拝見させていただきました。アドラー心理学を子育てに生かされているんですね。トアルさんの歩み、応援しています!
時間&体力限界までお話ししつつも、「もっと時間があったらなあ」と名残惜しかったです。
子ども達もおちびさんたちが可愛くてしょうがなかったようで、「ホンとに楽しかった!」と何度も言っていました。場を準備していただいたこと、改めてありがとうございます。そして、次回お話できる時を心より楽しみにしています!
先日の集まりに参加させていただきました、
直虎ちゃんと鰻の町のぽんみかんです。
今回、キャンセルがあり、急遽奈緒美先生からお声をかけていただき、充実した二日間を過ごさせていただきました。
マイコさんの記事は虹色教室からのリンクで前から拝見していました。なかなかコメントができず、今回ももっといろんなお話をさせていただきたかったな、アラスカのお話もたくさん聞かせてもらえば良かった!などと思っています(^^;)
でも、今回、自分自身もいつものように、あれ?私浮いてる?変なこと言った?などと気にすることも忘れて夢中で話をしていて、不思議とそれを後で落ち込むこともなく、誰の目を気にして子育てしてるんだろう、自分は何ができるだろう、何がしたいんだろうと考え続けていたところにこちらの記事を拝見しました。
ぽんすけが過敏なことはわかりすぎるくらい分かっているのに、自分に余裕がなくなるとダメですね。そしていつもそんな私を救ってくれているのがぽんすけだなと思います。
当のぽんすけ(初日うん◯発言を連発していた鯨のTシャツの男子です)は、ぽんはいっぱいみんなと英語で喋ったけどね〜(嘘つけー!!)とニヤニヤしていましたが、本当に楽しい時間を過ごさせていただきました!
マイコさんの記事を読んでやわらかな、しなやかな方だなと感じていましたが、その印象通りの素敵な方でした!
少しづつ他の記事の方も拝見させていただきますね!
そしてまたお話を聞かせていただける機会を楽しみにしています!
二日間ありがとうございました!
可愛いお子さんたちにもよろしくお伝えくだ
い。
急遽参加され、お会いすることができて、よかったです。我が家も思い出に残る充実した2日間となりました。
ブログを読んでいただいてありがとう。話は尽きず、2日間ではとてもとても間に合いませんよね。私も、もっとお話がしたかったですよ。
本当に、皆でのびのびと思いを言葉にし合えたのも、今回、奈緒美さんの周りに集まる方々が築く、そうした場の雰囲気があったからだなあと思います。周りにどう思われるかより、「とにかく、今の子育ての現状に何ができるだろう?」という気持ちが集まっていました。
ぽんすけくんの特性を理解しながら、包み込むように接してらっしゃったぽんみかんさんの様子が目に焼きついています。本当ですね、子どもにも教えられ、導かれ、支えられているんですよね。
「英語でいっぱいしゃべったよ~」と胸を張るぽんくんが可愛すぎます。
そんな風にいっていただいてありがとう!これからも、次回お会いするまで、ネットでよろしくお願いしますね。お互い、楽しい夏にしましょう!