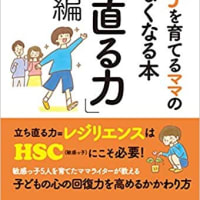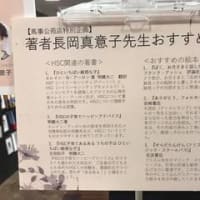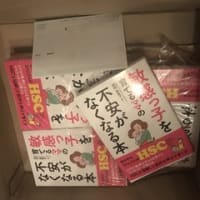昨日修学旅行から帰宅した次女6年生、
おかげさまで、かけがえのない5日間となったようです。
毎日大自然の中で、
ハイキングしたり(夜懐中電灯を持ってのハイキングも!)、
カヤックしたり、アスレチック施設で遊んだりと過ごしたそうです。
大の苦手の虫も、
お友達とわいわい楽しみながら、
随分と平気になったよう。
虫が苦手なのも、元々アラスカ生まれ育ちで、
これまで虫に慣れる機会というのがなかなかなかったのもあるんでしょうね。
年の半分近くは、氷と雪の銀世界でしたから。
とはいえ、同じ環境で過ごしてきても、
兄弟姉妹によって、全く平気な子もいますから、
やはり性質というのは大きいんだなあと実感しています。
今回5日間、コオロギや、アリや、毛虫に囲まれ、
何と、三女と次男が遊んでいたように、
お友達皆でそれぞれ1匹ずつ毛虫に名前をつけペットにしていたそう!(笑)
次女は、しましまだからと「ティガー」と名付けたそうです。
そしてマダニ!もそこかしこにいたようですが(シャワールームにも)、
付き添いの方が、常にピンセットを持ち歩き、
いつでも抜き取れる準備が整っていたようです。
同じキャビンのお友達もぬきとってもらったとのこと。
こちらで自然を楽しむには、常についてまわるものですね。
真っ青で大きな蛇にも2匹ほど出会ったと(ビーチから海に向かってゆうゆうと泳いで行ったのだそう)!
虫については、あとは「クモだけかな」と次女。
不安障害の7%を占めるのも「クモ恐怖症(Arachnophobia )」といいますが、
クモってなんなんでしょうね。
あの足が8本あってわさわさ歩く様子がだめなんですかね。
こちらの記事でも紹介した、「クモ恐怖症」の具体的セラピー方法について話すと、
この5日間でも随分と気持ちが楽になったことを振り返り、
「結局慣れなんだねー」と、
かなり納得のようでした。
大好きになる必要はないですが、
好きでもないけれど、大嫌いというほどでもない、
身体についたら、ぱぱっと払えばいいぐらいになれば、
より楽ですよね。
子供達も大きくなり、
「扁桃体が過剰に反応しやすい」といった
脳の特徴などについてもより具体的に話し合えるようになり、
「生き辛さの正体」が明確になることで、
少し楽になっていくように感じています。
我が家で有効な、
子供もイメージをとらえやすい比喩を用いた話し合いの内容など、
また後ほど書いていきます!