
『高慢と偏見』などの小説で知られるジェイン・オースティンの作品に、読書会のメンバー6人の人生を描き込んだヒューマンドラマ。全米ベストセラーとなった小説を基に、『SAYURI』の脚本家ロビン・スウィコードが初メガホンを取った。『プラダを着た悪魔』のエミリー・ブラントや『ワールド・トレード・センター』のマリア・ベロらが演じる読書会参加者が、オースティンへのアプローチを通して心に抱えた問題とも向き合っていく。彼女たちの悩みに提示されるシンプルな答えが、観る者の心にしみる。[もっと詳しく]
「オースティンは人生の最高の解毒剤よ」・・・なるほど。
読書会などというものを経験したことがない。
小説にしろ、評論にしろ、相手が男であれ、女性であれ、1対1で夢中になって感想を交換した事は、何度もある。
公園のベンチに座りながら、BARのカウンターでグラスを傾けながら、赤提灯の屋台で口から泡を飛ばしながら、あるいは遠距離の電話で明け方眠り込んでしまうまで・・・。
いや、読書会というものにつきあった1年程があった。
それは、大学に入った頃、いくつかの政治的な運動体から猛烈なオルグを受けたわけだが、最初は○○研究会のようなかたちで偽装されているのだ。
そこで、読書会(研究会)ということで何冊もテキストを渡された。
カール・マルクス「共産党宣言」「ドイツ・イデオロギー」「経済・哲学草稿」であったり、ヘーゲル「エンチクロペディ」であったり、レーニン「国家と革命」であったり・・・。
アジトのような部室の一角や、メンバーのアパートの炬燵を囲んで、文庫本にボールペンで線を引きながら、もちろん原書で読むほどの能力もなく、僕たちは「革命兵士」のひよこのように見られていたのかもしれない。
自堕落な僕は、すぐそういう空間から、ほどなくして落ちこぼれたというか抜け出したのであったが。
「ジェイン・オ-スティンの読書会」のような、ある意味優雅な「読書会」のようなものに誘われていたとしたら、(まああの時代のあの貧しい空間にあって、そんなことはありえないことなのだが)もう少し違った自分が存在しているかもしれないなと、想像してみたりもする。

ジェイン・オースティンは、イギリスの国民文学のようなものであり、ある意味で「ハーレークインロマンス」の原型のようなところもある。
英文学に造詣が深いインテリ層だけでなく、アメリカでも日本でも多くの(女性)読者に愛されている作家である。
「ジェイン・オースティンの読書会」では6冊の彼女の代表的小説を、女性5人、男性ひとりの6人の読書会のメンバーがそれぞれチューター役となって、毎月メンバーの家などに集まりながら、読書会を開くという構成になっている。
そして、チューター役のメンバーが実生活でおかれている状況と、取り上げる小説のヒロインたちの設定が、微妙にシンクロしているところに、脚本の妙がある。
半年間にわたる読書会を通じて、参加したメンバーの人生にも、ある変化が現れていくというところに、アメリカのいい意味で楽天的な、ほのぼのとさせる後味のよさが感じられる作品である。

2月。テキストは「エマ」。
チューターは「独身だけど幸せよ」という人の世話ばかり焼きながら、自分は大型犬であるリッジバッグのブリーダーをしているジョスリン(マリア・ベロー)。
主人公エマも、人の恋路のおせっかいやきをして、自分の幸せに臆病なヒロインである。
3月。テキストは「マンスフィールド・パーク」。
チューターは、20年連れ添った夫にある日突然、「もう、ときめかないんだ。他に好きな人が出来たから」と晴天の霹靂のような告白をされたシルヴィア(エイミー・ブレネマン)。夫の愛人が若い女ではなく、自分とあまり年が違わない女性であることにショックも倍増している。
物語の主人公ファニーも、富裕な一家に預けられて召使のような扱いをされる複雑な人生で、耐えることを宿命付けられている。
4月。テキストは「ノーサンガー・アビー」。
チューターは唯一の男性であり、オースティンなんか読んだこともないが、たまたま彼が属するSF研究会とジョスリンのブリーダー研究会の会合が同じ場所で開催された縁で、一目惚れしたジョスリンに誘われて参加することになったグリッグ(ヒュー・ダンシー)。
小説のヒロインであるキャサリンも、怪奇小説に影響を受けるという、オースティンでも異色の作品である。
5月。テキストは「自負と偏見」。
チューターは、メンバーのなかもっとも年上でお母さん役のような気配りをするが、自分は17歳で結婚し、その後6度の結婚を繰り返している人生の達人のようでもあるバーナデッド(キャシー・ベイカー)。
小説の中のエリザベスとダーシーも一筋縄ではいかない波乱の恋愛と結婚を体験している。

6月。テキストは「分別と多感」。
チューターはシルヴィアの娘であり、同性愛者で激情家であるアレグラ(マギー・グレイス)。手作りアクセサリーをネット販売しているが、スカイダイビングやロッククライミングなどの興奮型のスポーツにはまり込むが、ドジなところもありすぐに怪我をしてしまう。
小説の性格が対極のマリアンとエリナーというふたりの姉妹は、派手で多感なアレグラと、慎みがあり分別に縛られてもいる母のシルヴィアと、相似しているといえなくもない。
7月。テキストは「説得」。
チューターはヒッピーの母親と、スポーツ好きの夫を持ちながら、フランスに行ったこともないフランス語教師をしながら、自分を偽装しているかのように演じているプルーディー(エミリー・プラント)。
小説も婚約を破棄したアンとウエントワースが再び結びつくお話なのだが、それはプルーディーが、若い教え子と夫との間を揺れ動く感情と重なっている。

ジェイン・オースティンの小説世界は、貴族社会が平民社会に拡散されてくる時期(18世紀末から19世紀初頭にかけて)の近代心理劇のさきがけのような世界なのだが、登場人物たちに読者自身が投影されるような読み方ができるところから、絶大な人気を誇っているといえなくもない。
もう時代は200年も経過している。
オースティンが描いたイギリスの自然豊かな田舎町の中流社会とはかけ離れている。
この映画の冒頭も、テンポのよいスピードで、エレクトロニクス製品やIT社会のさまざまなデバイスに翻弄されストレスにさらされる現代の都市生活者の様相を風刺的にスケッチしている。
「ワインとおしゃべり、ときどき恋」といったこの作品のキャッチフレーズや、この作品に漂う軽妙で知的なおかしさということはあるとしても、それでも、オースティンが描いた「近代」の心理劇から、その人間関係の微妙な綾のようなものから、僕たちもそれほど遠く離れているわけではないのかもしれない。

監督・脚本はロビン・スウィコード。1952年生まれで、ほとんど僕と同世代だが、夫である劇作家であり映画監督でもあるニコラス・カザンの方が僕らには親しい。
「SAYURI」(05年)の脚本家でもあるのだが、今作の饒舌なおしゃべりと軽妙な読者会のメンバーたちの人生スケッチと読書に没入するときの各人の沈黙世界のバランスがとても上手にとれている。
次回作も、ジェイン・オースティン研究家の一家の物語ということなので、それはまた愉しみでもある。

女優たちはいずれも素晴らしい個性を出しているが、「プラダを着た悪魔」でブレイクしたエミリー・プラントは、ちょっと初期のオードリー・ヘップバーンを髣髴とさせるところがある。
あと、心優しきオタク青年であるグレッグのSFやミステリーや怪奇小説が並んでいるような蔵書室もいい感じだ。
グレッグが一目惚れしたジョスリンにSFにはこんな作品もあるんだぜ、と渡すのがル・グィンの「闇の左手」であり、僕のSFベスト3でもある作品である。もちろん、日本では「ゲド戦記」のファンが多いのだろうが。
「オースティンは人生の最高の解毒剤よ」と、登場人物のひとりに語らせている。
なかなかのものだ。
kimion20002000の関連レヴュー
「プライドと偏見」











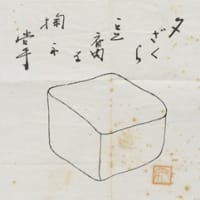


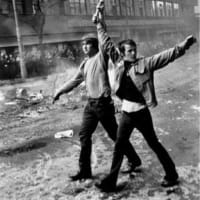



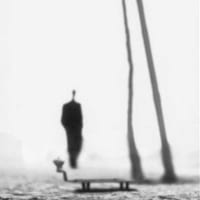

TBありがとございました。お返しが遅くなりごめんなさい。
>近代心理劇のさきがけのような世界なのだが、登場人物たちに読者自身が投影されるような読み方ができるところから、絶大な人気を誇っているといえなくもない。
なるほど…たしかにそんなところもありますね。
イギリスらしい、シニカルなモノの見方も独特な感じですね。そこに惹かれていく…
次回作…私も楽しみです。
世界中の女性たちに、共通したテーマを扱っているように思います。
通俗なんですけど、とても普遍的なものがあると思います。
「エマ」と言えば、90年代でアメリカでヒットした青春映画「クルーレス」は「エマ」の現代翻案版でしたし、「イルマーレ」アメリカ版では「説得」が多少モチーフになっていましたね。
かように現在オースティンは大人気ですけど、スケッチ的な描写の積み重ねは、ニューシネマ以降の映画に通ずるものがありますから、90年代以降映画界でも物凄い人気になったのが理解できますね。
オカピーさんが似非インテリなら、僕はその十乗ぐらいの似非ですけど(笑)
結局、人間というのは、近代以前と近代以降がいいも悪いもあるのかなと思います。
で、近代以降の精神というのは、あれこれいっても似たり寄ったりかもしれません。
時代意識は確実に変遷しているんですけど、家族とか自意識とか男女の心理劇などはそれほど変わっていないかもしれません。