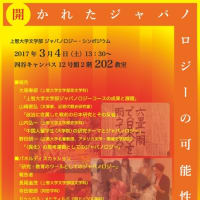『歴史評論』12月号で「『日本霊異記』から古代の社会をよむ」という特集が組まれ、私も参加して「説話の可能態」という駄文を寄せました。説話は伝承とは異なり、語りの場で絶えず変動する言説であるから、書かれたものから在地での内容に迫ることは難しい。物語を成り立たせている多様な文脈を探り当て、その変動領域(発現しうるかたち、すなわち可能態)を把握することが重要であると主張したものです。
2年前の宗教言説研究会でおおまかな内容は報告、今夏、首都大OU終了後の飲み会で構想を練り直し、8月末に文章化しました。多くの人に支えられてできあがった原稿ですが、ちょっと言葉足らずになってしまいましたかねえ……。
ぼくは『霊異記』を読む際、景戒の思想や社会認識以前に、その言葉が厄介だと考えています。言語論的転回以後、テクストの外にはテクストしかないという実証主義批判を受けて、言語の問題にはかなり慎重になってきました。例えば化牛説話でもいいですが、指示地域や採録時期、収録巻数なども異にする説話群が共通の表現・文言を持つというのは、景戒の整理・記録に由来すると考えた方が自然ですし、仏典や漢籍との共通項が見出せるのは、彼がそれらの言説をパッチ・ワーク的に繋いで文章を紡いでいったからでしょう。
これまでの研究史では、この景戒の筆録、というより、書くという行為がいかなる意味を持つものなのか、かなり軽視されてきたように思います。無色の記録などというものはありえませんから、書くことと解釈すること、創造することとは切り離せません。原説話が口承であるにしろ書承であるにしろ、景戒の筆録作業を介することで、それは景戒の文体になってしまいます。語りの現場がフレキシブルなものであればなおさらですし、第一、話し言葉と書き言葉が隔絶している古代、充分浸透していない仏教的言辞・表現を用いての文章化とすれば、説話は景戒による筆録の時点で生まれたともいいうるでしょう。よって、素材情報に在地社会との関係を問うことは不可能ではないものの、説話の内容から在地の実態を復原するのは大変困難な作業となり、実はほとんど確かな根拠がなくなってしまうのです。
こういうことをいっていると相対主義者のように思われてしまいますが、しかし私も実態の存在を否定しようとしているわけではなく、あくまでその把握のための準備作業を行っているつもりです。つまり、景戒が〈書いたもの〉から実態を読もうとする従来の研究では、実態はむしろ明らかにならず、かえって景戒の構築したテクスト内部で右往左往することになってしまう。そうではなく、景戒の〈書く〉という行為からこそ、実態に迫ることができるのではないか、というわけです。
研究史の流れに乗ってしまっているので不自然には感じませんが、『霊異記』に載っているということ以外、形成主体も時期も過程も分からない説話を、その登場人物や事物と直結させながら分析してゆくという方法は、たぶん日本史学でしか通用しないのではないでしょうか。例えば人類学や民俗学で、インフォーマントが明確に判明している(研究者の前で語ってくれている)物語り自体の不確定性が問題になり、より細密な方法が模索されている現在、歴史学における『霊異記』の研究情況は、ぼくにはものすごく牧歌的に思えてしまいます。じゃ、お前の方法はどうなのよ、といわれると、すごく困るんですけどね。
いずれにしても、『霊異記』については、今後も常にいろいろな方法を試しながら〈読み方〉を模索してゆこうと思っています。今回は、〈説話の可能態〉という視角で、書かれたもの=語られたものという誤解、話型は変動しないという信仰を壊し、現場の語りの多様性を再構成することが目的でした。あまり成功しませんでしたが、また次の機会に頑張ります。
2年前の宗教言説研究会でおおまかな内容は報告、今夏、首都大OU終了後の飲み会で構想を練り直し、8月末に文章化しました。多くの人に支えられてできあがった原稿ですが、ちょっと言葉足らずになってしまいましたかねえ……。
ぼくは『霊異記』を読む際、景戒の思想や社会認識以前に、その言葉が厄介だと考えています。言語論的転回以後、テクストの外にはテクストしかないという実証主義批判を受けて、言語の問題にはかなり慎重になってきました。例えば化牛説話でもいいですが、指示地域や採録時期、収録巻数なども異にする説話群が共通の表現・文言を持つというのは、景戒の整理・記録に由来すると考えた方が自然ですし、仏典や漢籍との共通項が見出せるのは、彼がそれらの言説をパッチ・ワーク的に繋いで文章を紡いでいったからでしょう。
これまでの研究史では、この景戒の筆録、というより、書くという行為がいかなる意味を持つものなのか、かなり軽視されてきたように思います。無色の記録などというものはありえませんから、書くことと解釈すること、創造することとは切り離せません。原説話が口承であるにしろ書承であるにしろ、景戒の筆録作業を介することで、それは景戒の文体になってしまいます。語りの現場がフレキシブルなものであればなおさらですし、第一、話し言葉と書き言葉が隔絶している古代、充分浸透していない仏教的言辞・表現を用いての文章化とすれば、説話は景戒による筆録の時点で生まれたともいいうるでしょう。よって、素材情報に在地社会との関係を問うことは不可能ではないものの、説話の内容から在地の実態を復原するのは大変困難な作業となり、実はほとんど確かな根拠がなくなってしまうのです。
こういうことをいっていると相対主義者のように思われてしまいますが、しかし私も実態の存在を否定しようとしているわけではなく、あくまでその把握のための準備作業を行っているつもりです。つまり、景戒が〈書いたもの〉から実態を読もうとする従来の研究では、実態はむしろ明らかにならず、かえって景戒の構築したテクスト内部で右往左往することになってしまう。そうではなく、景戒の〈書く〉という行為からこそ、実態に迫ることができるのではないか、というわけです。
研究史の流れに乗ってしまっているので不自然には感じませんが、『霊異記』に載っているということ以外、形成主体も時期も過程も分からない説話を、その登場人物や事物と直結させながら分析してゆくという方法は、たぶん日本史学でしか通用しないのではないでしょうか。例えば人類学や民俗学で、インフォーマントが明確に判明している(研究者の前で語ってくれている)物語り自体の不確定性が問題になり、より細密な方法が模索されている現在、歴史学における『霊異記』の研究情況は、ぼくにはものすごく牧歌的に思えてしまいます。じゃ、お前の方法はどうなのよ、といわれると、すごく困るんですけどね。
いずれにしても、『霊異記』については、今後も常にいろいろな方法を試しながら〈読み方〉を模索してゆこうと思っています。今回は、〈説話の可能態〉という視角で、書かれたもの=語られたものという誤解、話型は変動しないという信仰を壊し、現場の語りの多様性を再構成することが目的でした。あまり成功しませんでしたが、また次の機会に頑張ります。