すでに概要は述べたとおりですが、14日(土)、京都の龍谷大学にて仏教史学会の1月例会が行われました。報告者は、院生時代からの付き合いで、方法論懇話会の同志でもある師茂樹さん。人文学へのコンピュータ利用の分野でよく知られた師さんですが、今回は本当の専門、法相唯識学に関連する発表で、タイトルは「五姓各別説と観音の夢―『日本霊異記』下巻第三十八縁の読解の試み―」。まさに、下38の解釈としては、私の知る限りのなかで最も説得的な学説でした。報告の詳しい内容については、師さんがご自身のブログでも解説していますし、hp「もろ式」の方にもレジュメが公開されていますので、そちらを参照してください。ここでは、私の個人的な感想を述べるに止どめます。
今回の報告のなかで、私の関心に直結してきた論点は二つ。
ひとつめは、景戒による『霊異記』編纂が、同時代の法相/三論二宗による〈空有論争〉にリンクする可能性が示されたことです。これは中国に淵源し、一切皆成/一分不成仏をめぐる論争の内実を持ちつつ、徳一/最澄の三一権実論争にまで繋がってゆく長大な議論。景戒が自宗の存在意義、そして自らの仏教者としての主体性に関わるようなこの問題に、まったく無関心であったはずはない。そこで師さんは、下38の夢解きにおける五姓各別説を、法相の原則に沿って厳密に解釈すべきことを指摘する。一見至極当然のようですが、実はこのパースペクティヴは、戦後仏教史を規定する〈大乗主義的近代性〉への鋭い批判ともなっているのです。いま思い浮かんだ造語で厳密なものではありませんが、近代人権思想とも結びついた、一切皆成こそ最良であり一分不成仏など差別思想とする価値観ですね。これが歴史学の世界にも蔓延していて、研究者の認識を大きく束縛してきた。聖徳太子―行基―親鸞を日本仏教の核とする龍谷の二葉史学など、その典型ではないでしょうか(神祇不拝、習俗排除をうたう真宗の近代教学なんかも当てはまるでしょうね)。もちろん、二葉憲香の業績それ自体は偉大ですが(門下の宮城洋一郎さんや中川修さんには本当にお世話になっています)、例えば行基研究などでは、「法相宗ではあるが、民衆救済に尽くした行基が五姓各別説にはまりこんでいたはずはない。彼はその枠を超越し、大乗菩薩道に目覚めたのだ」という路線を敷いてしまい(真宗の僧侶でもある私も、かつてはそのなかにどっぷりと浸かりきっていたものです)、法相宗僧侶の思考をそれ自体として考察する道を閉ざしてしまった。景戒も同様の位置づけをされてきたわけで、師さんはこの認識枠組み自体に再考を迫り、法相の考え方においてもとうぜん菩薩行が可能であること(種子のとおりに教導し、無種姓者は人・天に生まれさせる)、下38も五姓各別説で整合的に読みうることを示したのです。
この点に関連してひらめいたのが、『霊異記』の歴史叙述としてのスタイルの問題。周知のとおり『霊異記』三巻は、それぞれ、上巻:聖徳太子に象徴される仏教伝来期、中巻:行基に象徴される聖武朝、下巻:孝謙朝から景戒の現在に至る時期、に区分され、説話で綴る日本仏教史としての構成をとっています。上巻の聖徳太子記述は、『書紀』を参照しつつも微妙に異なったイメージを創出していますが、それはやはり太子を日本仏教の原点に位置づけようとする大安寺グループとの、〈表象をめぐる闘争〉だったのではないでしょうか。『書紀』の仏教記述が、道慈をはじめとする大安寺グループの操作を受けていることは明白で、法王としての太子像も光明皇后から孝謙女帝への流れのなかで成立してくる。法相宗の景戒はこれらの人々に批判的で、教学的にも対立しており、とすれば、『書紀』とは異なる日本仏教史を自覚的に構想したと考えてもおかしくありません。『霊異記』自体のスタイルを決定づける根本的問題とも思われるわけです。夢想でしょうかね。
ふたつめは、下38の第一の夢を、菩薩戒に伴う観音の好相行として解釈した点。梵網戒の自誓受戒に観想行が伴うことについては、すでに山部能宜さんの研究があります。師さんもこの見方を踏まえて、景戒の慚愧と観音の聖示に、『梵網経』第23軽戒に即した得戒の保証・肯定をみているわけです。
山部さんの研究については、以前、私が中国における神身離脱言説の成立を論じた際、師さんとの間で話題になったことがありました。私は、「ふの会」という文学者・人類学者・民俗学者・歴史学者によるシャーマニズムの研究会に参加、仏教的言説を修行=神秘体験の観点から分析する方法を模索していました。師さんとのやりとりは、2003年の方法論懇話会メーリング・リストでも蒸し返されましたが(No.17-18を参照)、その際すでに彼は、「初期唯識派、玄奘とその弟子、日本中世の法相宗などに見られる弥勒信仰≒観仏≒菩薩行 etc... などをきちんと掘り起こし、哲学的、近代的な議論ばかりして偉そうにしている唯識研究者 (^_^;; が無視し続けてきた宗教的な部分をきちんと結び付けたいな」と語っているんですね。師さんはその後も精進して今回の報告にたどりつき、私は放っておいたまま何もしなかった、ということでしょうか。猛反省です。
しかし、そんな私もようやく奮起、24日に行った『三宝絵』研究会の発表では、先の関心を再燃させたのでした(これについてはまた書きます)。
例会終了後の懇親会では、師さん、稲城正己さん、佐藤文子さんと刺激的な議論で盛り上がりました。佐藤さんは、同一の用語として疑いなく使用されている私度僧/自度僧が、実はまったく異なるものであるという驚くべき見解を発表されたばかり(早く論文化してください!)。得度、受戒、修行、戒律……これまで歴史学では制度的なアプローチしかできなかった問題について、真に宗教的に取り組める方向性がみえてくるようでワクワクしました。師さん、本当にありがとうございました。それから、恐らくは歴史学会から無視もしくは大批判されるだけだろうと思っていた拙稿、「説話の可能態」の〈可能性〉を、最大限に引き出してくださったことにも感謝します。学問は独りでやっているんじゃない、その感動を味わえたひとときでした。
今回の報告のなかで、私の関心に直結してきた論点は二つ。
ひとつめは、景戒による『霊異記』編纂が、同時代の法相/三論二宗による〈空有論争〉にリンクする可能性が示されたことです。これは中国に淵源し、一切皆成/一分不成仏をめぐる論争の内実を持ちつつ、徳一/最澄の三一権実論争にまで繋がってゆく長大な議論。景戒が自宗の存在意義、そして自らの仏教者としての主体性に関わるようなこの問題に、まったく無関心であったはずはない。そこで師さんは、下38の夢解きにおける五姓各別説を、法相の原則に沿って厳密に解釈すべきことを指摘する。一見至極当然のようですが、実はこのパースペクティヴは、戦後仏教史を規定する〈大乗主義的近代性〉への鋭い批判ともなっているのです。いま思い浮かんだ造語で厳密なものではありませんが、近代人権思想とも結びついた、一切皆成こそ最良であり一分不成仏など差別思想とする価値観ですね。これが歴史学の世界にも蔓延していて、研究者の認識を大きく束縛してきた。聖徳太子―行基―親鸞を日本仏教の核とする龍谷の二葉史学など、その典型ではないでしょうか(神祇不拝、習俗排除をうたう真宗の近代教学なんかも当てはまるでしょうね)。もちろん、二葉憲香の業績それ自体は偉大ですが(門下の宮城洋一郎さんや中川修さんには本当にお世話になっています)、例えば行基研究などでは、「法相宗ではあるが、民衆救済に尽くした行基が五姓各別説にはまりこんでいたはずはない。彼はその枠を超越し、大乗菩薩道に目覚めたのだ」という路線を敷いてしまい(真宗の僧侶でもある私も、かつてはそのなかにどっぷりと浸かりきっていたものです)、法相宗僧侶の思考をそれ自体として考察する道を閉ざしてしまった。景戒も同様の位置づけをされてきたわけで、師さんはこの認識枠組み自体に再考を迫り、法相の考え方においてもとうぜん菩薩行が可能であること(種子のとおりに教導し、無種姓者は人・天に生まれさせる)、下38も五姓各別説で整合的に読みうることを示したのです。
この点に関連してひらめいたのが、『霊異記』の歴史叙述としてのスタイルの問題。周知のとおり『霊異記』三巻は、それぞれ、上巻:聖徳太子に象徴される仏教伝来期、中巻:行基に象徴される聖武朝、下巻:孝謙朝から景戒の現在に至る時期、に区分され、説話で綴る日本仏教史としての構成をとっています。上巻の聖徳太子記述は、『書紀』を参照しつつも微妙に異なったイメージを創出していますが、それはやはり太子を日本仏教の原点に位置づけようとする大安寺グループとの、〈表象をめぐる闘争〉だったのではないでしょうか。『書紀』の仏教記述が、道慈をはじめとする大安寺グループの操作を受けていることは明白で、法王としての太子像も光明皇后から孝謙女帝への流れのなかで成立してくる。法相宗の景戒はこれらの人々に批判的で、教学的にも対立しており、とすれば、『書紀』とは異なる日本仏教史を自覚的に構想したと考えてもおかしくありません。『霊異記』自体のスタイルを決定づける根本的問題とも思われるわけです。夢想でしょうかね。
ふたつめは、下38の第一の夢を、菩薩戒に伴う観音の好相行として解釈した点。梵網戒の自誓受戒に観想行が伴うことについては、すでに山部能宜さんの研究があります。師さんもこの見方を踏まえて、景戒の慚愧と観音の聖示に、『梵網経』第23軽戒に即した得戒の保証・肯定をみているわけです。
山部さんの研究については、以前、私が中国における神身離脱言説の成立を論じた際、師さんとの間で話題になったことがありました。私は、「ふの会」という文学者・人類学者・民俗学者・歴史学者によるシャーマニズムの研究会に参加、仏教的言説を修行=神秘体験の観点から分析する方法を模索していました。師さんとのやりとりは、2003年の方法論懇話会メーリング・リストでも蒸し返されましたが(No.17-18を参照)、その際すでに彼は、「初期唯識派、玄奘とその弟子、日本中世の法相宗などに見られる弥勒信仰≒観仏≒菩薩行 etc... などをきちんと掘り起こし、哲学的、近代的な議論ばかりして偉そうにしている唯識研究者 (^_^;; が無視し続けてきた宗教的な部分をきちんと結び付けたいな」と語っているんですね。師さんはその後も精進して今回の報告にたどりつき、私は放っておいたまま何もしなかった、ということでしょうか。猛反省です。
しかし、そんな私もようやく奮起、24日に行った『三宝絵』研究会の発表では、先の関心を再燃させたのでした(これについてはまた書きます)。
例会終了後の懇親会では、師さん、稲城正己さん、佐藤文子さんと刺激的な議論で盛り上がりました。佐藤さんは、同一の用語として疑いなく使用されている私度僧/自度僧が、実はまったく異なるものであるという驚くべき見解を発表されたばかり(早く論文化してください!)。得度、受戒、修行、戒律……これまで歴史学では制度的なアプローチしかできなかった問題について、真に宗教的に取り組める方向性がみえてくるようでワクワクしました。師さん、本当にありがとうございました。それから、恐らくは歴史学会から無視もしくは大批判されるだけだろうと思っていた拙稿、「説話の可能態」の〈可能性〉を、最大限に引き出してくださったことにも感謝します。学問は独りでやっているんじゃない、その感動を味わえたひとときでした。












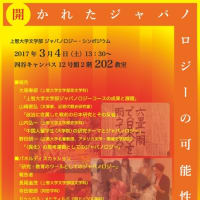













http://moromoro.jp/morosiki/resources/20060114.pdf
ご批正くださいませ。>皆様
あと「師さんはその後も精進して今回の報告にたどりつき」とおっしゃっていただいてますが、私も別に何か「精進」していたわけではなくて、このあいだの例会の準備は正味1週間ぐらいしかやっておらず泥縄もいいとこ、しかしチャンスを与えていただいたおかげで(そして何より聞き手がすばらしかったおかげで)、ようやく口だけ番長の汚名をわずかながら返上できたという次第です。