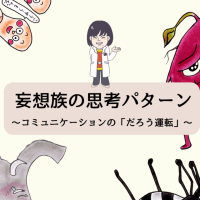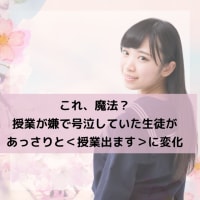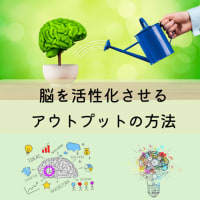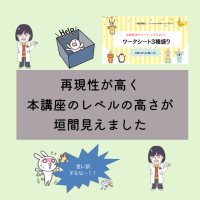(一社)ハートマッスルトレーニングジム代表
主体的人生を構築する人材育成トレーナー 桑原朱美です。
今日のテーマは
「感情コントロールよりビリーフに気づき緩めることが大事」です。
保健室コーチングや波動脳科学では
ビリーフやプログラムをX=Yという表現でお伝えしています。
セルフアクセプトコース第2講では、ビリーフがどのように現実を作り
その現実の体験がビリーフを強化するというお話をしました。
感情は、ビリーフから生まれそこから思考が生まれます。
そして、その思考が言葉を作り、行動を作り、
結果として感情を生み出します。
結果としての感情を何とかしようとするより
ビリーフに気づき、ビリーフを認め
緩めていくということが大事です。
プログラムとかビリーフを学ぶと
どうしても人間はそれを「悪いもの」と決めつけ
そのプログラムを変えなきゃ、消さなきゃ、排除しなきゃと
考えてしまいます。
それを自分自身やかかわる相手にやろうとすると
余計に苦しくなってしまいます。
ビリーフは、ただ、気づいて
緩めていくだけでよいのです。
今日の域では、執着や自己否定のパターンが緩まって
楽になったというAさんの感想をご紹介します。
------------------------
変性自我にどうやってかかわるか、
具体的な方法が分かり私にもできそう!
と思うことができました。
○○ちゃん出てきた!と言葉にしてみる、
そして、何らかのビリーフに気づいたら、手放す!
ということが、
先生の語る言葉と3枚のスライド(イラスト)で
頭の中にくっきりと刻まれました。
ストンと理解できたのは、
一つは「執着」という言葉が引っ掛かったからです。
執着しているから、
いつもの同じ思考で苦しむパターンが出るのですね。
私、自分を否定することに執着していたなと思うと、
なんだ、そういうことかと気持ちが楽になりました。
例えばパターン1 の「どうせ私、無理!」に気づいたら、
「出た~執着パターン!」とつぶやきます。
これで自分攻撃がストップできそうです。
その先の意図は?のところは次のステップにします。
2つ目は、ビリーフはゆるめることができるということ。
これをアロンアルフアからダイソーの糊でくっついた状態になる
という説明で、「ゆるまる」のイメージがすぐに浮かび、
ビリーフが緩まればいいんだな、
X =Y が緩まると、
いつもの思考も柔軟になるという流れが、
ぱっとイメージできたからです。
消す・なくすことにフォーカスしていると、
「出てきたらダメ、まだできない私」に苦しみます。
そこじゃないなと思えました。
そして、3つ目は、イメージできたからです。
握っていた蝶が手を開くとひらひら飛んでいき、
周りの花がキラキラしているスライドを見たときは、
ほんわか和みました。
えっ、今、簡単に飛んだ?
手を開いたらいいだけ…かと、
こんな単純な動作でよかったんだと
初”理解し、ホッとしました。
「手放す」という言葉だけでやるより、
断然効果ありそうです。
出てきた感情をコントロールしようとすると、
時間も日にちもかかるし
エネルギーも大量に出さないと自分を取り戻せません。
(そのエネルギーどこから出しているのでしょう?と言いたいですが。笑)
かなり疲れます。
結局、落ち込み、そして八つ当たり→自己嫌悪。
こうやっていつも同じ思考とつぶやきにより、
嫌なビリーフは自分で強化していることも納得でした。
赤枠と黒枠で囲まれて強化されていくビリーフのイラストが
インパクトありすぎでした。
感情が動いたら…やること、準備は整いました。
ビリーフ崩しを楽しみます。
------------------------
A先生 ありがとうございます。
保健室での子どもたちへのかかわりにおいても
結果としての相手の「感情」をなぐさめよう
何とかしなくてはと考えてしまうことがあります。
桑原も、脳科学に出会うまでは
そこに陥ってしまうことがありました。
大切なのは、誰かの感情を「何とかしてあげる」
ということではないと考えています。
何とかしてもらうばかりだと、
その相手は、ずっと、それを「してくれる」相手を
探すことになります。
しかし、その感情を生み出すビリーフがあることを知り
自分でなんとかできるんだということを
その子が学び、実践できるようにするすると
何かの感情が起きたとき
自分で自分を整えることができます。
そのためには、まずは、子どもにかかわる大人自身が
自分のパターンを理解し、自分で手放すことができること!
もちろん、学校現場においては
子どもたちの感情を整えてあげるというかかわりも
大切です。
両方やりながら、最終的には
自分のパターンを生み出すビリーフに気づき
自分で自分を扱うことができる(自分のトリセツ)
を身に着けることなのだと思います。
誰かを助けることを目的とするのではなく
自分で自分を救うことができる
生きる力を育てることが大事なのです。
それでは、今日も
素敵な1日を!
この記事は、メルマガ「可能性をあきらめたくない女性のための時間と思考の使い方」
2022年8月26日号で紹介した内容に加筆修正した内容です。
![]() 公式LINEアカウントでつながると、ブログの更新情報や講座の情報が最速で届きます
公式LINEアカウントでつながると、ブログの更新情報や講座の情報が最速で届きます