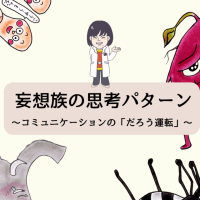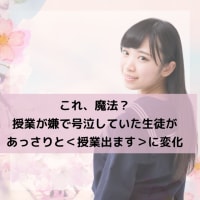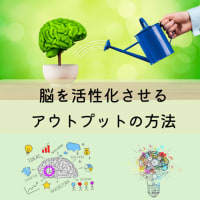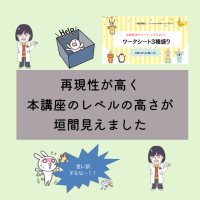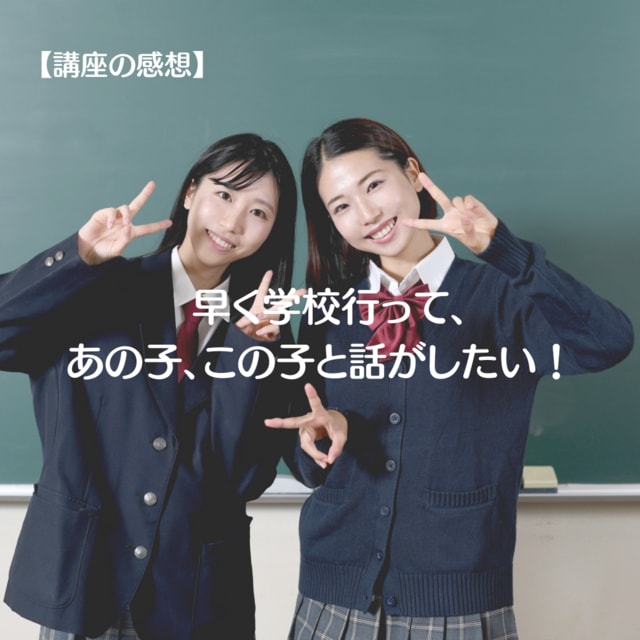
(一社)ハートマッスルトレーニングジム代表
主体的人生を構築する人材育成トレーナー
桑原朱美です。
今日のテーマは
「【講座の感想】 早く学校行って、あの子、この子と話がしたい!」です。
アドバンスコース第5講の感想その3です。
私たちは、傾聴において「言語」を聴きます。しかし、お互いの地図は違います。
それを意識することなく、ただ相手のストーリーを聴くだけでは、傾聴の本来の機能を果たすことはありません。
共感やら繰り返しやらというスキルで聞くことが大事なのではないのです。
脳科学傾聴は、言語の生成過程で脳の中で何が起きているのかを理解したうえで行います。
それが腑に落ちると、傾聴によって、相手の気づきの深まりが変わります。
① 「早く学校行って、あの子、この子と話がしたい」
講座中から、早く学校行って、生徒と話がしたいと思っていました。(その後、行事、修学旅行、コロナ濃厚接触での自宅待機のためまだ生徒たちと会ってじっくり話をしていません)
講座の最初の最初の「保健室コーチングのアプローチの構造」からわかっていないことがよくわかりました。長期的、継続的な戦略と行動のための伴走ができていません。以前よりは、生徒のX=Yを考えながら話を聴いたり、生徒のことを考えるときにX=Yを考えるようになって来ていますが、ワークについては戦略的とは程遠いのが現状です。今回の講座でアプローチの構造、現状から達成までの溝を埋めることについて図で示していただきよくわかりました。私に足りていない言語化の必要性についても考えることが出来ました。継続的な戦略と行動を考えていきます。
② 「物わかりの悪い大人になるって難しい」
「先回りすると生きるチカラは育たない」何度も何度も講座で聴いて頭ではよくわかり、日々、実行しているつもりです。生徒にも保護者にも先生方にも伝えています。頭ではよくわかっているのですが、先回りした方が楽です。あまりに一言言いの生徒が多くて、うちの子どもも・・・自分で気づいているときは、先回りしないのですが、油断すると先回りしています。これもまた、私自身の変性自我ちゃんなのかなと思います。まだまだ、察してほしい、察して動く自分が出てきます。
③ 「脳科学傾聴の力を高める」
課題です。講座を聴いて、資料を読んで内容がわかるのと、生徒の話をしっかり聞くことにまだまだ溝があります。話を聴くときに頭の中で整理し、次の質問をするまでにスピードがついていかず、トンチンカンになってしまいます。ワークシート等があれば順を追って話を聴くことができるのですが、話を聴きながら頭の中で整理し、瞬時に考えることが極端に苦手かも。ただ、苦手というと苦手になることはわかっているので「どうしたらできるか」思考で100本ノックのように経験を積み重ね、力を高めていきたいと思います。次回も楽しみです。どうぞよろしくお願いします。
講座中から、早く学校行って、生徒と話がしたいと思っていました。(その後、行事、修学旅行、コロナ濃厚接触での自宅待機のためまだ生徒たちと会ってじっくり話をしていません)
講座の最初の最初の「保健室コーチングのアプローチの構造」からわかっていないことがよくわかりました。長期的、継続的な戦略と行動のための伴走ができていません。以前よりは、生徒のX=Yを考えながら話を聴いたり、生徒のことを考えるときにX=Yを考えるようになって来ていますが、ワークについては戦略的とは程遠いのが現状です。今回の講座でアプローチの構造、現状から達成までの溝を埋めることについて図で示していただきよくわかりました。私に足りていない言語化の必要性についても考えることが出来ました。継続的な戦略と行動を考えていきます。
② 「物わかりの悪い大人になるって難しい」
「先回りすると生きるチカラは育たない」何度も何度も講座で聴いて頭ではよくわかり、日々、実行しているつもりです。生徒にも保護者にも先生方にも伝えています。頭ではよくわかっているのですが、先回りした方が楽です。あまりに一言言いの生徒が多くて、うちの子どもも・・・自分で気づいているときは、先回りしないのですが、油断すると先回りしています。これもまた、私自身の変性自我ちゃんなのかなと思います。まだまだ、察してほしい、察して動く自分が出てきます。
③ 「脳科学傾聴の力を高める」
課題です。講座を聴いて、資料を読んで内容がわかるのと、生徒の話をしっかり聞くことにまだまだ溝があります。話を聴くときに頭の中で整理し、次の質問をするまでにスピードがついていかず、トンチンカンになってしまいます。ワークシート等があれば順を追って話を聴くことができるのですが、話を聴きながら頭の中で整理し、瞬時に考えることが極端に苦手かも。ただ、苦手というと苦手になることはわかっているので「どうしたらできるか」思考で100本ノックのように経験を積み重ね、力を高めていきたいと思います。次回も楽しみです。どうぞよろしくお願いします。
①伝えたことは、伝わったことではない
すぐ来ると言われても1時間待ちぼうけをした体験があるため、時間については確認するくせがついているが、普段、自分が使っている言葉の定義が人とは違うことを全く意識せずに過ごしていたと思う。講座中にハッとした。「友達」という言葉でも、使っている意味が全く違うので、「自分の中の言葉の定義=思い込みだらけ」を確認したいと思った。
②コミュニケーションの前程
「相手のことをわかっていない」=「自分のこともわかってもらえていない」ということである。そのことを意識して過ごしていなかったと思う。自分の言っていることは、全て理解してもらっているぐらいに感じていたけど、言葉の定義やその背景、思い込みも全く違うはずなので、確認して話をするようにしたいと思う。
③ニューロロジカルレベルを意識して聴く
「私はバカだから、、、」という生徒が来たことがある。どんな理由でそう思ったかを聴いたとは思うが、ニューロロジカルレベルを気にせずに聴いていたと思う。行動が理由だったら行動を変えるにはどうしていきたいかを話すとよい。意識してないと咄嗟にはできないので、日頃からニューロロジカルレベルを意識しておこうと思った。
気づき:自分の話が伝わっていると思ったら大間違い!聞き手の粗相は言いての粗相。
Action:伝わらないことを知りながら、伝える努力をする。
すぐ来ると言われても1時間待ちぼうけをした体験があるため、時間については確認するくせがついているが、普段、自分が使っている言葉の定義が人とは違うことを全く意識せずに過ごしていたと思う。講座中にハッとした。「友達」という言葉でも、使っている意味が全く違うので、「自分の中の言葉の定義=思い込みだらけ」を確認したいと思った。
②コミュニケーションの前程
「相手のことをわかっていない」=「自分のこともわかってもらえていない」ということである。そのことを意識して過ごしていなかったと思う。自分の言っていることは、全て理解してもらっているぐらいに感じていたけど、言葉の定義やその背景、思い込みも全く違うはずなので、確認して話をするようにしたいと思う。
③ニューロロジカルレベルを意識して聴く
「私はバカだから、、、」という生徒が来たことがある。どんな理由でそう思ったかを聴いたとは思うが、ニューロロジカルレベルを気にせずに聴いていたと思う。行動が理由だったら行動を変えるにはどうしていきたいかを話すとよい。意識してないと咄嗟にはできないので、日頃からニューロロジカルレベルを意識しておこうと思った。
気づき:自分の話が伝わっていると思ったら大間違い!聞き手の粗相は言いての粗相。
Action:伝わらないことを知りながら、伝える努力をする。