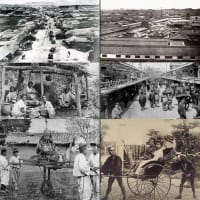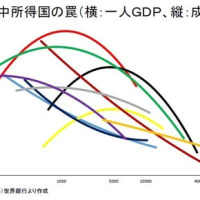勝又壽良の経済時評
週刊東洋経済元編集長の勝又壽良
2015-05-19
韓国、「集団的うつ病」日本に謝罪を求め続ける「病理」の本質
*******************
韓国社会学者の妄言
トインビー理論に学べ
本来、隣国の批判は慎むべきことであろう。
ましてや、民主主義政治体制の国に対して、タイトルのような「集団的うつ病」というレッテル張りが、いかに礼を失しているか。私は、それを十分に心得ている積もりだ。
こうした人間的「規範」を飛び越えて、このテーマで書こうと決意した背景には、後掲のソウル大学社会学教授の日本批判が、韓国紙『中央日報』に掲載されたからだ。
ならば、私もその批判に応えて、韓国の「社会病理」を書いて、韓国に反省を求めたい。
そういう気持ちに傾いたのである。
小難しい議論をしようとは思わない。
ただ、社会学の教授が執筆したエッセイは反論する題材として好適である。
これを使って、韓国社会がいかに「病んでいるか」を明確にしたいと思う。
70年前の問題を引っ張り出して、戦後日本が相変わらず蛮行を継続している。
そんな前提での「日本批判」に、一度は歴史学的な見地から真っ当に応えておきたいのだ。
一回限りの「謝罪」では、韓国を満足させられない。永遠に謝罪し続けろ。
間欠泉のごとく、定期的に噴き出す「日本批判」は、そういう意味であろう。
こうなると、日本自体に問題があるのでなく、韓国社会が抱える「集団的うつ病」が原因である。
韓国自身が、その病理を治癒すべく内省することが先決であろう。私は強くそう思う。
一般的な「うつ病」克服と同じ治療法の採用を勧めたい。
医学的な処方を施しても、「うつ病」は完治しない。
本人がその原因を自覚し、自らが内省して克服する。
それが最善の治療法であろう。韓国も同じである。
過去1000年以上、中国の属国として生きてきた。
その間の鬱積した不満が、形を変えて「日本批判」になっている。
韓国自身がそれに気づいていないのだ。
人間に喩えれば、幼児期に受けた精神的なダメージが、成人になって「うつ病」として発症するのと同じ理屈である。
今こそ、韓国の「精神分析」が必要である。
韓国社会学者の妄言
韓国紙『中央日報』(5月6日付け)は、宋虎根(ソン・ホグン)ソウル大教授(社会学)のコラム「ワシントンに桜が咲く」を掲載した。
① 「4月末、安倍首相が戦後初めて米上下両院合同会議で演説をした日にも、10万本の桜の花が一斉に降り、ワシントンDCを覆ったはずだ。
そのためか起立拍手を10回も受けた。
米議会があれほど薄情に思えることはなかった。
『不動の軍事同盟』を担保に日本右翼の念願だった『平和憲法改正』に目をつぶったオバマ大統領もそうだった。
世界最強の軍事同盟になったというのに感激しないはずはない。
さらに『軍隊のない国』の70年の歳月に終止符を打ったのだから。
安倍首相は感慨に浸り、賛辞を惜しまなかった」。
美文調である。感情移入が過多とも言える。
社会科学者が書くエッセイとしては悪い意味での「出色」である。
社会科学の視点から執筆するエッセイには、論理と根拠が不可欠である。
残念ながら、その二つを欠いているから散漫な美文調になるのだろう。
若干の「自己陶酔」も感じられる。自らの心情と違う相手を「右翼」と分類して攻撃する。
これは、学問をする人間の立場を著しく逸脱するものだ。
なぜ「右翼」は悪く、「左翼」は良いのか。
この延長線に立てば、韓国や中国も「左翼」である。
こういった分類は非論理的である。ソウル大学教授の肩書きに傷がつくだろう。
米国上下両院の合同会議では、安倍演説に対して15回ものスタンディング・オーベーションがあった。
ただの拍手でなく、席から立ち上がっての拍手喝采である。
韓国が国会議長まで米国へ送り込んで、安倍演説を阻止しようとしたのだから、この光景は最も見たくなかったに違いない。
だからといって、「米議会があれほど薄情に思えることはなかった」という表現のなかに、韓国の「感情論」が明確に投影されている。
学者のエッセイとしては「不合格」という烙印が押されるのだ。
オバマ米大統領が、「不動の軍事同盟」を担保に日本右翼の念願だった「平和憲法改正」に目をつぶったとして批判している。
なぜ、日米で「不動の軍事同盟」ができたのか。
それは、中国の軍拡と周辺海域での軍事的な示唆行動が原因である。
こうした因果関係には一切目をつぶり、日米両国を批判している。
きわめて偏った論旨である。「圧巻」は、次のパラグラフだ。
② 「日本精神史の盲点を突いた東京大の丸山真男教授(引用者注:当時)の痛恨の概念が思い浮かぶ。
日本の精神空間には過去の記憶の欠片と異質的要素が混在する。
それらの倫理的緊張を管轄する中枢的論理がない。
すべての行為を正当化する源泉である天皇は、支配集団の『共同謀議』に対する責任回避の公用安全弁だ。
現実の擁護と未来の出口のためなら、過去の記憶を再配置し、時には忘却の倉庫に送る」。
丸山真男氏は戦後日本の論壇をリードした日本政治思想史の研究者である。
その「丸山論文」を足がかりにして、日本精神史を批判している。
「日本の精神空間には過去の記憶の欠片と異質的要素が混在する。
それらの倫理的緊張を管轄する中枢的論理がない」と批判している。
要するに、日本は「過去の記憶を再配置し、時には忘却の倉庫に送る。
過去が自覚的に現実と向き合わない」というのだ。
敷衍すれば、日本には過去を反省する中心的な論理が存在しない。
その背後には天皇制が存在して過去を美化する。
まさに、戦時中の亡霊が戦後に大手を振って徘徊している。そういう論理を展開しているのだ。
戦後70年間、日本は一度も戦争していない。この現実をどう解釈するのか。
戦前の「蛮行」を反省したから、平和憲法を守ってきたのである。
この一事をもって、前記の日本批判は瓦解するのだ。
日本人は、戦前の誤りを繰り返すほど愚かな存在だろうか。
丸山氏は、著書『日本の思想』(岩波新書 1961年)において、戦前の日本を厳しく批判している。その通りである。
天皇制=神道が日本の政治と思想を牛耳ってきたのだ。
だが、次のように言っている。
「天皇制が戦後も戦前と連続性を保ち、今後再び権力と精神の統合体としての旧姿にまで膨張する可能性を孕んでいるという意味ではない」(39ページ)。
明らかに戦前と戦後を区別して論述している。
それにも関わらず、意図的に混同して日本批判を行っている。学者としてあるまじき行為である。
(2015年5月19日)