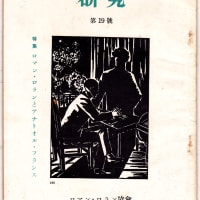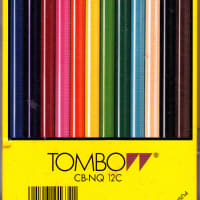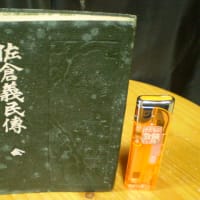宇津木矩之允(のりのすけ)。号は静区。29歳。
彦根藩家老の次男。
天保2年に大塩塾に入門するが、翌年には塾頭。大塩の著作に訓点をするなど、学問的に優れ、大塩は弟子というよりも、同学の朋友感覚で接したといわれる。大塩の学問を最もよく理解する弟子。
天保6年に長崎に遊学することになるが、そのときに、大塩は餞別として、10両と国光という刀を与えたそうだ。
この愛弟子がよりによって、蜂起の前日か前々日(はっきりとはわからないが、直前であることはたしかだろう)、大塩塾に帰ってくる。なぜ帰ったのだろう。門人かだれかが大塩を説得できるのは、宇津木しかないと、緊急の要件で呼び戻したのではなかろうか。
宇津木は、大塩を諫止したそうだ。武装し、だれもが血相を変えた雰囲気の中で
大塩に意見をすることはだれにもなしがたいことだ。
大塩は「救民のために決起する」と語るが、宇津木は、「先生がそんな言葉を言うとは信じられない。災いを救い民をめぐむ、それは官のすることである。豪家をこらしめて、民を救う。それは民を救うのではなく、民に災いをかけることです。乱民の所業です」
奉行を斬り、豪商の家を焼く行為がなぜ救民なのか。陽明学のどこからそんな結論が出るのか。
もちろん、大塩が実行をとりやめるはずがない。
19日の朝、午前8時ごろ、予定より4時間早めて決起するが、出発の前に宇津木は、大塩の門人大井正一郎という男に槍で殺されることになる。大塩の命令か、あるいは門人大井がすすんで手を下したのかそれはわからない。
この場面は、森鴎外の「大塩平八郎」にも書かれています。
宇津木は殺される直前、下僕に手紙を渡して、自分は義のために死ぬことを家族に知らせている。武士としての心得があるではないか。もし黙って死んだら、大塩の一味として殺されたとも思われる。
勝海舟の「氷川清話」に岡本黄石について書いてある。詩人であり彦根藩の家老であった岡本黄石はこの宇津木矩之丞の兄とある(一方、幸田成友の「大塩平八郎」には宇津木の実弟とあるけど)。
勝は、ここで、岡本黄石を絶賛している。井伊大老が暗殺されたとき、彦根藩ではすぐに水戸屋敷に斬り込もうと大騒ぎしたそうだが、黄石はそれをなだめ、穏便にすませたそうだ。「およそ、あんな場合に、一時の感情に制せられず、冷ややかな頭をもって国家の利害を考え、群議を排して自分の信じるところを行うということは、かならず胸中に余裕がなくてはできないものだ」といっている。
彦根藩家老の次男。
天保2年に大塩塾に入門するが、翌年には塾頭。大塩の著作に訓点をするなど、学問的に優れ、大塩は弟子というよりも、同学の朋友感覚で接したといわれる。大塩の学問を最もよく理解する弟子。
天保6年に長崎に遊学することになるが、そのときに、大塩は餞別として、10両と国光という刀を与えたそうだ。
この愛弟子がよりによって、蜂起の前日か前々日(はっきりとはわからないが、直前であることはたしかだろう)、大塩塾に帰ってくる。なぜ帰ったのだろう。門人かだれかが大塩を説得できるのは、宇津木しかないと、緊急の要件で呼び戻したのではなかろうか。
宇津木は、大塩を諫止したそうだ。武装し、だれもが血相を変えた雰囲気の中で
大塩に意見をすることはだれにもなしがたいことだ。
大塩は「救民のために決起する」と語るが、宇津木は、「先生がそんな言葉を言うとは信じられない。災いを救い民をめぐむ、それは官のすることである。豪家をこらしめて、民を救う。それは民を救うのではなく、民に災いをかけることです。乱民の所業です」
奉行を斬り、豪商の家を焼く行為がなぜ救民なのか。陽明学のどこからそんな結論が出るのか。
もちろん、大塩が実行をとりやめるはずがない。
19日の朝、午前8時ごろ、予定より4時間早めて決起するが、出発の前に宇津木は、大塩の門人大井正一郎という男に槍で殺されることになる。大塩の命令か、あるいは門人大井がすすんで手を下したのかそれはわからない。
この場面は、森鴎外の「大塩平八郎」にも書かれています。
宇津木は殺される直前、下僕に手紙を渡して、自分は義のために死ぬことを家族に知らせている。武士としての心得があるではないか。もし黙って死んだら、大塩の一味として殺されたとも思われる。
勝海舟の「氷川清話」に岡本黄石について書いてある。詩人であり彦根藩の家老であった岡本黄石はこの宇津木矩之丞の兄とある(一方、幸田成友の「大塩平八郎」には宇津木の実弟とあるけど)。
勝は、ここで、岡本黄石を絶賛している。井伊大老が暗殺されたとき、彦根藩ではすぐに水戸屋敷に斬り込もうと大騒ぎしたそうだが、黄石はそれをなだめ、穏便にすませたそうだ。「およそ、あんな場合に、一時の感情に制せられず、冷ややかな頭をもって国家の利害を考え、群議を排して自分の信じるところを行うということは、かならず胸中に余裕がなくてはできないものだ」といっている。