
昨晩の特効薬も期待通りの効き目はなく、午前中ちょっと動いたら、体がだるくてしかたありません。老体(笑)に無理は禁物と、昼から2時間ほど喫茶店でサボタージュです。
「バブ君、『歌姫』っていうドラマ知ってる?」と常連のTさん
(「え~~~い、休んでいるときに話しかけんな!」)という気持ちはあったものの、喫茶店で休もうとしている私も悪いわけで、
「いやぁ、あんましドラマって見ないから」
「なんだそうか、残念だなぁ、いやね、そのドラマに出ている相武紗季ちゃんが可愛いわけさ・・・・・・」
相武紗季という女優がどの子かもよく理解できなかった私は、ミスタードーナッツのCMの女の子と聞いて、なんとなく顔が浮かぶていど、それをどうのこうの言われてもちんぷんかんぷんなわけでして。
「あ~あ、なかなか可愛い子ですもんね。」と話を合わせるだけです。
でも、よくよく話を聞いてみれば、Tさんが相武紗季の特別なファンという事ではなく、土佐を舞台にしたそのドラマで、土佐弁を話す彼女がみょうに可愛くてしょうがないのだと言うのです。
女性が話す土佐弁と聞くと、思いつくのは映画『鬼龍院花子の生涯』の夏目雅子ですかね。「なめたらいかんぜよ~」ってあれですが、たしかに土佐弁だけでなく、お国言葉やお国なまりというのは、女性を可愛く見せる不思議な力を持っているようにも思えます。
私も高校生の頃、部活(厳密には部活動ではなかったのですが)の全国大会が福岡であったとき、会場の準備を手伝っていた女子高校生が使う博多弁を聞いて「可愛い!」と思いましたもん。
私は東北出身ですが、地方出身者が東京あたりで生活するとき、言葉にタイするコンプレックスというものは常に感じるものです。(特にその傾向は東北出身者に多いようにも思えますが)
私はどうだったかといえば、上京して間もなく大学の同僚に
「バブは、東北出とは思えねぇよなぁ、なまってねぇし」
と言われました。
おっと、勘違いしないでください。これは自慢話じゃないんです、いや逆に悲しい話でして、
私の場合父が転勤族だったので、小・中学校時代は転校を繰り返していました。あれは3校目の小学校へ転校したときだったと思います。気を付けていたつもりが何気に前に住んでいた地域の方言を使ってしまったのでした。まわりの友達は大爆笑、その時です「俺は二度と話し方で笑われないぞ」と心に決めたのです。
人間やれば出来るもので、以降、言葉の順応は何処へ行ってもまぁ早い、半月もあればそれなりに対応できるようになりました。
ところが、今になってこのことが原因でとても寂しい思いをしています。というのは、自分の本当の言葉が無いように思えてきたからです。
母と話せば中途半端な会津弁、誰それと話すときにはこれまた中途半端な○○弁、すでに完璧だと思い込んでいた横浜弁ですら中途半端になっています。
「俺って、いったい何語をはなしてんだ?」分からないかもしれませんが、これって凄い寂しいんですよ。
言葉の端にお国言葉がポロッと出てポッと顔を赤らめたり、半べそかきながらお国言葉で怒ってきたり・・・・可愛いですよねぇ、うらやましいですよねぇ、自分の言葉が有るって素敵なことなんだと思います。
みなさん、お国の言葉を大切にしてくださいね。
あれ?なんの話でしたっけ?
そうそう、土佐弁を話す相武紗季ちゃんが、とっても可愛いんですって。
今度『歌姫』なるドラマを見てみようと思ったバブ君でした。
さて、今日の一枚は、昨晩『コーヒー一杯のジャズ』を読んでいて、突然思い出したように先ほどからかけているゲーリー・バートンです。
同書の冒頭で、「植草氏はバートンのレコードでは「ダスター」(ビクター)がいちばんぼくは気にいっている。」とふれられているだけなのですが、「そういえばずいぶん聴いていなかったなぁ」となったわけです。
バートンというと、どうしてもミルト・ジャクソンという巨匠がいて、ボビー・ハッチャーソンがいて、そこからずーっと水を空けたところにいる人といったイメージがあります。(私だけかもしれませんが)
しかし、このアルバムを聴くと、彼自身もそういったことを意識していたのではないかと感じるのです。
しかるに、リズミカルで手数が多い奏法とハーモニーの使い方を駆使し、ミルト、ボビーとの差別化を主張、ロックを取り入れることでさらにそれを強調したかったのではないか、なんてね。
ともかく、新たな世界を求めたバートンのこのアルバムは、失敗には終わらなかったということ、久しぶりに聴いてもそのユニークさに興味をひかれます。
DUSTER / GARY BURTON
1967年4月18, 19, 20日録音
GARY BURTON(vib) LARRY COYELL(g) STEVE SWALLOW(b) ROY HAYNES(ds)
1.BALLET
2.SWEET RAIN
3.PORTSMOUTH FIGURATION
4.GENERAL MOJO'S WELL LAID PLAN
5.ONE, TWO, 1-2-3-4
6.SING ME SOFTLY OF THE BLUES
7.LITURGY
8.RESPONSE














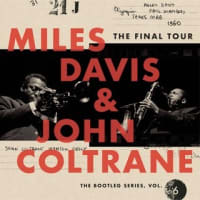


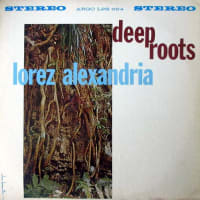


追伸!・・・女子高校生が使う博多弁を聞いて「可愛い!」と思いましたもん・・・とのお言葉、可愛い女子高校生だから博多弁が可愛く聞こえたんじゃないですかあ?なんて思うワタクシメであります。とほほ。
Tさんがおっしゃられるように、ミスドーナッツことヒロインの相武紗季チャン、カワイイです。このドラマは好き嫌いがはっきり分かれると思いますが、我が家では全員集合で見ています。(なにぶん土佐に住んじょりますき)
ゲイリー・バートンのアルバムで真っ先に買ったのが、今回ハブさんんが紹介されているこのアルバムでした。タイトルが「埋葬」ではなかったかしら。違うかな?ラリー・コイエルが参加してるのに魅かれて買ったのですが、思えば、バートンはず~っと前からギタリストが好きだったのですねぇ。玄人衆(?)に評判がよかったようにも記憶しています。
転校の辛さを知ってればこそ、引っ越し先で一人泣いたこともありました。
転校してどれだけ慣れようとも、例えば幼稚園時代からいっしょだった、なんていう連中とは、何処か自分は違うという意識はありました。
早く溶け込もうとする努力は、時に自分を殺すことだったりもして「自分の子供には絶対転校はさせない」と真剣に思っていましたよ。(笑)
なにしろ、カワイコチャンには目がないものですから(笑)
ゲーリー・バートンが最も影響を受けたのは、ビル・エバンスだったといわれていますが、それが、彼の音楽にどのように生かされたのか?私も詳しくは知りません。
その音楽に、ギターというアイテムが必要だったのかもしれません。
バークリーの講師を務めていたとき、そのあたりの講義があったのかなぁ?指導を受けたミュージシャンに訊いてみたいようにも思います。