【歴文編】
○「ドルメンと真牛」~太古の海の民のにおい ~:1997年1月11日
宮古島で、太古に造られた巨石建造物(ドルメン)が発見された。
森の中に岩が無造作に転がり、巨石を組み立てた構造物が崩れたものである。数十年に一度あるかないかの大発見だそうで、約二千年前の巨石文化が、にわかに注目されることになった。
この発見で柳田国男の『海上の道』が見直されている。柳田国男は、ココ椰子の実が伊良湖岬に流れ着いたのを見て、南の文化がさまざまな形で日本にやってきたことを推測する。「稲の渡来にも、琉球列島の島伝いに北上したルートもあるのではないか」と説き、「東南アジアとの交易に、宮古は大切な役割をはたしたのではないか」ともいっているのだ。
宮古の保良の沿岸地帯からは南蛮がめ、青磁などの破片が発掘されている。宮古はかつて中国大陸の南部や東南アジア各地との交易を続けていたという。昔の宮古は海上の道の中核的な拠点だったのだ。
宮古の伝説には、ベトナム、インドネシア、ニューギニア、インドなどと共通するものがあり、城辺町の海辺の貝塚からは、南太平洋やフィリピンで使われていた水字貝製のオノと同種のものが出土している。
平良真牛は東平安名崎のある保良の人だ。一八九三年、人頭税の重圧に苦しんでいた宮古の人たちを代表して上京し、悪税の撤廃を訴えたことはよく知られている。
当時、上京を阻止しようとする役人たちの目を逃れて、真牛たちはひそかに小舟に乗って島を脱出した。人頭税が廃止されたのはその十年後だった。
真牛の次男である嘉弘さんがいっていた。「親父は、この人頭税撤廃請願の仕事が成功しなかったら宮古に帰っても殺されるだろう、だからその時は汽車に飛び込んで死ぬ覚悟だった、といっておりましたね」
かつて交易の中核地として栄えた宮古は、琉球王府に抑えられ、薩摩藩・明治政府の支配下におかれ、海の民のエネルギーは隆起珊瑚礁岩の貧しい土地に押しこまれていた。
数世紀にわたって抑えられていた激しいエネルギーが真牛たちのなかでよみがえり、噴出したのだろうか。どんな暗い歴史も、海の民の生命力を奪うことはできない。
○先人の知恵生かす~新しい雨水文化の創造を~:1997年4月5日
我田引水といわれそうだが、今回は「雨水」の話を書きたい。
なぜ我田引水なのかというと、私は仲間と一緒に、かなり前から「雨水を活用する運動」を続けているからだ。
去年の十一月、大田知事にお会いして、お願いした。「雨水利用をひろめるために、沖縄で大会あるいはシンポジウムを開いていただけませんか」
大田さんは即座に「それはいい話です」と応じてくれた。
大田さんに初めてお会いしたのは今から三十二年も前になる。私は朝日新聞の社会部記者だった。那覇の酒場で、夜を徹して話を聞かせてもらった。沖縄戦のむごたらしさについて、本土政府の頼りなさについて、基地の害のすさまじさについて、若き日の大田さんは時には言葉を荒らげて語り続けた。
知事は、私に「沖縄学」の基本を教えてくださった「師」でもある。
私「私たちは、東京の墨田で何回も雨水利用の大会を開きました。一九九四年には雨水利用東京国際会議を開き、大成功をおさめました。今後、この運動を全国にひろめてゆくために、どこかの県に先進県になってもらいたいのです。それにふさわしいのは、沖縄県ではないでしょうか」
知事「雨水利用は沖縄の暮らしにとってきわめて重要なことです。やりましょう」
話は早かった。知事はその場に担当者を呼び、大会開催の予算の準備をするように指示した。この夏、『雨水フェアINおきなわ』が開かれることになったのは、たくさんの方々の力によるものだが、そのときの知事の決断が大きい。
三月二十七日、第一回実行委員会が発足し、私も出席した。雨水フェアは八月八日から十日までの三日間、沖縄市で開かれる。
翌日は、沖縄市水道局の人たちの案内で瀬底島へ行った。古い天水利用の跡が残っていると聞いたからだ。
仲松ウタさんの家の庭には、「アナガー」あるいは「アニガー」と呼ばれる池の跡があった。池の回りには木が繁茂しており、昔はこれらの木の幹を伝わる雨をわら縄にはわせ、あるいは竹のトイにはわせて池に流し込んだそうだ。池はさんご礁岩を砕いて焼いたものを原料にして固めてあった。たまった水は雑用水に使ったそうだ。
○赤がわら礼賛~亜熱帯に心浮き立つ朱色~:1997年5月3日
那覇市、沖縄市、本部町、石垣市を回って、街の様変わりに驚いた。きれいな建物がふえたし、立派な庭もふえている。それに反比例して、あの赤瓦の家が少なくなっていることが気になった。
最初に沖縄を訪ねた一九六五年ごろは、まだ赤い瓦が目についた。黒ずんだところもある赤瓦と古びたしっくいとがよく調和していて、それにさまざまな表情を見せてくれるシーサー、風格のある石垣とヒンプン、緑の濃い福木、などが加わると、「ああ、沖縄に来ているんだ」という思いがこみあげてきたものだ。亜熱帯の太陽に光るあの朱色の瓦を見るたびに心が浮き立つ思いだった。
その赤瓦の風景が、訪れるたびに確実に減っていった。
「赤瓦礼賛は旅びとの自由だが、沖縄の台風のこわさを知れば、今のコンクリートの家がはやりだした理由がわかるよ」と沖縄の友人にいわれて、なるほどと頭では納得するのだが、心の奥底では納得していなかった。
東京の国立劇場で沖縄舞踊『めでる華ごころ』の舞台を見た。
沖縄の宝といわれる舞踊家の「作田」「川平節」「護身の舞」「高平良万歳」などを見ながら、異次元の世界に心は飛んだ。どんな動きのときでも、下半身は見事に安定していて、上半身はやわらかな線を描いている。ゆったりと水が流れるような舞台があるかと思うと、軽快な、心のはずむ舞いがある。
これほどまでに多彩な、これほどまでに洗練された伝統舞踊を持ち、伝え、新しい作品を創造し、ますます舞踊人口をふやしている県はほかにない。沖縄タイムスを見て驚くのは、伝統芸能に関する記事の多さだ。琉舞やエイサーや各地の芸能祭の記事が出ない日はない。
ここでいいたいのは、なぜ伝統の沖縄舞踊が隆盛をきわめ、伝統の赤瓦が衰退の道をたどっているのか、ということである。
舞踊、芭蕉布、紅型、陶器の場合は無形文化財の指定があるが、赤瓦を作る技術保持者に対してはそういう指定がない。これはなぜなのか。
いまはセメントに細工を施した新しい赤瓦が生まれていて、それはそれで見栄えがいいのだが、やはり、昔ながらのあの赤瓦の味が捨て難い。
赤瓦の技術者養成、赤瓦使用の場合の補助、国の赤瓦援助制度、屋根だけではなくて、さまざまな形での赤瓦利用法、そういうことをぜひ検討して欲しいものだ。
○ナイチャー論議~よそ者は溶け込む努力当然 ~:1997年7月5日
沖縄タイムスのコラムの「ナイチャー論議」特集がおもしろかった。
東京から那覇にやって来た青年が「ナイチ?」といわれるたびにうんざりする、とぼやいている。逆に「ナイチのどこから」「沖縄には慣れた?」と話しかけられて結構、うれしかったという主婦もいるから人さまざまだ。ウチナンチュの女性はこういっている。
「ヤマトンチュとかナイチャーとかの言葉は決して悪い意味ではなく、親しみをこめてのごあいさつなのです」
「ナイチャーは出て行け」といういじめがあった、と書いている人がいたが、これが第一の驚きだ。実態はどの程度のものなのだろうか。
第二の驚きは、ナイチャーと呼ばれるだけで不愉快になる、失礼だ、差別だと感じるヤマトンチュがいるということだった。
私が三十数年前、初めて沖縄の土を踏んだときもよく「ホンドから?」と聞かれたが、それはちょうど、ヨーロッパの旅で会ったアメリカ人同士が「どこから」「アイオワだよ」なんていっているのと同じだと私は受け取っていた。差別を感じたことはなかった。私が鈍感だったのか、それとも時代が変わって「ヤマト」への反感が高まってきたのか。
いや、ヤマトは沖縄を見捨てようとしているという反感は、当時も強かった。強かったけれども、それは個人に向けられた怒りではなかった。
最近の「ナイチャー現象」の底には、もっと個人へ向けられた攻撃があるのだろうか。私にはわからない。どんな土地でも「よそもの」は浮く運命にある。溶け込むにはそれなりの努力が必要なのは当然のことだ。
沖縄の本土化がいわれながら、音楽の面では逆に本土の沖縄化現象が起こっている。真剣に沖縄の心を学ぼうとしている若者は少ない数ではないだろう。いいものは自然に伝わってゆく。
○雨こそ命~自然の摂理に深い祈り~:1997年8月2日
文明の一つの悲劇は、雨と人とのつながりが断ち切られたことである。
都会で暮らしていると、つい雨がうっとおしいもの、いやなものになってしまう。
私自身、家には二百リットル入りの天水槽を二つ備え、散水や洗車に使っている。暮らしの水の大半は水道に頼っている。だからつい「雨の日=天気が悪い」の図式が頭に浮かぶのだろう。
沖縄の人々の雨への思いも、ずいぶん変わったとは思うが、それでも天水を活用している人は多いし、本土の私たちより密度の濃いつきあい方をしていると思う。雨水利用は一滴の水を神様の贈りものと思うことから始まる。元日の朝、御嶽の井戸から水をくんで床の間に供えるという若水の習慣も本土より数多く残っている。
波照間でアミニゲー(雨願い)の話を聞いたことがある。アミニゲーの歌は、私のように沖縄の言葉に不案内のものにも実に快く響く。これなら神様も心を動かさずにはおられまいと思えるような名調子である。
白雲は雨である
乗雲は水である
天の上を昇りて
この島の上に昇りて
波照間の上に昇りて
時を待ツことなく給われ
寸時を待つことなく給われ
沢山の雨を給われ
石垣の雨乞いの歌も名調子だ。
石の雨戸をはねあげて
鉄の雨戸を切開けて
黒い雨雲をお恵み下さい
白い叢雲よ、水をお恵み下さい
海鳴りのするような大雨を
山鳴りがするほどの豪雨をお恵み下さい
ここには大自然の摂理にぬかづく謙虚さがある。雨こそ命だという深い祈りがある。
○テルリン会見記~沖縄文化なチャンプル~:1997年9月6日
八月、「雨水フェア」が沖縄市で開かれたとき「コザ独立国」のテルリン大統領に会った。
林助さんは「雨水フェア」のトークショウにも参加して、得意のジョークで会場を笑わせていた。
私は昔、林助さんが今の大統領官邸兼私邸にあたるところで民宿を経営していたころ、しばらくお世話になったことがある。だから、林助さんの父君、林山さんにも会っている。三線作りの名人といわれた人だ。
昔のよしみを利用して、大統領に単独会見を申し入れた。
「トークショウでは、ダムは山の中に造らず、川の下流に造れと発言していましたね。あれは卓見でした」
「そうです。大自然を破壊して山の中に造ることはない。下流に造れば、海の赤土汚染だって防ぐことができる」
「沖縄に高い山を造れば雪が降る。その雪の水を利用せよとも…」
「なかなかいい発言だったでしょう。私は、いずれは新しい家を建てるときは雨水利用を義務づけ、家々の地下タンクをつないで、街の下を一大地下タンク網にすることを主張しています」
雨水フェアの会場でも飛び出した大統領の名案珍案である。
「せっかくの機会ですから、コザ独立国の国是についてうかがいましょう」
「きまりを守らないことです。何時に集まるなんていうことは全然、守らない。そのほうが人生たのしいですよ。今はみんなきまりを守ることに慣らされているからそういう人はこの国にはなじめません。わが国には日本的規律はありません」
規律大きらいのテルリン大統領ではあるが、「ごまかし」はもっときらいだ。たとえば敗戦を終戦といったり、侵略戦争を「正義の戦い」だといったりすることへの嫌悪感はいまも強い。
「日本は正義の戦いだといって沖縄をめちゃめちゃにしてしまった。正義を声高に叫ぶものには注意しないとね」
「沖縄の独立よりも、日本に向かって早く独立しなさいというのが先だろう。日本が国として独立して自分の考えで動くようになれば別だが、日本が独立もしていないのに、沖縄が独立できるか」
「国是にはチャンプラリズムもある、と聞きましたが」
「あれもだめ、これもだめというんじゃなくて、あれもよいこれもよいと全部ひとつにしてというのがチャンプルです。黒潮は、さまざまな南方のものを沖縄に寄せています。私たちはそれを暮らしに取り入れた。黒潮に乗って日本に行った連中も何かを持って帰る。沖縄の文化にはいろんなものがごっちゃになっている」
「チャンプルこそ沖縄文化の本質である」
国としての目標は? 「そんなものはありません。遊ぶこと自体が目的です」
○愚直・春潮・良顕~志に誠実に生きた先達~:1997年10月4日
豊平良顕さんのことを思うと、なぜかすぐ比嘉春潮さんの顔を思い出す。比嘉春潮さんのことを思うと、すぐ豊平良顕さんの顔が浮かぶという具合いで、この二人の大先達がどうしても重なりあうのだ。
歴史学者、比嘉春潮さんにお会いしたのはもう二十五年も前になる。
沖縄で半世紀に一人出るか出ないかの秀才といわれた人だが、人の面倒ばかりを見ていて、才能を世に問う機会が遅れた。富や地位を求めぬ暮らしを続けながら、名著『沖縄の歴史』をまとめた。七十六歳のときだ。『新稿・沖縄の歴史』が完成したときは八十七歳だった。
「沖縄のこころとはなんでしょう」
比嘉さんはちょっと考えてから答えた。
「それは、愚直ということでしょうね」
「愚直?」
「愚直というのは、よくいえば、小利口に立ち回らない。思い込んだらなかなか変えない。悪くいえば変えることができない。そういうことでしょうか。私自身は融通がきかなくてずいぶん損をしてきましたが、人をかきわけて出世するつもりはなく、まあ、これでよかったと思います」
そんな話を新聞に書いたあと、沖縄を訪れた折に豊平良顕さんにお会いした。
「比嘉春潮さんがいわれた愚直、私も、大賛成です。あれが沖縄のこころです」
以後はお会いするたびに愚直論になった。誤解のないようにいっておきたい。ここでいう愚直とは、己の生き方、己の志にかたくななまでに誠実であることの意味だ。それに、沖縄のこころを愚直だけでくくる割り切り方をするつもりはない。ただ、沖縄独自の自然や文化を壊そうとするものに対し、愚直に立ち向かった豊平さんの姿勢がなつかしい。
○「ドルメンと真牛」~太古の海の民のにおい ~:1997年1月11日
宮古島で、太古に造られた巨石建造物(ドルメン)が発見された。
森の中に岩が無造作に転がり、巨石を組み立てた構造物が崩れたものである。数十年に一度あるかないかの大発見だそうで、約二千年前の巨石文化が、にわかに注目されることになった。
この発見で柳田国男の『海上の道』が見直されている。柳田国男は、ココ椰子の実が伊良湖岬に流れ着いたのを見て、南の文化がさまざまな形で日本にやってきたことを推測する。「稲の渡来にも、琉球列島の島伝いに北上したルートもあるのではないか」と説き、「東南アジアとの交易に、宮古は大切な役割をはたしたのではないか」ともいっているのだ。
宮古の保良の沿岸地帯からは南蛮がめ、青磁などの破片が発掘されている。宮古はかつて中国大陸の南部や東南アジア各地との交易を続けていたという。昔の宮古は海上の道の中核的な拠点だったのだ。
宮古の伝説には、ベトナム、インドネシア、ニューギニア、インドなどと共通するものがあり、城辺町の海辺の貝塚からは、南太平洋やフィリピンで使われていた水字貝製のオノと同種のものが出土している。
平良真牛は東平安名崎のある保良の人だ。一八九三年、人頭税の重圧に苦しんでいた宮古の人たちを代表して上京し、悪税の撤廃を訴えたことはよく知られている。
当時、上京を阻止しようとする役人たちの目を逃れて、真牛たちはひそかに小舟に乗って島を脱出した。人頭税が廃止されたのはその十年後だった。
真牛の次男である嘉弘さんがいっていた。「親父は、この人頭税撤廃請願の仕事が成功しなかったら宮古に帰っても殺されるだろう、だからその時は汽車に飛び込んで死ぬ覚悟だった、といっておりましたね」
かつて交易の中核地として栄えた宮古は、琉球王府に抑えられ、薩摩藩・明治政府の支配下におかれ、海の民のエネルギーは隆起珊瑚礁岩の貧しい土地に押しこまれていた。
数世紀にわたって抑えられていた激しいエネルギーが真牛たちのなかでよみがえり、噴出したのだろうか。どんな暗い歴史も、海の民の生命力を奪うことはできない。
○先人の知恵生かす~新しい雨水文化の創造を~:1997年4月5日
我田引水といわれそうだが、今回は「雨水」の話を書きたい。
なぜ我田引水なのかというと、私は仲間と一緒に、かなり前から「雨水を活用する運動」を続けているからだ。
去年の十一月、大田知事にお会いして、お願いした。「雨水利用をひろめるために、沖縄で大会あるいはシンポジウムを開いていただけませんか」
大田さんは即座に「それはいい話です」と応じてくれた。
大田さんに初めてお会いしたのは今から三十二年も前になる。私は朝日新聞の社会部記者だった。那覇の酒場で、夜を徹して話を聞かせてもらった。沖縄戦のむごたらしさについて、本土政府の頼りなさについて、基地の害のすさまじさについて、若き日の大田さんは時には言葉を荒らげて語り続けた。
知事は、私に「沖縄学」の基本を教えてくださった「師」でもある。
私「私たちは、東京の墨田で何回も雨水利用の大会を開きました。一九九四年には雨水利用東京国際会議を開き、大成功をおさめました。今後、この運動を全国にひろめてゆくために、どこかの県に先進県になってもらいたいのです。それにふさわしいのは、沖縄県ではないでしょうか」
知事「雨水利用は沖縄の暮らしにとってきわめて重要なことです。やりましょう」
話は早かった。知事はその場に担当者を呼び、大会開催の予算の準備をするように指示した。この夏、『雨水フェアINおきなわ』が開かれることになったのは、たくさんの方々の力によるものだが、そのときの知事の決断が大きい。
三月二十七日、第一回実行委員会が発足し、私も出席した。雨水フェアは八月八日から十日までの三日間、沖縄市で開かれる。
翌日は、沖縄市水道局の人たちの案内で瀬底島へ行った。古い天水利用の跡が残っていると聞いたからだ。
仲松ウタさんの家の庭には、「アナガー」あるいは「アニガー」と呼ばれる池の跡があった。池の回りには木が繁茂しており、昔はこれらの木の幹を伝わる雨をわら縄にはわせ、あるいは竹のトイにはわせて池に流し込んだそうだ。池はさんご礁岩を砕いて焼いたものを原料にして固めてあった。たまった水は雑用水に使ったそうだ。
○赤がわら礼賛~亜熱帯に心浮き立つ朱色~:1997年5月3日
那覇市、沖縄市、本部町、石垣市を回って、街の様変わりに驚いた。きれいな建物がふえたし、立派な庭もふえている。それに反比例して、あの赤瓦の家が少なくなっていることが気になった。
最初に沖縄を訪ねた一九六五年ごろは、まだ赤い瓦が目についた。黒ずんだところもある赤瓦と古びたしっくいとがよく調和していて、それにさまざまな表情を見せてくれるシーサー、風格のある石垣とヒンプン、緑の濃い福木、などが加わると、「ああ、沖縄に来ているんだ」という思いがこみあげてきたものだ。亜熱帯の太陽に光るあの朱色の瓦を見るたびに心が浮き立つ思いだった。
その赤瓦の風景が、訪れるたびに確実に減っていった。
「赤瓦礼賛は旅びとの自由だが、沖縄の台風のこわさを知れば、今のコンクリートの家がはやりだした理由がわかるよ」と沖縄の友人にいわれて、なるほどと頭では納得するのだが、心の奥底では納得していなかった。
東京の国立劇場で沖縄舞踊『めでる華ごころ』の舞台を見た。
沖縄の宝といわれる舞踊家の「作田」「川平節」「護身の舞」「高平良万歳」などを見ながら、異次元の世界に心は飛んだ。どんな動きのときでも、下半身は見事に安定していて、上半身はやわらかな線を描いている。ゆったりと水が流れるような舞台があるかと思うと、軽快な、心のはずむ舞いがある。
これほどまでに多彩な、これほどまでに洗練された伝統舞踊を持ち、伝え、新しい作品を創造し、ますます舞踊人口をふやしている県はほかにない。沖縄タイムスを見て驚くのは、伝統芸能に関する記事の多さだ。琉舞やエイサーや各地の芸能祭の記事が出ない日はない。
ここでいいたいのは、なぜ伝統の沖縄舞踊が隆盛をきわめ、伝統の赤瓦が衰退の道をたどっているのか、ということである。
舞踊、芭蕉布、紅型、陶器の場合は無形文化財の指定があるが、赤瓦を作る技術保持者に対してはそういう指定がない。これはなぜなのか。
いまはセメントに細工を施した新しい赤瓦が生まれていて、それはそれで見栄えがいいのだが、やはり、昔ながらのあの赤瓦の味が捨て難い。
赤瓦の技術者養成、赤瓦使用の場合の補助、国の赤瓦援助制度、屋根だけではなくて、さまざまな形での赤瓦利用法、そういうことをぜひ検討して欲しいものだ。
○ナイチャー論議~よそ者は溶け込む努力当然 ~:1997年7月5日
沖縄タイムスのコラムの「ナイチャー論議」特集がおもしろかった。
東京から那覇にやって来た青年が「ナイチ?」といわれるたびにうんざりする、とぼやいている。逆に「ナイチのどこから」「沖縄には慣れた?」と話しかけられて結構、うれしかったという主婦もいるから人さまざまだ。ウチナンチュの女性はこういっている。
「ヤマトンチュとかナイチャーとかの言葉は決して悪い意味ではなく、親しみをこめてのごあいさつなのです」
「ナイチャーは出て行け」といういじめがあった、と書いている人がいたが、これが第一の驚きだ。実態はどの程度のものなのだろうか。
第二の驚きは、ナイチャーと呼ばれるだけで不愉快になる、失礼だ、差別だと感じるヤマトンチュがいるということだった。
私が三十数年前、初めて沖縄の土を踏んだときもよく「ホンドから?」と聞かれたが、それはちょうど、ヨーロッパの旅で会ったアメリカ人同士が「どこから」「アイオワだよ」なんていっているのと同じだと私は受け取っていた。差別を感じたことはなかった。私が鈍感だったのか、それとも時代が変わって「ヤマト」への反感が高まってきたのか。
いや、ヤマトは沖縄を見捨てようとしているという反感は、当時も強かった。強かったけれども、それは個人に向けられた怒りではなかった。
最近の「ナイチャー現象」の底には、もっと個人へ向けられた攻撃があるのだろうか。私にはわからない。どんな土地でも「よそもの」は浮く運命にある。溶け込むにはそれなりの努力が必要なのは当然のことだ。
沖縄の本土化がいわれながら、音楽の面では逆に本土の沖縄化現象が起こっている。真剣に沖縄の心を学ぼうとしている若者は少ない数ではないだろう。いいものは自然に伝わってゆく。
○雨こそ命~自然の摂理に深い祈り~:1997年8月2日
文明の一つの悲劇は、雨と人とのつながりが断ち切られたことである。
都会で暮らしていると、つい雨がうっとおしいもの、いやなものになってしまう。
私自身、家には二百リットル入りの天水槽を二つ備え、散水や洗車に使っている。暮らしの水の大半は水道に頼っている。だからつい「雨の日=天気が悪い」の図式が頭に浮かぶのだろう。
沖縄の人々の雨への思いも、ずいぶん変わったとは思うが、それでも天水を活用している人は多いし、本土の私たちより密度の濃いつきあい方をしていると思う。雨水利用は一滴の水を神様の贈りものと思うことから始まる。元日の朝、御嶽の井戸から水をくんで床の間に供えるという若水の習慣も本土より数多く残っている。
波照間でアミニゲー(雨願い)の話を聞いたことがある。アミニゲーの歌は、私のように沖縄の言葉に不案内のものにも実に快く響く。これなら神様も心を動かさずにはおられまいと思えるような名調子である。
白雲は雨である
乗雲は水である
天の上を昇りて
この島の上に昇りて
波照間の上に昇りて
時を待ツことなく給われ
寸時を待つことなく給われ
沢山の雨を給われ
石垣の雨乞いの歌も名調子だ。
石の雨戸をはねあげて
鉄の雨戸を切開けて
黒い雨雲をお恵み下さい
白い叢雲よ、水をお恵み下さい
海鳴りのするような大雨を
山鳴りがするほどの豪雨をお恵み下さい
ここには大自然の摂理にぬかづく謙虚さがある。雨こそ命だという深い祈りがある。
○テルリン会見記~沖縄文化なチャンプル~:1997年9月6日
八月、「雨水フェア」が沖縄市で開かれたとき「コザ独立国」のテルリン大統領に会った。
林助さんは「雨水フェア」のトークショウにも参加して、得意のジョークで会場を笑わせていた。
私は昔、林助さんが今の大統領官邸兼私邸にあたるところで民宿を経営していたころ、しばらくお世話になったことがある。だから、林助さんの父君、林山さんにも会っている。三線作りの名人といわれた人だ。
昔のよしみを利用して、大統領に単独会見を申し入れた。
「トークショウでは、ダムは山の中に造らず、川の下流に造れと発言していましたね。あれは卓見でした」
「そうです。大自然を破壊して山の中に造ることはない。下流に造れば、海の赤土汚染だって防ぐことができる」
「沖縄に高い山を造れば雪が降る。その雪の水を利用せよとも…」
「なかなかいい発言だったでしょう。私は、いずれは新しい家を建てるときは雨水利用を義務づけ、家々の地下タンクをつないで、街の下を一大地下タンク網にすることを主張しています」
雨水フェアの会場でも飛び出した大統領の名案珍案である。
「せっかくの機会ですから、コザ独立国の国是についてうかがいましょう」
「きまりを守らないことです。何時に集まるなんていうことは全然、守らない。そのほうが人生たのしいですよ。今はみんなきまりを守ることに慣らされているからそういう人はこの国にはなじめません。わが国には日本的規律はありません」
規律大きらいのテルリン大統領ではあるが、「ごまかし」はもっときらいだ。たとえば敗戦を終戦といったり、侵略戦争を「正義の戦い」だといったりすることへの嫌悪感はいまも強い。
「日本は正義の戦いだといって沖縄をめちゃめちゃにしてしまった。正義を声高に叫ぶものには注意しないとね」
「沖縄の独立よりも、日本に向かって早く独立しなさいというのが先だろう。日本が国として独立して自分の考えで動くようになれば別だが、日本が独立もしていないのに、沖縄が独立できるか」
「国是にはチャンプラリズムもある、と聞きましたが」
「あれもだめ、これもだめというんじゃなくて、あれもよいこれもよいと全部ひとつにしてというのがチャンプルです。黒潮は、さまざまな南方のものを沖縄に寄せています。私たちはそれを暮らしに取り入れた。黒潮に乗って日本に行った連中も何かを持って帰る。沖縄の文化にはいろんなものがごっちゃになっている」
「チャンプルこそ沖縄文化の本質である」
国としての目標は? 「そんなものはありません。遊ぶこと自体が目的です」
○愚直・春潮・良顕~志に誠実に生きた先達~:1997年10月4日
豊平良顕さんのことを思うと、なぜかすぐ比嘉春潮さんの顔を思い出す。比嘉春潮さんのことを思うと、すぐ豊平良顕さんの顔が浮かぶという具合いで、この二人の大先達がどうしても重なりあうのだ。
歴史学者、比嘉春潮さんにお会いしたのはもう二十五年も前になる。
沖縄で半世紀に一人出るか出ないかの秀才といわれた人だが、人の面倒ばかりを見ていて、才能を世に問う機会が遅れた。富や地位を求めぬ暮らしを続けながら、名著『沖縄の歴史』をまとめた。七十六歳のときだ。『新稿・沖縄の歴史』が完成したときは八十七歳だった。
「沖縄のこころとはなんでしょう」
比嘉さんはちょっと考えてから答えた。
「それは、愚直ということでしょうね」
「愚直?」
「愚直というのは、よくいえば、小利口に立ち回らない。思い込んだらなかなか変えない。悪くいえば変えることができない。そういうことでしょうか。私自身は融通がきかなくてずいぶん損をしてきましたが、人をかきわけて出世するつもりはなく、まあ、これでよかったと思います」
そんな話を新聞に書いたあと、沖縄を訪れた折に豊平良顕さんにお会いした。
「比嘉春潮さんがいわれた愚直、私も、大賛成です。あれが沖縄のこころです」
以後はお会いするたびに愚直論になった。誤解のないようにいっておきたい。ここでいう愚直とは、己の生き方、己の志にかたくななまでに誠実であることの意味だ。それに、沖縄のこころを愚直だけでくくる割り切り方をするつもりはない。ただ、沖縄独自の自然や文化を壊そうとするものに対し、愚直に立ち向かった豊平さんの姿勢がなつかしい。












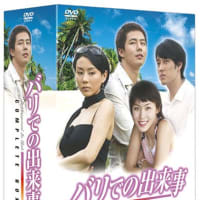
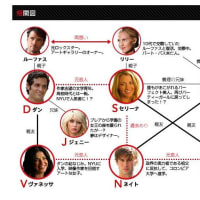
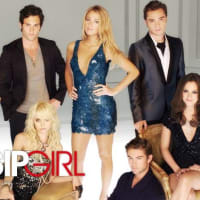

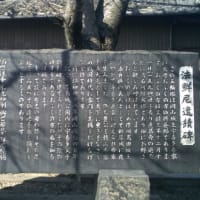



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます