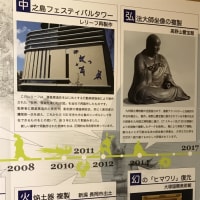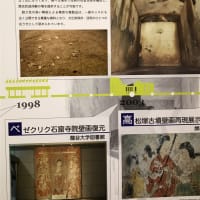同じく斎藤美奈子の「2008年の批評」で『日本語が滅びるとき』とともに、その対極にあるとして取り上げられていた本。
サブカルチャー批評や若者文化に関する批評がここ数年若手評論家の代表者である(といっても1971年生まれなのでもう40手前ですが)東浩紀の焼き直しにしか過ぎなかったこと、しかし東に代表される考え方は1990年代の「古い想像力」であり、2001年以降に芽生えてきた「新しい想像力」をとらえてはいない、という主張です。
(「1980年代の想像力」の僕としては半分、下手すると1割くらいしかわかっていないのかもしれませんが・・・)
ひとことで言えば
碇シンジ(引きこもり)では夜神月(決断主義)を止められない。
詳しく言えば
90年代は平成不況と地下鉄サリン事件に象徴される社会の流動化によって「大きな物語」が機能しないことが明らかになり(ポストモダン化)、社会的自己実現への信頼が大きく低下した。そのような「意味」と「価値」を社会が与えてくれないなかでは「なにかの価値観を信じれば(社会にコミット)すれば誰かを傷つける」ので「何も選択しないで(社会にコミットしないで)引きこもる」という考え方、「~する/~した」という社会的自己実現ではなく、価値観を相対化・宙づりにしたまま「~である/~ではない」という自己像(キャラクター)の承認によるアイデンティティの確立が志向された(最後の場面で戦うことを拒否して「引きこもって」しまう『新世紀エヴァンゲリオン』(1995~1996)の主人公碇シンジはその象徴。)。
それが東浩紀のいう「データベース消費」であり、そのような世界観の浸透は成長や社会変革を描く物語から「ほんとうの自分」や「過去の精神的外傷」を描く物語が選択され、その結果「キャラクター的実存」は数多くの排他的コミュニティを生み出すことになった。
一方で、2001年の同時多発テロや小泉政権下の構造改革、「格差社会」の浸透により、90年代後半のように「引きこもって」いると生き残れないという「サヴァイヴ感」が社会に共有され始めた。
「大きな物語」が失われた結果「小さな物語」は究極的には無根拠であるが、なにかの「小さな物語」を中心的な価値として自己責任で選択していかなければならない、という現実認識-それを受け入れなければ「政治」の問題としては生き残れず、「文学」の問題としては(「何も選択しない」ということもひとつの選択である以上)成立しない-です。
その「信じたいものを信じる」態度が広まった結果、「9.11以降の動員ゲーム(バトルロワイヤル)」が醸成された。
それを象徴するのが『DEATH NOTE』の主人公夜神月である。
ということです。
もっとも著者はそこで「信じたいものを信じる」という決断主義を無条件に礼賛しているわけではなく、データベース化した排他的コミュニティにタコツボ化した社会からコミュニケーションの可能性を模索しようとしています。
「どうせ世の中勝ったものが正義なのだから」と開き直り、思考停止と暴力を肯定する態度にどう対抗するか、が私たちの課題なのだ。
最終章で語られている将来への処方箋のヒント自体は非常に真っ当な主張です。
ただ、これはまっとう過ぎて、今の20代の人には「結局今までの批評家と同じじゃないか」と思われてしまうかもしれません。
本書が別の意味で圧巻なのは、「ゼロ年代の想像力」の切り口で90年代から現在までの小説・映画・テレビ番組などを次から次へと俎上に乗せて分析し、その有効性を主張している部分です。
僕自身はその中で「読んだ・見た」というのは1割「知っている・聞いたことがある」が4割、残りの5割は「見たことも聞いたこともない」というものでしたが、切り口の鮮やかさ(強引さ)はなかなか見ものでした。
さながら万能包丁の実演販売です(そういえば昔秋葉原の駅前でよくやってましたが、ある意味「アキバ系」かも・・・)。
思い出したのが80年代のパルコ出版のマーケティング誌「月刊アクロス」さまざまな事象を年表に並べて一つのトレンドの切り口でバッサリ切るという大胆な提案が話題になりました(今もWeb Acrossとして続いているんですね。 )。
昔月刊アクロスの編集者だった『下流社会』の著者の三浦展氏の感想を聞いてみたい感じもします。
|
斎藤美奈子曰く
確かにその通りだと思います。
年末につきおまけ(埋め込み無効になっているので画面を2回クリックしてください) 実演販売のコパ・コーポレーションビデオ ののじざく切り包丁 中島章吾実演
|