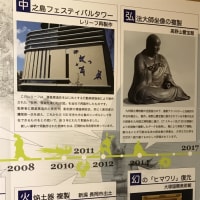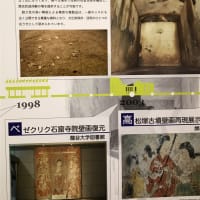また週末にかけて暑さがぶり返しそうです。
先日某社を訪問した際に、受付に「(節電のため)クールビズをやってますのでご理解を」という掲示がありますたが、トイレをお借りしたときにこの暑いというのに便座には暖房が入ったままでした。ビルの大きさを考えるとかなりの消費電力のように思うのですが・・・
東電、17年ぶり需給調整 電力10社の発電量が過去最高
(2007年8月22日(水)16:34 産経新聞)
このニュースも当然のように言われると、一瞬そりゃそうだよな、とも思ったのですが、東京電力が需給調整を要求できる根拠って何なんでしょう。
以前のエントリでちょっと触れたのですが、需要調整を受け入れる工場はもともとピークカットを受け入れる前提での優遇された契約になっているのではないでしょうか。
それにしても任意の要請に応じるのだとした場合、企業は機会損失について株主にどのように説明しないといけませんよね。
----<追記>------
東京電力のプレスリリースに、契約による需要抑制だと書いてありました。(参照)
----------------
また、契約による供給制限だとすれば、あたかも企業が自発的に協力しているかのようなマスコミ報道は「大工場は率先して節電に取り組んでいる」とアピールすることで一般市民に節電意識を植え付けようとあえてミスリードしているのでしょうか。
そうだとすればそれもちょいといやですね。
一方で、日本の電力会社の設備投資や料金体系の適正さや投資採算性について、株主からや他社との競争によるけん制が(自由化はされたものの現時点ではあまり)働いていないのも問題ではないかと思います。
映画『エンロン』では、カリフォルニア州の電力危機のときに、エンロンはあえて需要先に供給せず価格をぎりぎりまで吊り上げてから高値で供給しました。
そこまでの極端なことが望ましいとは思いませんが、電力会社も一私企業としては、異常気象などでのピーク時の需要に設備投資をあわせるのでなく一般的なピーク需要を目標にするのが一番効率的なはずです(逆に言えば今までは柏崎刈羽原発の原発7基分余裕があったということです。)。
それ以上の設備投資を「社会的使命」とか(調べていないのですが)電気事業法上の義務(または監督官庁の指導)として株主に対して正当化できるのでしょうか。
東京電力の有価証券報告書を見ても、「事業等のリスク」(p26)として電力自由化をうたってはいますが、逆に公益性を持つが故の過剰投資については言及していません。
許認可の条件として一定の(相当程度の?)公益性が求められる、逆に言うと過度に収益を追求すると許認可を取り消されて元も子もなくなる、というのは最大のリスクじゃないでしょうか。
マインド自体が公益企業的なように見えます。
日本の電力会社のようにきわめて公益性の高い、しかもほぼ地域独占が認められている(逆に言えばその独占が官庁の許認可に根拠があるというある意味不安定な)企業は求められる行為規範が違うわけで、そのような企業が上場する意味合い(資金調達も借入金と社債が大半ですし、電力会社なら上場していなくても社債発行も可能だと思います)って議論されてもいいように思います(これは成田空港会社の上場問題にも言えますね)。
それとも「改革路線」の中でもっと自由化に舵を切っていく方向なのでしょうか
それならそれでありだと思います。
でも原子力発電問題などは一企業のCSRという世界でなく政治問題としてきちんと議論するのもいいとも思うのですが・・・
先日某社を訪問した際に、受付に「(節電のため)クールビズをやってますのでご理解を」という掲示がありますたが、トイレをお借りしたときにこの暑いというのに便座には暖房が入ったままでした。ビルの大きさを考えるとかなりの消費電力のように思うのですが・・・
東電、17年ぶり需給調整 電力10社の発電量が過去最高
(2007年8月22日(水)16:34 産経新聞)
このニュースも当然のように言われると、一瞬そりゃそうだよな、とも思ったのですが、東京電力が需給調整を要求できる根拠って何なんでしょう。
以前のエントリでちょっと触れたのですが、需要調整を受け入れる工場はもともとピークカットを受け入れる前提での優遇された契約になっているのではないでしょうか。
それにしても任意の要請に応じるのだとした場合、企業は機会損失について株主にどのように説明しないといけませんよね。
----<追記>------
東京電力のプレスリリースに、契約による需要抑制だと書いてありました。(参照)
----------------
また、契約による供給制限だとすれば、あたかも企業が自発的に協力しているかのようなマスコミ報道は「大工場は率先して節電に取り組んでいる」とアピールすることで一般市民に節電意識を植え付けようとあえてミスリードしているのでしょうか。
そうだとすればそれもちょいといやですね。
一方で、日本の電力会社の設備投資や料金体系の適正さや投資採算性について、株主からや他社との競争によるけん制が(自由化はされたものの現時点ではあまり)働いていないのも問題ではないかと思います。
映画『エンロン』では、カリフォルニア州の電力危機のときに、エンロンはあえて需要先に供給せず価格をぎりぎりまで吊り上げてから高値で供給しました。
そこまでの極端なことが望ましいとは思いませんが、電力会社も一私企業としては、異常気象などでのピーク時の需要に設備投資をあわせるのでなく一般的なピーク需要を目標にするのが一番効率的なはずです(逆に言えば今までは柏崎刈羽原発の原発7基分余裕があったということです。)。
それ以上の設備投資を「社会的使命」とか(調べていないのですが)電気事業法上の義務(または監督官庁の指導)として株主に対して正当化できるのでしょうか。
東京電力の有価証券報告書を見ても、「事業等のリスク」(p26)として電力自由化をうたってはいますが、逆に公益性を持つが故の過剰投資については言及していません。
許認可の条件として一定の(相当程度の?)公益性が求められる、逆に言うと過度に収益を追求すると許認可を取り消されて元も子もなくなる、というのは最大のリスクじゃないでしょうか。
マインド自体が公益企業的なように見えます。
日本の電力会社のようにきわめて公益性の高い、しかもほぼ地域独占が認められている(逆に言えばその独占が官庁の許認可に根拠があるというある意味不安定な)企業は求められる行為規範が違うわけで、そのような企業が上場する意味合い(資金調達も借入金と社債が大半ですし、電力会社なら上場していなくても社債発行も可能だと思います)って議論されてもいいように思います(これは成田空港会社の上場問題にも言えますね)。
それとも「改革路線」の中でもっと自由化に舵を切っていく方向なのでしょうか
それならそれでありだと思います。
でも原子力発電問題などは一企業のCSRという世界でなく政治問題としてきちんと議論するのもいいとも思うのですが・・・