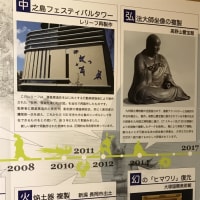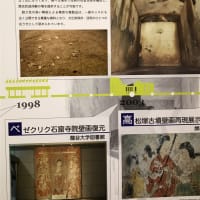幕末の越後長岡藩で、下級藩士の出から開明論者として頭角を現し、幕府の崩壊を予見して藩政を改革するとともに洋式の軍備を充実させ、幕末最大の激戦の一つと言われる北越戦争に散った河合継之助の話。
河合継之助は幕末の動乱の中で外国の事物にふれ、先見性と合理性を持って早い時期から幕府の崩壊、さらに「武士」という階級自体の消滅を見通す一方で、陽明学を自らの行動原理として自分を「長岡藩士」として規定します。
そして譜代である長岡藩を、大政奉還の中で徳川からも薩長からも中立で独立した存在にしようと、江戸屋敷の書画骨董を売り払って当時日本に3門しかなかったガトリング砲のうち2門を購入したりと徹底した軍備の強化をはかります。
しかし、最終的な勝利は無理としても抗戦する中で外交努力で独立を勝ち取るという考えは、徳川側の隣国の会津藩からも「官軍」からも理解されず、結局官軍との激戦の中で河合継之助は命を落とし、ほどなく長岡藩も降伏することになります。
一昨日取り上げた『日本の「安心」はなぜ、消えたのか』での「武士道」と「商人道」の関係でいえば、河合継之助は最後まで「武士道」を透徹したということになります。
そしてこれは、幕末から一貫して「商人道」を貫いた福沢諭吉との対面の場面で見事なコントラストを描きます。
「まずうかがいたいが、あなたは徳川家中心の立憲政治論(モナルキー)ですか。それとも今日と中心の立君政治論ですか」
と福沢はきいた。
「そういう議論に、できるだけ興味を持たぬように自分をいましめています」
「そういう議論に」
「左様、この一天下をどうするかという議論は、他の志士にまかせたい。私には越後長岡藩の家老であることの方が重く、それがこの河合継之助のすべてなのです」
「おどろいたな。わざと自分の窓を締め切っているのだ」
「締め切っている・・・」
「困ったお人だ。日本の世の中がひっくりかえってしまおうというこの時期に、あなたのようなことをいっては。あなたほどの世界感覚を持ち、思慮と胆略をもったひとが中央におどり出て日本の行くべき方角を指ささねばどうにもならぬ」
「・・・日本としては国を開き、貿易をさかんにし、欧米と交際していくことこそ宇内の大道にもとらぬことであり、それをいまこそ声を大きくして叫ばねばならぬ」
「そう、異存はない」
「われわれは薩長に対しても宇内の大道が何であるかを教えねばならぬ」
「それは福沢さんにまかせよう」
「まかせて?」
「私は長岡藩に閉じこもる」
それが結果として長岡城下を戦火で焼く尽くされるという悲劇を招いたことはさておき、武士道を透徹するということはこういうことなのかもしれません。
そして本書でも随所に出てくる幕末の雰囲気に便乗した「攘夷屋」の存在は、武士道と商人道を混ぜたときの「腐敗」を象徴して別の意味で印象的であります。
 |