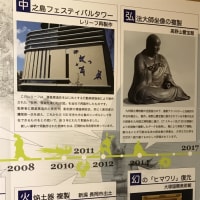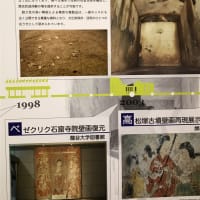これはおすすめです。
相次ぐ企業不祥事やいじめなど、日本社会の「モラルの低下」や「心の荒廃」がさけばれていますが、その原因と処方箋を社会心理学の観点から分析しています。
従来の日本社会は、閉ざされた環境の中で相互監視と制裁のメカニズムが構成員に安心を保証する「安心社会」だったものが、現代の複雑化した社会ではそれ維持できなくなっていることにあるといいます。
そして、必要なのはリスクをとって他人との関係を積極的に結んでいく、逆に他人に信頼を裏切る者は排除されていく「信頼社会」の構築が必要であると説きます。
「安心社会」(従来の日本社会)では実は「正直は美徳」ではなく、制裁のメカニズムによって強制されているだけで、それが働かないところでは不正直がまかりとおる。閉じられた関係の外にいる「他人を信じてはいけない」ので、外部との関係では信頼を結ぼうとしない、というあたりは説得力があります。
昔言われていた「ムラ社会」ってそういうものですよね。
また返す刀で、最近処方箋として流行の「品格」とか「武士道」を切って捨てています。
カナダ人の学者ジェイン・ジェイコブスの研究によれば、古来人類のモラルは大きく「市場の倫理」と「統治の倫理」に分けられます。
「市場の倫理」は「他人や外国人とも気安く協力せよ」「正直たれ」「契約尊重」というような信頼社会の基本原理であり、「統治の倫理」は「規律遵守」「位階尊重」「忠実たれ」という終端内部の秩序を維持するための安心社会の基本原則が並びます。
ジェイコブスの指摘の重要なところは、この二大倫理の体系が目指すものは全く対立する世界であり、この二つを混ぜることは矛盾と混乱を社会にもたらすだけでなく、最終的には「何をやってもかまわない」という究極的な堕落を生み出すということです。(確かに何をやっても何か一つはそれを正当化する倫理規範にひっかかるわけですから。)
そして著者はこれからは信頼社会を構築するために「武士道」(=統治の倫理)でなく「正しいことが自分の利益になる」という「商人道」(=市場の倫理)を広げて行く必要があると主張します。
「品格」とか「武士道」を大事にしろという主張は、自分を律することを求める一方で、組織の一番上の専横を止められないというところで基本的な欠陥があるんじゃないか、と胡散臭く思っていたところもあり、腹に落ちる一冊でした。
相次ぐ企業不祥事やいじめなど、日本社会の「モラルの低下」や「心の荒廃」がさけばれていますが、その原因と処方箋を社会心理学の観点から分析しています。
従来の日本社会は、閉ざされた環境の中で相互監視と制裁のメカニズムが構成員に安心を保証する「安心社会」だったものが、現代の複雑化した社会ではそれ維持できなくなっていることにあるといいます。
そして、必要なのはリスクをとって他人との関係を積極的に結んでいく、逆に他人に信頼を裏切る者は排除されていく「信頼社会」の構築が必要であると説きます。
「安心社会」(従来の日本社会)では実は「正直は美徳」ではなく、制裁のメカニズムによって強制されているだけで、それが働かないところでは不正直がまかりとおる。閉じられた関係の外にいる「他人を信じてはいけない」ので、外部との関係では信頼を結ぼうとしない、というあたりは説得力があります。
昔言われていた「ムラ社会」ってそういうものですよね。
また返す刀で、最近処方箋として流行の「品格」とか「武士道」を切って捨てています。
カナダ人の学者ジェイン・ジェイコブスの研究によれば、古来人類のモラルは大きく「市場の倫理」と「統治の倫理」に分けられます。
「市場の倫理」は「他人や外国人とも気安く協力せよ」「正直たれ」「契約尊重」というような信頼社会の基本原理であり、「統治の倫理」は「規律遵守」「位階尊重」「忠実たれ」という終端内部の秩序を維持するための安心社会の基本原則が並びます。
ジェイコブスの指摘の重要なところは、この二大倫理の体系が目指すものは全く対立する世界であり、この二つを混ぜることは矛盾と混乱を社会にもたらすだけでなく、最終的には「何をやってもかまわない」という究極的な堕落を生み出すということです。(確かに何をやっても何か一つはそれを正当化する倫理規範にひっかかるわけですから。)
そして著者はこれからは信頼社会を構築するために「武士道」(=統治の倫理)でなく「正しいことが自分の利益になる」という「商人道」(=市場の倫理)を広げて行く必要があると主張します。
「品格」とか「武士道」を大事にしろという主張は、自分を律することを求める一方で、組織の一番上の専横を止められないというところで基本的な欠陥があるんじゃないか、と胡散臭く思っていたところもあり、腹に落ちる一冊でした。
 |