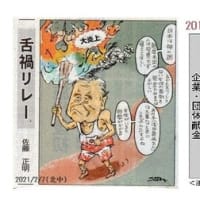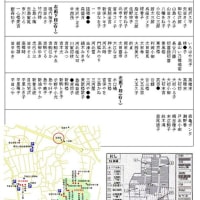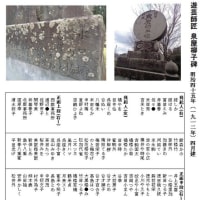【論考】3 石川県ゆかりの表現者と戦争、とくに室生犀星の戦争詩について
2020年5月2日
目次
はじめに:①戦争と弾圧の時代/②日本文学報国会
Ⅰ 犀星の戦争詩:動機/①随筆を対象化/②作家的原点/③プロレタリア文学への親和/④プロレタリア文学に別離/⑤政府高官との接触と躊躇/⑥追いつめられる犀星/⑦政府とメディアと作家/⑧戦後、戦争詩を削除
Ⅱ 石川県ゆかりの表現者:①泉鏡花/②徳田秋声/③鶴彬/④中野重治/⑤杉森久英/⑥長澤美津、永瀬清子、水芦光子/⑦深田久弥/⑧島田清次郎/⑨井上靖/⑩堀田善衛/⑪森山啓/⑫加能作次郎/⑬西田幾多郎、暁烏敏、鈴木大拙
Ⅲ 「戦争詩」を戦争遺産として
Ⅱ 石川県ゆかりの表現者(続き)
(9)井上靖
井上靖は1907年に生まれ、満州事変(24歳)、日中開戦(30歳)、日米開戦(40歳)、敗戦(44歳)を体験し、1991年83歳で亡くなった。井上靖は3回徴兵され、1936年の3回目の徴兵で中国に動員されたが、病気に罹り4カ月ほどで帰還した。この時期に「中国行軍日記」をのこしたが、公表せず、2009年に『新潮』誌上ではじめて公開された。
井上靖は「中国行軍日記」のなかで、「河上ニハ屍(しかばね)山ノ様ナリト ソノ水デ炊事シタ 相変ラズ人馬ノ屍臭紛々タリ」、「アヽフミ(ふみ)ヨ! 伊豆ノ両親ヨ 幾世(長女)ヨ!」、「神様! 一日モ早ク帰シテ下サイ」、「相変ラズ車輪ヲミツメ湯ケ島ノコトヲ考ヘテ歩ク……羊カンデモ汁粉デモ甘イモノガタベタイ」、「軍隊といふところはたゞ辛いだけ」など、行軍の過酷さ、家族や故郷への思いが綴られている。
井上の戦争詩
日中文化交流協会理事の佐藤純子さんは、何志勇さん(大連外国語大学)との対談(2012年「国際日本文化研究センター紀要」第7号)のなかで、井上靖について、「『行軍日記』には、戦争の悲惨さというものを書いています。…戦意を鼓吹していない」と述べているが、戦時期に公表されなかったので、このような評価は妥当ではないだろう。
戦争真っただ中の『辻詩集』(1943年)に掲載された井上靖の戦争詩「この春を讃ふ」(花ひとつない 狭いわが家の庭で/うららかに照る春の陽をあび/妻はふたりの幼き子らに語る。/遠いみんなみの海をおほふ/鋼鉄の いくさ船つくるために/幼ければ幼いままに/けふよりは 一粒の米を節し/一枚の紙を惜しめ と。…略…)については話題にしていない。
佐藤さんは中国人研究者何志勇さんにたいして、井上靖が軍事貯金を推奨する詩を書いていたことを指摘せず、「井上靖は昭和が終わる前に、戦争や昭和に触れた詩をたくさん書きました」などと話し、井上靖の戦争責任を隠しているようだ。
井上の天皇観
さらに言えば、敗戦翌日の「玉音ラジオに拝して」という井上靖の記事(1945年8月16日『毎日新聞』)では、「玉音は幾度も身内に聞え身内に消えた。幾度も幾度も――勿体なかった。申訳なかった。事茲(ここ)に到らしめた罪は悉くわれとわが身にあるはずであった。限りない今日までの日の反省は五体を引裂き地にひれ伏したい思いでいっぱいにした。いまや声なくむせび泣いている周囲の総ての人々も同じ思いであったろう。日本歴史未曾有のきびしい一点にわれわれはまぎれもなく二本の足で立ってはいたが、それすらも押し包む皇恩の偉大さ! すべての思念はただ勿体なさに一途に融け込んでゆくのみであった。」と書き、戦争に負けて申し訳ないと、天皇に謝罪してさえいるのである。
井上靖には、厭戦感情があったとしても、非戦でも、反戦でもなかった。「ご時世」に迎合して、戦争詩も詠んでいる。戦後、日中友好に尽力し、1980年代になって、戦争について書いたとしても、青年時代の戦争への係わりを対象化しなければ、自己欺瞞ではないだろうか。それ故に、佐藤純子さんも井上靖と戦争について、明確な評価ができないでいるのだ。やはり、戦争については、他者による批判ではなく、本人による自己批判が必要なのではないか。
【参考資料】井上靖の著作:「中国行軍日記」(1936年)、「玉音ラジオに拝して」(1945年8月16日『毎日新聞』)/『辻詩集』(1943年)/佐藤純子×何志勇(2012年「国際日本文化研究センター紀要」第7号)
(10)堀田善衛
堀田善衛は1918年富山県に生まれ、1931年金沢二中に進学し、1936年慶応大学に入学した。満州事変(13歳)、日中開戦(19歳)、日米開戦(23歳)、敗戦(27歳)を体験して、1998年80歳で亡くなった。
丁世理(日本大学)は堀田善衛の自伝的長編小説『若き日の詩人たちの肖像』(1968年)を分析している。その論文「堀田善衛の戦時体験―政治への漸近、運動の痕跡」によれば、堀田は早稲田大学学生を中心とした学生演劇団体「青年劇場」に関与し、特高にマークされていた(1940年2月「特高月報」)という。どの時点だか特定できないが、一度逮捕されているようだ。
また、堀田は従兄の野口務(1930年逮捕)の影響を受けており、小説中の主人公(堀田)は、山田喜太郎(和田喜太郎=1943年に横浜事件で逮捕)から託された手紙を大岡山に住む某共産党幹部(伊藤律)に送り届けている。
1942年ごろ
堀田は『若き日の詩人たちの肖像』で、室生犀星の詩「シンガポール陥落す」について、一人が「ひでぇものを書きやがったな。怒濤は天に逆巻きたぁなんだね」と不同意を表明し、別の人が「こんなもんのなかでは、おとなしくて品もあるし、いい方なんじゃないの」と、犀星を擁護すれば、すかさず「だけど、歴史にもかゞやけたぁ、これもまたなんだね」とやりかえし、当時の青年たちの反応を書いている。
作中で、堀田は1942年当時を振り返って、「こういうふうな詩をめぐる論議には、何かしら辛いものがある、日本国家への義理だてということもあってみれば、何かが咽喉か頭かにひっかかって徹底したことが、あるいは本当のことが言いにくいという気味がある、と感じていた」と、独白している。
戦後
戦後の堀田善衛は『時間』(1955年)で、「殺、椋、姦、火、飢荒、凍寒、瘡痍。妻の莫愁も、その腹にねむっていた、九カ月のこどもも、五歳の英武も、蘇州から逃れてきた従妹の楊嬢も、もはやだれもいなくなった」(未読)と、1937年の南京を克明に描いている。1960年代後半には、堀田は「ベトナムに平和を!市民連合」(ベ平連)に参加し、脱走米兵の支援活動にも取り組んでいた。
【参考資料】堀田善衛の著作:『若き日の詩人たちの肖像』(1968年)、『時間』(1955年)/丁世理(日本大学)の論文「堀田善衛の戦時体験―政治への漸近、運動の痕跡」
(11)森山啓
森山啓は1904年に新潟県で生まれ、1920年第四高等学校に進学し、1925年東京帝国大学に入学し、プロレタリア文学に傾倒し、1928年に大学を中退した。満州事変(27歳)、日中開戦(33歳)、日米開戦(37歳)、敗戦(41歳)を体験し、1941年から78年まで小松市で暮らし、1991年に87歳で亡くなった。
1930年代前半
『潮流』(1935年)には、1921年から35年までの森山の詩がおさめられている。1929年の「南葛の労働者」(荒川は南葛の無産者の/苦悩の夜を流れる静脈/荒川は南葛労働者の/奮起の朝に波立つ動脈/(…略…)/怒れる民衆の血脈の如く鼓(う)て荒川よ!/かつて民衆の朝をうたひ/やがて白熱のま昼、□□□□□(戦闘の大火)をうたはうとする/波よ 流れよ/春の血管のやうに、太陽を浴び、平野に脈打つもの□)が当時の階級闘争の荒々しさを伝えている。
1930年の「生き埋め」(掘り出された父親のなきがらを抱き/いとしい娘よ/お前のむせび泣きは/泌(し)み入るやうだ、犀河村の森にも川にも/またおいら土工の荒くれた胸にも。/…略…)と、「セメントの底」(…略…/夜は更け、夜は明けた/そして見よ/廿六時問の彼女の苦しみに対し/今、顔面手足が焼けただれたをつとの死骸が渡される/今、声もなくしゃくり泣く彼女の絶望と、夫の生命の代償として、金一封が約束される/一昨年は古ボイラーを破裂せ、今年はタンクを破裂させたNセメント会社重役らの、数日の遊興費にも足らぬ/金四百参拾円也が!)が、地元石川県での労働災害事故による犠牲者・家族の悔しさと悲しみを伝えている。
「生き埋め」(『戦旗』1930年2月)は1929年11月に犀川上流の上水道工事現場で起きた朝鮮人労働者圧死事件、「セメントの底」は同年10月の七尾セメント会社のタンク破裂労災事故を扱っている(『昭和前期の石川県における労働運動』、上田正行著『中心から周縁へ』)。
1931年の「戦士たちに(三月十八日に)」は1871年パリコンミューン60周年を讃える詩である。
詩は「…略…/おお□□□□□□の戦士らよ! お前たち/もうかえることのない先導者たちよ!/あのパリー市庁の□□の下で、あの□□□□□□万歳の歓呼の中で/春の風――「マルセエーズ」と「出発の歌」の吹奏の前で/あまりの感動に、頭を地面へ押しつけたお前らの老人達よ!/(おお彼らも戦死者を地下から呼びたかつたのだ!)/何と言ふ長い困難を/何と云ふ短い勝利を――お前たちみんなは持ったことか/不運な勝利者達、□□□□嵐の下に、/その春の新たな花が、みんな散るのを見ねばならなかつたお前たちよ!/どれほど お前たちが其の自由を、欲したことか/もう死地に落ちたことを感じ、□□を投げて救ひを乞ふ代りに、/あの□□□□□を築いたお前たち/敷石を掘る男たちの/敷石を運ぶ女たちの/泣かんばかりに緊張して手伝ふ子供たちの/おおその一人残らずの必死な息遣いを以て/…略…」と、パリコンミューンで倒れた同志たちを讃え、悲しみ、復活を期し、自らも、満州事変の1931年をたたかいぬく決意を詠っている。
検閲で、ずたずたに切り裂かれたこの詩について、槇村浩は「獄中のコンミューンの戦士の詩を憶って」( わたしは獄中で/若い憂愁が瞼を襲うとき/いつもあなた(森山啓)のコンミューンの詩(「戦士たちに」)を想い出した)と、「森山啓に」(階級的な仕事の中で/個人的な享楽とものを書くことより牢獄を選ばねばならぬときは/ふしぎと思い出したように、いつでもこの詩(「戦士たちに」)が愛誦されたときだった)で、森山を高く評価している。【1932年4月逮捕~1935年非転向で出獄後の作品か?】
パリコンミューンから98年目の1969年3月30日、パリの女性がベトナム戦争に抗議して自殺した。ベトナム反戦・大学闘争をたたかう私たちは、歩道の敷石を剥がし、車道に積み上げ、機動隊が姿を見せれば、それを砕いては投げ、一息ついたときに、バリケードのなかで、「フランシーヌの場合は」(新谷のり子)を歌った。森山や槇村と同じ気持ちでパリ労働者市民との連帯と追悼を歌った。
1930年代後半~
1937年には、戸坂潤(「文芸評論の方法について」)から、「(森山啓は)文芸学上の方法とシステムとに対して、眼に見えてタガがゆるんで来た。かくて今日彼の独自な有用性は可なり低下したようだ」と批判されている。
1943年、『日本文学報国会会員名簿』の小説部会、詩部会には、森山啓の名前は見あたらない。
戦後、平野謙は「(森山啓は)終始一貫プロレタリア文学擁護の論陣(を張り)…社会主義リアリズム論の日本的消化のために孤軍奮闘した人」(「文学・昭和十年前後」)であったと評し、桑尾光太郎は「『文学界』に参加(1935年)したのちの森山は、現実への無関心から体制無批判ひいては体制順応という、なし崩しの転向のコースを歩んでいった」(「森山啓の社会主義リアリズム」)と批判的に書いているが、実際のところはどうなのだろうか。
【参考資料】「生き埋め」(『戦旗』1930年2月)、「戦士たちに(三月十八日に)」(『潮流』1935年)/「文芸評論の方法について」(戸坂潤1937年)/『昭和前期の石川県における労働運動』(1975年)/『中心から周縁へ』(上田正行2008年)/「文学・昭和十年前後」(『平野謙全集』第4巻1975年)/論文「森山啓の社会主義リアリズム」(学習院大学・桑尾光太郎)/
(12)加能作次郎
加能作次郎は1885年に羽咋・西海村に生まれ、日清戦争(9歳)、日露戦争(19歳)、1911年大学卒業(26歳)、欧州戦争(29歳)、満州事変(46歳)、盧溝橋事件(52歳)を体験し、1941年日米開戦の年(56歳)に亡くなった。
大学卒業後の1913年から『文章世界』(1906~20年)の編集に携わり、翻訳や文芸時評を発表し、1918年に私小説『世の中へ』で認められ、作家として活躍する。
加能は1927年の『早稲田神楽坂』では、「ゴルキイの『夜の宿』(『どん底』、帝制末期のモスクワの木賃宿に住むどん底の人々の生活を描く)などを実際に稽古をしたりしたものだった」と書き、学生時代は左翼的スタンスに立っていたようだ。加能の最後の作品『乳の匂ひ』(1940年)では、日清・日露の戦間期の少年時代を追憶しながら、女性の貧困と不運について同情的に書いているが、体制への迎合も批判もない。
【参考資料】加能作次郎の著作:『世の中へ』(1918年)、『早稲田神楽坂』(1927年)、『乳の匂ひ』(1940年)
(13)西田幾多郎、暁烏敏、鈴木大拙
A 西田幾多郎
西田幾多郎は1870年にかほく市に生まれ、第四高等中学入学・中退(20歳)、日清戦争(24歳)、日露戦争(34歳)、満州事変(61歳)、日中戦争開戦(67歳)、日米開戦(71歳)を体験し、敗戦2カ月前に75歳で亡くなった。
明治期
上原麻有子は日清戦争前の1890年(20歳)の西田について、「出身地の石川県にある第四高等中学に在籍していました。しかし、当時の新しい学制により設立されたこの学校の教育に不満を抱き、同志と共に中途退学してしまいます」(「近代日本の哲学者、西田幾多郎にとって『自己』とは何であるか」)と書いている。ここで言う「新しい学制」とは1886年の中学校令であり、「社会上流ノ仲間ニ入ルベキモノ」、「社会多数ノ思想ヲ左右スルニ足ルベキモノ」を養成する学校(7校)として設立され(文科省HP)、西田は抑圧的な管理教育に反撥したようだ。
日露戦争後
外に向かっては日清戦争(24歳)、日露戦争(34歳)、国内的には自由と権利は制限され、貧富の格差の時代にあって、西田幾多郎はどのように考えていたのか。
1904年に弟が旅順で戦死し、西田は「私は今弟の墓標の前に立って、ただ涙を流すのみである」と、不条理な死を慨嘆する手紙を友人に送っている(ETV「死を見つめる心―西田幾多郎と鈴木大拙」浅見洋×白鳥元雄)。1905年1月5日の日記(35歳)に、西田は「正午公園(兼六園)にて旅順陥落祝賀会あり、万歳の声聞こゆ。今夜は祝賀の提灯行列をなすというが、幾多の犠牲と、前途の遼遠なるを思わず、かかる馬鹿騒ぎなすとは、人心は浮薄なる者なり」(『西田幾多郎哲学論集3』上田閑照の解説)と、冷静に受けとめている。にもかかわらず、西田は1905年の『倫理学草案』では、「家族は最完全なる社会である」「国家というのは一層大なる家族的結合」と、天皇を父とする疑似家族国家観を展開し、天皇によって宣戦布告された日露戦争での弟の戦死を容認しているのである。
1911年の『善の研究』の最終ページで、西田は「宗教は宇宙全体の上に於て絶対無限の仏陀其者に接するのである。…而してこの絶対無限の仏若しくは神を知るのは只之を愛するに因りて能くするのである、之を愛するが即ち之を知る(の)である。…神は分析や推論に因りて知り得べき者でない。実在の本質が人格的の者であるとすれば、神は最人格的なる者である。我々が神を知るのは唯愛又は信の直覚に由りて知り得るのである。故に我は神を知らず我唯神を愛す又は信の直覚に由りて知り得るのである」と締めくくっている。まさに、この「仏陀」や「神」はやがて「天皇」となり、有無を言わさぬ「滅私奉公」の世界へと導くのである。
1918年、西田は山本良吉宛の書翰で「萬世一系の皇室は大なる慈悲。没我、共同の象徴であると思ふ。此の深い精神をとかねばならぬと思ふ」と書き送っているが、『善の研究』からたどり着く当然の帰結であろう。
太平洋戦争期
1935年「教育勅語ノ奉体、国体観念、日本精神ノ体現」をめざした教学刷新評議会(会長:文部大臣)が設立され、西田幾多郎、和辻哲郎、田邊元といった京都学派系の哲学者が参加している。
日米開戦前年1940年の講演録『日本文化の問題』で、西田は「従来、東亜民族は、ヨーロッパ民族の帝国主義の為に、圧迫せられていた、植民地視されていた、各自の世界史的使命を奪われていた。…今日の東亜戦争は後世の世界史に於て一つの方向を決定するものであろう」と主張し、1937年から始まった中国侵略戦争を「植民地解放戦争」であるかのように欺瞞・讃美し、文化勲章を受けている。
大宅壮一の『西田幾多郎の敗北』(1954年)には、西田が右翼から狙われていたかのように書かれ、小林敏明の『夏目漱石と西田幾多郎』(2017年)には、戦中の西田は自由主義者であり、軍部から利用された「被害者」であったかのように描かれている。
しかし、文芸誌『文学界』が主宰した「近代の超克」の座談会(1942年)に京都学派が参加しており、西田自身も「国策研究会」に請われ、「世界新秩序の原理」を発表している。
1943年の『世界新秩序の原理』のなかで、西田は「皇室は過去未来を包む絶対現在として、皇室が我々の世界の始であり終である。皇室を中心として一つの歴史的世界を形成し来った所に、万世一系の我国体の精華があるのである。我国の皇室は単に一つの民族的国家の中心と云うだけでない。我国の皇道には、八紘為宇の世界形成の原理が含まれて居るのである」、「神皇正統記が大日本は神国なり、天祖はじめて基をひらき、日神ながく統を伝へ給ふ。我国のみ此事あり。異朝には其たぐひなしという我国の国体には、絶対の歴史的世界性が含まれて居るのである。我皇室が万世一系として永遠の過去から永遠の未来へと云うことは、単に直線的と云うことではなく、永遠の今として、何処までも我々の始であり終であると云うことでなければならない」、「日本精神の真髄は、…八紘為宇の世界的世界形成の原理は内に於て君臣一体、万民翼賛の原理である」、「英米が之に服従すべきであるのみならず、枢軸国も之に倣うに至るであろう」と書いているように、西田は天皇制と侵略戦争の理論的支柱となっている。
西田の生前最後の論文「場所的論理と宗教的世界観」(1945年)では、「今日の時代精神は、万軍の主の宗教(注:ユダヤ教)よりも、絶對悲願の宗教を求めるものがあるのではなからうか。仏教者の反省を求めたいと思ふのである」のあとに、脈絡もなく「世界戦争は、世界戦争を否定する為の、永遠の平和の為の、世界戦争でなければならない」と書いている。
この言葉は、第一次世界大戦時に、「すべての戦争を終わらせるための戦争」(The war to end all wars)として、戦争推進キャンペーンとして使われており、西田は、すでに破産したこの言葉を使って、敗戦濃厚な侵略戦争を全面肯定する論陣を張り、他方では、1945年5月11日の鈴木大拙宛手紙に、「民族の自信を唯武力と結合する民族は武力と共に亡びる」と書き送っている。西田は6月に亡くなった。
しかしこの論理は破綻している。ここでいう「世界戦争」は日本による侵略戦争のことであり、「世界戦争」はいずれかが敗北して、一旦の決着がつくとしても、戦争をもたらす根本的な資本主義の社会システムはそのままであり、資本の危機はふたたびみたび戦争を引き寄せることは自明である。寺内さんは、戦後に編集された『西田幾多郎全集』からこの論文が削除されたと指摘しているが、むべなるかな。
【参考資料】西田幾多郎の著作:『場所的論理と宗教的世界観』(1945年)、『世界新秩序の原理』(1943年、青空文庫)、講演録『日本文化の問題』(1940年)、『善の研究』(1911年、国会図書館デジタル)、『倫理学草案』(1905年)/寺内徹乗「西田幾多郎の知られざる闇」(『はばたき』27号2017年)、/寺内徹乗講演録「西田幾多郎とアジア太平洋戦争」(2020年2月)/小林敏明『夏目漱石と西田幾多郎』(2017年)/上原麻有子「近代日本の哲学者、西田幾多郎にとって『自己』とは何であるか」(2013年、明星大学元教員)/『西田幾多郎哲学論集3、』(上田閑照の解説)/「死を見つめる心―西田幾多郎と鈴木大拙」(浅見洋×白鳥元雄、2005年ETV)/『西田幾多郎の敗北』(大宅壮一、1954年)
B 暁烏敏
暁烏敏は1877年白山市の明達寺に生まれ、日清戦争(17歳)、日露戦争(27歳)、満州事変(54歳)、盧溝橋事件(60歳)、日米開戦(64歳)、敗戦(68歳)を体験し、1954年77歳で亡くなった。
青年期
もともと1910年代の暁烏は真宗が近代的宗教になるためには、封建的倫理を捨てねばならないと呼びかける高光大船や藤原鉄乗らに合流し、ロシア革命を讃え、米騒動や労働運動を支持し、朝鮮植民地支配に異を唱えていたのである。しかし、その後の暁烏は国家主義に転じていく。
戦時期
1931年、「長江貿易は日本の栄養線だ」と言って満州事変が起こされ、翌1932年の上海事変では6000人もの中国民間人を殺戮し、120万人もの避難民をだしている。しかし、当時の暁烏敏は『非戦争論者である私は、戦争が始まったら何をするか』(1931年)と問い、「ガンジーさんは、あの世界大戦の折りには、独立運動を中止して、英国のために戦費を集めたり、自ら看護兵となって、欧州の戦場に従軍せられたりしました。ガンジーさんのこの広い心がトルストイやロマン・ローランの心よりも尊いように思われます」と、ガンジーにならって、始まったばかりの中国侵略への支持と協力を宣明している。
暁烏敏全集別巻を見ると、1942年『大東亜新秩序建設の根本』、『大東亜を築く心』、『臣民道を行く』、1943年『大御心を仰ぎまつる』、1945年『教育勅語謹承』、『勝利への一歩』の論述がある。しかし、全集に収録されているものは『大東亜新秩序建設の根本』、『大御心を仰ぎまつる』だけであり、マスコミの大本営発表を批判し、「経済統制がうまくいっていない」と愚痴をこぼし、「愛国行進曲や日の丸行進曲に落ち着きがない」と揶揄しており、これを以て暁烏敏は戦争に批判的であったかのような編集になっている。
闇に葬られた著書
しかし暁烏敏は1928年、31年、36年、37年、38年、39年、40年、41年に朝鮮・中国にわたり布教活動をおこない、1937年に発行され、著述目録からも除外されている『皇道・神道・仏道・臣道』(北安田パンフレット第47)を読めば、暁烏がいかに戦争に全面的に協力していたかがわかる。このパンフレットは1936年に暁烏が朝鮮・ソウルの南山本願寺でおこなった説教の講演録(文庫判で、200頁)で、序文には「聖徳太子のお筆になった『十七条憲法』にたよって大日本臣民道を語った」、「近来神道といい、皇道といい、仏道といって自らを高くあげようとし、あらぬ邪道に陥っている人の多いのは臣民道を会得していないためだと思います。私共は、神道を承り、皇道を承り、仏道を承って、私共自身の臣民道を教えて頂かねばならぬと思います」と述べている。
1936年といえば、蘆溝橋事件の直前であり、日本が本格的に中国侵略に突入して5年目の年である。このような情勢のなかで、暁烏が朝鮮や中国に渡って、天皇制を謳歌し、日本軍の宣撫工作に全面的に協力している。
では、内容に立ち入っていこう。「我々は大日本の臣民であります。天皇陛下のやつこらと仰せられる臣民であります」と天皇に最敬礼し、「今日の日本臣民は子供をお国の役に立つように、天皇陛下の御用をつとめるように念願して育てにゃならんのであります。…日本の臣民は天皇陛下の家の子供として、天皇陛下の御用にたち、そしてお国のお役にたてさしていただくということは、役人ばかりでない、百姓でも、町人でも、すべてその心得がなくてはならんのであります」と天皇への忠誠を要求している。
「田圃を作るものは自分が悪いところを食べて、天皇様によいものを差上げる。それが神嘗祭を持ち、新嘗祭を持っておる日本の本当の臣民であります」、「我々は…お仕事をするのである。ただ労働するのではない。仕事である。日本のあの仕事という言葉は仕(つか)へ、事(つか)へるという字である。誰に仕へ、誰に事へるのか。天皇陛下にお事へするのであります。…身体に力のあるものは身体を出し、心の働きのあるものは心を捧げ、そして天皇陛下のしろしめすところのお国の御用立ちをさしてもらうのであります。それが神ながらの道であります。だからそこに臣の道を考えてゆくところに、神の道が成就し、仏の道が成就し、天皇の御心が成就して下さるのであります」、「信ずる心も、念ずる心もすべて他力より起こさしめたまうなり、何から何まで神様仏様や天皇様のお与えものによって今日この生活をさしてもらっておるのであります。…私共は、『君が代は千代に八千代にさざれ石のいわほとなりて苔のむすまで』と心から歌わしていただける日本臣民であります」と、仏陀を天皇の奴僕にしてしまったのである。
戦後の暁烏敏
このように暁烏敏は、国内はもとより植民地にまででかけて、天皇に身も心も捧げていたのであるが、それでは戦後をどのように迎えたのであろうか。暁烏敏全集の<思想篇9>によれば、『新発足の地盤』『仏教思想とデモクラシー』(1946年)などが敗戦直後に発表された。
『新発足の地盤』では、「この詔書が発せられて、国民は驚き且つ悲しみ、殆ど茫然としていたが、私は念仏と共に心の平静を得て、これからだぞという希望を味あうことが出来た」と語り、自らの責任の重大さについてはほおかむりしている。『仏教思想とデモクラシー』では、「人が人(天皇)のために命を捧げるということは要らんのであります。…キリストは『汝の敵を愛せよ』というておりますが、仏教にはその『敵』さえないと説かれてあります。…皆さんの国家建設に対する熱意が尊く思われ、皆さんの精神にお宿りになっている陛下の大御心を拝して、ここで皆さんを合掌する思いであります」と、天皇を形ばかりに「批判」しながら、天皇に跪いている、醜い仏教者の姿がある。
【参考資料】暁烏敏の著作:『非戦争論者である私は、戦争が始まったら何をするか』(1931年)、『皇道・神道・仏道・臣道』(1937年、北安田パンフレット第47)、『新発足の地盤』(1946年)、『仏教思想とデモクラシー』(1946年)
C 鈴木大拙
鈴木大拙は1870年に金沢市で生まれ、第四高等中学入学・中退、美川で小学校教員(20歳ころ)、日清戦争(24歳)、在米時代(27~38歳)、満州事変(61歳)、日中戦争開戦(67歳)、日米開戦(71歳)、敗戦(75歳)を体験し、1966年96歳で亡くなった。
現在(5月3日)、コロナウイルス対策という理由で、石川県内のすべての図書館が閉鎖され、知る権利(憲法13条)が抑圧されており、やむを得ずインターネット上の確かな情報を摘記することによって、鈴木大拙と戦争について確認する。
初期の大拙
守屋友江は大拙の「米国片田舎だより」の読後感想として、「(日露戦争を挟んだ在米時代(1897~1908年)の)大拙は天皇崇拝や教育勅語を批判し、社会主義に共感を示している。しかし、日露戦争に到ると、熱烈な愛国主義的感情を吐露するようになる」、「15年戦争下では、…島国的な民族主義に閉ざされることを批判し、日本の仏教を世界的な視野で見ようとしながら、それ故にかえって『世界思想戦』として、戦争を肯定してしまう」(『禅に生きる 鈴木大拙コレクション』)と書いている。
戦時期の大拙
市川白弦は『日本ファシズム下の宗教』で、「若き日の鈴木大拙は、『宗教とは、まず国家の存在を維持せんことを計り』という言葉を残している。さらに日本の勢力拡大を妨げる者(民族)は『邪道外道である』と言い、その相手、彼らの国を『暴国』と呼んだ。そして、『宗教の名に由りて、…正義の為に不正を代表せる国民を懲(こら)さんとするのみ』とまで書いた」と大拙を批判している。
元永常はブライアンの『禅と戦争』を読み、「軍国主義時代に鈴木は軍人たちに,禅の精神こそ武士道の精神であると強調し、戦争の現場にいる軍人たちに戦争のイデオロギーを付与した」(『鈴木大拙における禅仏教の論理と民族主義』)と述べている。
戦後の大拙
『霊性的日本の建設』(1946年)のなかで、大拙は「今だから脱白に公言できるが、自分等は今度の戦争は始めから負けるものと信じていた、また負けてくれれば日本のために好かろうとさへ思った」、「これは戦争終結前のものであったので、所述は自ずから限られたところがある」、「それを余りに直接にいふと当局の忌諱にふれて、出版は不可能になる」と記述しており、梅原猛は「今度の戦争が始めから負けると判っていたなら、思想家はやはりそれを公言すべきではないか。あやまった必勝の信念により日本は戦争に突入し、このあやまった必勝の信念により、絶望的な戦いを日本は長い間続けた。一日戦うことによって何万人の人の血がいたずらに流れた。思想家は、こういう状態を前にしてあえて沈黙すべきなのだろうか。それより彼はあやまった信念に固まった人間たちの蒙をといて一日も早く戦争を終わらせることに努力すべきではないだろうか」と批判している(『美と宗教の発見』2002年)。
『北國新聞』(2014年10月9日)に、鈴木大拙が「東西間の生きる文化の懸け橋として国際平和に貢献した」という理由で、1963年のノーベル平和賞の候補に推薦されたという記事がある。戦時中に、自国の戦争に反対もしないで、「平和賞」にノミネートされて、晩年の大拙はどのような心境だったのだろうか。佐藤栄作でさえもらっている賞だから、その程度の権威である。
【参考資料】『禅に生きる 鈴木大拙コレクション』(鈴木大拙著/守屋友江編訳)/『日本ファシズム下の宗教』(市川白弦、1975年)/『鈴木大拙における禅仏教の論理と民族主義』(元永常、2009年「印度學佛教學研究」第57巻第2号)/『禅と戦争―禅仏教は戦争に協力したか』(2001年、ブラィアン・アンドルー・ヴィクトリア)/『美と宗教の発見』(梅原猛、2002年)
2020年5月2日
目次
はじめに:①戦争と弾圧の時代/②日本文学報国会
Ⅰ 犀星の戦争詩:動機/①随筆を対象化/②作家的原点/③プロレタリア文学への親和/④プロレタリア文学に別離/⑤政府高官との接触と躊躇/⑥追いつめられる犀星/⑦政府とメディアと作家/⑧戦後、戦争詩を削除
Ⅱ 石川県ゆかりの表現者:①泉鏡花/②徳田秋声/③鶴彬/④中野重治/⑤杉森久英/⑥長澤美津、永瀬清子、水芦光子/⑦深田久弥/⑧島田清次郎/⑨井上靖/⑩堀田善衛/⑪森山啓/⑫加能作次郎/⑬西田幾多郎、暁烏敏、鈴木大拙
Ⅲ 「戦争詩」を戦争遺産として
Ⅱ 石川県ゆかりの表現者(続き)
(9)井上靖
井上靖は1907年に生まれ、満州事変(24歳)、日中開戦(30歳)、日米開戦(40歳)、敗戦(44歳)を体験し、1991年83歳で亡くなった。井上靖は3回徴兵され、1936年の3回目の徴兵で中国に動員されたが、病気に罹り4カ月ほどで帰還した。この時期に「中国行軍日記」をのこしたが、公表せず、2009年に『新潮』誌上ではじめて公開された。
井上靖は「中国行軍日記」のなかで、「河上ニハ屍(しかばね)山ノ様ナリト ソノ水デ炊事シタ 相変ラズ人馬ノ屍臭紛々タリ」、「アヽフミ(ふみ)ヨ! 伊豆ノ両親ヨ 幾世(長女)ヨ!」、「神様! 一日モ早ク帰シテ下サイ」、「相変ラズ車輪ヲミツメ湯ケ島ノコトヲ考ヘテ歩ク……羊カンデモ汁粉デモ甘イモノガタベタイ」、「軍隊といふところはたゞ辛いだけ」など、行軍の過酷さ、家族や故郷への思いが綴られている。
井上の戦争詩
日中文化交流協会理事の佐藤純子さんは、何志勇さん(大連外国語大学)との対談(2012年「国際日本文化研究センター紀要」第7号)のなかで、井上靖について、「『行軍日記』には、戦争の悲惨さというものを書いています。…戦意を鼓吹していない」と述べているが、戦時期に公表されなかったので、このような評価は妥当ではないだろう。
戦争真っただ中の『辻詩集』(1943年)に掲載された井上靖の戦争詩「この春を讃ふ」(花ひとつない 狭いわが家の庭で/うららかに照る春の陽をあび/妻はふたりの幼き子らに語る。/遠いみんなみの海をおほふ/鋼鉄の いくさ船つくるために/幼ければ幼いままに/けふよりは 一粒の米を節し/一枚の紙を惜しめ と。…略…)については話題にしていない。
佐藤さんは中国人研究者何志勇さんにたいして、井上靖が軍事貯金を推奨する詩を書いていたことを指摘せず、「井上靖は昭和が終わる前に、戦争や昭和に触れた詩をたくさん書きました」などと話し、井上靖の戦争責任を隠しているようだ。
井上の天皇観
さらに言えば、敗戦翌日の「玉音ラジオに拝して」という井上靖の記事(1945年8月16日『毎日新聞』)では、「玉音は幾度も身内に聞え身内に消えた。幾度も幾度も――勿体なかった。申訳なかった。事茲(ここ)に到らしめた罪は悉くわれとわが身にあるはずであった。限りない今日までの日の反省は五体を引裂き地にひれ伏したい思いでいっぱいにした。いまや声なくむせび泣いている周囲の総ての人々も同じ思いであったろう。日本歴史未曾有のきびしい一点にわれわれはまぎれもなく二本の足で立ってはいたが、それすらも押し包む皇恩の偉大さ! すべての思念はただ勿体なさに一途に融け込んでゆくのみであった。」と書き、戦争に負けて申し訳ないと、天皇に謝罪してさえいるのである。
井上靖には、厭戦感情があったとしても、非戦でも、反戦でもなかった。「ご時世」に迎合して、戦争詩も詠んでいる。戦後、日中友好に尽力し、1980年代になって、戦争について書いたとしても、青年時代の戦争への係わりを対象化しなければ、自己欺瞞ではないだろうか。それ故に、佐藤純子さんも井上靖と戦争について、明確な評価ができないでいるのだ。やはり、戦争については、他者による批判ではなく、本人による自己批判が必要なのではないか。
【参考資料】井上靖の著作:「中国行軍日記」(1936年)、「玉音ラジオに拝して」(1945年8月16日『毎日新聞』)/『辻詩集』(1943年)/佐藤純子×何志勇(2012年「国際日本文化研究センター紀要」第7号)
(10)堀田善衛
堀田善衛は1918年富山県に生まれ、1931年金沢二中に進学し、1936年慶応大学に入学した。満州事変(13歳)、日中開戦(19歳)、日米開戦(23歳)、敗戦(27歳)を体験して、1998年80歳で亡くなった。
丁世理(日本大学)は堀田善衛の自伝的長編小説『若き日の詩人たちの肖像』(1968年)を分析している。その論文「堀田善衛の戦時体験―政治への漸近、運動の痕跡」によれば、堀田は早稲田大学学生を中心とした学生演劇団体「青年劇場」に関与し、特高にマークされていた(1940年2月「特高月報」)という。どの時点だか特定できないが、一度逮捕されているようだ。
また、堀田は従兄の野口務(1930年逮捕)の影響を受けており、小説中の主人公(堀田)は、山田喜太郎(和田喜太郎=1943年に横浜事件で逮捕)から託された手紙を大岡山に住む某共産党幹部(伊藤律)に送り届けている。
1942年ごろ
堀田は『若き日の詩人たちの肖像』で、室生犀星の詩「シンガポール陥落す」について、一人が「ひでぇものを書きやがったな。怒濤は天に逆巻きたぁなんだね」と不同意を表明し、別の人が「こんなもんのなかでは、おとなしくて品もあるし、いい方なんじゃないの」と、犀星を擁護すれば、すかさず「だけど、歴史にもかゞやけたぁ、これもまたなんだね」とやりかえし、当時の青年たちの反応を書いている。
作中で、堀田は1942年当時を振り返って、「こういうふうな詩をめぐる論議には、何かしら辛いものがある、日本国家への義理だてということもあってみれば、何かが咽喉か頭かにひっかかって徹底したことが、あるいは本当のことが言いにくいという気味がある、と感じていた」と、独白している。
戦後
戦後の堀田善衛は『時間』(1955年)で、「殺、椋、姦、火、飢荒、凍寒、瘡痍。妻の莫愁も、その腹にねむっていた、九カ月のこどもも、五歳の英武も、蘇州から逃れてきた従妹の楊嬢も、もはやだれもいなくなった」(未読)と、1937年の南京を克明に描いている。1960年代後半には、堀田は「ベトナムに平和を!市民連合」(ベ平連)に参加し、脱走米兵の支援活動にも取り組んでいた。
【参考資料】堀田善衛の著作:『若き日の詩人たちの肖像』(1968年)、『時間』(1955年)/丁世理(日本大学)の論文「堀田善衛の戦時体験―政治への漸近、運動の痕跡」
(11)森山啓
森山啓は1904年に新潟県で生まれ、1920年第四高等学校に進学し、1925年東京帝国大学に入学し、プロレタリア文学に傾倒し、1928年に大学を中退した。満州事変(27歳)、日中開戦(33歳)、日米開戦(37歳)、敗戦(41歳)を体験し、1941年から78年まで小松市で暮らし、1991年に87歳で亡くなった。
1930年代前半
『潮流』(1935年)には、1921年から35年までの森山の詩がおさめられている。1929年の「南葛の労働者」(荒川は南葛の無産者の/苦悩の夜を流れる静脈/荒川は南葛労働者の/奮起の朝に波立つ動脈/(…略…)/怒れる民衆の血脈の如く鼓(う)て荒川よ!/かつて民衆の朝をうたひ/やがて白熱のま昼、□□□□□(戦闘の大火)をうたはうとする/波よ 流れよ/春の血管のやうに、太陽を浴び、平野に脈打つもの□)が当時の階級闘争の荒々しさを伝えている。
1930年の「生き埋め」(掘り出された父親のなきがらを抱き/いとしい娘よ/お前のむせび泣きは/泌(し)み入るやうだ、犀河村の森にも川にも/またおいら土工の荒くれた胸にも。/…略…)と、「セメントの底」(…略…/夜は更け、夜は明けた/そして見よ/廿六時問の彼女の苦しみに対し/今、顔面手足が焼けただれたをつとの死骸が渡される/今、声もなくしゃくり泣く彼女の絶望と、夫の生命の代償として、金一封が約束される/一昨年は古ボイラーを破裂せ、今年はタンクを破裂させたNセメント会社重役らの、数日の遊興費にも足らぬ/金四百参拾円也が!)が、地元石川県での労働災害事故による犠牲者・家族の悔しさと悲しみを伝えている。
「生き埋め」(『戦旗』1930年2月)は1929年11月に犀川上流の上水道工事現場で起きた朝鮮人労働者圧死事件、「セメントの底」は同年10月の七尾セメント会社のタンク破裂労災事故を扱っている(『昭和前期の石川県における労働運動』、上田正行著『中心から周縁へ』)。
1931年の「戦士たちに(三月十八日に)」は1871年パリコンミューン60周年を讃える詩である。
詩は「…略…/おお□□□□□□の戦士らよ! お前たち/もうかえることのない先導者たちよ!/あのパリー市庁の□□の下で、あの□□□□□□万歳の歓呼の中で/春の風――「マルセエーズ」と「出発の歌」の吹奏の前で/あまりの感動に、頭を地面へ押しつけたお前らの老人達よ!/(おお彼らも戦死者を地下から呼びたかつたのだ!)/何と言ふ長い困難を/何と云ふ短い勝利を――お前たちみんなは持ったことか/不運な勝利者達、□□□□嵐の下に、/その春の新たな花が、みんな散るのを見ねばならなかつたお前たちよ!/どれほど お前たちが其の自由を、欲したことか/もう死地に落ちたことを感じ、□□を投げて救ひを乞ふ代りに、/あの□□□□□を築いたお前たち/敷石を掘る男たちの/敷石を運ぶ女たちの/泣かんばかりに緊張して手伝ふ子供たちの/おおその一人残らずの必死な息遣いを以て/…略…」と、パリコンミューンで倒れた同志たちを讃え、悲しみ、復活を期し、自らも、満州事変の1931年をたたかいぬく決意を詠っている。
検閲で、ずたずたに切り裂かれたこの詩について、槇村浩は「獄中のコンミューンの戦士の詩を憶って」( わたしは獄中で/若い憂愁が瞼を襲うとき/いつもあなた(森山啓)のコンミューンの詩(「戦士たちに」)を想い出した)と、「森山啓に」(階級的な仕事の中で/個人的な享楽とものを書くことより牢獄を選ばねばならぬときは/ふしぎと思い出したように、いつでもこの詩(「戦士たちに」)が愛誦されたときだった)で、森山を高く評価している。【1932年4月逮捕~1935年非転向で出獄後の作品か?】
パリコンミューンから98年目の1969年3月30日、パリの女性がベトナム戦争に抗議して自殺した。ベトナム反戦・大学闘争をたたかう私たちは、歩道の敷石を剥がし、車道に積み上げ、機動隊が姿を見せれば、それを砕いては投げ、一息ついたときに、バリケードのなかで、「フランシーヌの場合は」(新谷のり子)を歌った。森山や槇村と同じ気持ちでパリ労働者市民との連帯と追悼を歌った。
1930年代後半~
1937年には、戸坂潤(「文芸評論の方法について」)から、「(森山啓は)文芸学上の方法とシステムとに対して、眼に見えてタガがゆるんで来た。かくて今日彼の独自な有用性は可なり低下したようだ」と批判されている。
1943年、『日本文学報国会会員名簿』の小説部会、詩部会には、森山啓の名前は見あたらない。
戦後、平野謙は「(森山啓は)終始一貫プロレタリア文学擁護の論陣(を張り)…社会主義リアリズム論の日本的消化のために孤軍奮闘した人」(「文学・昭和十年前後」)であったと評し、桑尾光太郎は「『文学界』に参加(1935年)したのちの森山は、現実への無関心から体制無批判ひいては体制順応という、なし崩しの転向のコースを歩んでいった」(「森山啓の社会主義リアリズム」)と批判的に書いているが、実際のところはどうなのだろうか。
【参考資料】「生き埋め」(『戦旗』1930年2月)、「戦士たちに(三月十八日に)」(『潮流』1935年)/「文芸評論の方法について」(戸坂潤1937年)/『昭和前期の石川県における労働運動』(1975年)/『中心から周縁へ』(上田正行2008年)/「文学・昭和十年前後」(『平野謙全集』第4巻1975年)/論文「森山啓の社会主義リアリズム」(学習院大学・桑尾光太郎)/
(12)加能作次郎
加能作次郎は1885年に羽咋・西海村に生まれ、日清戦争(9歳)、日露戦争(19歳)、1911年大学卒業(26歳)、欧州戦争(29歳)、満州事変(46歳)、盧溝橋事件(52歳)を体験し、1941年日米開戦の年(56歳)に亡くなった。
大学卒業後の1913年から『文章世界』(1906~20年)の編集に携わり、翻訳や文芸時評を発表し、1918年に私小説『世の中へ』で認められ、作家として活躍する。
加能は1927年の『早稲田神楽坂』では、「ゴルキイの『夜の宿』(『どん底』、帝制末期のモスクワの木賃宿に住むどん底の人々の生活を描く)などを実際に稽古をしたりしたものだった」と書き、学生時代は左翼的スタンスに立っていたようだ。加能の最後の作品『乳の匂ひ』(1940年)では、日清・日露の戦間期の少年時代を追憶しながら、女性の貧困と不運について同情的に書いているが、体制への迎合も批判もない。
【参考資料】加能作次郎の著作:『世の中へ』(1918年)、『早稲田神楽坂』(1927年)、『乳の匂ひ』(1940年)
(13)西田幾多郎、暁烏敏、鈴木大拙
A 西田幾多郎
西田幾多郎は1870年にかほく市に生まれ、第四高等中学入学・中退(20歳)、日清戦争(24歳)、日露戦争(34歳)、満州事変(61歳)、日中戦争開戦(67歳)、日米開戦(71歳)を体験し、敗戦2カ月前に75歳で亡くなった。
明治期
上原麻有子は日清戦争前の1890年(20歳)の西田について、「出身地の石川県にある第四高等中学に在籍していました。しかし、当時の新しい学制により設立されたこの学校の教育に不満を抱き、同志と共に中途退学してしまいます」(「近代日本の哲学者、西田幾多郎にとって『自己』とは何であるか」)と書いている。ここで言う「新しい学制」とは1886年の中学校令であり、「社会上流ノ仲間ニ入ルベキモノ」、「社会多数ノ思想ヲ左右スルニ足ルベキモノ」を養成する学校(7校)として設立され(文科省HP)、西田は抑圧的な管理教育に反撥したようだ。
日露戦争後
外に向かっては日清戦争(24歳)、日露戦争(34歳)、国内的には自由と権利は制限され、貧富の格差の時代にあって、西田幾多郎はどのように考えていたのか。
1904年に弟が旅順で戦死し、西田は「私は今弟の墓標の前に立って、ただ涙を流すのみである」と、不条理な死を慨嘆する手紙を友人に送っている(ETV「死を見つめる心―西田幾多郎と鈴木大拙」浅見洋×白鳥元雄)。1905年1月5日の日記(35歳)に、西田は「正午公園(兼六園)にて旅順陥落祝賀会あり、万歳の声聞こゆ。今夜は祝賀の提灯行列をなすというが、幾多の犠牲と、前途の遼遠なるを思わず、かかる馬鹿騒ぎなすとは、人心は浮薄なる者なり」(『西田幾多郎哲学論集3』上田閑照の解説)と、冷静に受けとめている。にもかかわらず、西田は1905年の『倫理学草案』では、「家族は最完全なる社会である」「国家というのは一層大なる家族的結合」と、天皇を父とする疑似家族国家観を展開し、天皇によって宣戦布告された日露戦争での弟の戦死を容認しているのである。
1911年の『善の研究』の最終ページで、西田は「宗教は宇宙全体の上に於て絶対無限の仏陀其者に接するのである。…而してこの絶対無限の仏若しくは神を知るのは只之を愛するに因りて能くするのである、之を愛するが即ち之を知る(の)である。…神は分析や推論に因りて知り得べき者でない。実在の本質が人格的の者であるとすれば、神は最人格的なる者である。我々が神を知るのは唯愛又は信の直覚に由りて知り得るのである。故に我は神を知らず我唯神を愛す又は信の直覚に由りて知り得るのである」と締めくくっている。まさに、この「仏陀」や「神」はやがて「天皇」となり、有無を言わさぬ「滅私奉公」の世界へと導くのである。
1918年、西田は山本良吉宛の書翰で「萬世一系の皇室は大なる慈悲。没我、共同の象徴であると思ふ。此の深い精神をとかねばならぬと思ふ」と書き送っているが、『善の研究』からたどり着く当然の帰結であろう。
太平洋戦争期
1935年「教育勅語ノ奉体、国体観念、日本精神ノ体現」をめざした教学刷新評議会(会長:文部大臣)が設立され、西田幾多郎、和辻哲郎、田邊元といった京都学派系の哲学者が参加している。
日米開戦前年1940年の講演録『日本文化の問題』で、西田は「従来、東亜民族は、ヨーロッパ民族の帝国主義の為に、圧迫せられていた、植民地視されていた、各自の世界史的使命を奪われていた。…今日の東亜戦争は後世の世界史に於て一つの方向を決定するものであろう」と主張し、1937年から始まった中国侵略戦争を「植民地解放戦争」であるかのように欺瞞・讃美し、文化勲章を受けている。
大宅壮一の『西田幾多郎の敗北』(1954年)には、西田が右翼から狙われていたかのように書かれ、小林敏明の『夏目漱石と西田幾多郎』(2017年)には、戦中の西田は自由主義者であり、軍部から利用された「被害者」であったかのように描かれている。
しかし、文芸誌『文学界』が主宰した「近代の超克」の座談会(1942年)に京都学派が参加しており、西田自身も「国策研究会」に請われ、「世界新秩序の原理」を発表している。
1943年の『世界新秩序の原理』のなかで、西田は「皇室は過去未来を包む絶対現在として、皇室が我々の世界の始であり終である。皇室を中心として一つの歴史的世界を形成し来った所に、万世一系の我国体の精華があるのである。我国の皇室は単に一つの民族的国家の中心と云うだけでない。我国の皇道には、八紘為宇の世界形成の原理が含まれて居るのである」、「神皇正統記が大日本は神国なり、天祖はじめて基をひらき、日神ながく統を伝へ給ふ。我国のみ此事あり。異朝には其たぐひなしという我国の国体には、絶対の歴史的世界性が含まれて居るのである。我皇室が万世一系として永遠の過去から永遠の未来へと云うことは、単に直線的と云うことではなく、永遠の今として、何処までも我々の始であり終であると云うことでなければならない」、「日本精神の真髄は、…八紘為宇の世界的世界形成の原理は内に於て君臣一体、万民翼賛の原理である」、「英米が之に服従すべきであるのみならず、枢軸国も之に倣うに至るであろう」と書いているように、西田は天皇制と侵略戦争の理論的支柱となっている。
西田の生前最後の論文「場所的論理と宗教的世界観」(1945年)では、「今日の時代精神は、万軍の主の宗教(注:ユダヤ教)よりも、絶對悲願の宗教を求めるものがあるのではなからうか。仏教者の反省を求めたいと思ふのである」のあとに、脈絡もなく「世界戦争は、世界戦争を否定する為の、永遠の平和の為の、世界戦争でなければならない」と書いている。
この言葉は、第一次世界大戦時に、「すべての戦争を終わらせるための戦争」(The war to end all wars)として、戦争推進キャンペーンとして使われており、西田は、すでに破産したこの言葉を使って、敗戦濃厚な侵略戦争を全面肯定する論陣を張り、他方では、1945年5月11日の鈴木大拙宛手紙に、「民族の自信を唯武力と結合する民族は武力と共に亡びる」と書き送っている。西田は6月に亡くなった。
しかしこの論理は破綻している。ここでいう「世界戦争」は日本による侵略戦争のことであり、「世界戦争」はいずれかが敗北して、一旦の決着がつくとしても、戦争をもたらす根本的な資本主義の社会システムはそのままであり、資本の危機はふたたびみたび戦争を引き寄せることは自明である。寺内さんは、戦後に編集された『西田幾多郎全集』からこの論文が削除されたと指摘しているが、むべなるかな。
【参考資料】西田幾多郎の著作:『場所的論理と宗教的世界観』(1945年)、『世界新秩序の原理』(1943年、青空文庫)、講演録『日本文化の問題』(1940年)、『善の研究』(1911年、国会図書館デジタル)、『倫理学草案』(1905年)/寺内徹乗「西田幾多郎の知られざる闇」(『はばたき』27号2017年)、/寺内徹乗講演録「西田幾多郎とアジア太平洋戦争」(2020年2月)/小林敏明『夏目漱石と西田幾多郎』(2017年)/上原麻有子「近代日本の哲学者、西田幾多郎にとって『自己』とは何であるか」(2013年、明星大学元教員)/『西田幾多郎哲学論集3、』(上田閑照の解説)/「死を見つめる心―西田幾多郎と鈴木大拙」(浅見洋×白鳥元雄、2005年ETV)/『西田幾多郎の敗北』(大宅壮一、1954年)
B 暁烏敏
暁烏敏は1877年白山市の明達寺に生まれ、日清戦争(17歳)、日露戦争(27歳)、満州事変(54歳)、盧溝橋事件(60歳)、日米開戦(64歳)、敗戦(68歳)を体験し、1954年77歳で亡くなった。
青年期
もともと1910年代の暁烏は真宗が近代的宗教になるためには、封建的倫理を捨てねばならないと呼びかける高光大船や藤原鉄乗らに合流し、ロシア革命を讃え、米騒動や労働運動を支持し、朝鮮植民地支配に異を唱えていたのである。しかし、その後の暁烏は国家主義に転じていく。
戦時期
1931年、「長江貿易は日本の栄養線だ」と言って満州事変が起こされ、翌1932年の上海事変では6000人もの中国民間人を殺戮し、120万人もの避難民をだしている。しかし、当時の暁烏敏は『非戦争論者である私は、戦争が始まったら何をするか』(1931年)と問い、「ガンジーさんは、あの世界大戦の折りには、独立運動を中止して、英国のために戦費を集めたり、自ら看護兵となって、欧州の戦場に従軍せられたりしました。ガンジーさんのこの広い心がトルストイやロマン・ローランの心よりも尊いように思われます」と、ガンジーにならって、始まったばかりの中国侵略への支持と協力を宣明している。
暁烏敏全集別巻を見ると、1942年『大東亜新秩序建設の根本』、『大東亜を築く心』、『臣民道を行く』、1943年『大御心を仰ぎまつる』、1945年『教育勅語謹承』、『勝利への一歩』の論述がある。しかし、全集に収録されているものは『大東亜新秩序建設の根本』、『大御心を仰ぎまつる』だけであり、マスコミの大本営発表を批判し、「経済統制がうまくいっていない」と愚痴をこぼし、「愛国行進曲や日の丸行進曲に落ち着きがない」と揶揄しており、これを以て暁烏敏は戦争に批判的であったかのような編集になっている。
闇に葬られた著書
しかし暁烏敏は1928年、31年、36年、37年、38年、39年、40年、41年に朝鮮・中国にわたり布教活動をおこない、1937年に発行され、著述目録からも除外されている『皇道・神道・仏道・臣道』(北安田パンフレット第47)を読めば、暁烏がいかに戦争に全面的に協力していたかがわかる。このパンフレットは1936年に暁烏が朝鮮・ソウルの南山本願寺でおこなった説教の講演録(文庫判で、200頁)で、序文には「聖徳太子のお筆になった『十七条憲法』にたよって大日本臣民道を語った」、「近来神道といい、皇道といい、仏道といって自らを高くあげようとし、あらぬ邪道に陥っている人の多いのは臣民道を会得していないためだと思います。私共は、神道を承り、皇道を承り、仏道を承って、私共自身の臣民道を教えて頂かねばならぬと思います」と述べている。
1936年といえば、蘆溝橋事件の直前であり、日本が本格的に中国侵略に突入して5年目の年である。このような情勢のなかで、暁烏が朝鮮や中国に渡って、天皇制を謳歌し、日本軍の宣撫工作に全面的に協力している。
では、内容に立ち入っていこう。「我々は大日本の臣民であります。天皇陛下のやつこらと仰せられる臣民であります」と天皇に最敬礼し、「今日の日本臣民は子供をお国の役に立つように、天皇陛下の御用をつとめるように念願して育てにゃならんのであります。…日本の臣民は天皇陛下の家の子供として、天皇陛下の御用にたち、そしてお国のお役にたてさしていただくということは、役人ばかりでない、百姓でも、町人でも、すべてその心得がなくてはならんのであります」と天皇への忠誠を要求している。
「田圃を作るものは自分が悪いところを食べて、天皇様によいものを差上げる。それが神嘗祭を持ち、新嘗祭を持っておる日本の本当の臣民であります」、「我々は…お仕事をするのである。ただ労働するのではない。仕事である。日本のあの仕事という言葉は仕(つか)へ、事(つか)へるという字である。誰に仕へ、誰に事へるのか。天皇陛下にお事へするのであります。…身体に力のあるものは身体を出し、心の働きのあるものは心を捧げ、そして天皇陛下のしろしめすところのお国の御用立ちをさしてもらうのであります。それが神ながらの道であります。だからそこに臣の道を考えてゆくところに、神の道が成就し、仏の道が成就し、天皇の御心が成就して下さるのであります」、「信ずる心も、念ずる心もすべて他力より起こさしめたまうなり、何から何まで神様仏様や天皇様のお与えものによって今日この生活をさしてもらっておるのであります。…私共は、『君が代は千代に八千代にさざれ石のいわほとなりて苔のむすまで』と心から歌わしていただける日本臣民であります」と、仏陀を天皇の奴僕にしてしまったのである。
戦後の暁烏敏
このように暁烏敏は、国内はもとより植民地にまででかけて、天皇に身も心も捧げていたのであるが、それでは戦後をどのように迎えたのであろうか。暁烏敏全集の<思想篇9>によれば、『新発足の地盤』『仏教思想とデモクラシー』(1946年)などが敗戦直後に発表された。
『新発足の地盤』では、「この詔書が発せられて、国民は驚き且つ悲しみ、殆ど茫然としていたが、私は念仏と共に心の平静を得て、これからだぞという希望を味あうことが出来た」と語り、自らの責任の重大さについてはほおかむりしている。『仏教思想とデモクラシー』では、「人が人(天皇)のために命を捧げるということは要らんのであります。…キリストは『汝の敵を愛せよ』というておりますが、仏教にはその『敵』さえないと説かれてあります。…皆さんの国家建設に対する熱意が尊く思われ、皆さんの精神にお宿りになっている陛下の大御心を拝して、ここで皆さんを合掌する思いであります」と、天皇を形ばかりに「批判」しながら、天皇に跪いている、醜い仏教者の姿がある。
【参考資料】暁烏敏の著作:『非戦争論者である私は、戦争が始まったら何をするか』(1931年)、『皇道・神道・仏道・臣道』(1937年、北安田パンフレット第47)、『新発足の地盤』(1946年)、『仏教思想とデモクラシー』(1946年)
C 鈴木大拙
鈴木大拙は1870年に金沢市で生まれ、第四高等中学入学・中退、美川で小学校教員(20歳ころ)、日清戦争(24歳)、在米時代(27~38歳)、満州事変(61歳)、日中戦争開戦(67歳)、日米開戦(71歳)、敗戦(75歳)を体験し、1966年96歳で亡くなった。
現在(5月3日)、コロナウイルス対策という理由で、石川県内のすべての図書館が閉鎖され、知る権利(憲法13条)が抑圧されており、やむを得ずインターネット上の確かな情報を摘記することによって、鈴木大拙と戦争について確認する。
初期の大拙
守屋友江は大拙の「米国片田舎だより」の読後感想として、「(日露戦争を挟んだ在米時代(1897~1908年)の)大拙は天皇崇拝や教育勅語を批判し、社会主義に共感を示している。しかし、日露戦争に到ると、熱烈な愛国主義的感情を吐露するようになる」、「15年戦争下では、…島国的な民族主義に閉ざされることを批判し、日本の仏教を世界的な視野で見ようとしながら、それ故にかえって『世界思想戦』として、戦争を肯定してしまう」(『禅に生きる 鈴木大拙コレクション』)と書いている。
戦時期の大拙
市川白弦は『日本ファシズム下の宗教』で、「若き日の鈴木大拙は、『宗教とは、まず国家の存在を維持せんことを計り』という言葉を残している。さらに日本の勢力拡大を妨げる者(民族)は『邪道外道である』と言い、その相手、彼らの国を『暴国』と呼んだ。そして、『宗教の名に由りて、…正義の為に不正を代表せる国民を懲(こら)さんとするのみ』とまで書いた」と大拙を批判している。
元永常はブライアンの『禅と戦争』を読み、「軍国主義時代に鈴木は軍人たちに,禅の精神こそ武士道の精神であると強調し、戦争の現場にいる軍人たちに戦争のイデオロギーを付与した」(『鈴木大拙における禅仏教の論理と民族主義』)と述べている。
戦後の大拙
『霊性的日本の建設』(1946年)のなかで、大拙は「今だから脱白に公言できるが、自分等は今度の戦争は始めから負けるものと信じていた、また負けてくれれば日本のために好かろうとさへ思った」、「これは戦争終結前のものであったので、所述は自ずから限られたところがある」、「それを余りに直接にいふと当局の忌諱にふれて、出版は不可能になる」と記述しており、梅原猛は「今度の戦争が始めから負けると判っていたなら、思想家はやはりそれを公言すべきではないか。あやまった必勝の信念により日本は戦争に突入し、このあやまった必勝の信念により、絶望的な戦いを日本は長い間続けた。一日戦うことによって何万人の人の血がいたずらに流れた。思想家は、こういう状態を前にしてあえて沈黙すべきなのだろうか。それより彼はあやまった信念に固まった人間たちの蒙をといて一日も早く戦争を終わらせることに努力すべきではないだろうか」と批判している(『美と宗教の発見』2002年)。
『北國新聞』(2014年10月9日)に、鈴木大拙が「東西間の生きる文化の懸け橋として国際平和に貢献した」という理由で、1963年のノーベル平和賞の候補に推薦されたという記事がある。戦時中に、自国の戦争に反対もしないで、「平和賞」にノミネートされて、晩年の大拙はどのような心境だったのだろうか。佐藤栄作でさえもらっている賞だから、その程度の権威である。
【参考資料】『禅に生きる 鈴木大拙コレクション』(鈴木大拙著/守屋友江編訳)/『日本ファシズム下の宗教』(市川白弦、1975年)/『鈴木大拙における禅仏教の論理と民族主義』(元永常、2009年「印度學佛教學研究」第57巻第2号)/『禅と戦争―禅仏教は戦争に協力したか』(2001年、ブラィアン・アンドルー・ヴィクトリア)/『美と宗教の発見』(梅原猛、2002年)