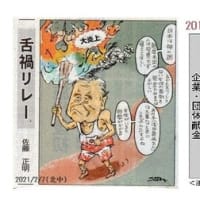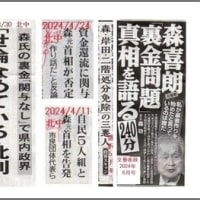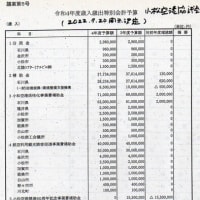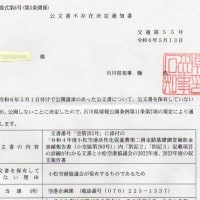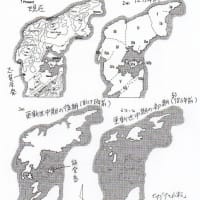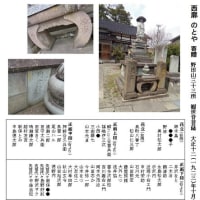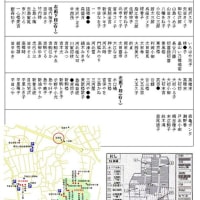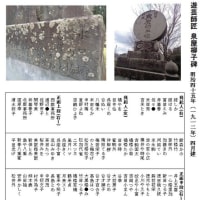20200424 図書館の全面閉鎖の再検討を! 表現の自由が危ない!
今朝の『北陸中日新聞』に、元金沢市長が「新型コロナウイルスの感染が拡大している事態を見ていて、今ほど世の中が日々、学習している時はない。…国民も、すべての人が勉強している」と、書いているが、実は石川県内のほとんどの図書館が閉鎖され、学習と勉強が阻害されていることを知らないのだろうか。
「図書館の自由に関する宣言」があり、図書館とその労働者はこの「宣言」に基づいて仕事をしている。1カ月間の閉館とは、「宣言」の「第2 図書館は資料提供の自由を有する」には、制限事項として、「(1)人権またはプライバシーを侵害するもの、(2)わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの、(3)寄贈または寄託資料のうち、寄贈者または寄託者が公開を否とする非公刊資料」とされており、完全に違反する行政行為である。
××××図書館との間で、何回かやり取りしているが、図書館労働者と利用者の健康を守るために、画一的、全面的な図書館閉鎖は、この「宣言」を守るために、どうしたらよいのかについて、考え抜かれた末の決定だとは到底思われない。
以下、××××図書館とのやり取りと、「宣言」を添附する。
<4月16日>××××図書館様
今日、貴館を訪問しようと思い、準備していましたが、HPで休館と知らされました。
図書館は知の宝庫であり、図書館は知的再生産の重要なツールです。
知的再生産を「不要不急」と考えているなら、それは、「図書館の死亡宣告」でしょう。インターネットで貴館の資料を検索し、予約し、受け取る。このシステムだけは残すべきではないですか。受け取る時のやり方を工夫すれば、十分にウイルス対策はできるはずです。早急な再開に期待し、再検討をお願いします。
<4月16日>××××図書館より
いつも××××図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
当館の休館につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、県の方針で県有施設の臨時休館を受けての休館となっております。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
<4月23日>××××図書館様
資料を何冊か予約してあるのですが、5月7日まで、受け取れないということですが、これでは、論考が進みません。予約した資料を、裏口で受け取ることはできないものでしょうか。裏口で、カードを渡して、私が外で待っていて、貸し出し作業が終わったら、裏口で資料を受け取るならば、ウイルス対策としては十分なのではないでしょうか。
レストランなどでは、ドライブスルーで解決しているわけですから、書籍だって、それでよいと思いますが、よろしくお願いします。
<4月23日>××××図書館より
いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。たいへんご不便をおかけしており、申し訳ありません。前回のメールでも回答させていただきましたが、先にお伝えしましたように、5月6日まで完全休館となっておりますので、申し訳ありませんが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
<4月24日>××××図書館様
約1か月間の休館は「図書館の自由に関する宣言」に反するのではないでしょうか。図書館は本当にこの「宣言」を守るために、創意工夫を凝らしているのでしょうか。
「宣言」には、「提供の自由は、次の場合にかぎって制限されることがある。これらの制限は、極力限定して適用し、時期を経て再検討されるべきものである。(1)人権またはプライバシーを侵害するもの、(2)わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの、(3)寄贈または寄託資料のうち、寄贈者または寄託者が公開を否とする非公刊資料」と書かれていますが、どこに該当するのでしょうか。私はいずれにも該当しないと思っています。
三密にならないようにするには、例えば、予約者を分散するような方法もあります。今日は20人(午前10人、午後10人)とか、…。前回提案したドライブスルー方式もあります。「宣言」を守り、図書館労働者と利用者の健康を守るために、創意工夫を凝らしてください。
再検討をよろしくお願いします。
<4月24日>××××図書館より
いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。繰り返しになりますが、県の方針により、5月6日まで完全休館となっておりますので、何卒ご理解の程、よろしくお願いいたします。
なお、7日以降の当館の利用につきましては、今後検討させていただきます。ご不便をおかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
「図書館の自由に関する宣言」
1954 採 択
1979 改 訂
図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。
日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である
知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。
知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。
すべての国民は、いつでもその必要とする資料を入手し利用する権利を有する。この権利を社会的に保障することは、すなわち知る自由を保障することである。図書館は、まさにこのことに責任を負う機関である。
図書館は、権力の介入または社会的圧力に左右されることなく、自らの責任にもとづき、図書館間の相互協力をふくむ図書館の総力をあげて、収集した資料と整備された施設を国民の利用に供するものである。
わが国においては、図書館が国民の知る自由を保障するのではなく、国民に対する「思想善導」の機関として、国民の知る自由を妨げる役割さえ果たした歴史的事実があることを忘れてはならない。図書館は、この反省の上に、国民の知る自由を守り、ひろげていく責任を果たすことが必要である。
すべての国民は、図書館利用に公平な権利をもっており、人種、信条、性別、年齢やそのおかれている条件等によっていかなる差別もあってはならない。
外国人も、その権利は保障される。
ここに掲げる「図書館の自由」に関する原則は、国民の知る自由を保障するためであって、すべての図書館に基本的に妥当するものである。
この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。
第1 図書館は資料収集の自由を有する
図書館は、国民の知る自由を保障する機関として、国民のあらゆる資料要求にこたえなければならない。
図書館は、自らの責任において作成した収集方針にもとづき資料の選択および収集を行う。その際、
(1)多様な、対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集する。
(2)著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはしない。
(3)図書館員の個人的な関心や好みによって選択をしない。
(4)個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりはしない。
(5)寄贈資料の受入にあたっても同様である。図書館の収集した資料がどのような思想や主 張をもっていようとも、それを図書館および図書館員が支持することを意味するものではない。
図書館は、成文化された収集方針を公開して、広く社会からの批判と協力を得るようにつとめる。
第2 図書館は資料提供の自由を有する
国民の知る自由を保障するため、すべての図書館資料は、原則として国民の自由な利用に供されるべきである。
図書館は、正当な理由がないかぎり、ある種の資料を特別扱いしたり、資料の内容に手を加えたり、書架から撤去したり、廃棄したりはしない。
提供の自由は、次の場合にかぎって制限されることがある。これらの制限は、極力限定して適用し、時期を経て再検討されるべきものである。
(1) 人権またはプライバシーを侵害するもの
(2) わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの
(3) 寄贈または寄託資料のうち、寄贈者または寄託者が公開を否とする非公刊資料
図書館は、将来にわたる利用に備えるため、資料を保存する責任を負う。図書館の保存する資料は、一時的な社会的要請、個人・組織・団体からの圧力や干渉によって廃棄されることはない。
図書館の集会室等は、国民の自主的な学習や創造を援助するために、身近にいつでも利用できる豊富な資料が組織されている場にあるという特徴を持っている。
図書館は、集会室等の施設を、営利を目的とする場合を除いて、個人、団体を問わず公平な利用に供する。
図書館の企画する集会や行事等が、個人・組織・団体からの圧力や干渉によってゆがめられてはならない。
第3 図書館は利用者の秘密を守る
読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。
図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。
利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。
第4 図書館はすべての検閲に反対する
検閲は、権力が国民の思想・言論の自由を抑圧する手段として常用してきたものであって、国民の知る自由を基盤とする民主主義とは相容れない。
検閲が、図書館における資料収集を事前に制約し、さらに、収集した資料の書架からの撤去、廃棄に及ぶことは、内外の苦渋にみちた歴史と経験により明らかである。
したがって、図書館はすべての検閲に反対する。
検閲と同様の結果をもたらすものとして、個人・組織・団体からの圧力や干渉がある。図書館は、これらの思想・言論の抑圧に対しても反対する。
それらの抑圧は、図書館における自己規制を生みやすい。しかし図書館は、そうした自己規制におちいることなく、国民の知る自由を守る。
図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。
図書館の自由の状況は、一国の民主主義の進展をはかる重要な指標である。図書館の自由が侵されようとするとき、われわれ図書館にかかわるものは、その侵害を排除する行動を起こす。このためには、図書館の民主的な運営と図書館員の連帯の強化を欠かすことができない。
図書館の自由を守る行動は、自由と人権を守る国民のたたかいの一環である。われわれは、図書館の自由を守ることで共通の立場に立つ団体・機関・人びとと提携して、図書館の自由を守りぬく責任をもつ。
図書館の自由に対する国民の支持と協力は、国民が、図書館活動を通じて図書館の自由の尊さを体験している場合にのみ得られる。われわれは、図書館の自由を守る努力を不断に続けるものである。
図書館の自由を守る行動において、これにかかわった図書館員が不利益をうけることがあっては ならない。これを未然に防止し、万一そのような事態が生じた場合にその救済につとめることは、 日本図書館協会の重要な責務である。
(1979.5.30 総会決議)
今朝の『北陸中日新聞』に、元金沢市長が「新型コロナウイルスの感染が拡大している事態を見ていて、今ほど世の中が日々、学習している時はない。…国民も、すべての人が勉強している」と、書いているが、実は石川県内のほとんどの図書館が閉鎖され、学習と勉強が阻害されていることを知らないのだろうか。
「図書館の自由に関する宣言」があり、図書館とその労働者はこの「宣言」に基づいて仕事をしている。1カ月間の閉館とは、「宣言」の「第2 図書館は資料提供の自由を有する」には、制限事項として、「(1)人権またはプライバシーを侵害するもの、(2)わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの、(3)寄贈または寄託資料のうち、寄贈者または寄託者が公開を否とする非公刊資料」とされており、完全に違反する行政行為である。
××××図書館との間で、何回かやり取りしているが、図書館労働者と利用者の健康を守るために、画一的、全面的な図書館閉鎖は、この「宣言」を守るために、どうしたらよいのかについて、考え抜かれた末の決定だとは到底思われない。
以下、××××図書館とのやり取りと、「宣言」を添附する。
<4月16日>××××図書館様
今日、貴館を訪問しようと思い、準備していましたが、HPで休館と知らされました。
図書館は知の宝庫であり、図書館は知的再生産の重要なツールです。
知的再生産を「不要不急」と考えているなら、それは、「図書館の死亡宣告」でしょう。インターネットで貴館の資料を検索し、予約し、受け取る。このシステムだけは残すべきではないですか。受け取る時のやり方を工夫すれば、十分にウイルス対策はできるはずです。早急な再開に期待し、再検討をお願いします。
<4月16日>××××図書館より
いつも××××図書館をご利用いただき、ありがとうございます。
当館の休館につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、県の方針で県有施設の臨時休館を受けての休館となっております。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
<4月23日>××××図書館様
資料を何冊か予約してあるのですが、5月7日まで、受け取れないということですが、これでは、論考が進みません。予約した資料を、裏口で受け取ることはできないものでしょうか。裏口で、カードを渡して、私が外で待っていて、貸し出し作業が終わったら、裏口で資料を受け取るならば、ウイルス対策としては十分なのではないでしょうか。
レストランなどでは、ドライブスルーで解決しているわけですから、書籍だって、それでよいと思いますが、よろしくお願いします。
<4月23日>××××図書館より
いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。たいへんご不便をおかけしており、申し訳ありません。前回のメールでも回答させていただきましたが、先にお伝えしましたように、5月6日まで完全休館となっておりますので、申し訳ありませんが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
<4月24日>××××図書館様
約1か月間の休館は「図書館の自由に関する宣言」に反するのではないでしょうか。図書館は本当にこの「宣言」を守るために、創意工夫を凝らしているのでしょうか。
「宣言」には、「提供の自由は、次の場合にかぎって制限されることがある。これらの制限は、極力限定して適用し、時期を経て再検討されるべきものである。(1)人権またはプライバシーを侵害するもの、(2)わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの、(3)寄贈または寄託資料のうち、寄贈者または寄託者が公開を否とする非公刊資料」と書かれていますが、どこに該当するのでしょうか。私はいずれにも該当しないと思っています。
三密にならないようにするには、例えば、予約者を分散するような方法もあります。今日は20人(午前10人、午後10人)とか、…。前回提案したドライブスルー方式もあります。「宣言」を守り、図書館労働者と利用者の健康を守るために、創意工夫を凝らしてください。
再検討をよろしくお願いします。
<4月24日>××××図書館より
いつも図書館をご利用いただき、ありがとうございます。繰り返しになりますが、県の方針により、5月6日まで完全休館となっておりますので、何卒ご理解の程、よろしくお願いいたします。
なお、7日以降の当館の利用につきましては、今後検討させていただきます。ご不便をおかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
「図書館の自由に関する宣言」
1954 採 択
1979 改 訂
図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。
日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である
知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。
知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。
すべての国民は、いつでもその必要とする資料を入手し利用する権利を有する。この権利を社会的に保障することは、すなわち知る自由を保障することである。図書館は、まさにこのことに責任を負う機関である。
図書館は、権力の介入または社会的圧力に左右されることなく、自らの責任にもとづき、図書館間の相互協力をふくむ図書館の総力をあげて、収集した資料と整備された施設を国民の利用に供するものである。
わが国においては、図書館が国民の知る自由を保障するのではなく、国民に対する「思想善導」の機関として、国民の知る自由を妨げる役割さえ果たした歴史的事実があることを忘れてはならない。図書館は、この反省の上に、国民の知る自由を守り、ひろげていく責任を果たすことが必要である。
すべての国民は、図書館利用に公平な権利をもっており、人種、信条、性別、年齢やそのおかれている条件等によっていかなる差別もあってはならない。
外国人も、その権利は保障される。
ここに掲げる「図書館の自由」に関する原則は、国民の知る自由を保障するためであって、すべての図書館に基本的に妥当するものである。
この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。
第1 図書館は資料収集の自由を有する
図書館は、国民の知る自由を保障する機関として、国民のあらゆる資料要求にこたえなければならない。
図書館は、自らの責任において作成した収集方針にもとづき資料の選択および収集を行う。その際、
(1)多様な、対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集する。
(2)著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはしない。
(3)図書館員の個人的な関心や好みによって選択をしない。
(4)個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりはしない。
(5)寄贈資料の受入にあたっても同様である。図書館の収集した資料がどのような思想や主 張をもっていようとも、それを図書館および図書館員が支持することを意味するものではない。
図書館は、成文化された収集方針を公開して、広く社会からの批判と協力を得るようにつとめる。
第2 図書館は資料提供の自由を有する
国民の知る自由を保障するため、すべての図書館資料は、原則として国民の自由な利用に供されるべきである。
図書館は、正当な理由がないかぎり、ある種の資料を特別扱いしたり、資料の内容に手を加えたり、書架から撤去したり、廃棄したりはしない。
提供の自由は、次の場合にかぎって制限されることがある。これらの制限は、極力限定して適用し、時期を経て再検討されるべきものである。
(1) 人権またはプライバシーを侵害するもの
(2) わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの
(3) 寄贈または寄託資料のうち、寄贈者または寄託者が公開を否とする非公刊資料
図書館は、将来にわたる利用に備えるため、資料を保存する責任を負う。図書館の保存する資料は、一時的な社会的要請、個人・組織・団体からの圧力や干渉によって廃棄されることはない。
図書館の集会室等は、国民の自主的な学習や創造を援助するために、身近にいつでも利用できる豊富な資料が組織されている場にあるという特徴を持っている。
図書館は、集会室等の施設を、営利を目的とする場合を除いて、個人、団体を問わず公平な利用に供する。
図書館の企画する集会や行事等が、個人・組織・団体からの圧力や干渉によってゆがめられてはならない。
第3 図書館は利用者の秘密を守る
読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。
図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。
利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。
第4 図書館はすべての検閲に反対する
検閲は、権力が国民の思想・言論の自由を抑圧する手段として常用してきたものであって、国民の知る自由を基盤とする民主主義とは相容れない。
検閲が、図書館における資料収集を事前に制約し、さらに、収集した資料の書架からの撤去、廃棄に及ぶことは、内外の苦渋にみちた歴史と経験により明らかである。
したがって、図書館はすべての検閲に反対する。
検閲と同様の結果をもたらすものとして、個人・組織・団体からの圧力や干渉がある。図書館は、これらの思想・言論の抑圧に対しても反対する。
それらの抑圧は、図書館における自己規制を生みやすい。しかし図書館は、そうした自己規制におちいることなく、国民の知る自由を守る。
図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。
図書館の自由の状況は、一国の民主主義の進展をはかる重要な指標である。図書館の自由が侵されようとするとき、われわれ図書館にかかわるものは、その侵害を排除する行動を起こす。このためには、図書館の民主的な運営と図書館員の連帯の強化を欠かすことができない。
図書館の自由を守る行動は、自由と人権を守る国民のたたかいの一環である。われわれは、図書館の自由を守ることで共通の立場に立つ団体・機関・人びとと提携して、図書館の自由を守りぬく責任をもつ。
図書館の自由に対する国民の支持と協力は、国民が、図書館活動を通じて図書館の自由の尊さを体験している場合にのみ得られる。われわれは、図書館の自由を守る努力を不断に続けるものである。
図書館の自由を守る行動において、これにかかわった図書館員が不利益をうけることがあっては ならない。これを未然に防止し、万一そのような事態が生じた場合にその救済につとめることは、 日本図書館協会の重要な責務である。
(1979.5.30 総会決議)