
asahi.comに出ていた書評(http://book.asahi.com/ebook/master/2013072500005.html?ref=comtop_fbox_d2)。
4分の1か5分の1程度の投票者で自公政権に信任が得られ、増税され、原発推進され、壊憲されてていいのだろうか? 選挙制度上の欠陥じゃないのか? それにやすやすとノせられて自公議員に投票してしまったツケはあまりに大きい。
================================================================================
【http://book.asahi.com/ebook/master/2013072500005.html?ref=comtop_fbox_d2】
本の達人
バカに民主主義は無理なのか? [著] 長山靖生
[評者]市川真人(文芸批評家・早稲田大学准教授)
[掲載] 2013年07月26日
■理想的ではない社会で最悪ではない選択をするために
7月の参議院選挙が終わって、2012年の暮れから続いた民主党中心から自民党中心への政権交代期も終わった。参議院の半数が改選された2010年の前回選挙からここまでが一続きの流れだったと言ってもよいし、民主党が大きく議席を伸ばして自民党からの政権交代への道筋をつけた2007年の参議院選挙から6年間が終わった、と言ってもよいだろう。「一度やらせてみてください」という2009年衆議院選挙の民主党のキャッチコピーを踏まえれば、有権者たちが民主党に「やらせて」みてからダメだったと判断して自民党に戻すまでの4年間だった、ということになる。
民主党政権のどこがどうダメだったのか――無謀な大言壮語だったのか、野党の立場や有権者からは見えぬ困難や計算違いがどのようにあったのか、実力不足か、まれに見る天災が襲った不運なのか……等々――は、有権者各自が判断する、あるいはすでにしたところだろう(リベラル政権の成立に長らく期待して、いまも期待せずにはいられぬ身から見てすら、報じられる民主党政権の姿は内輪モメだけでもため息が出るほど酷〈ひど〉かったけれど)。だが、個別の判断はさておき、「やらせてみた」4年間が意味あるものになるためには、「やってみた(やらせてみてもらった)」民主党自身と、官僚はじめ彼らと連携して政治にあたった者たちが、(責任を問う/問われるを棚上げしてでも)可能なかぎり客観的に把握し記述する必要がある。あまたの失敗を繰り返しながら電球を発明したトーマス・エジソンはじめ、多くの先人たちが失敗を“うまくいかない方法の発見”と捉えてきたことでもわかるとおり、“ただの失敗”と忘却することこそ、失敗をもっとも無意味な失敗に留めるからだ。
◇
そのことは、“ダメだった”と判断した有権者にとっても同様だ。
仮に「やらせてみた」のが失敗だったとして、単に“やらせた相手が悪かった”から元に戻せばよい、という話ではあるまい。それでは、選挙民としての失敗も“ただの失敗”で終わってしまい、経験として積まれない。そもそも「やらせてみた」理由が、直前に政権を担った自民党の第1次安部政権および麻生政権に納得いかなかったからであるのなら、もとに戻すときには“自分たちの判断がまちがっていて、あなた方が正しかった”のか、それとも“あなたたちの方がまだマシだった”という相対判断なのかを考えない限り、エジソンのような“うまくいかない方法”を発見できずに終わるだろう。
だが、結論が前者と後者のいずれであっても、(「やらせてみた」もふくめて)そこに共通するのは、それらの判断と選択が、主権行使の一定期間の白紙委任”を前提とする代議制の前提の下で行われていることだ。それが議会制民主主義の前提と言うべきものであることは確認するまでもないだろう。だが、前近代的な封建制から、制限選挙を伴うとはいえ天皇を戴(いただ)く君主制だった戦前と占領下にあった終戦直後を経て、この国の議会制民主主義下で実質的に初めての経験とすら言える長期間の政権交代は(わずか8か月しか存在しなかった1993年の細川護熙内閣は、選挙制度改革以外のことをほとんどしなかった)、そうした制度をあらためて考える、初めての契機でもありはしまいか。いったい、選挙とそれに基づいた今日の民主主義とは、いかなるものであるのだろうか。
■約半数が棄権する選挙
『バカに民主主義は無理なのか?』という扇情的なタイトルの本書は、現代の代議制民主主義について、たとえば次のように言う。「選挙制度の最大の欠陥は、立候補した人間のなかからしか、われわれの代表を選べないという点にある」つまり「出したい人ではなく、出たい人からしか選べない」。
なるほど、とひざを打つ人も少なからずいるはずだ。どの政党、どの候補者であれ、街頭演説や氏名を連呼する選挙カーに対する、あの既視感と倦怠(けんたい)は、結局のところ、候補者たちの誰もが「俺が俺が」と自己主張する凡庸さと決して無関係ではないだろう。といって、「謙虚で静謐(せいひつ)な生活を好むような人は、選挙には立候補しない」のだから(たとえ周囲に推されて立候補した人であっても、選挙というフォーマットに乗った瞬間に、謙虚さや静謐を身にまとうことは難しくなる)、そういう人を選ぶことは現状の選挙では容易ではない。“恥ずかしげもなく立候補する権力欲と自己主張の持ち主など、自分たちの代表に認めたくない”と考えるひとがいたとして、それが選挙である限り、そう考えるひとたちの選択肢は“自己主張するひとのなかから消去法的に選ぶ”か“棄権する”かのいずれかになる(その“出口なし”を解決するためには、積極的な棄権を選挙結果に反映するシステムを作るほかない)。
投票率が50%そこそこで(今回の参議院選挙の投票率は、戦後に参議院が発足して以来3番目に低い52.61%だった。過去の投票率は、高かったのが1980年の74.54%を筆頭に70%台が4回、低いのは50%台が10回。95年の第17回の44.52%を最低に、92年以降はずっと50%台以下が続いている)、比例代表で自民党の得票率が34.7%、民主党のそれが13.4%なのだから、全政党中最多得票だった前者でも全有権者の約18.3%、後者に至っては約7%程度しかいない。
といって、“だから、選挙は民意を正確に反映していない”という紋切り型をここで繰り返したいわけではないし、“風が吹いた”だの“吹かなかった”だのと、無党派層の動向を惜しみたいわけでもない(「小泉旋風」が吹き荒れたことになっている01年の参院選でも、投票率は56.44%で最多得票の自民党の得票率は38.57%、つまり全有権者の21.8%が投票したに過ぎないのだから、棄権した43.56%の半分でしかない)。
人々の半数近くが選挙に行かない/行きたくないことがここまで常態化し、全有権者の1/4とか1/5の得票によって選挙制度も包含する“憲法”改定の発議すらも可能な議席数が得られてしまうなら、“行かないヤツが悪い”“行けば変わる”等々と変わらぬ繰り言を続けるだけでなく、ごく一部の民意しか反映できない制度そのものを問う方が合理的というものだ。勉強ができない子どもに向かって“勉強しないお前が悪い”とか“やればできるようになる”とか“やってもらわないと困る”と言うことは、一度や二度ならあってもよいが、そのお小言を半世紀続けてもできないままならば、勉強の仕方を問い返すか、勉強そのものが向いていないと別の道を探してやるか、どちらかが必要なのと同じことだ。
◇
考えてみれば、1945年の普通選挙以後に生まれ育った私たちは、選挙による代議制こそが民主主義の唯一無二の手段であると信じているフシがある。戦前の選挙が25歳以上の男性のみを対象としたものだったり時期によって納税条件があったり、そもそも主権が国民にあると明記されていなかったり、さらには議会選挙すら存在しなかった時代を思えば、そう信じても無理はない(し、実際それらよりはマシだろう)。
だが『バカに民主主義は無理なのか?』は、「選挙に行くことだけが政治参加なのか」と、「『民主主義』の可能性と限界について」考えることから始めようとする。
いわく、「民主主義は、そもそも問題がある制度だということも、昔から言われてきた」と。デモクラシーの由来を持つ古代ギリシャでは「民衆はバカだと思われており、その『バカ』が口を出す」悪政のひとつとして民主主義が捉えられていたし、ある程度民主主義が達成されたと考えられている国でも、徹底した民意の反映を望む者にとっては「現行の議会制民主主義では十分に民衆の意見が反映されていない」と感じられる半面(民衆が多種多様で利害も相互に対立する以上、当たり前だ)、「民衆の不見識のために『正しい選択』が行われず、社会が混乱している」という不満も生じる。エリート官僚を含む知識人による「行き過ぎた民主主義批判」が生じる危うさがある一方で、「見かけは民主的であるような体裁をとりながら、実際には寡頭制」になる危惧もある(政治家の世襲制度は事実上の寡頭制だと言うこともできる)。
■まるで「同意の表明システム」
なかで、今日の私たちにまず興味く映るのは、20世紀前半のオーストリアの経済学・社会科学者のJ・A・シュムペーターを引用して著者の語る「選挙制度とは、『民衆の声を政治に届かせるデモクラティックな形態ではなく、上位権力が要求する同意の表明システムに過ぎない』」というくだりだ。
行為としての“選挙”とは、議員(およびときに彼らがその時点で所属する政党)を選ぶ行為以上でも以下でもない。彼らはしばしば“マニフェスト”等の名で政策を掲げるがそれがそのまま実行されることのめったにないことも、政策や政党を変えても任期中の議員が議席を失うわけではないことも、結果的に、選ばれているのが第一に“人”であることを示している。そうして、その“人”が能力や人格ですらなく“人”そのものであることは、公約した政策を実行できぬ力量不足が露呈してもその議員が辞職するわけではないことに明らかだし(その場合、間違っていたのは議員ではなく政策だった、ということになる)、最善を尽くすという前提=名目で「選挙で勝ったのだから在任期間に何をしてもよいだろう」的な傲岸不遜(ごうがんふそん)な勘違いが導かれることも、よくある光景だ。
そうした不都合は、すべて、「選挙によって選ばれた議員たち(の多数派)で構成される政府の行うことである」という理由によって、有権者たちを納得させることで埋め合わされる。その議員たちに投票した者たちは(自分たちが選んだのだから、という理由で)もちろんのこと、落選した候補者に投票した者たちも(自分たちは少数派なのだから、という理由で)渋々とであれ納得するか、一歩引いたところから反対を表明する(させられる)ことになる。しかも、少なくない“国務大臣”や“委員”たちが自身の専門外の役職に就き、専門家である官僚らの用意した原稿をもとに答弁を行う現状を見れば、いよいよそれは儀式めいてくる。原始の王から前近代の封建君主たちが、“占い”や“言霊”“血統”あるいは“武力”などを駆使して自身の権力の正当性を示そうと試みたのと同様に、議会制民主主義はしばしば、上位権力である者たちの振る舞いを「主権者」であるはずの者たちに納得させる儀式として機能するわけで、“言葉(政策)”ではなく“人”で選ばれた“議員”ならぬ“儀員”とは、しばしば、そこで演じる“役者”たちの別名であるだろう。「同意の表明システム」というのは、そのような意味においてである。
◇
このように考えれば、一般には“主権者である国民の、(ときに、ほとんど唯一無二の)政治参加の方法”のように感じられる現状の“選挙”と“代議制”が、けっして唯一無二のものでなどないばかりか、ときに逆方向の力として機能するものであることがわかる。もちろんそのことが選挙や代議制のすべての意義を否定するものでなどないが(もとより1から10まで個々の有権者の願望や意志と合致する代議員などいるはずがない以上、意見を反映することと同じくらいに意見を無視あるいは抑圧することも代議制の目的のひとつだ)、あくまでそれは、あまたありうる制度のなかのひとつ、弱点を多々持った“ひとつだけしか選べないとしたら、現時点で相対的にマシ”だったものでしかない。
代議制が最大に機能するのは、その政府に対して主権者たちが“NO”を突き付ける瞬間と、それを前提にした権力監視システムとしてだ(『バカに民主主義は無理なのか?』はそれを、政府が自然法に反する行為を繰り返した場合に国民が行使する“革命権”と結びつけている)。とすれば、投票率が下がり続けて50%台前半をうろうろする(地方選挙の場合はしばしば下回る)選挙の「棄権率」は、現行の代議員と候補者に対する否認であると同時にそれ以上に、現行の制度に対する不信任なのではないか。明治維新以後に輸入され、民主主義を担保するものと考えられ続けてきた“選挙=最強”の民主主義観は、決して唯一無二のものではない。なにしろそれは、今日のような各人が身につけたモバイル端末で構成された電子ネットワークの情報環境など夢にも思えなかった当時のシステムで、馬車や鉄道で運ばれる郵便や新聞が最良の通信手段だった時代の技術なのだ。21世紀の私たちが、そのシステムに縛られ続ける必要が、どこにあるだろうか。「選挙制度改革」が、“一票の格差”の問題や議員定数の問題に矮小(わいしょう)化され、投票率をここまで下げて選挙を虚しくさせてきたこの国の議会政治と政治家たちのありかたや選ばれかたについて踏み込もうとしないこと自体が、有権者の想像力を狭いところに押し込めている幻影なのだ。
「選挙に行っても何も変わらないよ」という呟(つぶや)きを、従来のようにただの怠惰と捉えるのでも、百年たって結局、失望しか生まなかった「選挙に行けば変わる」という明治以来の夢を共有しつづけることでもなく、(まして、そのような制度で選ばれた代議士たちが、彼らを選ぶ制度の根幹にある憲法を変えようとしているならばよけい)私たちはそろそろ、考え始めなければならない。
■「バカ」に込められた意味は
そんなとき、『バカに民主主義は無理なのか?』はとても示唆的かつ実践的な一冊になる。タイトルのインパクトとは逆に、同書はひどく真面目な本だ(そう書いてしまうと、あえて扇情的な題名をつけて興味を引こうとした著者の意図を裏切るようで悪いけれども)。先に引用した「出たい人からしか選べない」問題をはじめ、世襲政治家やポピュリストといった巷間言われる問題や、「バカが選挙権を持っていいのか」という疑問以上に深刻なのは「バカが政治をやっていいのか」であり、「嘘つきや私利私欲の徒でも、かしこければ政治を任せていいのか」という入りやすい問いを間口に、民主制が幕末の日本に移入された経緯からその根源としての古代ギリシャの民主制に遡(さかのぼ)ってプラトンやアリストテレスに学び、ホッブズの議会制民主主義やロックとルソーの社会契約論、そして日本の議会制民主主義が根付いてゆく歴史に至るまでを、わかりやすく整理してゆく。同時に、日本国憲法の成立過程やその理念、社会的指導者層が暗黙のうちに大衆を見下し、大衆が自分たちを拒絶しないものとしてのファシストやポピュリストたちに引きつけられてゆく構図、そして戦後の日本政治のありかたなどが、わかりやすく語られてゆく。
そのような同書の出発点であり終着点は、繰り返すが、「『民主主義』の可能性と限界について」つまりは“民主主義とはなにか”にある。そしてその一端を著者は、「民主主義にいいところがあるとしたら、それはこの制度が『われわれが生きている世の中は理想的ではない』ことがわかりやすいところだ」という。それは、単に制度やその制度で選ばれた政治家たちが「理想的ではない」からだけではなく、私たち自身が「愚かで、欲張りで、ずるく、卑怯(ひきょう)未練なところを持っている」「完璧ではない」存在であり、そういう人間の代表者たちが行う政治もまた、「ひどく愚かで、ひどく強欲で、ひどくずるいもの」でありうるのだ、と。
かつてギリシャのプラトンが「哲人政治(最高善の認識に達し、知的にも倫理的にも完成された存在による至上の専制)」を夢見たころは、まだ世界は狭かったし、人間の数も少なかった。社会を支える奴隷たちは、そもそも民主主義の枠から外されていた。人々が知りうる情報量や視野に収めなければならない世界も、ずっと小さかった。
けれども、人口も規模も情報流通の量も速度もはるかに肥大した今日の社会でそのような“哲人”を求めようとすれば、それはジョージ・オーウェル的な非人間的「ビッグ・ブラザー」にならざるをえないし(そうすればよいというのではない、むろん)、それに対して私たち個々人は、相対的により矮小たらざるをえない。そして、だからこそ、自分たちの無知と無力を見つめながら、考えていかなくてはならない。
終章で著者は書く。「代議制民主主義は、まだるっこしい。異なる意見にも冷静に耳を傾け、粘り強く調整を行わなければ、何も決められない。その過程で、さまざまな妥協を強いられる『バカ』は、その手続きに堪えられない。/しかし、あきらめてしまっては、望みは達成できない。(…)そんな面倒なことはイヤだ、と利害調整抜きの断行を唱えるヒーローを望む者は、自分のなけなしの権利が、何の前触れもなく消滅するのを知るだろう」
そのことは、『バカに民主主義は無理なのか?』という書名を見て、政治家や有権者を「バカ」と感じてシニカルに同意した者にも、自分が「バカ」に含まれると感じて面罵されたと苛立(いらだ)った者にも、“そうだよ、無理だよ”と諦めようとした者にも、同等に響いてくる。「バカ」とは知能や知識といった能力や、まして学歴や社会的地位のことではない。自分のいまの限界を超えて知ろうとしないこと、いまの枠組みを離れて考えようとしないこと、思考を感情を肯定するための道具として使って省みないこと、その態度こそが「バカ」なのだ。私たちは誰もが常に「バカ」に陥り、しかし「バカ」でなくなる契機を持っている。民主主義はそのことについて考えさせる、最大の契機のひとつであるはずだ。
================================================================================
最新の画像[もっと見る]
-
 ●《アイヌ民族からは、相次ぐ差別発言への罰則規定の導入など法改正を求める声が強い…先住民族に関して、この国の無関心の根本原因は何なのか》
18時間前
●《アイヌ民族からは、相次ぐ差別発言への罰則規定の導入など法改正を求める声が強い…先住民族に関して、この国の無関心の根本原因は何なのか》
18時間前
-
 ●アイヌの人々は何を求めているか? アイヌ民族の遺骨の盗掘、墓荒らし…倫理観無き情けない研究者・学会、《過去の盗掘の「謝罪」》無し
2日前
●アイヌの人々は何を求めているか? アイヌ民族の遺骨の盗掘、墓荒らし…倫理観無き情けない研究者・学会、《過去の盗掘の「謝罪」》無し
2日前
-
 ●《戦世(いくさゆ)の足音に危機感を抱きながら私たちは戦争犠牲者を悼み、平和を求める日を迎えた。きょうは沖縄戦から79年の「慰霊の日」》
3日前
●《戦世(いくさゆ)の足音に危機感を抱きながら私たちは戦争犠牲者を悼み、平和を求める日を迎えた。きょうは沖縄戦から79年の「慰霊の日」》
3日前
-
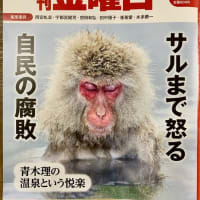 ●《30年前の平成の政治改革…「腐敗防止法どころか腐敗温存法」「政治はいつも談合」》、一方、利権裏金脱税党の泥棒達による裏金維持法成立
4日前
●《30年前の平成の政治改革…「腐敗防止法どころか腐敗温存法」「政治はいつも談合」》、一方、利権裏金脱税党の泥棒達による裏金維持法成立
4日前
-
 ●(リテラ)《神宮外苑の再開発…裏金事件のキーマンである森喜朗…と萩生田氏が暗躍し、都政を食い物…現在進行形の案件…小池氏はこれを推進》
5日前
●(リテラ)《神宮外苑の再開発…裏金事件のキーマンである森喜朗…と萩生田氏が暗躍し、都政を食い物…現在進行形の案件…小池氏はこれを推進》
5日前
-
 ●小池百合子東京「ト」知事のぶら下がり取材、学歴詐称の質問を遮ってのテレ朝記者「今日の御召し物は緑の勝負服でなく…」質問、酷かったなぁ…
6日前
●小池百合子東京「ト」知事のぶら下がり取材、学歴詐称の質問を遮ってのテレ朝記者「今日の御召し物は緑の勝負服でなく…」質問、酷かったなぁ…
6日前
-
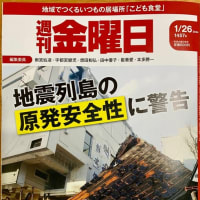 ●「利権」「裏金」「脱税」党・西村康稔前経産相「能登半島の地震は1000年に1回や。なんべんもくるもんやない、1000年に1回や。原発作ったらええ」
7日前
●「利権」「裏金」「脱税」党・西村康稔前経産相「能登半島の地震は1000年に1回や。なんべんもくるもんやない、1000年に1回や。原発作ったらええ」
7日前
-
 ●辺野古破壊について玉城デニー沖縄県知事「移設反対は揺るぎない思い」と強調…日々膨大なドブガネし、美ら海に大量の土砂をぶちまける愚行が続く
1週間前
●辺野古破壊について玉城デニー沖縄県知事「移設反対は揺るぎない思い」と強調…日々膨大なドブガネし、美ら海に大量の土砂をぶちまける愚行が続く
1週間前
-
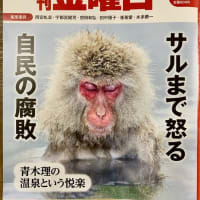 ●あぁ、お維案件…《政治資金規正法改正で自民と維新が犯罪的談合!「企業献金」を死守したい自民と「政策活動費」温存を図る維新の詐術》(リテラ)
1週間前
●あぁ、お維案件…《政治資金規正法改正で自民と維新が犯罪的談合!「企業献金」を死守したい自民と「政策活動費」温存を図る維新の詐術》(リテラ)
1週間前
-
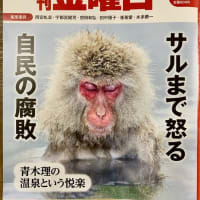 ●《自民党内で最後に残った『良識派』を自認する村上誠一郎衆院議員がずっと恐れていたことが、今自民党に、そして日本の政治に起きている》
1週間前
●《自民党内で最後に残った『良識派』を自認する村上誠一郎衆院議員がずっと恐れていたことが、今自民党に、そして日本の政治に起きている》
1週間前
「Weblog」カテゴリの最新記事
 ●《アイヌ民族からは、相次ぐ差別発言への罰則規定の導入など法改正を求める声が強...
●《アイヌ民族からは、相次ぐ差別発言への罰則規定の導入など法改正を求める声が強... ●アイヌの人々は何を求めているか? アイヌ民族の遺骨の盗掘、墓荒らし…倫理観無...
●アイヌの人々は何を求めているか? アイヌ民族の遺骨の盗掘、墓荒らし…倫理観無... ●《戦世(いくさゆ)の足音に危機感を抱きながら私たちは戦争犠牲者を悼み、平和を...
●《戦世(いくさゆ)の足音に危機感を抱きながら私たちは戦争犠牲者を悼み、平和を... ●《30年前の平成の政治改革…「腐敗防止法どころか腐敗温存法」「政治はいつも談合...
●《30年前の平成の政治改革…「腐敗防止法どころか腐敗温存法」「政治はいつも談合... ●(リテラ)《神宮外苑の再開発…裏金事件のキーマンである森喜朗…と萩生田氏が暗躍...
●(リテラ)《神宮外苑の再開発…裏金事件のキーマンである森喜朗…と萩生田氏が暗躍... ●小池百合子東京「ト」知事のぶら下がり取材、学歴詐称の質問を遮ってのテレ朝記者...
●小池百合子東京「ト」知事のぶら下がり取材、学歴詐称の質問を遮ってのテレ朝記者... ●「利権」「裏金」「脱税」党・西村康稔前経産相「能登半島の地震は1000年に1回や...
●「利権」「裏金」「脱税」党・西村康稔前経産相「能登半島の地震は1000年に1回や... ●辺野古破壊について玉城デニー沖縄県知事「移設反対は揺るぎない思い」と強調…日...
●辺野古破壊について玉城デニー沖縄県知事「移設反対は揺るぎない思い」と強調…日... ●あぁ、お維案件…《政治資金規正法改正で自民と維新が犯罪的談合!「企業献金」を...
●あぁ、お維案件…《政治資金規正法改正で自民と維新が犯罪的談合!「企業献金」を... ●《自民党内で最後に残った『良識派』を自認する村上誠一郎衆院議員がずっと恐れて...
●《自民党内で最後に残った『良識派』を自認する村上誠一郎衆院議員がずっと恐れて...

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます