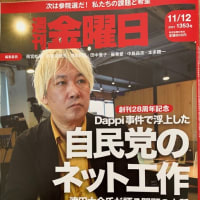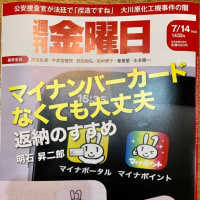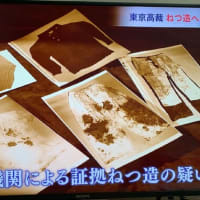【黒藪哲哉著、『「押し紙」という新聞のタブー/販売店に押し込まれた配達されない新聞』】
生々しい数字・実態、産経の「押し紙」。「・・・実配部数は3000部程度だった。約2000部が過剰になっていたのだ。/・・・小屋を建てて新聞を補完するように命じられ・・・。/・・・古紙回収業者に引き取ってもらっていた。・・・/たとえば、01年8月の回収は9回、約27トンの「押し紙」を回収している」(p.73)。
業界団体が主催する総会に出席してみると・・・「大浴場・・・裸の男たちの群れに、入れ墨をした者が複数混じっていたのだ。/・・・温泉総会を取材するたびに、浴場で入れ墨をした人々を目撃した。・・・顔を強ばらせ、「立派な入れ墨ですね」とお世辞を言っているのを聞いたこともある。/・・・欧米では、新聞人がマフィアと交友を結ぶことはありえない。・・・原則的には一線を画さなくてはいけないが。日本の新聞社では両者の関係が違和感なく受け入れられている。「新聞はインテリが作って、ヤクザが売る」という一句で、すべてが片付くのだ」(pp.144-145)。
ナベツネ氏の下品さ。「読売――〝1000万部〟をバックに総理を動かす!?」(pp.142-143)。「・・・一千万部の力で総理を動かせる。・・・政党勢力だって、自自連立だって思うままだし、・・・。/・・・魚住昭氏が『渡邉恒雄 メディアと権力』・・・渡邉氏に対して行ったインタビュー・・・。/渡邉氏の発言内容は、文化人の言葉というよりも、野心を内に秘めた政治家の言葉に近い。そこには本来新聞人が持つべき文化や知性の香りは、どこにも感じられない。ある種の下品さすら漂う」。
この下品なナベツネ氏は、日販協政治連盟の設立にも関わり(p.192)。「新聞業界と政治家との癒着には、政治家と番記者の情交、あるいは記者クラブを通じた馴れ合いのイメージがつきまとう。実際、元政治記者で2008年に保守の大連立構想をめぐって政界工作を行った読売新聞社の渡邉恒雄会長・・・自民党の大物政治家・大野伴睦と接するときの心境・・・。それは政治家と番記者の情交が、いかに権力を監視すべきジャーナリズムを骨抜きにするかを物語っている」(p.163)。「記者クラブは、〝談合〟の場か?」(p.174)。「・・・真実とは異なった情報が日本中に広がるおそれがある。・・・/念を押すまでもなく、新聞社にとって公権力からの最大の情報の受け皿となるのは記者クラブである。/・・・情報提供者の希望する情報だけが、新聞を通じて広がることになる。・・・記者クラブが提供する情報によって、世論が形成されていくと言っても過言ではない」。
元社長が別の意味でね。「・・・暴力をともなった拡販活動を警察が積極的に取り締まらない背景には、新聞社との癒着があるのかもしれない。・・・読売の場合、社内に読売防犯協力会という組織が設置されていて、多数の警察OBが参与になっている。警視庁OBの天下りも指摘されており、読売の元社長・正力松太郎氏も戦前の特高警察の出身である」(p.150)。検閲の手間を省くために1000紙以上の新聞社を50数社に削減することで「・・・新聞を通じて大本営発表をそのまま報じさせる体制を整えたのだ。それが日本を不幸に陥れたことは、歴史が証明している。/・・・戦前は国家権力によるメディアに対する強制があったが、戦後はそれがなくなった。とすれば、公権力は別の方法で、マスメディアをコントロールしていかなければならない。・・・/・・・『原発・正力・CIA』(新潮新書)の中で、読売の元社長・正力松太郎氏が、新聞を通じて親米世論を盛り上げるためにCIAの操作されていた事実・・・を明らかにしている。正力氏の暗号名は「ポダム」だったという」(p.170-171)。
新聞奨学生の悲劇。「・・・便利屋のような存在だ。・・・どんなに過酷な労働を課しても夜逃げするわけにはいかない。/・・・タコ部屋同然の部屋だったという」(p.155)。
無理・強引な拡販がもたらす悲劇。悪循環。「部数至上主義の旗の下で、新聞人はジャーナリズム活動を支えるための強い経営基盤を打ち立てるはずだった。そのためには、販売店の切り捨てもはばからなかった。拡販部隊としてのアウトサイダーの受け入れも、「必要悪」の論理の下で容認した。/しかし、肝心のジャーナリズムの灯は消滅した。後に残ったのは新聞乱売と人間疎外の索漠とした荒野だった。それが新聞離れに拍車を掛けて、新聞社を崩壊の危機へと追い込んでいるのではないだろうか」(pp.159-160)。
「日販協と新聞族議員の〝絆〟」(p.186)。中川秀直、小泉進次郎、小池百合子、与謝野馨。「・・・新聞販売懇話会は多数の有力政治家を「輩出」している。・・・塩川正十郎、小沢一郎、森山真弓、小渕恵三、与謝野馨、石原慎太郎、・・・島村宜伸、小泉純一郎、河野洋平、森喜朗、羽田孜、谷垣禎一、加藤六月、西岡武夫、・・・。・・・山本一太・・・。いわば政界の頂点と日販協が太いパイプでつながった時期もあったのだ」(pp.187-188)。中川秀直センセへの恩返し(p.191)や、山本一太センセへ800万円もの政治資金のばら撒きが(p.191)。衝撃的です。「政治献金によって政策が左右されるシステムが、民主主義であるはずがない」(p.193)。「・・・新聞業はジャーナリズムの看板を掲げているのだから、道義上の問題は免れない。それに、仮に献金の目的が再販制度などの既得権の防衛にあるとすれば、金で政策を買ったことにもなる」(p.196)。四大悪法との関わりが焙り出されてくる。「四大悪法の成立と引き替えに・・・・・・」、「再販問題の弱みを握られたことで、新聞社は政界の監視というジャーナリズムの役割を果し辛くなり、結果として政権党の国会運営を助けた可能性はないだろうか。/・・・辺見庸氏が提起した「1999年問題」という表現を思い出す。/・・・周辺事態法、盗聴法、国旗・国歌法、改正住民基本台帳法など矢継ぎ早に通過している。・・・高橋哲哉教授との対談・・・「新しい『ペン』部隊」とは、マスメディアのことである。/・・・新ペン部隊が陰に陽に展開し、百十本というおびただしい法律を矢継ぎ早に成立させるのを大いに助けた。わけても、前述の四大悪法を通す後押しをした」(pp.208-209)。
キッタナイ政治家どものキッタネエ手での「・・・改憲に向けた動きと考えて間違いない。/・・・背景には、企業のグローバリゼーションの影響・・・、太平洋戦争の犠牲者の上に成り立っている憲法の「改正」には、慎重にも慎重を重ねなければならない。当然、ジャーナリズムの役割は重要になってくる。・・・/・・・ところがそれを議論するための公平な土壌があるのか、はなはだ疑問が残る。新聞社が自らの権益を守るため、政界との癒着を強めているからだ。」(pp.214-215)。