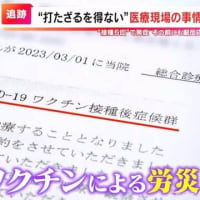記事の紹介です。
記事の紹介です。
マイケル・オースリン
2010年 12月 24日 18:21久しく待望されていた新たな「防衛計画の大綱」(新防衛大綱)が先週発表され、日本もようやくポスト冷戦時代に入った。日本政府は、日本の国益に脅威をもたらす可能性の最も高い国が中国であることを認識し、それに沿って戦略の焦点をシフトさせた。
日本政府は、中国の海軍・空軍増強に対抗する上で最重要な兵器システムをささやかに増強させる意向も示唆している。現時点における疑問は、日本のこうした施策が果たして十分かどうか、そして、日本の新たな防衛態勢が、高まりつつある東アジアの海上の緊張にどういう影響を及ぼすかという点だ。
新防衛大綱は、民主党政権が打ち出した初の本格的な防衛戦略だ。これは、併せて発表された、今後5年間の装備を定める「中期防衛力整備計画(中期防)」の指針となるものだ。民主党政権がすべての府省に予算の再編成を余儀なくさせるなか、新防衛大綱と中期防は共に発表が1年遅れた。米海兵隊普天間飛行場の移転をめぐる鳩山前首相とオバマ政権のあつれきも遅れにつながった。新防衛大綱が日中間の対立関係にどれほど直接的に対処するかについては、日米双方で多くの憶測がなされていた。最終的な結果は、長短相半ばといったところだ。しかし、良いスタートとして評価すべき要素が十分にある。
最も重要な変更点は、新たな防衛戦略の導入だ。日本政府は過去数十年間、「基盤的防衛力構想」に誘導されていた。これは、日本の国益が直接的に脅かされた場合にのみ脅威に対処するという、事実上受け身の戦略だった。新しいアプローチは、地域環境を形づくるための「動的防衛力」の構築を求め、米国との一層緊密な協力・連携、海外における防衛活動の活発化、ほかのアジア諸国との協力強化を提案している。
とはいえ、新防衛大綱は防衛予算のさらなる削減を命じているため、この新しい積極的戦略を実施する能力が果たして自衛隊にあるかどうかが疑問になる。日本の厳しい財政状況を反映して、政府は陸上自衛官を1000人減らし、常備自衛官の定数を14万7000人とすることにした。人員を削減しながらどのように防衛活動を拡大させるのかは、まさに、安全保障問題に関して民主党がどれほど信頼できるかの試金石となる。
新防衛大綱の目標は、筆者が数週間前に本欄で触れた、有識者による「新たな時代の安全保障と防衛力に関する懇談会」の報告書を受けたものだ。一部の観測筋が述べているとおり、この報告書と新防衛大綱は共に、中国と北朝鮮からの予測される脅威を真っ向から迎え撃つための、日本の防衛力の劇的増強は提案していない。
むしろ、両者とも、特定の重要な防衛力を強化するべく、防衛力の再編成を試みている。新防衛大綱は、日本の潜水艦装備を現行の16隻から22隻に増加すること、およびイージス弾道ミサイル防衛システムを搭載した護衛艦をさらに2隻追加することを求めている。航空自衛隊は、那覇基地に迎撃戦闘飛行部隊1個を移動させるとともに、次世代戦闘機を調達する計画を推し進める。次世代戦闘機として、日本政府は米国のF-35戦闘機を望んでいたが、目下、交渉は中断している。
実効性がより低い兵器システムも削減される。この中には、冷戦時代に、日本の北方領土へのソビエト侵攻の脅威に対処するために増強された陸上自衛隊の戦車部隊の三分の一削減も含まれる。
こうしたすべての変更の目標は、中国の海軍・空軍力の増大から日本の南西地域の島嶼部(とうしょぶ)を守ることに日本がより確実に焦点を絞れるようにすることだ。こうした焦点シフトの抜け目なさは、新防衛大綱の発表後間もなく、中国国営の英字紙チャイナ・デーリーが、新防衛大綱を「挑発的」で「偏執的」と非難したことからも明らかだ。日本の懸念を裏書きするかのように、中国政府も、問題となっている尖閣諸島の沖合に漁業巡視船を定期的に派遣する意向を表明した。
今年9月、尖閣諸島沖で日本の海上保安庁の巡視船が中国漁船船長を逮捕し、日中政府間の大きな紛争の引き金となった。中国は報復として、中国本土で働いていた日本人4人を逮捕するとともに、日本企業への、重要なレアアース(希土類)供給を劇的に削減した。この事件は、広く報道された今年3月における中国海軍艦船の日本領海通過をはじめとする、日本の南西諸島周辺での中国海軍の活動増大に引き続いて発生した。
日本政府は、中国の海軍力拡大が近隣諸国に対する中国の領土的主張の拡大につながるのを目の当たりにしてきた。ここ数年間に、南シナ海における排他的経済水域にまつわるベトナムやインドネシアとの新たな紛争も勃発している。中国政府報道官は、今夏、黄海における韓国との海軍合同演習を実施しないよう、米国にまで警告した。
70隻近い潜水艦と増強中の海上艦隊を擁する中国海軍は、目下、東アジアの重要シーレーンに常駐している。とはいえ、日本やその他のアジア諸国の疑念をあおってきたのは、中国が公海上における共通の「交通規則」に同意することを拒否してきたことや、同国の海事上の主張、民間漁船団防衛面での中国の積極行動だ。
ここが、中国への対応方法についての意見の分かれるところだ。東アジア水域での安定を維持する最善の方法は信頼できる海上自衛力を日本が持つことだと考える向きは、新防衛大綱を一歩前進ととらえるだろう。中国のように、そう考えない向きは、これを不必要に挑発的ととらえるだろう。
いずれの見方をとるにせよ、日本の新しい防衛体制は、ささやかな防衛力増強にとどまる。菅政権がこれまでのところ、武器輸出禁止の見直しを行わないとしている点は、観測筋をさらに落胆させるだろう。見直しを行えば、日本政府が防衛技術面で諸外国と協力することや日本の軍事技術を売ることが可能となり、日本の防衛装備品調達のコスト低減に役立つだろう。
同様にまた、菅首相が、日本にとっての新たな脅威を認識しつつも、長期的な安全保障面の課題へのより確かな対応を可能にする防衛予算増大を行わないとしている点も、広く失望を生むだろう。
したがって、いろいろな意味で、新防衛大綱の成否は、日本が米国と同盟関係を維持することに依存する。自衛隊と同様、米国の海空軍も、将来的な予算の緊縮と人員装備需要の増大に直面している。米軍はここしばらくは、東アジアにおける最大かつ最も有力な勢力であり続けるだろうが、米政府は今後、防衛負担の一層多くを同盟諸国に分担してもらうことが必要になる。
この点を認識して、日本の民主党は、米国と一層緊密に協力する意向を再確認している。今後、日米は、アジアの海の平和を維持するための具体的な兵力、計画、政策を打ち出す必要がある。日米が防衛面の確実性を維持するなら、中国が、高圧的な姿勢ではなく建設的な対話のメリットを認識する見込みも高まるだろう。
(マイケル・オースリン氏はアメリカン・エンタープライズ研究所の日本部長。ウォール・ストリート・ジャーナル電子版のコラムニスト)
http://jp.wsj.com/Japan/Politics/node_163749

 記事の紹介終わりです。
記事の紹介終わりです。
■ Site Information ■
■ 2009年7月9日
「我が郷は足日木の垂水のほとり」 はじめました。
本稿はその保管用記事です。
■ 2010年3月2日![]() 人気blogランキング(政治)にエントリーしました。 => ランキングを見る
人気blogランキング(政治)にエントリーしました。 => ランキングを見る