トリックテイキングの基本みたいな流れをしてますが得点の稼ぎ方がちょっと変わってます。簡単なルールですが得点に繋げるには運も計画も必要。
「Voodoo Prince」のご紹介です。
原題: Voodoo Prince
日本語タイトル: 同上(日本語版:数寄ゲームズ)
デザイナー: Reiner Knizia
発売: 2017(独)
可能人数: 2~5人
プレイ時間: 30分程度
ボックスサイズ: 125×98×24(mm)
カードサイズ: 87×57(mm)
「トリックテイキング」「ハンドマネジメント」
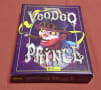
クニツィア博士の小箱ゲーム。以前から気になってたものなんですが今回数寄ゲームズさんから日本語版が出たことで確保できました。わーいわーい。
バックグラウンドとしての設定は…あまりない(笑)
いや、ブードゥーの儀式を行って霊(ロア)と交信しようって事くらいなんですよね…
ブードゥーってアフリカ土着信仰を元に、奴隷として中南米に連れてこられた黒人たちによって発展変化したものだったかと。その途中で白人の弾圧から逃れるためにキリスト教もちょっとだけ混ざったことからハイチではキリスト教徒であると同時にブードゥー信仰をされている方も多いらしいです。
なお、ブードゥー信仰はありますが「ブードゥー教」は教義として正式に伝えられているモノもなく、正統な教団もありません。山をご神体として拝むとかの山岳信仰や所謂精霊信仰に近い…ってのがウチが昔にかるくググった時の印象です。今も総本山みたいなのが無いかどうかは不勉強にて解りません。(2020/06/11)
ホラー映画で人を喰ったり感染したり頭だけになっても蠢いてたりするのを「ゾンビ」と呼称しますが、本来の「ゾンビ」はブードゥの術によって犯罪者の死体に肉体労働をさせるって感じです。術によって命じられた簡単なことしか実行できないし勝手に歩き回ったり人を食べたりもしないとのこと。
エンタメでいう(そしてボドゲで扱われるほとんどの)ゾンビは死霊術とかそっち方面です。
閑話休題。
まぁこのゲームはその辺りの事は興味がなかろうと遊べます(笑)。
ゲームは5ラウンドのトリックテイキング。5ラウンド終了時に最も得点の高いプレイヤーが勝者となります。

コンポーネントはこんな感じ。左上の色だけのカードは切り札の表示カード。見ての通り5色。
そしてその5色のブードゥーカードがあります。各色16枚。あとはサマリ。
ゲームの流れは1ラウンド目とその他のラウンドは最初の部分が少し違ってきますがそれ以外は一緒です。

まず1ラウンド目開始時に5枚の切り札カードをシャッフルし、1枚を公開することでこのラウンドの切り札カードを決定します。

その後、プレイヤーにそれぞれ規定枚数のプレイ用のブードゥーカードを配ります。プレイ人数によってカードの「使う枚数」と「配る枚数」は決まっています。
セットアップはこんなもんですね。では流れを見ていきましょう。
ゲームは1ラウンド中に「トリック」と呼ばれる小さな戦いを繰り返していきます。

「トリック」はまずスタートプレイヤーが手札からカードを1枚出すことから始まります。このカードはなんでも構いません。
で、重要なのはまず「色」、次に「数字」です。

スタートプレイヤーが出したカードを見て他のプレイヤー達が順番にカードを出していく訳ですが、この時に「色」の縛りが発生します。
スタートプレイヤーが出したカードが黒だった場合、他のプレイヤー達の手札に黒があるならば黒以外のカードを出すことが出来ないということになります。この時点では色が合っていれば数字は何でも構いません。
で、写真ではスタートプレイヤーの【黒4】から始まって【黒10】【黒12】【黒6】【黒13】と黒のカードが並びました。1ラウンド目から1色欠けてるというのは配られたカードの枚数から考えてあまりないんですよね(笑)
全員のカードが1枚ずつ出揃ったらこのトリックの勝者を確認します。今回は全てのプレイヤーがスタートプレイヤーと同じ色のカードを出しているので単純に「一番大きな数字」を出したプレイヤー…つまり最後の人になります。

トリックの勝者となったプレイヤーは全員が出したカードをまとめて自分の前に置いておきます。これは勝利トリックの数
として他プレイヤーに公表する役割となります。
ここまでが1トリックとなりトリックを取ったプレイヤーが次のスタートプレイヤーとして最初にカードにカードを出し、次のトリックが始まります。
という感じで1回の勝負でやることはスタートプレイヤーが出したカードに合う色のカードを手札から出すだけという簡単なモノで、さらにかなり短く終わります。基本、とのトリックという勝負を繰り返すことで進んでいきます。なお、このラウンド中に手札の補充はありませんので段々と出せるカードは減っていきます。これが基本です。
すぐ思いつくでしょうが…出せるカードがなかったらどうするんだろうと思うでしょう。

例えばスタートプレイヤー(右上)が出した黒のカードに対して右下プレイヤーは青のカードを出しています。現状では別にルール違反ではないです…この後に彼が黒のカードを出さない限り(笑)

これが次にカードを出すプレイヤーの手札なんですが…黒のカードがないんですよね。トリックの回数が進んでいくにつれてこういうことはよくあります。

この場合は色違いでも良いので何のカードを出しても構いません。なので黄色のカードを出しました。
じゃあ問題となるのがトリックの勝者は誰かとなるわけですが気を付けるのは「切り札」です。
ラウンド最初に公開している切り札の色はそのラウンド中、他の色より、そしてスタートプレイヤーが指定した色よりも「強い」と定義されます。他のプレイヤーが同じように切り札色を出していない場合、どんなに数字が小さくてもトリックに勝利が出来ます。
また、切り札色ではないカードを出したプレイヤーの場合、どんなにカードの数字が大きくても勝利することは出来ません。色が違うから(笑)
あと特殊ルールが2つあるんですがとりあえず1つだけ。

同じトリック内で同色の【0】【15】が同時に場に出た場合、【0】は【15】よりも強い…要するに【16】等で扱われることになります。
とはいえ切り札色が出ている場合は負けることもありますし、スタートプレイヤーが出した色ではない場合もトリックに勝つ事は出来ませんけど。

さて、上記のようにラウンドが進む中、規定回数のトリックを獲得したプレイヤーはラウンドのプレイから抜け、得点計算をします。4~5人でプレイしている場合は3回トリックを取ったらラウンドから抜けます。残った手札はまとめてカクトクトリックとは別に置いておきます。
そして獲得できる得点はラウンドから抜けた時点での「他のプレイヤーが獲得したトリック数」です。

上の写真で手前プレイヤーが3トリックを獲得してラウンドから抜けるときの獲得点は右隣プレイヤーの2トリック、反対側の2人が1トリックずつなので4点獲得となります。
これラウンドから最初に抜けたプレイヤーの得点ということになるわけですが…

次に抜けた右隣のプレイヤーの場合の得点は手前プレイヤーの3トリックと反対側2人の1トリックずつで5点となります。つまり、後にラウンドを抜けたプレイヤーの方が獲得点は高くなります。
なので、ラウンド序盤の流れは大体トリックを獲得したくないプレイヤーが多いです(笑)
ラウンドは規定トリックを獲得したプレイヤーがどんどん抜けていき、参加するプレイヤーが最後の1人になるまで続けられます。基本的に一番獲得点が高いのは最後に抜けたプレイヤーですので、みんながその位置を狙いますが、失敗すると最後まで規定トリック数を獲得できず、無得点でラウンドが終了します。
5ラウンド目だった場合はこれでゲーム終了ですが、4ラウンドまでの場合はカードを配りなおして次のラウンドに進みます。
なお、2ラウンド目以降はラウンド最初に「カードを配り確認する」後に「切り札色を選ぶ」ことになります。
大きな変更点はこの時で、1ラウンド目はらんだむに選ばれていた切り札の色を2ラウンド目以降はスタートプレイヤー(前ラウンドで最後までプレイに残っていたプレイヤー)が独断で決めることが出来ます。
ついでに言うと、「カードを配り確認する」方が先に行われるので、スタートプレイヤーは自分の手札を見た上で切り札色を決定することが出来ます。
5ラウンド終了でゲーム終了、最も得点が高いプレイヤーが勝者となります。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
トリックテイキングの基本である「リード」「マストフォロー」「切り札」等を踏襲したオーソドックスなプレイ感覚のタイトルだと思ってたら得点計算が独特で最初はちょっと混乱する可能性があります(笑)
ゲーム自体は
…しかし、トリテ(トリックテイキング)の基礎用語を使わずに紹介するのってやっぱり長くなるんですよねー(笑)
ある程度のトリテ用語をまとめて過去ログの中に忍ばせておきましょうかね…
「Voodoo Prince」のご紹介です。
原題: Voodoo Prince
日本語タイトル: 同上(日本語版:数寄ゲームズ)
デザイナー: Reiner Knizia
発売: 2017(独)
可能人数: 2~5人
プレイ時間: 30分程度
ボックスサイズ: 125×98×24(mm)
カードサイズ: 87×57(mm)
「トリックテイキング」「ハンドマネジメント」
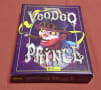
クニツィア博士の小箱ゲーム。以前から気になってたものなんですが今回数寄ゲームズさんから日本語版が出たことで確保できました。わーいわーい。
バックグラウンドとしての設定は…あまりない(笑)
いや、ブードゥーの儀式を行って霊(ロア)と交信しようって事くらいなんですよね…
ブードゥーってアフリカ土着信仰を元に、奴隷として中南米に連れてこられた黒人たちによって発展変化したものだったかと。その途中で白人の弾圧から逃れるためにキリスト教もちょっとだけ混ざったことからハイチではキリスト教徒であると同時にブードゥー信仰をされている方も多いらしいです。
なお、ブードゥー信仰はありますが「ブードゥー教」は教義として正式に伝えられているモノもなく、正統な教団もありません。山をご神体として拝むとかの山岳信仰や所謂精霊信仰に近い…ってのがウチが昔にかるくググった時の印象です。今も総本山みたいなのが無いかどうかは不勉強にて解りません。(2020/06/11)
ホラー映画で人を喰ったり感染したり頭だけになっても蠢いてたりするのを「ゾンビ」と呼称しますが、本来の「ゾンビ」はブードゥの術によって犯罪者の死体に肉体労働をさせるって感じです。術によって命じられた簡単なことしか実行できないし勝手に歩き回ったり人を食べたりもしないとのこと。
エンタメでいう(そしてボドゲで扱われるほとんどの)ゾンビは死霊術とかそっち方面です。
閑話休題。
まぁこのゲームはその辺りの事は興味がなかろうと遊べます(笑)。
ゲームは5ラウンドのトリックテイキング。5ラウンド終了時に最も得点の高いプレイヤーが勝者となります。

コンポーネントはこんな感じ。左上の色だけのカードは切り札の表示カード。見ての通り5色。
そしてその5色のブードゥーカードがあります。各色16枚。あとはサマリ。
ゲームの流れは1ラウンド目とその他のラウンドは最初の部分が少し違ってきますがそれ以外は一緒です。

まず1ラウンド目開始時に5枚の切り札カードをシャッフルし、1枚を公開することでこのラウンドの切り札カードを決定します。

その後、プレイヤーにそれぞれ規定枚数のプレイ用のブードゥーカードを配ります。プレイ人数によってカードの「使う枚数」と「配る枚数」は決まっています。
セットアップはこんなもんですね。では流れを見ていきましょう。
ゲームは1ラウンド中に「トリック」と呼ばれる小さな戦いを繰り返していきます。

「トリック」はまずスタートプレイヤーが手札からカードを1枚出すことから始まります。このカードはなんでも構いません。
で、重要なのはまず「色」、次に「数字」です。

スタートプレイヤーが出したカードを見て他のプレイヤー達が順番にカードを出していく訳ですが、この時に「色」の縛りが発生します。
スタートプレイヤーが出したカードが黒だった場合、他のプレイヤー達の手札に黒があるならば黒以外のカードを出すことが出来ないということになります。この時点では色が合っていれば数字は何でも構いません。
で、写真ではスタートプレイヤーの【黒4】から始まって【黒10】【黒12】【黒6】【黒13】と黒のカードが並びました。1ラウンド目から1色欠けてるというのは配られたカードの枚数から考えてあまりないんですよね(笑)
全員のカードが1枚ずつ出揃ったらこのトリックの勝者を確認します。今回は全てのプレイヤーがスタートプレイヤーと同じ色のカードを出しているので単純に「一番大きな数字」を出したプレイヤー…つまり最後の人になります。

トリックの勝者となったプレイヤーは全員が出したカードをまとめて自分の前に置いておきます。これは勝利トリックの数
として他プレイヤーに公表する役割となります。
ここまでが1トリックとなりトリックを取ったプレイヤーが次のスタートプレイヤーとして最初にカードにカードを出し、次のトリックが始まります。
という感じで1回の勝負でやることはスタートプレイヤーが出したカードに合う色のカードを手札から出すだけという簡単なモノで、さらにかなり短く終わります。基本、とのトリックという勝負を繰り返すことで進んでいきます。なお、このラウンド中に手札の補充はありませんので段々と出せるカードは減っていきます。これが基本です。
すぐ思いつくでしょうが…出せるカードがなかったらどうするんだろうと思うでしょう。

例えばスタートプレイヤー(右上)が出した黒のカードに対して右下プレイヤーは青のカードを出しています。現状では別にルール違反ではないです…この後に彼が黒のカードを出さない限り(笑)

これが次にカードを出すプレイヤーの手札なんですが…黒のカードがないんですよね。トリックの回数が進んでいくにつれてこういうことはよくあります。

この場合は色違いでも良いので何のカードを出しても構いません。なので黄色のカードを出しました。
じゃあ問題となるのがトリックの勝者は誰かとなるわけですが気を付けるのは「切り札」です。
ラウンド最初に公開している切り札の色はそのラウンド中、他の色より、そしてスタートプレイヤーが指定した色よりも「強い」と定義されます。他のプレイヤーが同じように切り札色を出していない場合、どんなに数字が小さくてもトリックに勝利が出来ます。
また、切り札色ではないカードを出したプレイヤーの場合、どんなにカードの数字が大きくても勝利することは出来ません。色が違うから(笑)
あと特殊ルールが2つあるんですがとりあえず1つだけ。

同じトリック内で同色の【0】【15】が同時に場に出た場合、【0】は【15】よりも強い…要するに【16】等で扱われることになります。
とはいえ切り札色が出ている場合は負けることもありますし、スタートプレイヤーが出した色ではない場合もトリックに勝つ事は出来ませんけど。

さて、上記のようにラウンドが進む中、規定回数のトリックを獲得したプレイヤーはラウンドのプレイから抜け、得点計算をします。4~5人でプレイしている場合は3回トリックを取ったらラウンドから抜けます。残った手札はまとめてカクトクトリックとは別に置いておきます。
そして獲得できる得点はラウンドから抜けた時点での「他のプレイヤーが獲得したトリック数」です。

上の写真で手前プレイヤーが3トリックを獲得してラウンドから抜けるときの獲得点は右隣プレイヤーの2トリック、反対側の2人が1トリックずつなので4点獲得となります。
これラウンドから最初に抜けたプレイヤーの得点ということになるわけですが…

次に抜けた右隣のプレイヤーの場合の得点は手前プレイヤーの3トリックと反対側2人の1トリックずつで5点となります。つまり、後にラウンドを抜けたプレイヤーの方が獲得点は高くなります。
なので、ラウンド序盤の流れは大体トリックを獲得したくないプレイヤーが多いです(笑)
ラウンドは規定トリックを獲得したプレイヤーがどんどん抜けていき、参加するプレイヤーが最後の1人になるまで続けられます。基本的に一番獲得点が高いのは最後に抜けたプレイヤーですので、みんながその位置を狙いますが、失敗すると最後まで規定トリック数を獲得できず、無得点でラウンドが終了します。
5ラウンド目だった場合はこれでゲーム終了ですが、4ラウンドまでの場合はカードを配りなおして次のラウンドに進みます。
なお、2ラウンド目以降はラウンド最初に「カードを配り確認する」後に「切り札色を選ぶ」ことになります。
大きな変更点はこの時で、1ラウンド目はらんだむに選ばれていた切り札の色を2ラウンド目以降はスタートプレイヤー(前ラウンドで最後までプレイに残っていたプレイヤー)が独断で決めることが出来ます。
ついでに言うと、「カードを配り確認する」方が先に行われるので、スタートプレイヤーは自分の手札を見た上で切り札色を決定することが出来ます。
5ラウンド終了でゲーム終了、最も得点が高いプレイヤーが勝者となります。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
トリックテイキングの基本である「リード」「マストフォロー」「切り札」等を踏襲したオーソドックスなプレイ感覚のタイトルだと思ってたら得点計算が独特で最初はちょっと混乱する可能性があります(笑)
ゲーム自体は
…しかし、トリテ(トリックテイキング)の基礎用語を使わずに紹介するのってやっぱり長くなるんですよねー(笑)
ある程度のトリテ用語をまとめて過去ログの中に忍ばせておきましょうかね…










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます