こんばんは

悠です。
最近の主流を意識し、
画像や映像が真っ先に目に入るように、
これから意識していこうと思いまして、
ちょっと導入を変えてみました。
まぁ本当は、
インパクトや、
皆さんの興味のあることを、
サムネでも見たくなるような、
キャッチーな出だしで始めるべきなんでしょうが、
あいにくとこのブログは文字が中心だったので、
ままま、
そのうちですね、
ガラっと切り替える気持ちだけはありますから、
もう少々、
くだけた文章を読むという、
ブログ本来の形にお付き合いください。
一応、
このブログ、
文章にちょっとこだわっているところもあるんですよ。
文の流れと言いますか、
目で追って、
読みやすい文章があるのですが、
このブログの文章は、
印象に残りやすいよう、
あえて、
目で見た文字を音声化しないと、
一見すると文脈が捉えずらいようにしているわけです。
例を言えば、
一応、
このブログ、
文章にちょっとこだわっているところもあるんですよ。
このブログ、
一応こだわっているところもちょっとあるんですよ。
何がどう違うのか、
この誰も興味ないことから、
私の文章を書いていく人生が始まりました。
どこがどう違うのか、
誰も興味がないこんなところから、
文章を書く、
という私の人生が始まりました。
まぁ要は言い回しですね、
読んだ人がどう印象を受けるか、
逆に自分はどう印象を与えたいのか、
こういうことを考えながら書くのも、
日本語の文章を書くというおもしろさです。
政治とか弁護とか、
そういう対外的なプロフェッショナルな世界とは違って、
私のは純粋に物語としての文章ですが。
あ、
このブログは、
完全にフリーハンドなライブ書きで、
別に高度なテクとかは使ってないですからね。
読んだらわかりますが。
話しは変わって、
人生の成功の秘訣って何かなぁと考えた時、
真っ先に思い浮かぶのが、
やっぱりタイミングかなぁと。
まぁ、
そもそも、
成功をどういう物差しで、
どういう角度で測るか、
そういう前提はありますが、
情熱を注いだ量と、
その成果による本人の満足度、
そして結果的に成功者と周囲が思う、
という観点から鑑みると、
一番重要なのは、
やっぱりタイミングだと思うようになったんですね。
もちろん、
実力とか、
努力とか、
素質とか、
環境とか、
周囲とか、
そういう様々な要因はあり、
タイミングだけで見ると、
運の要素が大きいような印象を与えますが、
でもタイミングが来るってことは、
やっぱり時流に乗ってるとか、
先見の明があるとか、
発想を転換できるとか、
呼び寄せるだけの経験と人脈があるとか、
そういうのも全部ひっくるめて考えると、
人生の成功の秘訣は、
タイミングを掴む力、
これ一点じゃないかなと。
結局、
この力がないと、
行動力や、
ポジティブ思考、
その他、
掃除や断捨離、
筋トレや運動など、
自己啓発で人生を変えようと思っても、
環境や状況、
本人の準備や心が整ってない時点で、
なにも変わらないんじゃないかと。
じゃあ、
私のような凡人以下のような者は、
どうすればいいのか。
そう考えたところで、
出る結論と言えば、
やっぱり、
継続、
これしかないわけですよ。
タイミングが来るまで待つ、
タイミングかどうかの見極める目を養う、
タイミングが来たら動き出せるようにしておく、
そして、
見誤りでも時期尚早でもなく、
また遅すぎるような後の祭りでもない、
そんなタイミングで、
満を持してチャンスを掴む。
タイミングを掴むのか乗るのか、
けっきょくはチャンスじゃないのか、
書いているうちによくわからなくなってきた今日この頃、
いかがお過ごしでしょうか。
こんばんは、
悠です(2回目)。
いやね、
このブログ
私が思っているよりも、
相当若い方が読まれているっぽいんですよ。
それも何人かの方が。
いやこのね、
文字だけの情報量がよく見たら少ないブログでも、
何かのお役に立てるかと思い、
熟語などをいっぱい並べてみました。
言ってることがよくわからなかったので、
ネペンテスのところしか読んでませんと、
悪気のない正直な告白を受けたことも過去にあります。
さ、
長くなってしまいましたが、
お待ちかね、
ここからが本当にネペンテスの時間です。
ええ、
私のブログは、
ちゃんと読んでくれた方にだけ伝われば、
それで十分な内容ですから、
ええ。
で、
前回の続きですが、
植物の手入れ、
でしたね。
まぁ植物の手入れって言うと、
水やりか、
庭でご老人が盆栽をちょっとだけチョキチョキして、
あとは眺めてるだけ、
というイメージかもしれませんが、
まぁそれはその通りです。
あとは伸びすぎた雑草や枝を刈ったり切ったりも、
まぁこれも手入れでしょう。
植物というか、
庭のお手入れかもしれませんが。
あとは野菜とか畑ですが、
私はあまり育てたことがないのでよくわかりませんが、
まぁ病害虫の予防や駆除のための、
薬剤散布や、
間引きや天地返しや畝づくりも、
まぁ手入れと表現していいんですかね。
そういう、
語弊が出そうな微妙なニュアンスや題材は、
申し訳ないですがここでは置いといて、
このネペンテスブログで言う、
ネペンテスの手入れとは、
植物体を綺麗な状態で保っておくための作業、
という形で定義したいと思います。
初心者の方はやむをえないことですが、
どうしても、
育て方とか重要情報とか、
そういうものが知りたい、
という考え方が多いですが、
ネペンテスに限って言えば、
栽培のベースとして、
温度は20度以上、
用土はミズゴケがおすすめ、
風通しのいい明るい日影がベスト、
湿度が高いほうが袋ができやすいよ、
という内容が、
考え方や言い回し、
環境や原種の特性によって、
説明が多様に変化しているだけで、
超おおまかにですが、
だいたいの言ってることは全部一緒なんですね。
いや湿度が、
用土が、
誰かがこう言ってました、
とか、
情報は沢山出てくると思いますが、
ネペンテスの生存限界点が決まっている以上、
全部がベースに対してのアレンジ、
ということになってしまうわけです。
そうは言っても、
上手く育てている人もいれば、
失敗して上手くいかなかった人もいる、
どうせなら、
上手くいく方法が知りたい、
と、
情報が溢れてる世の中で過ごしている身としては、
真っ先に思うのは当然のことです。
じゃあ初心者が正しい情報を見て、
栽培のコツを掴むには、
いったいどうしたらいいのか。
そこで私がおすすめするのが、
何度も出てきて散々引っ張ってきましたが、
このネペンテスの手入れ、
というわけです。
一見すると、
非効率で、
めちゃくちゃ遠回りな情報収集ですが、
誰もが知りたがっている、
ネペンテス本体から情報が引き出せるわけですから、
これからネペンテスを、
いや植物の栽培すらほぼ初めてという、
初心者の方にこそ、
新たな発見のベースとして、
ぜひ日ごろからやっていただきたいと思います。
さて、
実際にその手入れですが、
難しい作業は一切ありません。
ネペンテスを、
パッと見きれいな状態にすればいいわけですから、
ハサミ一つと、
水を流せる場、
そしてジョウロやシャワーがあれば、
基本的にもう十分でしょう。
ここで、
私が一番に推すのが、
専用の作業台です。
手入れをするためだけの、
専用の台を準備するわけです。
これは本当にこだわった方がいい、
と本気で思っています。
ていうか、
ぶっちゃけ、
初心者が一番力を入れれるところは、
ここしかない、
と思っています。
人には様々な事情がありますから、
場所、
時間、
家庭、
金銭、
その他もろもろ、
色々な制限がある中で、
唯一、
自分と表現を満たせる場所、
それが専用の作業台、
というわけです。
ちなみに、
これが私の手入れ専用の作業台です。

いやいやいや。
いやいやいやいや。
こだわりこだわりって、
全然なにもないじゃん、
ていうか、
花を置く、
ただのフラワーボードじゃん、
と思ったそこのあなた。
わかってないなぁ。
こだわりって、
そういうものなんですよ。
私が言うこだわりというのは、
自分にしっくりくる、
という意味で、
自分が使いやすく、
とても合っている、
ということです。
まぁ見た目とか、
ブランドとか、
そういう形で満足する場合は、
そこにはとことんこだわった方がいいですし、
テンションが上がるというのであれば、
それはとても大事なことです。
で、
今の私は、
これがとても良く合っていた、
ということです。
理由は幾つかありますが、
重要なのは、
すぐに移動できる、
台が頑丈でしっかりしている、
水が流れ落ちやすい、
物を置いた時に余計な音がしない、
組み合わせで台の形や高さが変えられる、
長すぎず短すぎない、
奥行きがない、
すぐ洗える、
腰かけとちょうどいい高さ、
植物移動の一時置きが出来る、
など、
ちょっとすぐは書ききれないのと、
一個一個の詳しい説明ができないのが残念ですが、
私が最も作業しやすい姿勢が、
防波堤でクーラーボックスに腰かけて釣りをしている、
それよりちょい低い位置、
まぁボックスというよりもバケツの高さですかね、
そこに腰を下ろす形なので、
自然とこの形に落ち着いてきた、
というわけです。
なので、
見た目が自分にとって重要であれば、
ふざけてるわけでも興味がないわけでもなく、
私としてはとことんこだわって欲しいし、
ハサミ一つにしても、
ここがこだわりどころと思ったのであれば、
メーカー品から特用品まで取り揃えて、
とことん使い倒して合うものを見つけた方がいいと思います。
要は、
他人ではなく、
自分にとってのこだわりを大事にして欲しい、
ということです。
私なんかは、
枯れた葉や抜いた草を捨てるゴミ箱も、
位置や大きさ、
持ったまますぐに移動できたり、
水だけ流れ落ちるよう形状にこだわっていますし、
誰かに動かされたり修正されたりすると、
気分を悪くするだけのこだわりはあります。
はたから見ると、
ネペンテス一つ手入れするための作業台に、
なんでそこまでこだわるのか。
すべては、
作業に集中するため、
そのただ一点です。
雑草を抜いたり、
水をかけたり、
枯れた葉を切ったりと、
時間にすれば1分もかからないようなことでも、
できれば私は、
この作業台に鉢を移して行いたいわけです。
それはただ私が、
偏屈で偏執狂なだけではないか、
という見方もありますが、
ネペンテスを本気で栽培しようと思ったら、
まずはこの作業台一つに力を入れてみるのも、
一つの手かなと。
ちょっと時間がなくなってきたので、
あとは巻きで。
私はこの作業台で、
植え替えから剪定、
土の配合や施肥に至るまで、
全部行います。
初心者の方は、
まずは、
枯れた葉のカットから始まるといいかもしれません。
よく、
枯れ始めた袋は、
どのタイミングでカットするか、
それとも残しておいた方がいいのか、
と聞かれる時がありますが、
私は基本的に、
見栄えが悪かったら、
すぐ切った方がいいですよ、
と言います。
画像がないのであれですが、
葉であれば、
このくらいの色になったら即カットですね。

一部だけ葉焼けや変色しているところは、
残しててもいかもしれませんが、
全体的に色が変わってきた葉は、
もう葉としては機能してない可能性が高いので、
早急に切ってしまった方がいいと思います。
葉や袋を早く切ってしまった方がいい理由としては、
病害虫の誘因、
用土の汚染、
上からの潅水や光の妨げ、
移動時の他の植物との接触など、
逆に残しておいた方がいい理由が思いつきません。
あとは、
最初からついているパターンがほとんどですが、
あえて自作のネームプレートを作ってみるのもおすすめです。

なんの意味が、
と思われるでしょうが、
同じ種類の系統違いで、
同じ作業台で連続で作業してしまうと、
ラベルの入れ違いや紛失で、
作業が大きくストップしてしまうことが、
マジでよくあるんですよ。
その予防策として作っておくだけで、
だいぶ安心して作業に集中できるわけです。
枯れた葉を切って、
植物を仕立ててやるだけでも、
だいぶマシに見えて、
上手く育てていると自負して自信をつけることもできます。
これは挿し木しているうちに、
時間がなくなり、
鉢に使っていたペットボトルもなくなるという、
ズボラ栽培の典型例ですが、
取り合えず一本にブスブス挿しておいたものです。

結局、
ペットボトルが用意できず、
見栄えが悪いので、
後日に取り合えず整理して挿しなおしましたが、
いま一本一本が鉢別に植えてある状態です。

これも同じような状況だったかな、
8月入ったあたりの画像なんで、
詳細を忘れてしまいました。

まぁ今は一本一本で植えられてますが、
確かユグドラシルにセットする前のスタンバイ状態の時なはずです。

これもそうですね。

いや鉢とか準備してからやれよという話しですが、
いやマジで忙しいですし、
家族から見れば空のペットボトルを集めだした、
ゴ〇屋敷の家主候補にしか見えないわけですから、
これでも最小限にするために、
苦労しているんですよほんと。

まぁまぁまぁ、
けっきょく何が言いたいかと言うと、
枯れかけてるっぽく見えてるネペンテスでも、
実はしっかり生きていて、
手入れをすればそれなりに見えますし、
よく見たら、
栽培が上手くいってるかもしれないわけです。
それを確かる目を養う一番の近道、
それが植物の手入れ、
というわけですね。
観察は続けているが、
どこをどう見たらいいか、
よくわからない、
栽培も上手くいってるか自信がない、
という方は、
ここは思い切って、
自分だけの専用台で、
ネペンテスの手入れから始めてみませんか。
見えないものが見えてくる、
いや、
見ていたはずのものに気づき始める、
そこから、
自分が知りたかった情報を再度集めなおす、
それも一つの上達方法です。
ではでは、
また次回、
お会いしましょう。

悠です。
最近の主流を意識し、
画像や映像が真っ先に目に入るように、
これから意識していこうと思いまして、
ちょっと導入を変えてみました。
まぁ本当は、
インパクトや、
皆さんの興味のあることを、
サムネでも見たくなるような、
キャッチーな出だしで始めるべきなんでしょうが、
あいにくとこのブログは文字が中心だったので、
ままま、
そのうちですね、
ガラっと切り替える気持ちだけはありますから、
もう少々、
くだけた文章を読むという、
ブログ本来の形にお付き合いください。
一応、
このブログ、
文章にちょっとこだわっているところもあるんですよ。
文の流れと言いますか、
目で追って、
読みやすい文章があるのですが、
このブログの文章は、
印象に残りやすいよう、
あえて、
目で見た文字を音声化しないと、
一見すると文脈が捉えずらいようにしているわけです。
例を言えば、
一応、
このブログ、
文章にちょっとこだわっているところもあるんですよ。
このブログ、
一応こだわっているところもちょっとあるんですよ。
何がどう違うのか、
この誰も興味ないことから、
私の文章を書いていく人生が始まりました。
どこがどう違うのか、
誰も興味がないこんなところから、
文章を書く、
という私の人生が始まりました。
まぁ要は言い回しですね、
読んだ人がどう印象を受けるか、
逆に自分はどう印象を与えたいのか、
こういうことを考えながら書くのも、
日本語の文章を書くというおもしろさです。
政治とか弁護とか、
そういう対外的なプロフェッショナルな世界とは違って、
私のは純粋に物語としての文章ですが。
あ、
このブログは、
完全にフリーハンドなライブ書きで、
別に高度なテクとかは使ってないですからね。
話しは変わって、
人生の成功の秘訣って何かなぁと考えた時、
真っ先に思い浮かぶのが、
やっぱりタイミングかなぁと。
まぁ、
そもそも、
成功をどういう物差しで、
どういう角度で測るか、
そういう前提はありますが、
情熱を注いだ量と、
その成果による本人の満足度、
そして結果的に成功者と周囲が思う、
という観点から鑑みると、
一番重要なのは、
やっぱりタイミングだと思うようになったんですね。
もちろん、
実力とか、
努力とか、
素質とか、
環境とか、
周囲とか、
そういう様々な要因はあり、
タイミングだけで見ると、
運の要素が大きいような印象を与えますが、
でもタイミングが来るってことは、
やっぱり時流に乗ってるとか、
先見の明があるとか、
発想を転換できるとか、
呼び寄せるだけの経験と人脈があるとか、
そういうのも全部ひっくるめて考えると、
人生の成功の秘訣は、
タイミングを掴む力、
これ一点じゃないかなと。
結局、
この力がないと、
行動力や、
ポジティブ思考、
その他、
掃除や断捨離、
筋トレや運動など、
自己啓発で人生を変えようと思っても、
環境や状況、
本人の準備や心が整ってない時点で、
なにも変わらないんじゃないかと。
じゃあ、
私のような凡人以下のような者は、
どうすればいいのか。
そう考えたところで、
出る結論と言えば、
やっぱり、
継続、
これしかないわけですよ。
タイミングが来るまで待つ、
タイミングかどうかの見極める目を養う、
タイミングが来たら動き出せるようにしておく、
そして、
見誤りでも時期尚早でもなく、
また遅すぎるような後の祭りでもない、
そんなタイミングで、
満を持してチャンスを掴む。
タイミングを掴むのか乗るのか、
けっきょくはチャンスじゃないのか、
書いているうちによくわからなくなってきた今日この頃、
いかがお過ごしでしょうか。
こんばんは、
悠です(2回目)。
いやね、
このブログ
私が思っているよりも、
相当若い方が読まれているっぽいんですよ。
それも何人かの方が。
いやこのね、
文字だけの情報量がよく見たら少ないブログでも、
何かのお役に立てるかと思い、
熟語などをいっぱい並べてみました。
ネペンテスのところしか読んでませんと、
悪気のない正直な告白を受けたことも過去にあります。
さ、
長くなってしまいましたが、
お待ちかね、
ここからが本当にネペンテスの時間です。
ええ、
私のブログは、
ちゃんと読んでくれた方にだけ伝われば、
それで十分な内容ですから、
ええ。
で、
前回の続きですが、
植物の手入れ、
でしたね。
まぁ植物の手入れって言うと、
水やりか、
庭でご老人が盆栽をちょっとだけチョキチョキして、
あとは眺めてるだけ、
というイメージかもしれませんが、
まぁそれはその通りです。
あとは伸びすぎた雑草や枝を刈ったり切ったりも、
まぁこれも手入れでしょう。
植物というか、
庭のお手入れかもしれませんが。
あとは野菜とか畑ですが、
私はあまり育てたことがないのでよくわかりませんが、
まぁ病害虫の予防や駆除のための、
薬剤散布や、
間引きや天地返しや畝づくりも、
まぁ手入れと表現していいんですかね。
そういう、
語弊が出そうな微妙なニュアンスや題材は、
申し訳ないですがここでは置いといて、
このネペンテスブログで言う、
ネペンテスの手入れとは、
植物体を綺麗な状態で保っておくための作業、
という形で定義したいと思います。
初心者の方はやむをえないことですが、
どうしても、
育て方とか重要情報とか、
そういうものが知りたい、
という考え方が多いですが、
ネペンテスに限って言えば、
栽培のベースとして、
温度は20度以上、
用土はミズゴケがおすすめ、
風通しのいい明るい日影がベスト、
湿度が高いほうが袋ができやすいよ、
という内容が、
考え方や言い回し、
環境や原種の特性によって、
説明が多様に変化しているだけで、
超おおまかにですが、
だいたいの言ってることは全部一緒なんですね。
いや湿度が、
用土が、
誰かがこう言ってました、
とか、
情報は沢山出てくると思いますが、
ネペンテスの生存限界点が決まっている以上、
全部がベースに対してのアレンジ、
ということになってしまうわけです。
そうは言っても、
上手く育てている人もいれば、
失敗して上手くいかなかった人もいる、
どうせなら、
上手くいく方法が知りたい、
と、
情報が溢れてる世の中で過ごしている身としては、
真っ先に思うのは当然のことです。
じゃあ初心者が正しい情報を見て、
栽培のコツを掴むには、
いったいどうしたらいいのか。
そこで私がおすすめするのが、
何度も出てきて散々引っ張ってきましたが、
このネペンテスの手入れ、
というわけです。
一見すると、
非効率で、
めちゃくちゃ遠回りな情報収集ですが、
誰もが知りたがっている、
ネペンテス本体から情報が引き出せるわけですから、
これからネペンテスを、
いや植物の栽培すらほぼ初めてという、
初心者の方にこそ、
新たな発見のベースとして、
ぜひ日ごろからやっていただきたいと思います。
さて、
実際にその手入れですが、
難しい作業は一切ありません。
ネペンテスを、
パッと見きれいな状態にすればいいわけですから、
ハサミ一つと、
水を流せる場、
そしてジョウロやシャワーがあれば、
基本的にもう十分でしょう。
ここで、
私が一番に推すのが、
専用の作業台です。
手入れをするためだけの、
専用の台を準備するわけです。
これは本当にこだわった方がいい、
と本気で思っています。
ていうか、
ぶっちゃけ、
初心者が一番力を入れれるところは、
ここしかない、
と思っています。
人には様々な事情がありますから、
場所、
時間、
家庭、
金銭、
その他もろもろ、
色々な制限がある中で、
唯一、
自分と表現を満たせる場所、
それが専用の作業台、
というわけです。
ちなみに、
これが私の手入れ専用の作業台です。

いやいやいや。
いやいやいやいや。
こだわりこだわりって、
全然なにもないじゃん、
ていうか、
花を置く、
ただのフラワーボードじゃん、
と思ったそこのあなた。
わかってないなぁ。
こだわりって、
そういうものなんですよ。
私が言うこだわりというのは、
自分にしっくりくる、
という意味で、
自分が使いやすく、
とても合っている、
ということです。
まぁ見た目とか、
ブランドとか、
そういう形で満足する場合は、
そこにはとことんこだわった方がいいですし、
テンションが上がるというのであれば、
それはとても大事なことです。
で、
今の私は、
これがとても良く合っていた、
ということです。
理由は幾つかありますが、
重要なのは、
すぐに移動できる、
台が頑丈でしっかりしている、
水が流れ落ちやすい、
物を置いた時に余計な音がしない、
組み合わせで台の形や高さが変えられる、
長すぎず短すぎない、
奥行きがない、
すぐ洗える、
腰かけとちょうどいい高さ、
植物移動の一時置きが出来る、
など、
ちょっとすぐは書ききれないのと、
一個一個の詳しい説明ができないのが残念ですが、
私が最も作業しやすい姿勢が、
防波堤でクーラーボックスに腰かけて釣りをしている、
それよりちょい低い位置、
まぁボックスというよりもバケツの高さですかね、
そこに腰を下ろす形なので、
自然とこの形に落ち着いてきた、
というわけです。
なので、
見た目が自分にとって重要であれば、
ふざけてるわけでも興味がないわけでもなく、
私としてはとことんこだわって欲しいし、
ハサミ一つにしても、
ここがこだわりどころと思ったのであれば、
メーカー品から特用品まで取り揃えて、
とことん使い倒して合うものを見つけた方がいいと思います。
要は、
他人ではなく、
自分にとってのこだわりを大事にして欲しい、
ということです。
私なんかは、
枯れた葉や抜いた草を捨てるゴミ箱も、
位置や大きさ、
持ったまますぐに移動できたり、
水だけ流れ落ちるよう形状にこだわっていますし、
誰かに動かされたり修正されたりすると、
気分を悪くするだけのこだわりはあります。
はたから見ると、
ネペンテス一つ手入れするための作業台に、
なんでそこまでこだわるのか。
すべては、
作業に集中するため、
そのただ一点です。
雑草を抜いたり、
水をかけたり、
枯れた葉を切ったりと、
時間にすれば1分もかからないようなことでも、
できれば私は、
この作業台に鉢を移して行いたいわけです。
それはただ私が、
偏屈で偏執狂なだけではないか、
という見方もありますが、
ネペンテスを本気で栽培しようと思ったら、
まずはこの作業台一つに力を入れてみるのも、
一つの手かなと。
ちょっと時間がなくなってきたので、
あとは巻きで。
私はこの作業台で、
植え替えから剪定、
土の配合や施肥に至るまで、
全部行います。
初心者の方は、
まずは、
枯れた葉のカットから始まるといいかもしれません。
よく、
枯れ始めた袋は、
どのタイミングでカットするか、
それとも残しておいた方がいいのか、
と聞かれる時がありますが、
私は基本的に、
見栄えが悪かったら、
すぐ切った方がいいですよ、
と言います。
画像がないのであれですが、
葉であれば、
このくらいの色になったら即カットですね。

一部だけ葉焼けや変色しているところは、
残しててもいかもしれませんが、
全体的に色が変わってきた葉は、
もう葉としては機能してない可能性が高いので、
早急に切ってしまった方がいいと思います。
葉や袋を早く切ってしまった方がいい理由としては、
病害虫の誘因、
用土の汚染、
上からの潅水や光の妨げ、
移動時の他の植物との接触など、
逆に残しておいた方がいい理由が思いつきません。
あとは、
最初からついているパターンがほとんどですが、
あえて自作のネームプレートを作ってみるのもおすすめです。

なんの意味が、
と思われるでしょうが、
同じ種類の系統違いで、
同じ作業台で連続で作業してしまうと、
ラベルの入れ違いや紛失で、
作業が大きくストップしてしまうことが、
マジでよくあるんですよ。
その予防策として作っておくだけで、
だいぶ安心して作業に集中できるわけです。
枯れた葉を切って、
植物を仕立ててやるだけでも、
だいぶマシに見えて、
上手く育てていると自負して自信をつけることもできます。
これは挿し木しているうちに、
時間がなくなり、
鉢に使っていたペットボトルもなくなるという、
ズボラ栽培の典型例ですが、
取り合えず一本にブスブス挿しておいたものです。

結局、
ペットボトルが用意できず、
見栄えが悪いので、
後日に取り合えず整理して挿しなおしましたが、
いま一本一本が鉢別に植えてある状態です。

これも同じような状況だったかな、
8月入ったあたりの画像なんで、
詳細を忘れてしまいました。

まぁ今は一本一本で植えられてますが、
確かユグドラシルにセットする前のスタンバイ状態の時なはずです。

これもそうですね。

いや鉢とか準備してからやれよという話しですが、
いやマジで忙しいですし、
家族から見れば空のペットボトルを集めだした、
ゴ〇屋敷の家主候補にしか見えないわけですから、
これでも最小限にするために、
苦労しているんですよほんと。

まぁまぁまぁ、
けっきょく何が言いたいかと言うと、
枯れかけてるっぽく見えてるネペンテスでも、
実はしっかり生きていて、
手入れをすればそれなりに見えますし、
よく見たら、
栽培が上手くいってるかもしれないわけです。
それを確かる目を養う一番の近道、
それが植物の手入れ、
というわけですね。
観察は続けているが、
どこをどう見たらいいか、
よくわからない、
栽培も上手くいってるか自信がない、
という方は、
ここは思い切って、
自分だけの専用台で、
ネペンテスの手入れから始めてみませんか。
見えないものが見えてくる、
いや、
見ていたはずのものに気づき始める、
そこから、
自分が知りたかった情報を再度集めなおす、
それも一つの上達方法です。
ではでは、
また次回、
お会いしましょう。
















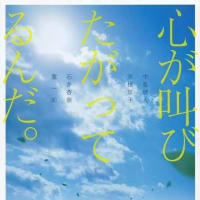





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます