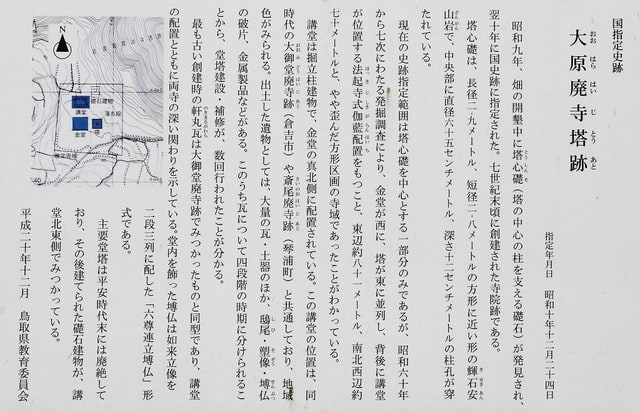景行天皇(屋主忍男武雄心命)は倭姫命が亡くなった後、都を奈良の纒向に移したが豊鋤入姫命は都を鳥取県中部(倭)に戻した
1 魏志倭人伝に「卑弥呼は死に、塚を大きく作った。直径は百余歩。徇葬者は男女の奴隷、百余人である。さらに男王を立てたが、国中が不服で互いに殺しあった。当時千余人が殺された。また、卑弥呼の宗女、十三歳の壹與を立てて王と為し、国中が遂に安定した。張政たちは檄をもって壹與に教え諭した。壹與は大夫の率善中郎将、掖邪拘等二十人を遣わして、張政等が帰るのを送らせた」とある。
「梁書倭国伝」「北史倭国伝」では「臺與」と記述されている。「壹與」は正しい表記ではなく「臺與」(とよ)が正しいと思われる。国史で「とよ」とは豊鋤入姫である。もともと倭姫命と豊鋤入姫命の巡行は時代も目的も違うものであった。藤原氏は伊勢神宮の由緒を創るために、同じ目的で引き継いだとする倭姫命世記を創作した。順番も書き換えた。日本書紀の系譜も書き換えた。
2 10代天皇から12代天皇までの問題となる系譜
⑴ 崇神天皇(本拠地は岡山県津山市中山神社)
皇后:御間城姫(御真津比売命) ー 大彦命(孝元天皇の皇子)の娘
◎活目入彦五十狭茅尊
妃:遠津年魚眼眼妙媛 ー 紀伊国(木国=津山市)荒河戸畔の娘
◎豊鍬入姫命 ー 史実は彦太忍信の娘であった
⑵ 垂仁天皇(本拠地は岡山県美咲町大宮神社)ー 彦太忍信か
皇后:日葉酢媛命(丹波道主王の娘)
◎五十瓊敷入彦命、大足彦忍代別尊 ー この位置は屋主忍男武雄心命である
◎葛木志志見興利木田忍海部刀自(住吉大社神代記による) ー 豊鋤入姫(台与)であり神功皇后
◎倭姫命 ー 史実は孝霊天皇皇女であった
妃:迦具夜比売(かぐやひめ)。 ー 開化天皇の曾孫(ひまご)。
⑶ 景行天皇(屋主忍男武雄心命)皇居は纒向日代宮 ー 屋主忍男武雄心命か
皇后:播磨稲日大郎姫 ー 若建吉備津日子の娘 ー この位置は津山市にいた影姫であった
◎大碓命 ー 身毛津君(牟宜都国造)等祖
◎小碓命(倭建命=若日子建吉備津日子) ー この位置は武内宿禰であった
妃:迦具漏比売(かぐろひめ)。 ー 倭建命の曾孫(ひまご)。
※ 私見
古事記によれば景行天皇には80人の御子がいたことになっている。また、古事記では「倭建命(小碓命)の曾孫(ひまご)の迦具漏比売(かぐろひめ)が景行天皇の妃となって大江王(彦人大兄)をもうける」とするなど矛盾があり、このことから景行天皇と倭建命との親子関係に否定的な説がある。
また、景行天皇自身に纏わる話は全くと言ってよいほど出てこないので、景行天皇が実在した可能性は低いとする説も少なくない。
3 屋主忍男武雄心命について
正しいと思われる史料
「紀氏系図」では、孝元天皇皇子に彦太忍信命、その子に屋主忍雄命、その子に武内宿禰と甘美内宿禰とする。
「日本書紀」によると、天皇は紀伊(御真木国=津山市)に行幸して神祇祭祀を行おうとしたが、占いで不吉と出たため、代わりに武雄心命が遣わされた。武雄心命が阿備柏原(津山市)にて留まり住むこと9年、その間に影媛との間に武内宿禰を儲けた。
「古事記」では「木国造の宇豆比古の妹の山下影日売を娶って建内宿禰(武内宿禰)を生む」とある。
「梁書倭伝」に「また卑彌呼の宗女、臺與を立てて王にした。その後、また男王が立ち、並んで中国の爵命を受けた」(復立卑彌呼宗女臺與為王 其後復立男王並受中國爵命)とある。
※ 私見
紀国・紀伊国は木国の読みを別漢字に直したものであり、木国とはもとは岡山県津山市のことであった。
孝元天皇・開花天皇・崇神天皇は孝霊天皇の皇子であり兄弟承継をしていた。従って、11代垂仁天皇と彦太忍信命は「いとこ」、12代景行天皇と屋主忍男武雄心命は「またいとこ」になり年代的に一致する。
豊鋤入姫(台与)は彦太忍信の子であり12代屋主忍男武雄心大王の妹になる。武内宿禰は12代屋主忍男武雄心の子であり13代男王であった。13代武内宿禰大王は女王の叔母の豊鋤入姫(臺與)と一緒に行動していた。
11代倭国大王は垂仁か彦太忍信かは現時点では不明であるが、「住吉大社神代記」によると、彦太忍信には葛木志志見興利木田忍海部刀自という娘がいたとする。彼女が豊鋤入姫(神功皇后)であった可能性が高い。彼女は牟賀足尼命と嶋東乃片加加奈比女の子である田乃古乃連と結婚し、古利比女、久比古、野乃古連を生んだという。神功皇后(豊鋤入姫)は倉吉市上神におり、倉吉市北面で出産したという伝承がある。倉吉市上神・北面は葛木地域にあたる。
「梁書倭伝」にある男王は武内宿禰大王であった。豊鋤入姫の甥の武内宿禰は13代倭国大王となり、鳥取県北栄町原の元野神社に皇居をおいた。父親ほどではないが多くの御子を作った。記紀の神功皇后のモデルは豊鋤入姫命と思われるが、百済色に強く染めてあり、新羅と兄弟国であった倭の姫とはかけ離れている。百済が新羅を攻めた時のことを原古事記にあった豊鋤入姫の事績を用いて創作した物語が神功皇后ではないかと思われる。藤原氏による改ざん創作物語である。
4 迦具夜比売と迦具漏比売、大碓命と小碓命について
※ 私見
景行天皇は106歳まで生きたのだから皇子のひ孫を「妃」と出来るかもしれない、という説があるが、不可能である。
垂仁天皇の系譜に「迦具夜比売(かぐやひめ)は開花天皇の曾孫(ひまご)」とある。開花天皇は垂仁天皇の2代前なので、迦具夜比売は開花天皇の孫ならおかしくない。開花天皇の曾孫(ひまご)であれば迦具夜比売は景行天皇の妃がふさわしい。
迦具夜比売と迦具漏比売は姉妹であり二人とも景行天皇の妃であったと思われる。原古事記には「開花天皇(倭建命)の曾孫(ひまご)の迦具夜比売(姉)と迦具漏比売(妹)は景行天皇の妃となって・・・」とあった。倭建命と開花天皇は同一人物であった。
このように、古事記・日本書紀の系譜は改ざんが多い。豊鋤入姫命も倭姫命も改ざんされている。豊鋤入姫命の父は彦太忍信命であり、倭姫命の父は孝霊天皇であった。
大碓命・小碓命の物語も大吉備津日子(崇神天皇)と若日子建吉備津日子(開花天皇)をモデルにした創作であった。小碓命(倭建命)の位置は武内宿禰でなくてはならない。
景行天皇は実在せず、その時の倭国大王は屋主忍男武雄心命であった。
5 魏志倭人伝によると「国中が服さず、更に互いが誅殺しあった」とある。なぜ、男王に服さなかったのであろうか。
崇神天皇、垂仁天皇の活動本拠地は岡山にあったが、皇居は鳥取県湯梨浜町(師木)に置いていた。男王の皇居は鳥取県湯梨浜町(師木)に置いていたが、都は女王倭姫命(卑弥呼)の住む志摩国であった。神道の各地の代表者は奈良の纒向に集まり倭姫命の祭祀に参加していた。倭姫命(卑弥呼)が亡くなってから景行天皇(屋主忍男武雄心命)は都を奈良の纒向に遷したが子孫を増やすことに専念しており、倭姫命のようにうまく祭祀ができなかった。倭朝廷に深く関係する一族のいた地域では失望して誅殺しあった。景行天皇(屋主忍男武雄心命)は国中が不服の状態を見過ごすことはできず倭姫命に代わる女王を立てなければならなかった。景行天皇(屋主忍男武雄心命)は妹の豊鋤入姫に誅殺しあっている地域を巡行させ、鳥取県中部(倭)に本拠地を置かせることにした。

豊鋤入姫が巡行した本当の比定地は以下の通りであった。
(1)倭の笠縫邑(鳥取県琴浦町八橋)(2)但波の吉佐宮(京丹後市丹後町の竹野神社)(3)倭の伊豆加志本宮(鳥取県倉吉市長谷集落長谷神社)(4)木乃国奈久佐浜宮(津山市二宮の高野神社)(5)吉備国名方浜宮(倉敷市上東)(6)倭の弥和乃御室嶺上宮(鳥取県北栄町下神の三輪神社)。
別稿「倭姫命世記において豊鋤入姫の巡行した本当の比定地」を参照されたし。
豊鋤入姫(台与)は鳥取県北栄町下神の三輪神社で祭祀をしたあと、倉吉市鋤集落を本拠地にした。
第13代倭国男王の武内宿禰は鳥取県北栄町原の元野神社に皇居を置いた。