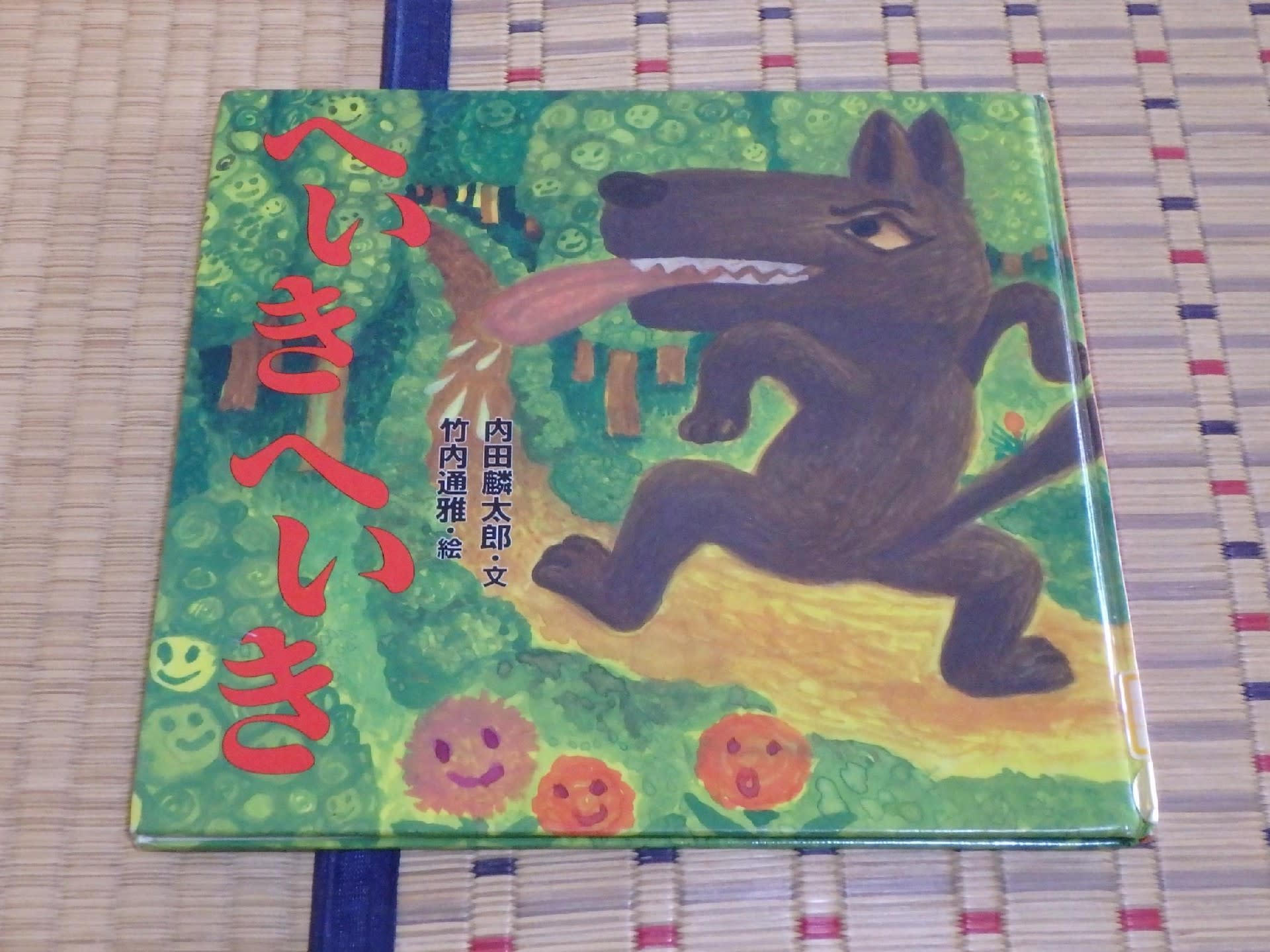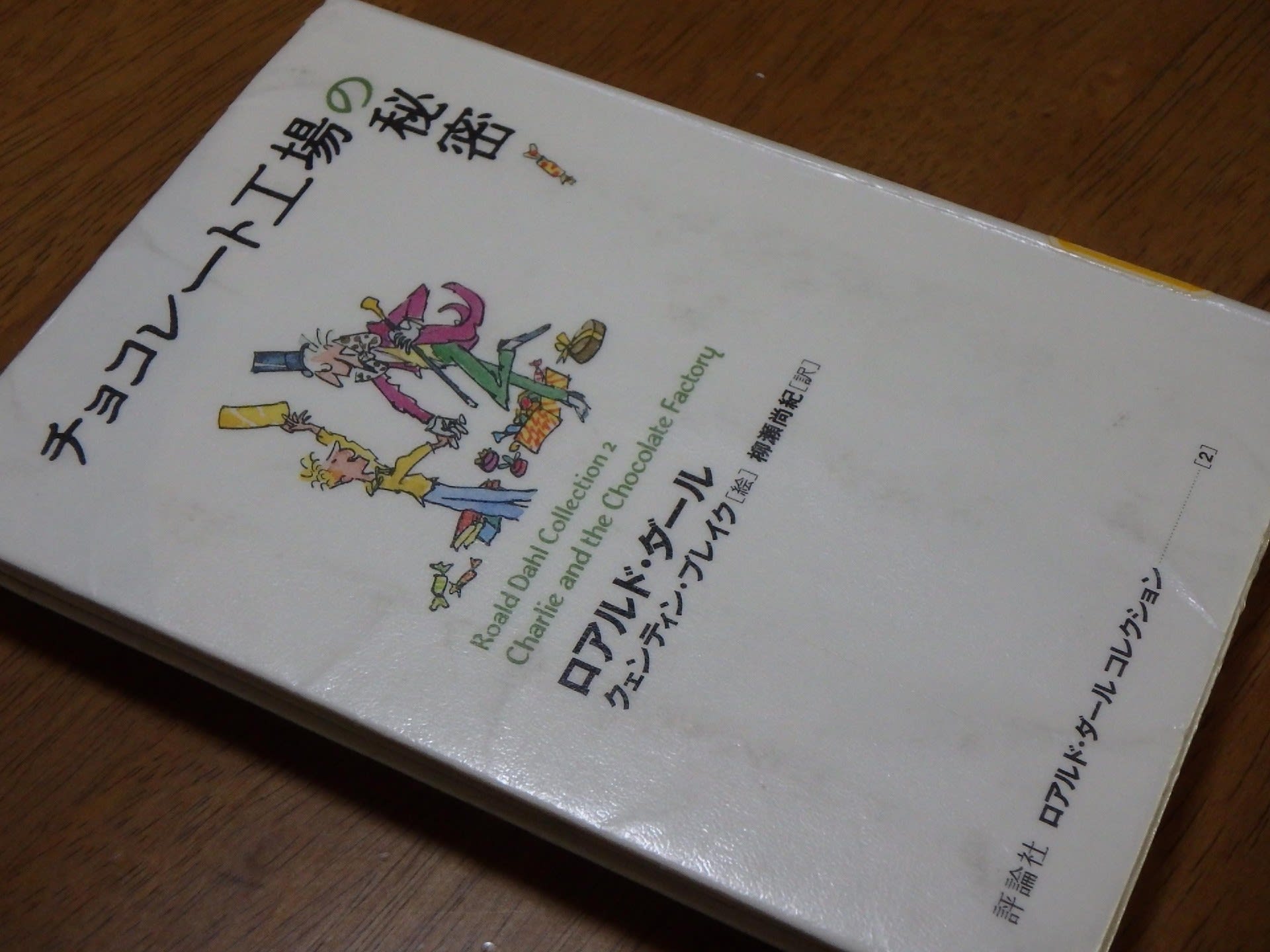「む」と「め」は3冊ずつ、計6冊ご紹介します。
 ムニャムニャゆきのバス 長新太 偕成社
ムニャムニャゆきのバス 長新太 偕成社

また借りてしまいました(笑)、長さんの絵本。
ベエーベエーというバスのブザーの音が最初から印象的でしたが、アカンベエーのベエーなのね。
長さんワールドの奇想天外な存在が次から次へと、バスから降りてくるのは良いけどこのバスに乗る人が誰もいないのが面白い。
トンネルの中だとベエーベエーも少し小さく聞こえる(笑)
ムニャムニャを目指していくバスから途中下車するこれらのあらゆる存在たちは、それぞれ、どこへ行くのだろうか。
そしてバスそのものの行先であるムニャムニャとは?ネタバレっぽくなってしまうけど、最後のページにあるとおり、わからないから面白い。
 ムーミン谷へのふしぎな旅 トーベ・ヤンソン作 渡部翠 訳 講談社
ムーミン谷へのふしぎな旅 トーベ・ヤンソン作 渡部翠 訳 講談社

「む」と言ったらやっぱりムーミンでしょう(笑)
この絵本に出てくるスサンナという女の子(ムーミン全集には出て来ないキャラクター)は普通の人間のよう。
ムーミン谷を目指す旅の途中、あべこべ世界での冒険のシーンは、干上がった海や火山の爆発が『ムーミン谷の彗星』を思わせるし、吹雪のシーン(言葉では出て来ないけど絵ではモランも登場)では『ムーミン谷の冬』を思わせます。
途中ではスナフキンも出てくるし、トゥーティッキ(おしゃまさん)は頼もしいし、最後の、ムーミン谷に到着した見開きの絵ではミイやパパ、ママ、ミムラ姉さん、そしてムーミントロールなどおなじみの、懐かしい顔ぶれが出てきて嬉しい。
ムーミンシリーズを愛読したことのある人で、ムーミン谷に行ってみたいと思ったことがない人などいるのだろうか?
 むらさきふうせん 作・クリス・ラシュカ 訳・谷川俊太郎 BL出版
むらさきふうせん 作・クリス・ラシュカ 訳・谷川俊太郎 BL出版

小さなサイズの可愛い絵本で、訳が谷川俊太郎さんなので迷わず選んだけれど、前書きを読んでみたらかなり重い内容でした。
自分の死が近いことを意識するようになったこどもは、よく、「今の気持ちを絵に描く」機会を与えられると、青や紫の風船が手から離れて飛んでいく絵を描くそうです。
ホスピスなどで、死に近づきつつある人たちのために働いている人たちはそういういわば現象をしばしば目にするのでしょう。
お年寄りがなくなるのは悲しい。でも、こどもがその命の灯を思う存分輝かせる前に死んでしまうのは言葉にできないくらい悲しいことです。
いまこの瞬間も、病気で自由に外を走り回ることもできずにいる子供たちが日本にも世界中にもたくさんいることを思うと、自分の日常生活でツライと思うことなど何でもないと思えます。
そういうこどもたちの夢をかなえる Make a Wish という団体があって、寄付をした後に送られてきた会報を読むと、病気のこどもたちの「夢」で、ディズニーランドに行きたい、という夢が本当に多くて驚きました。
微力ながら、これからも支援させていただきたいと思います。
この絵本と Make a Wish は関係ないのですけど、ご紹介しました。
「死」ってなんなんでしょうね。。。『ピーターパン』で、ピーターが死はきっとすごい冒険だぞ、と言って胸を張っている絵を見て感心したのですが、死のことをそんな風に、新しい旅に旅立つかのように、むしろ楽しみとさえ思えるくらいになれたらすごいのでしょうけど。。。
 めがねうさぎ 作・絵 せなけいこ ポプラ社
めがねうさぎ 作・絵 せなけいこ ポプラ社

「お」で紹介した『おばけのてんぷら』でも出てきたうさことおばけ。
「めがねうさぎ」と友達に呼ばれてちょっと恥ずかしくもありちょっと得意でもあるうさこが可愛いです。
この作品でもこわいお化けに気づかないというのは、『おばけのてんぷら』と同じく、めがねをなくしてよく見えないせい。
おおらかなうさこは、本当は自分を怖がらせようとしているおばけのことも「親切だなあ」と思ってにこにこしています。
いつも穏やかなほほえみを浮かべているうさこのように、おっちょこちょいだけどおおらかな人になりたいですね。
うさこのめがねを探すおばけが汗ぐっしょりというのが笑えます。おばけも汗をかくんだ(笑)
 めざめる 阿部海太 あかね書房
めざめる 阿部海太 あかね書房

言葉がとても短くて、全体で小さな、研ぎ澄まされた詩のよう。
朝、めざめるという何気ないことから、「問い」は宇宙レベルにまで広がっていく。
様々な感覚。気持ち。
確かに、夢を見ている時のわたしは一体、誰なのだろう。
最後の言葉の見開きページに、絵がなくて真っ白なページなのがちょっとハッとします。
この問いの答えがわかったら、怖い気もする。
 めをとじてみえるのは マック・バーネット ぶん イザベル・アルスノー え まつかわまゆみ やく 評論社
めをとじてみえるのは マック・バーネット ぶん イザベル・アルスノー え まつかわまゆみ やく 評論社

大きめの本です。
寝る前にお父さんにあれこれ質問する、好奇心旺盛な女の子。
お父さんの表情が、「困ったな」というふうに見えるときもあれば質問に答えるのを楽しがっているように見えるときも。
お父さんの答えがどれも夢があって感心します。
質問攻めの見開きページがあるけど、私だったらどれ一つとして、夢のある答えが思い浮かばない(汗)
寝る前の暗い部屋のイメージに沿って、どの絵も黒やグレー+黄色、黒やグレー+緑、といった控えめな色合いですが、最後の夢の世界はカラフル。
こどもも大人も、夜、素敵な夢が見られたら幸せですよね。
さて、「も」の絵本はどんなのを選ぼうか、楽しみです。
私の大好きなあの果物(笑)関連もあるかな?
コメント欄閉じています。読んでくださってありがとうございました












 も、氷も、滝も、草の上の露も、虹
も、氷も、滝も、草の上の露も、虹 も、川も、湖も、そして海
も、川も、湖も、そして海 も。
も。







 の女湯に目が行ってしまった(笑) 大丈夫、ちゃんと見えないようにたくさんのみかんが隠してくれています(笑)
の女湯に目が行ってしまった(笑) 大丈夫、ちゃんと見えないようにたくさんのみかんが隠してくれています(笑)


 は何世代が生きたのだろうと思ってしまいました。
は何世代が生きたのだろうと思ってしまいました。


 を拾って、それをタネのようにまいたら芽が出て木に育ち。。。
を拾って、それをタネのようにまいたら芽が出て木に育ち。。。