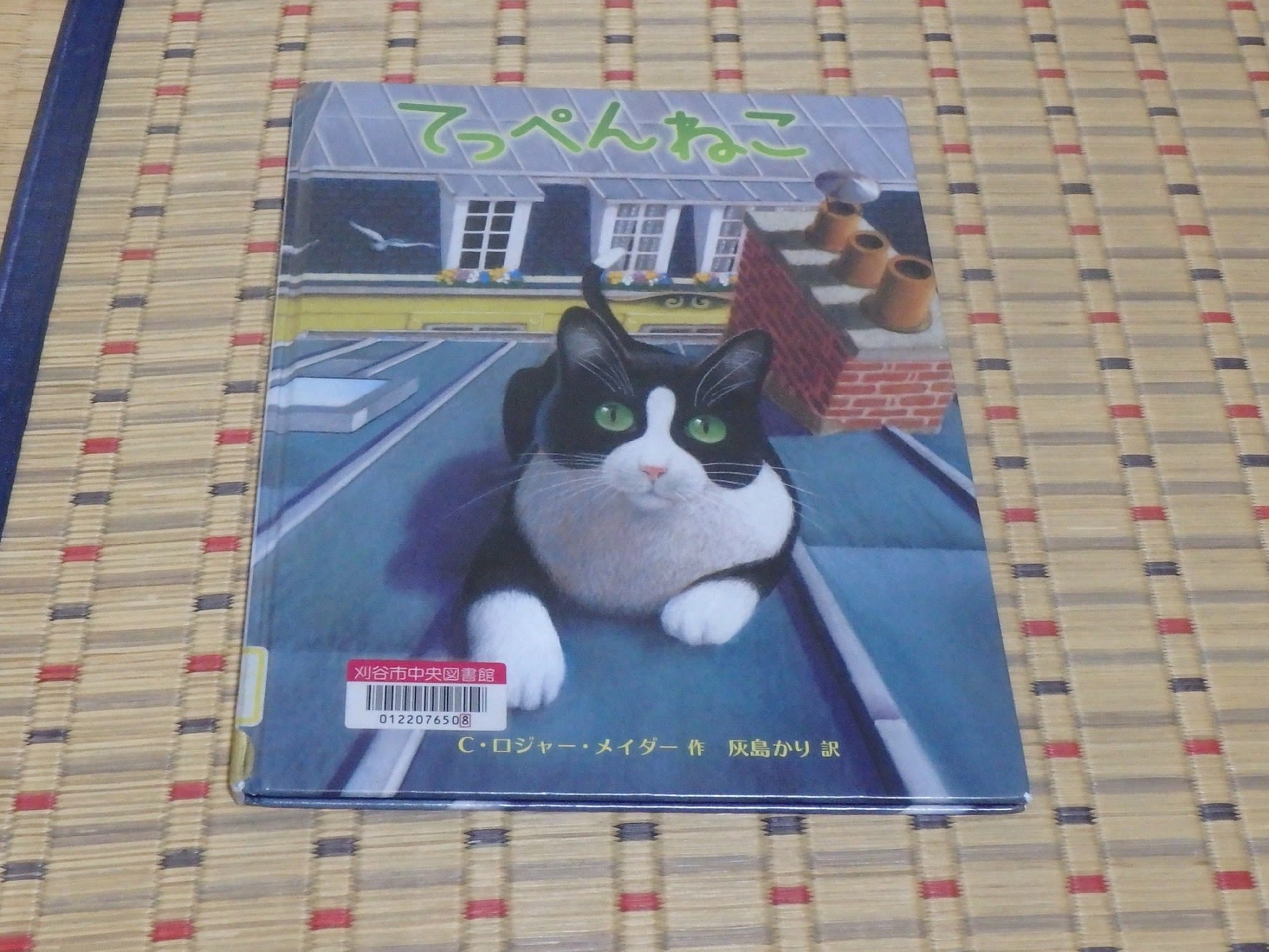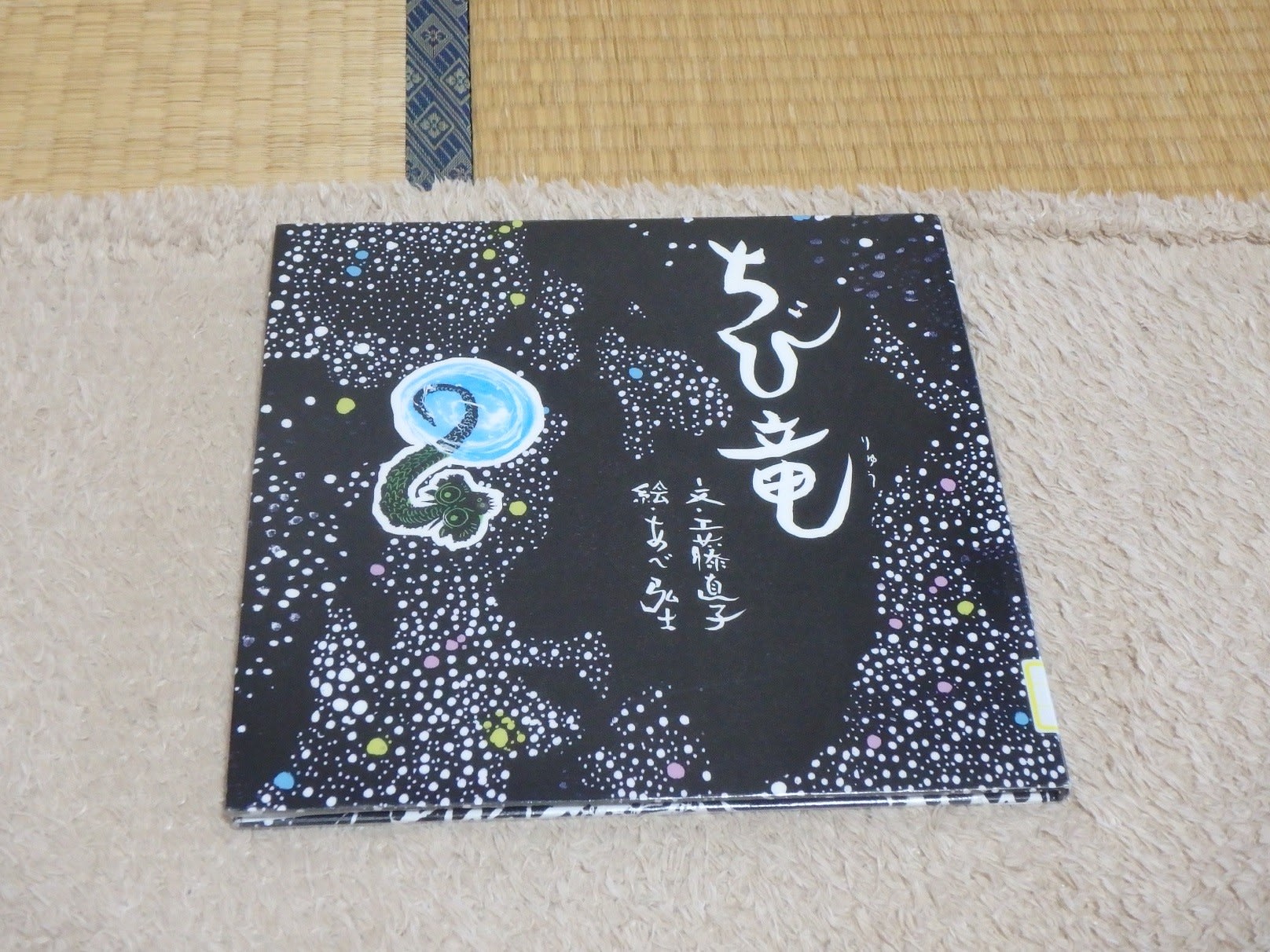「な」の絵本2巡目は3冊とも日本の作品です。
 ナキウサギの山 本田哲也 偕成社
ナキウサギの山 本田哲也 偕成社

氷河期の頃に北海道に渡ってきて、その後も大雪山に生息し、「氷河期の生き残り」と言われるナキウサギのことをどれだけの人が知っているのだろう。
ただ、大雪山系に登ってその姿を見、虜になってしまった人は少なくない。
この絵本も、そんな作者さんが自らのナキウサギとの出会い、そして再会や観察の様子を描いています。
耳が短く、そして鳴くということから、ナキウサギはうさぎの仲間としてはかなり個性的だけれど、たくさんの天敵たちにも負けず懸命に生きるたくましさ、その可愛らしさが本田さんの絵にとても良く表現されています。
 なんにもできなかったとり 刀根里衣 NHK出版
なんにもできなかったとり 刀根里衣 NHK出版

ページ数は多いけれど、ミッフィーの絵本のように左が文字ページ、右が絵で、その文字もほんの1行から数行なのでどんどん読めます。
鳥なのに飛べず、歌えず、木の実も取れない、タイトル通りなんにもできなかったとりが、最後には。。。
強い意志と優しい心の大切さが伝わってきます。刀根さんのファンタジックな可愛らしい絵にも癒されます。
 ならの木のみた夢 やえがしなおこ 文 平澤朋子 絵 アリス館
ならの木のみた夢 やえがしなおこ 文 平澤朋子 絵 アリス館

サイズは小さな本ですが、文字が多くて読みごたえがあり、内容的にも大人向けの絵本かなと感じました。
絵本の世界では、木と人間の寿命の長さの違いからくるせつないストーリーが少なくないですが、この作品もその一つ。
小さな男の子がしてくれた約束を待ち続けるならの木。待ち続ける間に男の子は大人になり、老人になり。。。
四十雀の「急いで急いで。おまつりは、すぐすんでしまうよ」「急いで急いで。おまつりはもう半分すぎた」「もう時間がない。おまつりは終わってしまう」という言葉になんだかドキッとする。
ドキッとするのも、子供の読者ではなく私自身が大人だからですね。
それにしても木は、夢を見るのだろうか。
雨の日も風の日も、晴れた日もその場に立ち続け、春夏秋冬、そこにいる。そんな木が、夢を見ないなどと誰が言えるでしょう。
次は「に」からはじまる絵本の2巡目です。