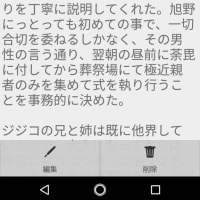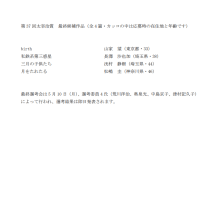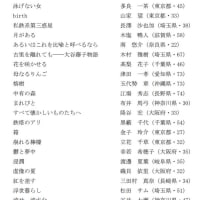7月中旬。
僕たちは午前6時半発のフェリーに乗り込んだ。結局フェリーの上でも特に具体的な説明はなかったが,僕以外にベネディクト,マシュー,ゲイリーという3人,いずれもイギリス国籍の仲間がいて,スイスで簡単な訓練を受けてから様々な地域へ散らばる旨の予定が告げられた。
「肉体はただの“器”だから,その使い方が自分達の課題なのだ」といった内容の説教を受けてから「万一に備えて」家族への遺書を書くように言われて,船旅を楽しむ余裕を一気に奪われてしまった。遺書なんて書くのは勿論初めてのことだったし,渡されたカードに両親や姉弟へ宛てた一言ずつを綴っていると死の恐怖が現実味を帯びて何だか悲しい気持ちになった。
ドーバーまではそれぞれ別の牧師が同行して来たが,フェリーに乗ってからは物静かなフランス人が1人で僕たちの船頭を務めていて,淡々と予定説明を終えた後,船内のラウンジで読書をしながら僕たちの遺書の提出を待っていた。彼が小さく頷きながら無言で遺書を受けとる強ばった表情が印象的だった。
カレーに到着するとそのまま牧師が運転する赤いフォードエスコートに乗り込んでブリュッセルの「本部」という所へ向かった。2時間ほどのドライブの間,緊張からか僕たちはほとんど口を開くことはなかったから時間が物凄く長く感じられた。
本部ではパスポート等の荷物を預けてから予め用意されていた薄いカーキー色の作業服に着替えさせられた。爪先に鉄板が入った安全靴はサイズが4種類しかないので履いたときに少し余裕のあるものを選んで踝まである紐で調節しなければならなかった。
ドーバーから一緒になった4人でせっせと着替えていると,続々と別のグループが到着して,1時間程の間に21人のボランティアと8人の牧師で部屋が一杯になった。すると更にグループ分けが行われて,僕はイギリスから一緒だったゲイリーという「イギリス生まれの中国人」と一緒に,フランスから来たジェイ,パトリック,ラファエルと5人でアジャの住む国の手前にある「基地」と呼ばれる場所へ向かうことを確認した。皆物腰が優しい好青年だったが,ジエイは僕には関心がないといったあからさまな素振りを見せた。メンバーのほとんどが敬虔なクリスチャンで皆一様に十字架のアクセサリーを大切そうに上着のポケットに入れていた。いきなり跪いて黒表紙の聖書を開いた途端数人で祈り始めるグループもいて少し居心地が悪かった。準備が整うと10ポンド程度だという少額な現地の通貨が配られ,ようやく出発となった。
ブリュッセルからは全員マイクロバスに乗り込み,更に7時間程かけてスイスに入った。そこで初めて射撃訓練を受けると告げられた。人助けのつもりで参加したはずなのに人を撃つ訓練を受けなければならないという矛盾に一抹の不安を感じるのと同時に,遺書を書いたときに感じた死の存在が再び僕の脳裏で渦巻いたが,他の誰もが動揺する様子もなく質問する者もいなかったから仕方なく黙って指示に従った。
迷彩服を着用した背の高いスイスの兵士数人から2時間ほどかけて様々な距離に設置された皿のような金属の板を撃ったり,分解や組み立てなどの練習をして一通りピストルの扱い方を教わると, 新しい弾丸が7発ずつマガジンに装填された状態で支給された。そして休息を取ることもなく其々用意されたトラックに便乗し現地に向かうことになった。ベルンの日暮れはイギリスと同じくらいで遅いらしく,腕時計を確認すると既に午後10時前くらいだった。
最初は柔いサスペンションのせいで船酔いの様な嫌な感覚に苦しんでいたが,嘔吐するまで酷いことはならずに済んだ。疲れていただけかも知れないが,そのうちトラックの荷台の簡易シートに横向きに座っていても,幌を支える細いバーに寄りかかってぐっすり眠れるまで慣れた。未だに自分が置かれた世界に対して疑いを抱きながらアジャに会えるかもしれないという奇跡を信じて気持ちは少しだけ高揚していた。
トラックが何度か燃料補給するのに立ち寄る場所で用を足したりしながら,基地に到着したのは明くる日の夕方だった。確か国連の介入は公式に発表されてはいなかったが,両側面に「UN」と言う文字が大きく書かれた白い装甲車が3台,同じく白い塗装が施された車両が数台整然と駐車してあって,周囲には青いヘルメットカバーを掛けた兵士達がのんびりと寛いでいた。僕たちが到着すると,彼らが着用している草色のものとは違う土色に近い僕たちの服装に気付いたのか,じっとこちらに視線を向けている者もいた。
僕たちは食事も取らされずに基地に横付けしてあった大きなトレーラーから数台のトラックに支援物資を積み替える任務についた。誰もが疲労感の局地にあったはずだが窮屈な荷台から解放されてホッとした様子だった。僕はと言えば,漠然とではあったが,アジャの傍に1ミリでも近づけた様な感覚に絵も言えぬ嬉しさを禁じ得ず軽やかに体が動いた。
しばらくすると,赤いベレー帽を被った兵士が2人近寄ってきて黒い防弾ベストと茶色いカバーがかけられたヘルメットを1人ずつに渡した。重たいベストの脇のベルトやヘルメットの顎のバックルを留めるのに苦労していると別のトラックが到着して,荷台から僕たちと同じ格好をした3人が亡霊の様に降りて重々しい足取りで近づいていた。
「ガードマンは明日だ。途中戦闘があってな・・・」
彼らがフランス語訛りのある英語でベレー帽の兵士と勢い良く話してるのが聞こえた。
ドーバーまではそれぞれ別の牧師が同行して来たが,フェリーに乗ってからは物静かなフランス人が1人で僕たちの船頭を務めていて,淡々と予定説明を終えた後,船内のラウンジで読書をしながら僕たちの遺書の提出を待っていた。彼が小さく頷きながら無言で遺書を受けとる強ばった表情が印象的だった。
カレーに到着するとそのまま牧師が運転する赤いフォードエスコートに乗り込んでブリュッセルの「本部」という所へ向かった。2時間ほどのドライブの間,緊張からか僕たちはほとんど口を開くことはなかったから時間が物凄く長く感じられた。
本部ではパスポート等の荷物を預けてから予め用意されていた薄いカーキー色の作業服に着替えさせられた。爪先に鉄板が入った安全靴はサイズが4種類しかないので履いたときに少し余裕のあるものを選んで踝まである紐で調節しなければならなかった。
ドーバーから一緒になった4人でせっせと着替えていると,続々と別のグループが到着して,1時間程の間に21人のボランティアと8人の牧師で部屋が一杯になった。すると更にグループ分けが行われて,僕はイギリスから一緒だったゲイリーという「イギリス生まれの中国人」と一緒に,フランスから来たジェイ,パトリック,ラファエルと5人でアジャの住む国の手前にある「基地」と呼ばれる場所へ向かうことを確認した。皆物腰が優しい好青年だったが,ジエイは僕には関心がないといったあからさまな素振りを見せた。メンバーのほとんどが敬虔なクリスチャンで皆一様に十字架のアクセサリーを大切そうに上着のポケットに入れていた。いきなり跪いて黒表紙の聖書を開いた途端数人で祈り始めるグループもいて少し居心地が悪かった。準備が整うと10ポンド程度だという少額な現地の通貨が配られ,ようやく出発となった。
ブリュッセルからは全員マイクロバスに乗り込み,更に7時間程かけてスイスに入った。そこで初めて射撃訓練を受けると告げられた。人助けのつもりで参加したはずなのに人を撃つ訓練を受けなければならないという矛盾に一抹の不安を感じるのと同時に,遺書を書いたときに感じた死の存在が再び僕の脳裏で渦巻いたが,他の誰もが動揺する様子もなく質問する者もいなかったから仕方なく黙って指示に従った。
迷彩服を着用した背の高いスイスの兵士数人から2時間ほどかけて様々な距離に設置された皿のような金属の板を撃ったり,分解や組み立てなどの練習をして一通りピストルの扱い方を教わると, 新しい弾丸が7発ずつマガジンに装填された状態で支給された。そして休息を取ることもなく其々用意されたトラックに便乗し現地に向かうことになった。ベルンの日暮れはイギリスと同じくらいで遅いらしく,腕時計を確認すると既に午後10時前くらいだった。
最初は柔いサスペンションのせいで船酔いの様な嫌な感覚に苦しんでいたが,嘔吐するまで酷いことはならずに済んだ。疲れていただけかも知れないが,そのうちトラックの荷台の簡易シートに横向きに座っていても,幌を支える細いバーに寄りかかってぐっすり眠れるまで慣れた。未だに自分が置かれた世界に対して疑いを抱きながらアジャに会えるかもしれないという奇跡を信じて気持ちは少しだけ高揚していた。
トラックが何度か燃料補給するのに立ち寄る場所で用を足したりしながら,基地に到着したのは明くる日の夕方だった。確か国連の介入は公式に発表されてはいなかったが,両側面に「UN」と言う文字が大きく書かれた白い装甲車が3台,同じく白い塗装が施された車両が数台整然と駐車してあって,周囲には青いヘルメットカバーを掛けた兵士達がのんびりと寛いでいた。僕たちが到着すると,彼らが着用している草色のものとは違う土色に近い僕たちの服装に気付いたのか,じっとこちらに視線を向けている者もいた。
僕たちは食事も取らされずに基地に横付けしてあった大きなトレーラーから数台のトラックに支援物資を積み替える任務についた。誰もが疲労感の局地にあったはずだが窮屈な荷台から解放されてホッとした様子だった。僕はと言えば,漠然とではあったが,アジャの傍に1ミリでも近づけた様な感覚に絵も言えぬ嬉しさを禁じ得ず軽やかに体が動いた。
しばらくすると,赤いベレー帽を被った兵士が2人近寄ってきて黒い防弾ベストと茶色いカバーがかけられたヘルメットを1人ずつに渡した。重たいベストの脇のベルトやヘルメットの顎のバックルを留めるのに苦労していると別のトラックが到着して,荷台から僕たちと同じ格好をした3人が亡霊の様に降りて重々しい足取りで近づいていた。
「ガードマンは明日だ。途中戦闘があってな・・・」
彼らがフランス語訛りのある英語でベレー帽の兵士と勢い良く話してるのが聞こえた。