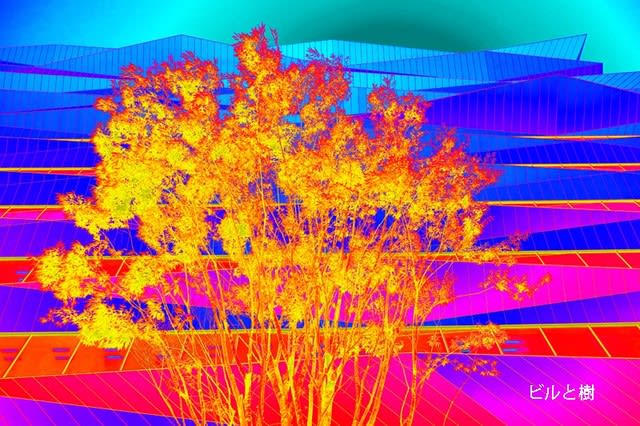あいちトリエンナーレ2019の企画展「表現の不自由展・その後」をめぐる騒動を見て、グレーバーの言う「自由」をもとに、その一つとなる「表現の自由」について考えてみた。 . . . 本文を読む
「人権」という言葉を耳にする機会は多く、また、何となくわかっているつもりで使ったりしている。でも、「人権て何?」と問われてはっきりと説明できる人はあまりいないのではないだろうか。そこで、「人権」について考えてみた。 . . . 本文を読む
小学館が編集発行している『週刊ポスト』が、現在の嫌韓ムードをさらに煽る記事を掲載した。いったい嫌韓を煽ることによって何を狙っているのだろう。徴用工問題への対応といい、自ら平和的解決への出口を塞いでいるように見える。このままゆくと、本当に戦争になるかもしれない。 . . . 本文を読む
前回の『負債論』の紹介の中で、「自由」という概念が、「奴隷ではない」というところから形成されたのだというところが、非常に新鮮で興味深く感じられた。そこで、この点について少し考えてみたことを書く。 . . . 本文を読む
この章では、われわれがそれほど考えることもなく使っている「名誉」とか、現代文明の基盤となっている「私的所有権」とか「自由」という概念について、哲学的に考えるのではなく、人類学的知見をベースとして、それが人間の歴史の中で、どのように生まれ、使われてきたのかということが語られる。そして、そこには「物理的な暴力=棍棒、綱、槍、銃による脅迫」が深くかかわっていることが明かされる。また、家父長制や女性の自由の全般的低下についても、その淵源が語られる。 . . . 本文を読む
「人(の命)は、ほかの何ものにも代えることができないものである」という大前提のもとに築かれてきた結婚の制度や、死(殺人)への償いの制度が変質して、「人」がモノと同様に売り買いされるような事態になってしまったのはどうしてか。
それは、先の制度が市場経済と接触するところで、そして暴力が介在することによって起きる。つまり、「人」をも売り買い可能な商品としてしまう市場経済というものなしに、また、「人をその人たらしめている相互関係や共有された歴史、集合的責任の織物から、人間を切り離」すための暴力なしに、人を奴隷にすることはできないということである。
. . . 本文を読む
人は経験として、過去を認識することはできる。しかし、これからの世界=未来は見えない。目がない背中を前にし、過ぎ去った世界を見ながら後ろ向きに進むことしかできない。そのとき、進む方向に何があるかを推測する手掛かりは過去にしかない。だから、けっして過去をないがしろにすることはできない。 . . . 本文を読む
憲法や法律をないがしろにし、好き勝手をしている人たちが改憲を声高に叫んでいる。彼らにとって、憲法などあってなきかのようなものであり、詭弁でなんとでも解釈できるのだから、改憲など不要のはずだ。それなのに、どうして改憲を叫ぶのだろう。きっと彼らは、憲法は国民を縛るものと考えているからだろう。だから、その縛りを強くしたいのだろう。 一方、国民をより強く縛り付けようとしているそんな彼らを「他の内閣よりよそさそうだから」と多くの国民が支持しているのはいったいどういうことだろう。それは、彼らが何をしようとしているのかを国民が知らないから、知ろうとしないからではないか。そして、そういうことを国民に知らしめるべき役割を持つ報道機関が、その役割を果たそうとしないからではないか。 . . . 本文を読む
「シンギュラリティ」、「2045年問題」ということばをよく聞くようになった。いま話題になっているシンギュラリティは技術的特異点(Technological Singularity)を指しており、特に指数関数的に進歩するAI技術の特異点を指している。その特異点は「人間の知的能力と人工知能の能力が逆転する点」を指し、それが2045年だと提唱しているのが人工知能の権威であるレイ・カーツワイル博士である。「2045年問題」とはそこからきている。しかし、その論じられ方には違和感を感じるので、少し私見を述べる。 . . . 本文を読む
「第五章 経済的諸関係のモラル的基盤についての小論」である。また長くなってしまった。ここでは、経済的関係が基盤をおくことのできる三つの主要なモラルの原理「コミュニズム」、「ヒエラルキー」、「交換」の話が主となるが、中でも「コミュニズム」についての話がおもしろい。なお、本題に入る前に少し言い訳が入っている。 . . . 本文を読む
「第四章 残酷さと贖い」である。今回は世界を商業的観点から想像しようとしたとき生じる事態を、たぐいまれなる明晰さをもって透視できた人として、ニーチェとその主張が紹介される。そして、世界宗教の一つとしてのキリスト教における「贖いと救済」について、その実際の意味が明らかにされる。 . . . 本文を読む
今回は第三章 原初的負債について。「わたしたちは、かつてわたしたちを創造した神々にわたしたちの生を負っていた。動物を生贄にするというかたちでその利子を支払い、究極的にはみずからの生によって返済を完了した。今日わたしたちはじぶんたちを形成した〈国〉(Nation)に対してみずからの生を負っているのであり、税というかたちでその利子を支払い、敵から国を防衛するさいにはみずからの生命をもって支払っている」という考え方について。 . . . 本文を読む
「むかしむかし物々交換がありました。でも物々交換が成り立つにはとても骨が折れたのです。そこでひとは、お金を発明しました。そこから銀行や信用が発展したのです」この章では、このお話が神話に過ぎないことが明かされる。事実はこの逆であると。そして、このお話はアダム・スミスが経済学を創設する中で生まれたものであることも。 . . . 本文を読む
デーヴィッド・グレーバーという人類学者が書いた『負債論』という本がある。「負債」という概念を中心に据えて、この世界の歴史を見直し、これからの世界を考えるための材料を提供するものである。わたくし自身の読後の整理のためにも、ブログとして、感想を含め、その内容を書いておこうと考えた。かなり分量のある本なので、章を単位として、少しずつというかたちになる。今回は、「第1章 モラルの混乱の経験をめぐって」となる。 . . . 本文を読む