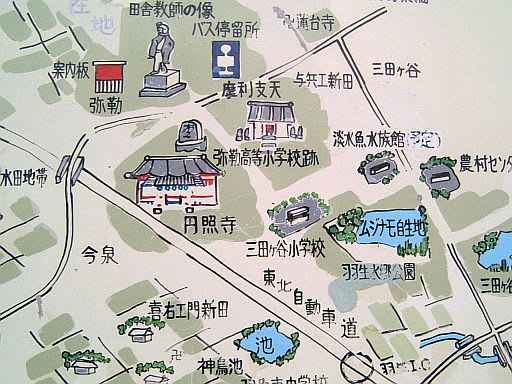加須市外野の利根川沿いに川圦(かわいり)神社があります。
境内は、大きなイチョウの木で囲まれ、本殿は少し高い所に建てられている。
川圦とは、水門という意味があります。
この神社には「川圦さま」伝説があり、川の氾濫で水害が起こり、神のお告げで旅人の母娘を人柱にして村を守る事ができたが、その母娘の祟りにより村に不幸ごとが続き、その母娘の霊を弔う為に、この神社を建てて祀った所、村に平穏が訪れたというものです。
境内のイチョウの木の下には、銀杏の実がいっぱい落ちており、拾っておられる方もおられました。少し小振りの実のようです。
20個程拾って持って帰って洗って干して食べましたが、少し苦味はありましたが、噛んでると甘みも感じられおいしくいただけました。