この本は「フィオレンツァ」への恋文。
学生の頃、故意に読み終えなかった本が(覚えている限り)3冊ある。
与謝野晶子訳「源氏物語」、塩野七生「チェーザレ・ボルジア あるいは優雅なる冷酷」、
そして辻邦生「背教者ユリアヌス」。
この3冊は最後の数ページを読み残した。その理由は、物語が終わってしまうのが厭だったので。
大人になってしまった今はもう滅多にないことだが、
本を読みつつ、残りのページ数を物惜しく数えることもあった若かりし頃の話。
さてその後、源氏物語関連はけっこうハマり、塩野七生は好きな作家として挙げるようになったけれども、
なぜか辻邦生には手が伸びなかった。背教者ユリアヌスがあまりにも面白かったせいかもしれない。
2冊目を読んでそれより面白くなかったらどうしよう、と尻込みをした記憶がある。
しかしその癖、基本的に再読をしない方なので、「背教者ユリアヌス」を読み返すこともなく……
ものすごく時が経った。
先日、ふと「辻邦生を読もう」と思った。「春の戴冠」と「西行花伝」のどちらにしようか迷ったが、
なんとなく「春の戴冠」を選び。図書館から借りて来た本は、かなり年代物の布表紙。
ぼろぼろで、相当汚れている。その古び具合が昔馴染みのようで、妙に懐かしかった。
この本の主題は一応、画家サンドロ・ボッティチェリの生涯ということになっており、
彼の幼友達のフェデリコの回想録という形をとっている。
が、実際にはそれだけでは収まらない。
もちろんサンドロは、主要な一本の筋として最初から最後まで重要な位置を占めるけれども、
作者が一番力をこめて書いているのは、フィレンツェそのもの。
(作中では一貫して、古名のフィオレンツァで呼ばれている。)
その町の花の盛り、衰微の影、動揺、静かな破滅。じっくりと憧れと愛着をこめて辻邦生は辿る。
この憧れにわたしは共感する。わたしもフィレンツェが好きだ。
世界でたった一ヶ所、と問われたら、迷いながらもフィレンツェと答えるだろうし、
世界のたった一枚の絵、と言われたら「ヴィーナスの誕生」を挙げる。
そういう人間が読めば、書き手であるフェデリコは本当に自分の分身だ。
老境に至ってあの花の盛りを懐かしむ視線は、500年後の人間があの町のあの時代を
憧憬をもって見つめる目と容易に重なる。そしてフェデリコは、もちろん作者本人の目。
作者と何かを共有していると感じられる作品は、その本を読んだ人間にとって大切なものになる。
読書の最上の部分はそこかもしれない。面白い、笑える、感動する、そういうものも
もちろん読書の楽しみとしてあるだろうが、それよりもなかなか手に入らぬ、
深い喜びは「共有」ではないだろうか。
日常的に接している人間関係でも、心が通じ合っていると実感できることはそう多くはない。
文字を辿ることで、時間も空間も越えて作者と何かを共有できる(と信じられる)というのは、
稀有な幸福といえる。
読むのが非常に愉しかったのは間違いないが、作品としては少々不満もあった。
全体的にはやっぱり「書きすぎ」……。いや、わたしは内容が好きだから多少しつこくてもいいけど。
にしても、もうちょっと枝葉を刈り込んで、すっきりさせるべきじゃないかね。
書きたいことをあまり捨てずにみな書いてしまったというような、放恣な部分を感じる。
プロはストイックに、というのがわたしの好みだ。
それから、ボッティチェリのことを書くなら、出来ればサヴォナローラとの関わりをもっと
しっかり書いて欲しかったなー。
わたしが一番興味を持っていたのがこの部分。ここを辻邦生がどう見るかと楽しみにしていた。
ボッティチェリは、前半は夢のように美しい絵を描いていたのに、いつからか画風を変えて、
とてもせせこましい、窮屈な絵を描くようになった。人物が小さいボッティチェリに魅力なんてない。
それはサヴォナローラの影響だと、一般的にもそう言われているはず。
あの画風があの画風に転換するには、内面的になにかものすごいことが起こっていたんだろうと思う。
その辺りを期待したのだが。
全然触れられていないわけではないんだけれど、わりとあっさりだった。
それと関連するんだけれども、最後は少々はしょりすぎている。
「虚飾の焼却」が下巻の450ページに来るようでは、わたしが期待した部分が書けるはずもない。
エピローグも、無理に収束させたきらいがある……。外的な理由か、内的な理由か。
内的な理由だとしたら残念だが。大作は上手く着地してこそ、だと思うし。
辻邦生、これからツブす(=全著作制覇)つもりでいる。軽く100冊は越えるのだけれど。
何年かかることやら。まあ、のんびりいきましょう。
これは上下一冊版。何も956ページの本を作らずとも良いと思うが……。
学生の頃、故意に読み終えなかった本が(覚えている限り)3冊ある。
与謝野晶子訳「源氏物語」、塩野七生「チェーザレ・ボルジア あるいは優雅なる冷酷」、
そして辻邦生「背教者ユリアヌス」。
この3冊は最後の数ページを読み残した。その理由は、物語が終わってしまうのが厭だったので。
大人になってしまった今はもう滅多にないことだが、
本を読みつつ、残りのページ数を物惜しく数えることもあった若かりし頃の話。
さてその後、源氏物語関連はけっこうハマり、塩野七生は好きな作家として挙げるようになったけれども、
なぜか辻邦生には手が伸びなかった。背教者ユリアヌスがあまりにも面白かったせいかもしれない。
2冊目を読んでそれより面白くなかったらどうしよう、と尻込みをした記憶がある。
しかしその癖、基本的に再読をしない方なので、「背教者ユリアヌス」を読み返すこともなく……
ものすごく時が経った。
先日、ふと「辻邦生を読もう」と思った。「春の戴冠」と「西行花伝」のどちらにしようか迷ったが、
なんとなく「春の戴冠」を選び。図書館から借りて来た本は、かなり年代物の布表紙。
ぼろぼろで、相当汚れている。その古び具合が昔馴染みのようで、妙に懐かしかった。
この本の主題は一応、画家サンドロ・ボッティチェリの生涯ということになっており、
彼の幼友達のフェデリコの回想録という形をとっている。
が、実際にはそれだけでは収まらない。
もちろんサンドロは、主要な一本の筋として最初から最後まで重要な位置を占めるけれども、
作者が一番力をこめて書いているのは、フィレンツェそのもの。
(作中では一貫して、古名のフィオレンツァで呼ばれている。)
その町の花の盛り、衰微の影、動揺、静かな破滅。じっくりと憧れと愛着をこめて辻邦生は辿る。
この憧れにわたしは共感する。わたしもフィレンツェが好きだ。
世界でたった一ヶ所、と問われたら、迷いながらもフィレンツェと答えるだろうし、
世界のたった一枚の絵、と言われたら「ヴィーナスの誕生」を挙げる。
そういう人間が読めば、書き手であるフェデリコは本当に自分の分身だ。
老境に至ってあの花の盛りを懐かしむ視線は、500年後の人間があの町のあの時代を
憧憬をもって見つめる目と容易に重なる。そしてフェデリコは、もちろん作者本人の目。
作者と何かを共有していると感じられる作品は、その本を読んだ人間にとって大切なものになる。
読書の最上の部分はそこかもしれない。面白い、笑える、感動する、そういうものも
もちろん読書の楽しみとしてあるだろうが、それよりもなかなか手に入らぬ、
深い喜びは「共有」ではないだろうか。
日常的に接している人間関係でも、心が通じ合っていると実感できることはそう多くはない。
文字を辿ることで、時間も空間も越えて作者と何かを共有できる(と信じられる)というのは、
稀有な幸福といえる。
読むのが非常に愉しかったのは間違いないが、作品としては少々不満もあった。
全体的にはやっぱり「書きすぎ」……。いや、わたしは内容が好きだから多少しつこくてもいいけど。
にしても、もうちょっと枝葉を刈り込んで、すっきりさせるべきじゃないかね。
書きたいことをあまり捨てずにみな書いてしまったというような、放恣な部分を感じる。
プロはストイックに、というのがわたしの好みだ。
それから、ボッティチェリのことを書くなら、出来ればサヴォナローラとの関わりをもっと
しっかり書いて欲しかったなー。
わたしが一番興味を持っていたのがこの部分。ここを辻邦生がどう見るかと楽しみにしていた。
ボッティチェリは、前半は夢のように美しい絵を描いていたのに、いつからか画風を変えて、
とてもせせこましい、窮屈な絵を描くようになった。人物が小さいボッティチェリに魅力なんてない。
それはサヴォナローラの影響だと、一般的にもそう言われているはず。
あの画風があの画風に転換するには、内面的になにかものすごいことが起こっていたんだろうと思う。
その辺りを期待したのだが。
全然触れられていないわけではないんだけれど、わりとあっさりだった。
それと関連するんだけれども、最後は少々はしょりすぎている。
「虚飾の焼却」が下巻の450ページに来るようでは、わたしが期待した部分が書けるはずもない。
エピローグも、無理に収束させたきらいがある……。外的な理由か、内的な理由か。
内的な理由だとしたら残念だが。大作は上手く着地してこそ、だと思うし。
辻邦生、これからツブす(=全著作制覇)つもりでいる。軽く100冊は越えるのだけれど。
何年かかることやら。まあ、のんびりいきましょう。
これは上下一冊版。何も956ページの本を作らずとも良いと思うが……。











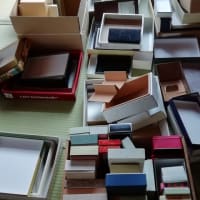
















さて、先年、フィレンツェを再訪しようと思い立ち、それならばと、書架の奥から黄ばんだ辻邦生の「春の戴冠」を取り出して再読しました。ボッティチェリがシニョーリア広場脇の横丁から飛び出してくるような生き生きとした描写が、フィレンツェやメディチ家の栄光と衰退の物語を改めて思い起こさせてくれました。
b0287285_19281747.jpg
数日後、残影の「プリマヴェーラ」とともにウフィッツィ美術館を出ると、アルノ川は、早春の光を川面に燦めかせてゆったりと流れていました。そこから、ボッティチェリの暮らしたオグニッサンティ教会界隈までは20分ほどです。建物の陰や石畳の上に、フィレンツェの春の盛りを謳歌した人々やボッティチェリの姿が重なるような気がしました。
それから数か月後、子供の頃よく遊んだ郷里の路地を歩きました。かつてと変わらない道端のさもない石や土蔵の漆喰の剥がれ跡などを目にすると、記憶の底に沈んでいた様々な情景が次々と浮かび上がってきました。路地に向かって開け放たれた縁側には、すでに亡くなられたお婆さんが、日向ぼっこをしながら繕い物をしていました。石崖の間から美しい光沢をまとってトカゲが姿をあらわしました。
フィレンツェにしろ、この路地にしろ、佇まいの中に時間の流れや暮らしていた人々の息づかいが感じられる街は、一人の人間が空間や時間を超えてあらゆる世界と連続性をもって繋がっているという豊かな感覚をもたらしてくれるものなのですね。
やはりフィレンツェはミケランジェロ広場からの風景がまず一番ですね。
コメント欄では写真の再現は出来ないようです。
辻邦生の著作は地道に読み続け、残すところ十数冊となりました。
読み終わったら佐保子さんの著作も読んでみようと思います。