「野球小説の最高峰」という言葉に釣られて読んでみた。
http://www.webdokusho.com/soudan/answer/view_date.php?date=2006/03/25
そもそも野球小説ってどんなもんをいうんだろう。
野球マンガなら例えば「ドカベン」。ドラマなら「ルーキーズ」。(見たことないけど。)
小説も、近年は「バッテリー」とかけっこう人気あったな。(読んでないけど。)
ああいう類だろうか。
……という予想をしていたら、実はこの作品、そういうものとは全然違いました。
上記に挙げたものはどれも、野球選手とか、ゲームとしての野球とかを描いている作品。
「野球をテーマにした」と言った時にはそっちの方が普通だと思うけど、
この小説は野球小説というより、ずばり球界再編小説です。
※※※※※※※※※※※※
こんな球界じゃダメだ、こういう野球を見たいんじゃないんだ、というところからスタートした
名コミッショナーが、ほのぼのと(?)暗躍(??)し、地域密着の球界を作っていく話。
作中では、最終的に3リーグ18チームが実現することになる。基本的に選手構成は
近隣県出身の選手が7割程度を占めるような。
野球と政治をずいぶん結びつけて描いていて、コミッショナーの敵は政財界のおえら方。
その敵にいかに対抗していくか、というところがこの話の山場……
……であるべきだと思うのだけれど、なにしろほのぼのとした小説なので、
手に汗握るようなストーリー上の攻防は実はない(汗)。
作者の「こんな球界がいいよなあ」というファンタジー。しかもとっても地味。
正直、再編の流れとしては話が甘すぎます。
だって、今までのプロチームを一旦全解散にして、最初からやり直すんですよ。
ファンだって寝耳に水の話なら、そんな簡単に受け入れがたい。
いくら水面下で相当に話を進めていたとしたって、2ヶ月程度で各都市が新球団設立のための
要件を満たせるとは思えない。選手がそんなにすんなりと再編を受け入れるとは思えない。
政治屋さんたちが一個人相手にそれほど後手後手に回ることはまずない。
その辺を、作者はとても都合良くあれよあれよという間に乗り越えさせてしまうのですけどね。
なので、実際の再編のノウハウとしては全く役に立たないけれど、
……まあそこらへんはファンタジーなので割り切る。
そうか、作者はこういう夢を描いたのか、というスタンスで読む。
これはね。2004年の球界再編騒動を経た後に読んだからこそ、生まれた面白味があるんですよ。
この作品が書かれたのはかなり昔で、1982年出版。
だが2004年を、及ばずながら自分の問題として捉えたファンからすると、
書かれたことと現実との似姿に、多少なりとも目を瞠る。
ま、この部分をあまり過大に評価するのも違うと思うけど。
しかし1982年に書かれたことが、20年経ってようやく表面化したのかという感慨にはなる。
この部分が、わたしは一番面白かった。
多分、仙台の楽天ファンが読むと一番楽しめるんじゃないかなあ。
というのは、「おらがまちの」チームが出来た嬉しさを、一番味わっている地域だから。
言いすぎですか。移転によるものとは言え、日ハムファンも同じ気持ちか。
本拠地を移してからずいぶん経っているけど、福岡のファンも「おらがまちの」意識は強いだろうな。
ただ、よちよち歩きの球団の姿をすぐそばで見ていられたというのは、
なかなか得難い経験であり、良い思い出になっている。
それから、楽天に今年小坂が入ったが、その時の地元メディアのはしゃぎようは特筆ものでしたよ。
実はわたしもはしゃいでいた。小坂だから嬉しいというのはあるけどね。
ストーリーのメインは再編のことなんだけど、当時活躍していた選手の名前がちらほらと
出てくるのも楽しい。作者は悪ノリして(シュミに走って?)、再編された18チームに
どういう選手が所属しているかを書いている。
例えば札幌ベアーズのプレーイングマネージャーには若松勉氏が就任してます。
仙台ダンディーズには八重樫さんがいます。
京都エンペラーズの監督は野村さんです。新チームで初めての始球式では、相手チーム監督の
稲尾が投げ、野村が受けということを行いました。
この辺、ほんと作者は楽しかったろうと思うよ。わくわくしながら話を作ったに違いない。
わたしは1982年当時は全く野球を見てないので、ピンとくる名前は半分くらいなんだけど、
それでも面白かった。
新生18チームの名前も、作者は全部考えている。
……これなー、面白かったから書きうつしておこうと思ったんだけど忘れた。
もう図書館に返却してしまった。記憶によってメモしておくと、
札幌ベアーズ。仙台ダンディーズ。長野アルプス。東京ジャイアンツ。横浜アンカーズ。
名古屋グランパス。京都エンペラーズ。大阪タイガース。奈良テンプルズ。神戸マリナーズ。
岡山モモタローズ。広島ドリンカーズ。高松パイレーツ。博多ドンタクズ。熊本モッコス。
名前は忘れたけど、浜松もあったんだ。川崎もあったかな。千葉もあっただろうなー。
この中で注目は名古屋グランパス。まあサッカーですけど。意味を知っていればこれしかない、
という命名ではあるけど。
地味に仙台ダンディーズにもにやりとさせられた。これもサッカーだけど、
ベガルタ仙台になる前のチーム名はブランメル仙台で、これは「伊達男」を意図して
つけたらしいから。
広島は、ドリンカーズだったらスリーアローズまでたどり着いて欲しかったところだね。
熊本モッコスだけが意味がわからん。
作者の赤瀬川隼は、赤瀬川原平さんのおにーさん。
わたしはゲンペーさんが好きでおにーさんは初作品だが、何となくやっぱり兄弟だなあ、という作風。
のんびり系です。この作品が第一作らしいので(これを最初に書くとはなかなかに図々しい……)
その後どうなっていったのかはまだ知らない。でも野球小説は多いらしいよ。
もう2、3作、それから映画関連のエッセイもあるらしいので、そっちも読んでみる予定。
……ところで、作品を読んでいてわかるが、おにーさんはアンチ読売らしい。
贔屓は広島らしい。(重要な登場人物として広島ドリンカーズの監督が設定されている。架空。)
で、ゲンペーさんの方は、これがけっこうな読売ファンなんだよね。
わたしにとっては彼の最大の瑕がここだ。ここさえなければなあ。残念なことよ。
だってゲンペーさんは、とあるエッセイで「ヤクルトみたいなつまらないチーム相手に」とか
書いたことがあるんだよ!ぷんぷん。……まあ、だからといってキライにはならないけどね。
球は転々宇宙間 (文春文庫 (351‐1))
posted with amazlet at 09.03.03
赤瀬川 隼
文芸春秋
売り上げランキング: 466173
文芸春秋
売り上げランキング: 466173
しかしね。再編の時にしみじみ思ったが、ほんとに日本球界のシステムはキッツイよね。
最高権力機関がオーナー会議。
しかもそのオーナーというのは、正確に言えば子会社の雇われ社長。
……利害だけで物を見がちなオーナー会議が最高権力機関ってだけでもツライのに、
それが子会社で雇われ社長となると。親会社の都合でしょ、自己の保身でしょ、権限もないでしょ、
在任期間無難に務めればいいだけだから、大局を見るなんてこと構造的に無理じゃないですか。
せめて「自チームの利害」を一番に考えるということで12球団が一致しているなら
妥協点を見出すことも出来そうだからマシなんだが、何しろ子会社だから
「自チームには不利だが親会社には有利」という状況が有り得る。
ここらへんで足並みが揃わないよねー。
楽天の場合は野球を一応本業として捉えている。だから、野球でどれだけ儲けるかというのを
本気で考えている。が、単に広告塔として捉えているチームは、進化の努力をしないからなあ。
体質も構造も、近々に劇的に改善されるとは思い難い。
以前も考えたけど、コミッショナーの権限をもっと強化することくらいが
実現可能な構造改善ではないのか。再編騒動も日々遠くなり、改善の努力は忘れられがち。
でも差し迫った話ではなくとも、10年先、20年先を考えるのであれば、
今から出来ることを進めていかないとあかんのやないかなあ。










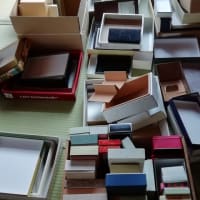













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます