うーん。わたしは時代小説と歴史小説は似て非なるものだと思うんだよなあ。
この作品の解説では歴史小説と言われており、たしかに井伊直弼をはじめとして
実在の人物について書いた作品だが、これは違うんじゃないかなあ。
歴史小説には歴史観が必要だと思う。
歴史観とは何か、説明せよと言われても自信がないが、
「ここがこうだったから結果的にこうなった」
「もしこうであれば結果はこうだったかもしれない」
「ここが分岐点で、こちらを選んだ(のは正しかった、あるいは間違っていた)」
という自分なりの解釈を含むものだと思う。
諸田玲子は時代小説の名手だけれども。本作には上記のようなところが全然ない気がするんだよ。
文庫600ページ超の前半くらいはずっと時代小説の手法で、
村山たかと井伊直弼の若い頃の熱い恋の話。
隠さなければならなかった“しのぶ恋”で、会えなかったり会えたり、
会えば熱い逢瀬が……の繰り返し。これで作中時間5年。ページ数およそ300ページ。
長いっちゅうねん。
上手いんだけどね。読ませるんだけどね。ただ長さに辟易する。
こんなに無意味に長いということは、これは新聞小説だろう……と思ったら案の定。
新聞小説は書きながら着地点を模索するから、バランスが悪くなりがちなんだよね。
同じことを何度も書いてるしね。これを1冊で読むとその繰り返しがツライ。
そして後半は歴史部分ではあるんだけどね。
単に歴史の流れをたどっているだけで、いかにも調べて書きました感が強い。
特に直弼がね。前半あんなにたかへの想いや、心服した長野義言について心情も述べているし、
台詞も多いのに、藩主になって歴史上の人物の動きをするようになってから、ほとんど台詞を喋らない。
全然心情も描かれなくなって、単に動きを追っているだけ。
直弼を主要人物とするんなら、安政の大獄についての直弼の考え方や心境などを
もっと書かなきゃだめでしょう。
さすがに主人公のたかがおざなりということはないんだけどね。
ただ、女忍びの主人公に終始寄り添って書いても、あまり大局を見ることに繋がらないというか……
繋げられたらそれはお手柄だが、相当難しいと思う。
長野義言なる人は、わたしは今作で初めて知って、終盤までは魅力的なのだが、
逆境に立った時の崩れぶりが……。
「実は逆境に弱い人だったのだ」と実際書いているし、書こうとしていることは伝わるが、
伝えたからそれでいいってもんでもなく。
前半からそれはそれは褒めそやされているので、ここでこうやられちゃうと、
騙されたみたいに感じてしまう。
最初と最後に梁川星厳・紅蘭夫妻が印象的に出て来るが、あまりに印象的すぎて若干違和感が。
たかにとってそこまで……な人だっただろうか。印象的にではあるにせよ、
最初と最後を締めるくらい?
「夫と同志」という意味では長野義言の奥さんの多紀の方がたくさん出て来るし、
多紀がいなかったら紅蘭の描き方もありかもしれないが、
多紀がいる以上、紅蘭の描き方がこうであると、キャラというか存在が被るのではないかと。
新田次郎文学賞受賞作。
まあわたしは諸田玲子なら「お鳥見女房シリーズ」が好きですよ。
この作品の解説では歴史小説と言われており、たしかに井伊直弼をはじめとして
実在の人物について書いた作品だが、これは違うんじゃないかなあ。
歴史小説には歴史観が必要だと思う。
歴史観とは何か、説明せよと言われても自信がないが、
「ここがこうだったから結果的にこうなった」
「もしこうであれば結果はこうだったかもしれない」
「ここが分岐点で、こちらを選んだ(のは正しかった、あるいは間違っていた)」
という自分なりの解釈を含むものだと思う。
諸田玲子は時代小説の名手だけれども。本作には上記のようなところが全然ない気がするんだよ。
文庫600ページ超の前半くらいはずっと時代小説の手法で、
村山たかと井伊直弼の若い頃の熱い恋の話。
隠さなければならなかった“しのぶ恋”で、会えなかったり会えたり、
会えば熱い逢瀬が……の繰り返し。これで作中時間5年。ページ数およそ300ページ。
長いっちゅうねん。
上手いんだけどね。読ませるんだけどね。ただ長さに辟易する。
こんなに無意味に長いということは、これは新聞小説だろう……と思ったら案の定。
新聞小説は書きながら着地点を模索するから、バランスが悪くなりがちなんだよね。
同じことを何度も書いてるしね。これを1冊で読むとその繰り返しがツライ。
そして後半は歴史部分ではあるんだけどね。
単に歴史の流れをたどっているだけで、いかにも調べて書きました感が強い。
特に直弼がね。前半あんなにたかへの想いや、心服した長野義言について心情も述べているし、
台詞も多いのに、藩主になって歴史上の人物の動きをするようになってから、ほとんど台詞を喋らない。
全然心情も描かれなくなって、単に動きを追っているだけ。
直弼を主要人物とするんなら、安政の大獄についての直弼の考え方や心境などを
もっと書かなきゃだめでしょう。
さすがに主人公のたかがおざなりということはないんだけどね。
ただ、女忍びの主人公に終始寄り添って書いても、あまり大局を見ることに繋がらないというか……
繋げられたらそれはお手柄だが、相当難しいと思う。
長野義言なる人は、わたしは今作で初めて知って、終盤までは魅力的なのだが、
逆境に立った時の崩れぶりが……。
「実は逆境に弱い人だったのだ」と実際書いているし、書こうとしていることは伝わるが、
伝えたからそれでいいってもんでもなく。
前半からそれはそれは褒めそやされているので、ここでこうやられちゃうと、
騙されたみたいに感じてしまう。
最初と最後に梁川星厳・紅蘭夫妻が印象的に出て来るが、あまりに印象的すぎて若干違和感が。
たかにとってそこまで……な人だっただろうか。印象的にではあるにせよ、
最初と最後を締めるくらい?
「夫と同志」という意味では長野義言の奥さんの多紀の方がたくさん出て来るし、
多紀がいなかったら紅蘭の描き方もありかもしれないが、
多紀がいる以上、紅蘭の描き方がこうであると、キャラというか存在が被るのではないかと。
新田次郎文学賞受賞作。
まあわたしは諸田玲子なら「お鳥見女房シリーズ」が好きですよ。











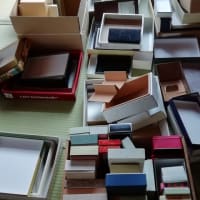













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます