もっと違う物語を読みたかったというのが正直なところ。
アステカってけっこう一般受けがいい素材ですよね?
近隣のミュージアムでエキシビも何回かやっているし、時々テレビで特番もある。
そのわりには、そういえば滅亡の時の話はあまり知らないなと思ったんだ。
コルテスをケツァルコアトルだと誤認したという話しか。
その辺を詳しく、そして北米の先住民出身の視点から深く描いて欲しかった。
が、それほど深くはなかったですからね。
まあ何をもって深いというかは人ぞれぞれだと思うけど、
あまり啓蒙はされなかったなあ。
今まで知らないことを読んで、「はー、なるほど、こういう理由で……」と
深く納得したかった。
ケツァルコアトルと誤認したことが軸で、
その他にコルテスに協力し愛人になった現地人の女、
アステカに心服してなかった周辺住民の反乱が絡んだストーリー。
内部に反乱分子を抱えていたことは聞いたことがあったし、
利を見て征服者につく女というのも歴史的に繰り返された存在だから
目新しさがなかった。
目新しくないから悪いというものでもないが……
結局、何が気に入らなかったかというと、話のキーであるモクテスマ王の
キャラクターと行動だな。納得出来なかった。
ここが納得出来なかったら話に説得力がないだろう。
語り手は“きこり”、現人神であるモクテスマ王の森に薪だかなんだかを
盗みに入り、そこで王に偶然出会い、死刑も覚悟したがそれが一転、召し出される。
その出会いにおいては自由で名君っぽい佇まいなのに、仕えるうちに
気まぐれな暴君になっていく。「きこり」はお気に入りだったはずなのに、
いつの間にか嫌われ、主従の心は離れていく。
このモクテスマの心の動きがわからない。
コルテスの存在が王の心を不安定にしたというのならわかるが、
コルテスが現れる前から変になっているんだよなあ。
王は現人神だから一般人には(そこらの家臣にも)接触せず、
きこりが、何人かいる「代言者(取次)」のうちの1人になるのだが、
側近のきこりが王に不信感を持つ流れがすっきりしない。
コルテスが現れてからも、
真実ケツァルコアトルだと信じて行動しているようには全然見えず
(だとしたら積極的におもてなしに行くだろう)
単に恐れているだけのように見えるし、
他の人々がコルテスの行動から「あれは神ではない」と判断しているのに、
モクテスマがどっちつかずでぐずぐずしていたり、変に擁護していたりする。
一体何を考えているのか、納得出来ないのだ。
心底からケツァルコアトルの再来だと信じていたならまだわかるのだが。
モクテスマを黄昏た世紀末的な性格に描きたかったのかなあ。
そうならばもっと心理的な小説にする必要があって、アステカの滅亡というのは
その舞台としてはそぐわない気がする。
前から思っているんだけど、「馬に乗った人」を見てそこまで驚くかなあ?
一瞬驚くのはまあわかる。特に甲冑を着た人と馬の組合せは初めて見れば異様で、
人間とは感じなくても仕方ない。
しかしそれは最初だけだと思うんだよね。騎士もいつかは馬から降りるだろうし、
面も外すだろうしさ。南米にだってアルパカとかラマとかいたんだから、
観察していれば使役動物であるとわかるはずなんだよね。
別してこの本の中では、犬にも驚いている。しかし狼が普通にいる状況で
犬にそんなに驚かなくない?はっきりいって同じようなもんでしょう。
まあ犬種によるかもしれないが。
しかし狼以上に獰猛だといって犬を恐れている。狼を家畜化したものが犬だと
いうのは後世の知識だとしても、狼以上というのは納得できない。
さらに変だと思うのは、作品の中で「狂犬のような」と「お前らは奴らのイヌ
だ!」
という表現を使っていることなんだよね。おかしいだろう。
犬を知らないのに「奴らのイヌ」ってさ……
金原瑞人の名前があるからそんなに不安はなかったんだけど、
ちょっとこの話は納得出来ませんね。
そう思ってみるとタイトルがなあ……。
原題が「THE SUN,HE DIES」で「滅びの符合」にするかねえ。
「滅びの符合」ってあんまり小説っぽくないと感じていたんだよね。
タイトルだけだと概説書のように感じていた。
せっかくSUNというシンボリックな名詞が原題にあるのに。
もっともこの小説では、モクテスマは太陽っぽいところは全くないわけだが。
まあ期待外れな小説でした。次は「アンパオ」を読んでみる。
これはアメリカ・インディアンの伝説をモチーフにしているそうだから
王道で、期待出来るはずなのだが。
アステカってけっこう一般受けがいい素材ですよね?
近隣のミュージアムでエキシビも何回かやっているし、時々テレビで特番もある。
そのわりには、そういえば滅亡の時の話はあまり知らないなと思ったんだ。
コルテスをケツァルコアトルだと誤認したという話しか。
その辺を詳しく、そして北米の先住民出身の視点から深く描いて欲しかった。
が、それほど深くはなかったですからね。
まあ何をもって深いというかは人ぞれぞれだと思うけど、
あまり啓蒙はされなかったなあ。
今まで知らないことを読んで、「はー、なるほど、こういう理由で……」と
深く納得したかった。
ケツァルコアトルと誤認したことが軸で、
その他にコルテスに協力し愛人になった現地人の女、
アステカに心服してなかった周辺住民の反乱が絡んだストーリー。
内部に反乱分子を抱えていたことは聞いたことがあったし、
利を見て征服者につく女というのも歴史的に繰り返された存在だから
目新しさがなかった。
目新しくないから悪いというものでもないが……
結局、何が気に入らなかったかというと、話のキーであるモクテスマ王の
キャラクターと行動だな。納得出来なかった。
ここが納得出来なかったら話に説得力がないだろう。
語り手は“きこり”、現人神であるモクテスマ王の森に薪だかなんだかを
盗みに入り、そこで王に偶然出会い、死刑も覚悟したがそれが一転、召し出される。
その出会いにおいては自由で名君っぽい佇まいなのに、仕えるうちに
気まぐれな暴君になっていく。「きこり」はお気に入りだったはずなのに、
いつの間にか嫌われ、主従の心は離れていく。
このモクテスマの心の動きがわからない。
コルテスの存在が王の心を不安定にしたというのならわかるが、
コルテスが現れる前から変になっているんだよなあ。
王は現人神だから一般人には(そこらの家臣にも)接触せず、
きこりが、何人かいる「代言者(取次)」のうちの1人になるのだが、
側近のきこりが王に不信感を持つ流れがすっきりしない。
コルテスが現れてからも、
真実ケツァルコアトルだと信じて行動しているようには全然見えず
(だとしたら積極的におもてなしに行くだろう)
単に恐れているだけのように見えるし、
他の人々がコルテスの行動から「あれは神ではない」と判断しているのに、
モクテスマがどっちつかずでぐずぐずしていたり、変に擁護していたりする。
一体何を考えているのか、納得出来ないのだ。
心底からケツァルコアトルの再来だと信じていたならまだわかるのだが。
モクテスマを黄昏た世紀末的な性格に描きたかったのかなあ。
そうならばもっと心理的な小説にする必要があって、アステカの滅亡というのは
その舞台としてはそぐわない気がする。
前から思っているんだけど、「馬に乗った人」を見てそこまで驚くかなあ?
一瞬驚くのはまあわかる。特に甲冑を着た人と馬の組合せは初めて見れば異様で、
人間とは感じなくても仕方ない。
しかしそれは最初だけだと思うんだよね。騎士もいつかは馬から降りるだろうし、
面も外すだろうしさ。南米にだってアルパカとかラマとかいたんだから、
観察していれば使役動物であるとわかるはずなんだよね。
別してこの本の中では、犬にも驚いている。しかし狼が普通にいる状況で
犬にそんなに驚かなくない?はっきりいって同じようなもんでしょう。
まあ犬種によるかもしれないが。
しかし狼以上に獰猛だといって犬を恐れている。狼を家畜化したものが犬だと
いうのは後世の知識だとしても、狼以上というのは納得できない。
さらに変だと思うのは、作品の中で「狂犬のような」と「お前らは奴らのイヌ
だ!」
という表現を使っていることなんだよね。おかしいだろう。
犬を知らないのに「奴らのイヌ」ってさ……
金原瑞人の名前があるからそんなに不安はなかったんだけど、
ちょっとこの話は納得出来ませんね。
そう思ってみるとタイトルがなあ……。
原題が「THE SUN,HE DIES」で「滅びの符合」にするかねえ。
「滅びの符合」ってあんまり小説っぽくないと感じていたんだよね。
タイトルだけだと概説書のように感じていた。
せっかくSUNというシンボリックな名詞が原題にあるのに。
もっともこの小説では、モクテスマは太陽っぽいところは全くないわけだが。
まあ期待外れな小説でした。次は「アンパオ」を読んでみる。
これはアメリカ・インディアンの伝説をモチーフにしているそうだから
王道で、期待出来るはずなのだが。










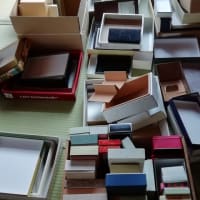













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます