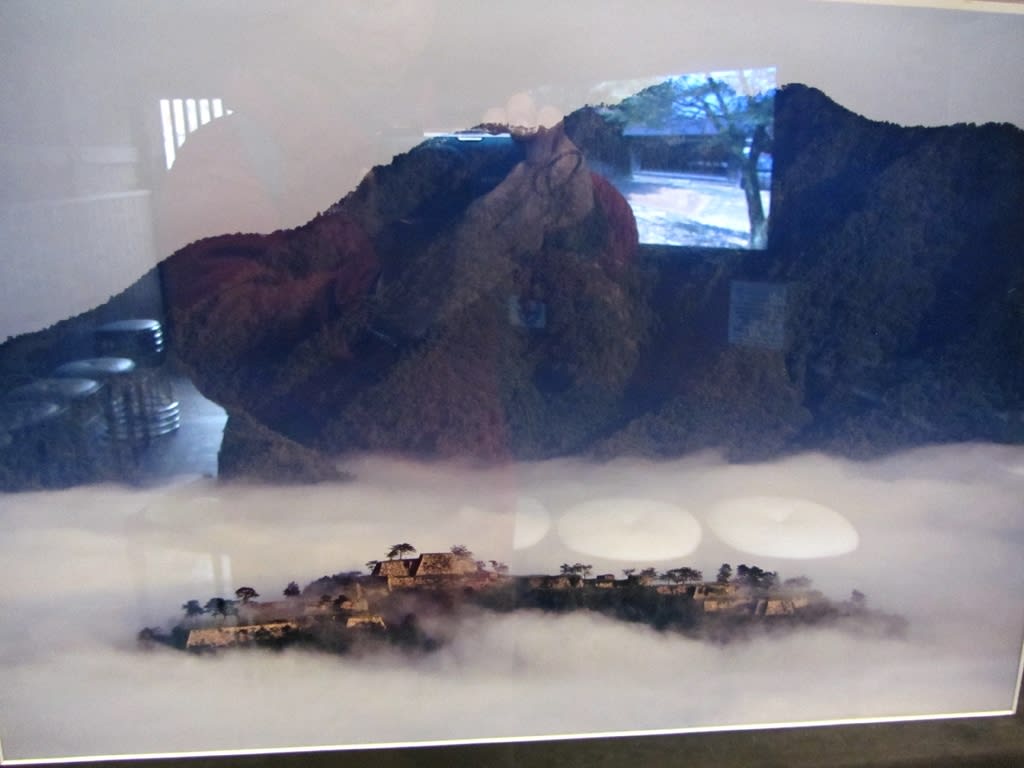情報館・天空の城から出て来て、これから播但線の踏切を渡ります。

踏切を渡るときに見た竹田駅の方向

黄色の線に沿って、番号順に歩きます。

踏切を渡ると、寺町通りに来ました。

お寺が並んでいて、綺麗な水路が流れていました。
白壁の寺と、水路で、落ち着く景色をかたちづくってっています。
最初に左側にある善證寺です。

慈雲山 善證寺(ぜんしょうじ)
1334年に、対岸の金梨山のふもとに開創。
1625年の火災で消失し、1652年にこの場所に移転したそうでした。
1706年に現在の本堂を再建立し、門前の石橋には享保17年(1732年)の年号が刻まれています。

寺町通を歩きます。

すぐ隣には、常光寺がありました。

常光寺の石橋は、宝永4年(1707)に架橋で、但馬で最古の石橋
本堂

この寺は、竹田城の初代城主の太田垣光景の菩提寺でした。
1594年に開創し、1610年に現在地に移っています。
太田垣光景 石塔

ここからさらに寺町通りを北へ歩きます。
常光寺の隣りには、勝賢寺がありました。

本堂


この地は、赤松広秀公の家臣の平位善右衛門屋敷跡とされています。
境内には、第九代城主である桑山重晴の長男、一重夫妻の五輪供養塔があるそうです。
寺町通りにそう小さな川の流れ


一番最後の寺は「法樹寺」

本堂

本堂の裏側には赤松広秀の供養塔があります。
(寺には、赤松広秀愛用の膳、お椀があるそうです。)
赤松広秀は1562年に、播磨龍野城主赤松政秀の子として生まれ、16歳で龍野城主となります。
後に、秀吉の家臣となり、四国征伐等の戦功により、1585年に竹田城主となりました。
竹田城の最後の城主です。
文人としても優れ、領民から慕われる武将でしたが、”関ヶ原の合戦”で西軍にくみしたため敗北します。
その後、鳥取城攻めで城下に火を放ったとされ、鳥取の真教寺で自刃しました。享年39歳でした。
供養塔を探しましたが、うまく見つけることができませんでした。
境内の外へ出て、寺町通りをさらに北へ歩きました。

(通りの右側にありました。)
この通りから、竹田駅が見れます。

もうすぐ、”駅裏登山道”に到着します。

登山口に来ました。


踏切を渡るときに見た竹田駅の方向

黄色の線に沿って、番号順に歩きます。

踏切を渡ると、寺町通りに来ました。

お寺が並んでいて、綺麗な水路が流れていました。
白壁の寺と、水路で、落ち着く景色をかたちづくってっています。
最初に左側にある善證寺です。

慈雲山 善證寺(ぜんしょうじ)
1334年に、対岸の金梨山のふもとに開創。
1625年の火災で消失し、1652年にこの場所に移転したそうでした。
1706年に現在の本堂を再建立し、門前の石橋には享保17年(1732年)の年号が刻まれています。

寺町通を歩きます。

すぐ隣には、常光寺がありました。

常光寺の石橋は、宝永4年(1707)に架橋で、但馬で最古の石橋
本堂

この寺は、竹田城の初代城主の太田垣光景の菩提寺でした。
1594年に開創し、1610年に現在地に移っています。
太田垣光景 石塔

ここからさらに寺町通りを北へ歩きます。
常光寺の隣りには、勝賢寺がありました。

本堂


この地は、赤松広秀公の家臣の平位善右衛門屋敷跡とされています。
境内には、第九代城主である桑山重晴の長男、一重夫妻の五輪供養塔があるそうです。
寺町通りにそう小さな川の流れ


一番最後の寺は「法樹寺」

本堂

本堂の裏側には赤松広秀の供養塔があります。
(寺には、赤松広秀愛用の膳、お椀があるそうです。)
赤松広秀は1562年に、播磨龍野城主赤松政秀の子として生まれ、16歳で龍野城主となります。
後に、秀吉の家臣となり、四国征伐等の戦功により、1585年に竹田城主となりました。
竹田城の最後の城主です。
文人としても優れ、領民から慕われる武将でしたが、”関ヶ原の合戦”で西軍にくみしたため敗北します。
その後、鳥取城攻めで城下に火を放ったとされ、鳥取の真教寺で自刃しました。享年39歳でした。
供養塔を探しましたが、うまく見つけることができませんでした。
境内の外へ出て、寺町通りをさらに北へ歩きました。

(通りの右側にありました。)
この通りから、竹田駅が見れます。

もうすぐ、”駅裏登山道”に到着します。

登山口に来ました。