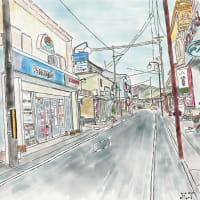昭和23年創業の甘味処。
私の生まれと同じ年ですね。
ここから黄色の線に沿って番号順に歩きます。

茶屋から、大きな道路を渡ると、急な石段がありました。

この上に行くと、目の前に、若草山が現れます。

山全体が芝生でおおわれていました。
3つの笠を重ねたような形なので、「三笠山」の名もあります。
高さ342m,広さ33haあり、山のあちこちに鹿が見れます。
ニュースでよく取り上げられる「若草山の山焼き」は、冬の代表的な行事でした。
起源には、諸説ありますが、若草山の山頂にある前方後円墳(鷺塚古墳)の霊魂を鎮める杣人(そまびと)の祭礼ともいうべきものとのこと。
杣人とは、きこりのことです。
私も、学生の時に遠足で来て、この山に入って、弁当を食べた記憶があります。
遠足といえば、弁当は、必ず寿司屋さんの巻き寿司でした。
修学旅行の学生さんに会いました。

中学生か? 高校生か?
ここから、しばらくのんびりと、地図のハイキングコースを行きます。
次の目的地の「手向山八幡宮」を目指しました。
八幡宮に入る直前に通った「古梅園製墨」。

奈良で製墨を始めて、四百有余年を数える店のようでした。
もうすぐ、「手向山八幡宮」です。

八幡宮に到着しました。


奈良時代、聖武天皇が大仏の造営をされたとき、これに協力のため、749年に宇佐から八幡宮を迎え、大仏殿の近くの鏡池(八幡池)の東に鎮座したことに始まりました。
以後、東大寺を鎭守しました。
鎌倉時代、1250年に、北条時頼によって現在の位置に遷座したとのことです。

ここから、少し歩くと「法華堂(三月堂)」があります。

東大寺建築のなかで最も古い建物。
不空羂索観音を本尊として祀るためのお堂です。
旧暦3月に、法華会(ほっけえ)が行われるようになり、法華堂、または三月堂と呼ばれるようになりました。
ここで、少し休憩します。