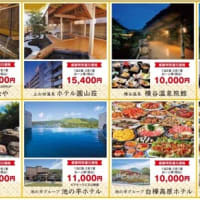慶長七年(1602)の中山道制定にともない、真田氏の配下で、本陣・問屋の石合氏、問屋の小林氏が中核となり、当初は現在の位置より西下の依田川沿いに宿場が設けられた。
しかし、寛永八年(1631)の大洪水により宿場が流失したため、現在地に移り、東西方向に「竪町」、後に宿場が賑わうにつれ、南北方向に「横町」が形成されて、特異なL字型の町並みとなった。
寛政元年(1789)以降、40軒程度の旅籠があり、中山道信濃26宿のなかでは、塩尻宿に次ぐ数であった。
それは、宿場の前後に笠取峠、和田峠の交通難所があったことや、大門道、大内道、北国街道へ接する交通の要衝にだったことによることではないかと思われます。(出典:長和町教育委員会「長久保歴史資料館」)
「本陣・石合家」
御殿は、中山道最古の本陣遺構とされている。
「一福処 濱屋」
旅籠で明治になってから建てられた旅籠で、長久保宿の歴史資料館として活用されている。
「出梁造り(だしばりづくり)」という総二階建ての大きな建物で、古地図などの資料、宝物、道具、籠や古い看板など、宿場の面影を感じさせるものが保管、展示されている。
「一福処 濱屋」の二階
この建物は、「出梁造り(だしばりづくり)」の総二階。中は「囲炉裏と板の間」「通り土間」がきれいに保たれている。明治時代初期に旅籠として建てられたが、交通量が減少し旅籠として利用されなかった。
最新の画像[もっと見る]