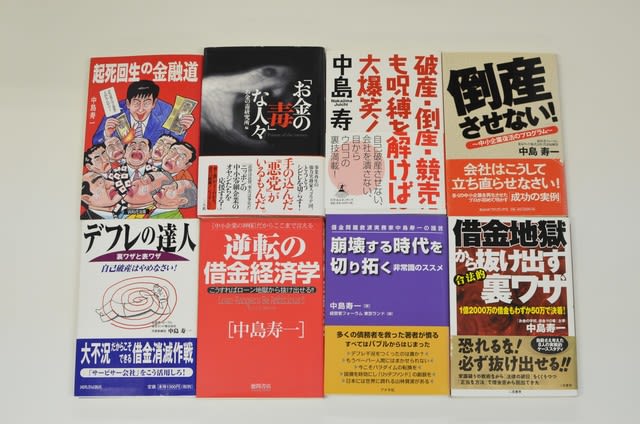2016年8月吉日
周囲の事象は全てが我が心の反映である
「心」が経営に大きな影響を及ぼします。
経営者としての心構え、精神状態がどうあるべきか、ということが経営の要諦
なのです。
権謀術策を弄さない
相手が権謀術策を弄する悪い人であっても、それに同調したり、対抗してはならない。
害を及ぼさないためにも無防備であってはなりませんから、此方も色々な作戦を立てようとします。
しかし、そのこと自体がもう自分の心を汚くするのだそうです。では対策は・・・
常に反省のある人生を
人格の相当な部分を占めるのが潜在意識だそうです。
その潜在意識が、くり返しの反省によって変わってくるのだそうです。
※袁(えん)了(りょう)凡(ぼん)「陰騭録(いんしつろく)」を読んでみては・・・
人は皆利他の心を持っている
人間の心は利己的な心と他利的な心、自分だけよければよいという心と、みんなのために何かしてあげようという心、この二つに分かれます。
他利とは他人に対する思いやりの心です。
その思いやりの心、優しい心、美しい心、この様な心は強く意識しなければ育ちません。
美しくて、優しくて、思いやりのある心。
これが、我々大和民族の本質なのです。
老化物質をためないために
AGEと呼ばれる体内の余剰な糖分とタンパク質が結び付き出来る物質で、日常的に体内で少しずつ生成され排出されにくいと言われています。AGEが血管に蓄積し動脈硬化や糖尿病、骨粗しょう症、アルツハイマーなどのリスク要因になるようです。AGEを多く含む食品「とんかつ、唐揚げ、ステーキ(脂肪多)、高温で料理食品、人工甘味料はブドウ糖の10倍の速さでAGEを生成するそうです。対策として、ワイン、レモン、お酢などの抗酸化成分を摂取し老化を押さえることが、医療費負担削減となり国家負担を抑える自助努力になります。
国家に期待するのではなく、「自身が国家に何が出来るか」安岡正篤翁から
周囲の事象は全てが我が心の反映である
「心」が経営に大きな影響を及ぼします。
経営者としての心構え、精神状態がどうあるべきか、ということが経営の要諦
なのです。
権謀術策を弄さない
相手が権謀術策を弄する悪い人であっても、それに同調したり、対抗してはならない。
害を及ぼさないためにも無防備であってはなりませんから、此方も色々な作戦を立てようとします。
しかし、そのこと自体がもう自分の心を汚くするのだそうです。では対策は・・・
常に反省のある人生を
人格の相当な部分を占めるのが潜在意識だそうです。
その潜在意識が、くり返しの反省によって変わってくるのだそうです。
※袁(えん)了(りょう)凡(ぼん)「陰騭録(いんしつろく)」を読んでみては・・・
人は皆利他の心を持っている
人間の心は利己的な心と他利的な心、自分だけよければよいという心と、みんなのために何かしてあげようという心、この二つに分かれます。
他利とは他人に対する思いやりの心です。
その思いやりの心、優しい心、美しい心、この様な心は強く意識しなければ育ちません。
美しくて、優しくて、思いやりのある心。
これが、我々大和民族の本質なのです。
老化物質をためないために
AGEと呼ばれる体内の余剰な糖分とタンパク質が結び付き出来る物質で、日常的に体内で少しずつ生成され排出されにくいと言われています。AGEが血管に蓄積し動脈硬化や糖尿病、骨粗しょう症、アルツハイマーなどのリスク要因になるようです。AGEを多く含む食品「とんかつ、唐揚げ、ステーキ(脂肪多)、高温で料理食品、人工甘味料はブドウ糖の10倍の速さでAGEを生成するそうです。対策として、ワイン、レモン、お酢などの抗酸化成分を摂取し老化を押さえることが、医療費負担削減となり国家負担を抑える自助努力になります。
国家に期待するのではなく、「自身が国家に何が出来るか」安岡正篤翁から