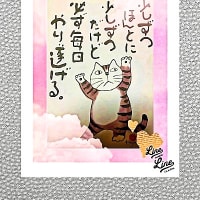三月十日の強風で根こそぎに倒れた、鶴岡八幡宮(鎌倉市)の大銀杏は、根本から4㍍で幹を切断、移植された。八幡宮は十八日、「移植された幹や、残された根本部分からの芽吹きを祈る神事」(3月19日付『讀賣新聞』第35面。写真上段は同新聞から転写)を営んだ。
三月十日の強風で根こそぎに倒れた、鶴岡八幡宮(鎌倉市)の大銀杏は、根本から4㍍で幹を切断、移植された。八幡宮は十八日、「移植された幹や、残された根本部分からの芽吹きを祈る神事」(3月19日付『讀賣新聞』第35面。写真上段は同新聞から転写)を営んだ。
神奈川県の天然記念物に指定されている、この推定樹齢千年の御神木の災難に関して、例の「巷論」執筆者が相変わらず支離滅裂な「論」(3月18日付『釧路新聞』第3面)を展開している。
■「この10日、私たちは一つの歴史の終わりを見た」⇒「終わり」とあれば当然「始まり」がある。文脈から判断して、「一つの歴史」は「武士道の歴史」で、「始まり」は「鎌倉幕府の成立」ということになるが、今日まで続くそのような「一つの歴史」は存在しない。また、大銀杏は鶴岡八幡宮の御神木であって、武士の魂ではない。
■「千有余年、栄枯盛衰の鎌倉幕府『いざ鎌倉』という忠誠心、武家政権、関東武者、武士道の歴史を見つめ続けた大銀杏」⇒鎌倉幕府の成立年については諸説があって決着がついていないが、十二世紀末(1183~1192)である。樹齢千年の大銀杏が、鎌倉幕府成立以来今日まで人間の歴史を見つめ続けたのは、たかだか八百年なにがしでしかない。武士道に関しては、鎌倉・室町時代と江戸時代とでは内容に大きな違いがあり、明治時代のキリスト者の解釈もまた異なる。「いざ鎌倉」=武士道ではない。
■「とにかく、鎌倉幕府は、三代将軍実朝が、おいの公暁にこの階段で暗殺され終わる」⇒実朝暗殺の後も、北条執権政治のもとで幕府は存続し、滅亡は1333年。
■「もっと動転したらとはいわないが、危機管理意識が足りないのではなかったのか」⇒大仰な言葉や仕草だけが驚きの表現ではない。驚きのあまり声が出ないこともある。大銀杏が倒れたのは、自然の猛威が人間の浅知恵に勝(まさ)っただけのことだ。
■「10日の早朝を涙が出るほど辛く思うのに、『びっくりした』。程度の管理意識かといまさら、…(中略)…、危機意識がなさすぎた」⇒句読点の使い方を知らないで真っ当な文章は書けない。小学校で作文の勉強をやり直したらどぉ。
最近の「学芸文化」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事

![人生残り10年の読書記録 (7) 『[詳解] 独ソ戦全史』](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/20/fe/251517596a253652d298f2f3c577b6d9.jpg)