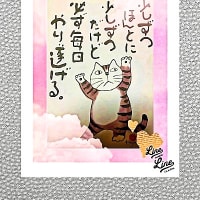私の文章修行の根底には、鴨長明の『方丈記』が存在している。高等学校の「古文」の授業で一部分を読んだのが初めての出会いだが、大学受験の勉強の合間に、全文を何度も読み返し、完璧ではないにしても、ほとんど暗唱できた。たかが高校生の身に、仏教的無常観の露わな提示など関係がない。長明の和漢混淆文の力強いリズムに魅せられたのである。緊張感のないまったりとした口語訳など、読む気がしなかった。
私の文章修行の根底には、鴨長明の『方丈記』が存在している。高等学校の「古文」の授業で一部分を読んだのが初めての出会いだが、大学受験の勉強の合間に、全文を何度も読み返し、完璧ではないにしても、ほとんど暗唱できた。たかが高校生の身に、仏教的無常観の露わな提示など関係がない。長明の和漢混淆文の力強いリズムに魅せられたのである。緊張感のないまったりとした口語訳など、読む気がしなかった。
細部を理解するために利用した淺尾芳之助監修『要説文語文法』(日栄社)は、高校生の副教材として編集された小冊子だが、なかなかの優れもので、現在でも、手の届く範囲に置いて利用している。
山本夏彦の『完本文語文』(文藝春秋)は、夏彦の知識・関心の幅広さを如実に示している。第1部の目次を見よ。中江兆民・二葉亭四迷・樋口一葉・萩原朔太郎・佐藤春夫・中島敦の個人的逸話を語り、最後に「祖国とは国語だ」と結ぶことができる物書きを、私は他に全く知らない。いたら教えてもらいたい。
巻頭のコラム「文語文」は、明治・大正の国語教育から始まり、文語と口語を論じ、芥川龍之介・佐藤春夫と藤村藤村・土井晩翠との文語の違いを明確に指摘している。正岡子規の「歌よみに与ふる書」を難じている。私は、「各人にオリジナリテがあるという考え方と、ないという考え方があって、私はないと思っている。もしあるとすればまねしているうちに自然にあらわれるものだと思っている。個性なんてちやほやされて出てくるものではない」という説に同調するものである。言葉や文章は、他人の真似から出てきて、自分の身に付くのである。文語文の暗唱を侮るなかれ、と強く主張したい。何度も真似をしているうちに、語彙がふくらみ、やがて自家薬籠中のものとして利用できる。それが個性というものだろう。
最近の「学芸文化」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事

![人生残り10年の読書記録 (7) 『[詳解] 独ソ戦全史』](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/20/fe/251517596a253652d298f2f3c577b6d9.jpg)